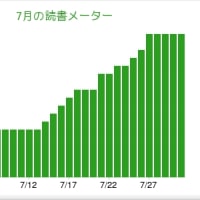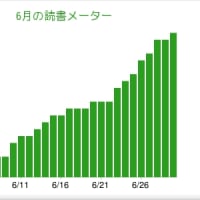マクベス夫妻は、フォレスの宮殿から、ダンシネインの城に居住を移していた。マクベス夫人の侍医と侍女が登場し、夫人が病に患っていることが分かる。
夫を励まして仕事をさせるかと思えば、自分自身の手に付いた血痕を清めようと空しい努力をする。
また、彼女の心の中ではバンクォーのことが、ダンカンが殺された夜の回想と混ざり合っている。
彼女は、夫の秘密を分担したことから、自身を過信していた。自分が演じた血生臭い役割の記憶が恐ろしく、それに堪えられなかった。
'Since his majesty went into the field, I have seen her rise from her bed, throw her nightgown upon her, unlock her closet, take forth paper, hold it, write upon it, afterwards seal it, and again return to bed; yet all this while in a most fast asleep.' (陛下が戦場にお出掛けになって以来、ずっと毎夜のこと、急に寝床から起き出して、 夜着をお羽織となり、戸棚の鍵をお開けになるのです、そして紙をお出しになって、 何やらお書きにして、もう一度お目を通され、封をしてようやく寝床にお戻りになるのです。 しかも、その間ずっと、ぐっすりと眠っておられるのです)
いわゆる「マクベス夫人症候群(シンドローム)」と呼ばれるもので、罪の意識が潜在的に本人を圧迫して、特に眠っている時など、無意識に行動に現れてしまうという精神錯乱の一種だ。
夫人の場合、毎晩ベットから起き上がり、手に付いた血の染み(もちろん付いてなどいないのだが)を洗い落とそうと手を擦り合わせてる(手を洗っているつもり)、しかも全て無意識に眠ったまま行っているという夢遊病で、本人はその行為を憶えていない。
夫人の場合、毎晩ベットから起き上がり、手に付いた血の染み(もちろん付いてなどいないのだが)を洗い落とそうと手を擦り合わせてる(手を洗っているつもり)、しかも全て無意識に眠ったまま行っているという夢遊病で、本人はその行為を憶えていない。
'Fie, my load, fie ! A soldier, and afeard ?' (武人だというのに、陛下は、恐がる! それでよいのですか?)
夫を励まして仕事をさせるかと思えば、自分自身の手に付いた血痕を清めようと空しい努力をする。
'Here's the smell of the blood still: all the perfumes of Arabia will not sweeten this little hand,' (まだ、ここに血の臭いがする、アラビア中の香料を振りかけても、この小さな手に甘い香りを添えることが出来ない)
また、彼女の心の中ではバンクォーのことが、ダンカンが殺された夜の回想と混ざり合っている。
'Wash your hands, put on your nightgown; look not so pale:―― I tell you yet again, Banquo's buried; he can not come out of his grave.' (手をお洗いになって、寝間着をお召しになって。そんな顔色をなさっていたのではいけません―― 分かっておいででしょうが、バンクォーはすでに墓の中、出てこられるはずがありませんわ)
彼女は、夫の秘密を分担したことから、自身を過信していた。自分が演じた血生臭い役割の記憶が恐ろしく、それに堪えられなかった。
彼女が今までじっと耐えてこられたのは、彼女自身の重荷というより夫マクベスを助けるためであったのだ。だからこそ、苦しい緊張の日々であったが、夫を励まし、国王暗殺が露見する結果から彼を守らなければならない間は、その役割を見事に演じることが出来た。
しかし、殺人が終わり、夫が戦場に出るようになって、巧妙な偽善から、直接的な打撃に舞台が移るようになってからは、彼女の介入の余地はなくなり、犯罪を隠し通してきた極度の緊張から神経が崩れ落ちてしまった。
しかし、殺人が終わり、夫が戦場に出るようになって、巧妙な偽善から、直接的な打撃に舞台が移るようになってからは、彼女の介入の余地はなくなり、犯罪を隠し通してきた極度の緊張から神経が崩れ落ちてしまった。
彼女の頭には、繰り返し繰り返し、あの殺人の回想がめぐっていた。眠っていても醒めていても、常に頭を休めることがなかったのだ。
つまり、ここに至って彼女の役割が終わったことを意味する。冷たい言い方ではあるが、マクベスにとってもはや有用ではなくなったということなのだ。
侍医は、夫人の病は心の病であり、自分にはどうすることも出来ない、原因に心当たりはあるが口の出すことは出来ないと侍女に話し、夫人から目を離さぬようにと告げるのだった。