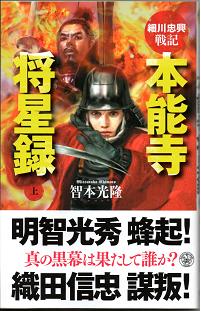さて、「本能寺将星録紀行」第2回は長岡京市の「勝龍寺城」です。
この城は織田政権で細川家の居城となり、今作では度々登場しております。
古来においてこの地は桓武天皇により、長岡京が造成されたのは有名なところ。
この一帯は久我畷と称され、京都―難波間の交通の要所でもあり、同時に軍事的対立の場所でもありました。
智本光隆は元々、専攻は南北朝時代ですが元弘、建武、そして観応の擾乱と幾度も戦いの舞台となっております。
特に有名なのは元弘3年4月、足利尊氏はこの地で鎌倉幕府に離反し、丹波篠村八幡宮で宮方の旗を掲げています。
この軍勢の中には細川家の祖先も、当然加わっていた訳で。
時代はやや下り、1338年(延元4 暦応2)、南朝は北畠顕家、新田義貞が立て続けに死んだその年、
足利方が洛南のこの地に築いたのが勝龍寺城です。
淀川南の男山は南朝の拠点のひとつであり、都奪還を目指す宮方に備える目的があったとされます。
そして、この城を築いたのが細川頼春。その子が藤孝、忠興の祖先となる細川頼有になります。
しかしながら、この伝承は後に勝龍寺城城主となった細川氏が、正統性を強調する為の創作との説もあります。
ただ、当時の南北朝の力関係から、この地の北朝方拠点を任せられるのは、京都守護を務める細川頼春というのが妥当な気も。
実際、頼春は正平の一統による宮方の京都乱入で、都を守って戦死していますし。
さて、そんな感じで長岡京駅から、いざ勝龍寺城へ!・・・・・休園日でした!!
現在、城跡は「勝龍寺公園」になっているそうです。
仕方なく、これだけ撮って帰るさ。平成4年から「長岡京ガラシャ祭り」があるそうです。

かかり付けの眼科さんに聞いた話なのですが、熊本にも「ガラシャ通り」があるそうな。
・・・地元の皆さん、忠興にも少し触れてあげて下さい。
で、めげずに二日後。


ちなみにイベントの際には、城門に「九曜」と「二引両」の旗が立つようです。
作中でも触れていますが、永禄11年(1568)の織田信長の上洛時、勝龍寺城は三好三人衆のひとり岩成友通の支配下。
藤孝はこれを討ち果たし、信長より先祖由来の城と長岡の一帯を与えられました。
忠興と珠子はこの勝龍寺城において婚儀を上げております。公園内には平成3年鋳造の銅像が。


以前のものと別アングル。そして、城内の様子を。
ちなみに、勝龍寺城は小説(主にガラシャ主人公や明智物)ではただの小城に描かれることが多いですが、
発掘調査ではかなりの規模の城であったとのこと。作中では折衷的な描写になってますが。
他の作中描写としては大手道の松並木とかあります(現存はせず)
そちらは「山城国西岡御領地之図」(永青文庫)に拠っています。
勝龍寺城は本能寺の変当時、帰属が少々不明な面もあります。
基本、地元では細川家の城と位置付けているようです。
そんな訳で、今作でもそのように(笑)

別アングルと言いながら、前のと似てたので別の角度を。スイマセン。