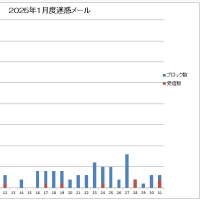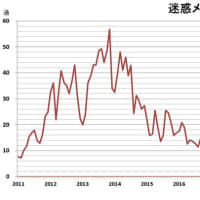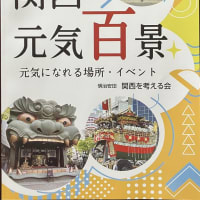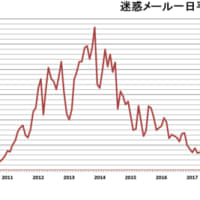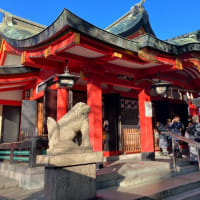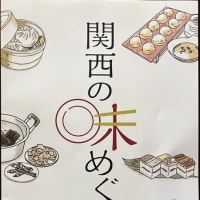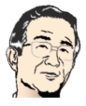3月14日、大阪市立大学文化交流センター専門家講座3月を受講しました。文化・歴史コース<大阪と大阪をたずねる?>の2回目(最終回)は「上方落語の考察」と題してNPO法人宝豊連理事長・上方社会人落語連盟理事の庄野達也(芸名:桂 一豚)さんが講義を行いました。
庄野さんは受験勉強中にラジオ番組で笑福亭 仁鶴師匠の落語を録音(50本位)し、大阪市立大学入学後に落語研究会に入り活躍した。卒業後は一旦落語から離れたが、先輩から誘われて社会人落語家の人たちと交流するようになった。阪神大震災後に地元で落語会を開催した。笑うことで活力が向上し、免疫力が高まる。NPO法人宝豊連を設立。
1950年代に上方落語は瀕死の状態であったが、現在は200人以上の噺家が活躍している。松鶴・米朝・春団治・文枝が上方落語の噺家四天王といわれた。
1950年代のドン底の時期に噺家は10~15人で滅びると言われていた。また、落語を公演する場所もなかった。1960年代に関西の各大学でオチケンが誕生し、アマチュア落語家が草の根文化の担い手となった。1970年代に落語がブームとなった。現在はブームでなく、安定している。ゆとり社会が文化・芸術を育てる。
落語人気が上昇する条件(木津川 計さん著書「上方芸能と文化」)として、①話芸に秀でた落語家の輩出、②自由時間を多く持つゆとり人間の増加、③経済拡大期でなく安定社会の現実、を挙げている。
詳細は[こちら]をご覧ください。
庄野さんは受験勉強中にラジオ番組で笑福亭 仁鶴師匠の落語を録音(50本位)し、大阪市立大学入学後に落語研究会に入り活躍した。卒業後は一旦落語から離れたが、先輩から誘われて社会人落語家の人たちと交流するようになった。阪神大震災後に地元で落語会を開催した。笑うことで活力が向上し、免疫力が高まる。NPO法人宝豊連を設立。
1950年代に上方落語は瀕死の状態であったが、現在は200人以上の噺家が活躍している。松鶴・米朝・春団治・文枝が上方落語の噺家四天王といわれた。
1950年代のドン底の時期に噺家は10~15人で滅びると言われていた。また、落語を公演する場所もなかった。1960年代に関西の各大学でオチケンが誕生し、アマチュア落語家が草の根文化の担い手となった。1970年代に落語がブームとなった。現在はブームでなく、安定している。ゆとり社会が文化・芸術を育てる。
落語人気が上昇する条件(木津川 計さん著書「上方芸能と文化」)として、①話芸に秀でた落語家の輩出、②自由時間を多く持つゆとり人間の増加、③経済拡大期でなく安定社会の現実、を挙げている。
詳細は[こちら]をご覧ください。