本来なら「橋本コレクションと煎茶席」なのでしょうが、私にとってのメインがお煎茶席だったので
「煎茶席と橋本コレクション」で!

外市さんの夏御召とカニの帯
今年は沢山夏物を下ろしません
あんまり着る機会がなさそうだし、1回袖を通しただけで洗いに出すのは悔しいから(笑)
会場は大阪市立美術館

ここは何度か来ていますが、毎回暑い盛りなのです…
次回の9月からの展示は紅型なので、次回も来ようと思います
中国書画ということで、書は興味があったのですが、展示物はほとんど画のほうで…
あっさりめに見学を終えて、目指すは貴賓室


↑ 目的は右下に小さく張り紙されている「煎茶席」
入り口で受付を済ますと、ちょうどタイミングよく、これから始まるというところ
立礼のお席で、重厚な椅子が12脚
ちょっと、、コレは良い

かなりテンションUPです

ちなみにこのお席は昌隆社さんが担当されていまして、どこかで昌隆社さんがお茶会されないか、アンテナ張っていたのです
大阪美術倶楽部ではされているみたいですけど
私以外はお知り合いの方がほとんどみたいな雰囲気です
何人かの方が写真を撮られていたので、私もちょっと失礼して…

貴賓室は天井がとても高くて、その天井の高さを生かした瀧の絵が掛けられていました
脇のお花(葉)がとても清清しい
すーっと自然の風が吹いてくるような錯覚に陥ります

花器は美術館所有のもので、染付けで「こうき時代」って言われたと思いますが、清朝のこうき帝のことでしょうかね(漢字忘れたわ…康○帝なんだけどな)
中国書画の添え釜だから、お客様はそれくらいの知識はあって当然ということなのか、特に説明はなし
私もたまたま清朝の歴代皇帝だけは全部知ってたから、想像が付いたけど、こうき帝時代のものだったら古いものですね

貴賓室はこんな感じ
以前はお抹茶のお席で入ったことがありますが、使い方が全然違う

展示会にあわせて、唐物を多く使われていました

バカラがとても涼しげです
冷茶だったので、氷が浮かんでいます。
柄杓のような変わったお道具…、、お水をすくって小さな器に入れるのがとても難しそうでした


私の情報源


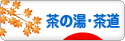 にほんブログ村
にほんブログ村



































