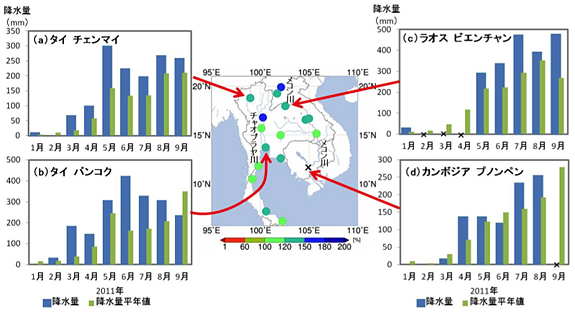食品からの放射線被害を防ぐ18の大事な事!

放射線防護の仕方(食品編)1
●水道水は汚染されている。
自治体の計測で”ND”と出ていても、限られた核種のみの測定。
トリチウムに汚染されている場合には、どんな濾過も通用しない。
なるべく西でボトリングされた水を飲む。
乳幼児には特に配慮する。
放射線防護の仕方(食品編)2
●安全とされた食品でも、それだけを食べるのではなく、できるだけまんべんなく(安全とされた)いろんな物を食べるようにする。
限られたものだけを食べていて、それが汚染されていた場合には悲劇になる。
放射線防護の仕方(食品編)3
●大量に被曝してしまった場合、塩辛いものを摂取する。
爆弾をうけた人には塩がいい。
玄米飯に沢山塩をつけてにぎる。
塩からい味噌汁をつくって毎日食べさせる。
そして、甘いものを避けること。
砂糖は絶対にダメ!
放射線防護の仕方(食品編)4
●発酵食品が良い。
放射線防護の仕方(食品編)4の補足(要約)
●切断されたDNAの修復には酵素の力が必要です。
酵素は生の果物、野菜、漬け物に含まれる。ビタミンミネラル。
ちゃんと醗酵した酵素を沢山取る事が大切です!
ジュースでも絞って25分以上たったものは酸化して酵素がなくなってしまう。
放射線防護の仕方(食品編)4の補足2(要約)
●ペクチンが放射能を排出する。
毎日摂取すれば25パーセントから50パーセントぐらい排出される。
お腹のすいた時に酵素の入ったものを食べる。
放射線防護の仕方(食品編)4の補足3(要約)
●酸化したものを食べると酵素を浪費する。抵抗力を落とす。
放射線防護の仕方(食品編)4の補足4(要約)
●あまりにも毎日のメニューが豪華になっています。
すごい単品の方がいいです。
食品によって分解する酵素ぜんぶ違うので酵素を浪費する。
豪華メニューは酵素を浪費する(カツ丼等)。
放射線防護の仕方(食品編)4の補遺5(要約
)ごちそうで消化に酵素を使うと全身の酵素が使われてしまう。優先して酵素が使われてしまう。その分抵抗力が落ちる。
眠くなるのです。
放射線防護の仕方(食品編)5
●放射能は物質や体を酸化させる。
ゆえに、スナック菓子などの「酸化している食品」の摂取を控える。
放射線防護の仕方(食品編)6
●牛乳と野生のキノコ類の摂取は控える。
チェルノブイリの人体汚染は牛乳から。
キノコは根が広く、汚染を集積しやすい。
放射線防護の仕方(食品編)7
●最初は野菜。野菜と果物はとにかく「洗って、むいて、また洗う」ことが大切だ。
まず表面を流水でよく洗い、放射性物質を取り除く。
放射線防護の仕方(食品編)8
●葉物野菜ならば外側の3、4枚の葉は捨てる。
長ねぎも表面の皮1枚ははぎ取る。
そのほかの野菜も皮の部分に放射性物質が多く取り込まれているので皮をむく。
放射線防護の仕方(食品編)9
●普段は皮を むかないキュウリやナス、トマトなどの皮もむこう。
ヘタの部分も大きくカットする。そして、最後に再び流水で洗う。
放射線防護の仕方(食品編)10
●キノコは特に放射性物質が沈着しやすい。
十分注意が必要だ。キノコの種類によっても違う。
傘の部分に多く付着していることが多いので傘の表面を薄くそぎ落とす。
そして数時間塩水にさらしておく。
このとき酢や、クエン酸を加えると除染効果は高くなる
放射線防護の仕方(食品編)10の補足
●キノコ類は根から吸い上げるという説もあります。
結果がでるまで、摂取を控えたほうがいいと思います。

放射線防護の仕方(食品編)11
●最後は野菜と同様に流水で洗う。
手間はかかるが、目に見えない放射能と闘うのだから仕方がない。
放射線防護の仕方(食品編)12
● 肉や魚からも放射性物質を取り込む可能性は高い。
特にセシウムは動物の内臓系に取り込まれやすく、ストロンチウムは骨組織に沈着する。
放射線防護の仕方(食品編)13
●塊の肉は薄切りやブツ切り、ひき肉にして2%の塩水にさらす。
このときにビタミンCや酢を加えると効果が高くなるばかりか、肉の栄養分の流出も食い止めてくれる。
そしてその状態でひと晩置く。
放射線防護の仕方(食品編)14
●肉は時間がないときはゆでる方法もある。
沸騰したお湯で8~10分間ゆでるのも可。
ゆで汁には放射性物 質が溶け出しているので必ず捨てる。
放射線防護の仕方(食品編)15
●魚もまずはよく洗い、骨にストロンチウムが沈着している可能性があるので、内臓とともに取り除く。
さらに放射能を減らすには、 肉と同様に塩水につけるか、ゆでる。
エビや貝類にもストロンチウムの沈着が心配されるので同様の処置をする。
放射線防護の仕方(食品編)16
●ある研究では、ストロンチウムは水洗いで 10~30%、3%の食塩水で30~70%が除去されたという。
とにかく洗うことを習慣づけるしかない。
放射線防護の仕方(食品編)17
●中国ではお茶の作法として、飲む前に一度 お茶の葉に熱湯を注いで湯を捨てる「洗茶」といういれ方がある。
日本茶でも、まずこの「洗茶」をして、その1杯目を捨てることで放射性物質の除去を期待できる。
放射線防護の仕方(食品編)18
●ストロンチウムが体内に入って骨組織に沈着しないように、鶏卵を固ゆでにして殻をむき、その殻を粉末状になるまで砕き、一日に 2gずつ摂取する方法。
こうすることでストロンチウムが沈着しやすい骨組織の隙間を埋めてくれるのだそうだ。
- 全般
- 牛乳と魚、原発近くの食材を避ける
- 産地を表示しないスーパーを避ける
- EU輸入制限地域(食品および飼料の輸出に際し検査が必要とされる輸入制限対象地域):福島、群馬、茨城、栃木、宮城、長野、山梨、埼玉、東京、千葉、神奈川、静岡(2011/07/04 山形と新潟の規制は解除。静岡が7月中から正式に規制対象に。次回見直しは9月)
- 肉牛の出荷停止に指定されたのは、福島、宮城、岩手、栃木(2011/08/02 時点)
- 簡易検査機で食品の汚染度を測る場合は、土壌や建物などに付着している放射性物質の影響で食品だけの数値を正確に測ることは難しいことに注意。また、厚みのある食品は、内部の放射能は測定できない
- 一度でも変な食品を流通させた経歴のある会社のものは買わない(放射能汚染食品情報)
- 厚労省発表の食品の放射性物質検査データをみる(食品の放射能検査データ が使いやすくまとまっている)
水産物(魚、海藻)
- 水産物の産地表示は義務。国内産の場合は水域名または地域名(主たる養殖場が属する都道府県名)を記載する。水域名の記載が困難な場合は水揚港名または水揚港が属する都道府県名を記載することができる。輸入品は原産国名を記載する。
魚
- 貝、小魚、魚卵は汚染されやすい食物。注意が必要。
- 宮城沖〜駿河湾沖まで危険。和歌山の魚の件補足:単位がベクレルでないことに注意。何かが検出されているのは確かだが、線源がはっきりとは特定できない。いくつかのツイートから測定器の積算線量を読んでいる可能性あり。シーベルトからベクレルを推定するのは難しく、人体に対する影響度はこの測定報告からは不明なため、和歌山県の魚が汚染されているとは今のところ判断できない。ちなみに通常の食品の汚染度検査は、燃やして灰にしてから測定する。←さらに補足:海はつながっているので、和歌山の魚がまったく安全だとは言い切れない。今後の測定報告を待ち、判断したい。
- 生物濃縮するので、最初は小魚、6月は中型、7月は大型と注意する範囲は拡大する
- 大型の魚類ほど高濃度。チェルノブイリの場合、事故の1年後が汚染のピークだった
- 太平洋側のものより日本海側(若狭湾付近を除く)のものを買うほうがより安全そう
- 淡水魚は水底に住む魚ほど汚染されている。生育環境の閉鎖性により、汚染度が高くなることもある
- 三重県の魚受入について:汚染された魚を買い上げる復興支援策を発表していたが、三重県産として販売するというのは誤解で、放射能の計測値を添付して安全確認された魚というのが前提で、現時点では流通の条件が満たされていないとコメントを発表
- 買う前に、都道府県が実施している水産物の放射能検査の結果集計を参照(勝川俊雄公式サイトにまとめあり。最新は水産庁HP。食品の放射能検査データも参照。)
- 養殖魚の個体識別検索 PC、モバイル
海藻
- 汚染されやすい食物。全体に注意が必要。
- 福島沖〜千葉沖までの昆布、わかめは絶対にダメ。
- 昆布の漁期は5月から7月の解禁日から9月の中旬まで。
- くらこんの塩昆布は、7月1日から自社検査を開始。第三者機関による検査も引き続き行う。賞味期限の下に採取時期の表記もあり。
畜産物(牛乳、乳製品、肉)
- 畜産物の産地表示は義務。国内産の場合は国産と記載する。輸入品は原産国名を記載する。
牛乳、乳製品
- 牛乳はどの地域のものも危険
放射能汚染地域の牧草や乳牛が他の飼育地へ移動しているため(乳牛は基本的に長距離移動は難しい)
- 雪印、メグミルクは、独自検査はしていない。牛乳には福島産の原乳が使われている
- 明治乳業は、独自検査はしていない。福島産の原乳は使用していない。1:12:35経過あたりの発言(明治牛乳には放射能が入っていると明治乳業の人が認めた)を元に、電話問合せを行ったところ、独自検査は行わず都道府県の検査を信頼している。ちなみにその検査は土が汚染されているかどうかによる。
-
- そして土が汚染されているかどうかの検査は事故前事故後の空気中の線量に変わりなければ行われない。つまり関西や北海道では変わりないので原乳の検査は行われていない。明治牛乳の特に産地を明記していない商品は原則その地域の周辺の原乳を使っている。
-
- つまり関東で販売されている牛乳は、栃木、群馬、埼玉から東北にかけての物を使用している。各都道府県の原乳検査は週1回程度である」との回答でした。すでに問合せが殺到しているらしく、回答もしっかりしたものが用意されている印象。意図的に放射能をまぜた牛乳を販売しているわけではないが、結果混ざっちゃってるかも、というようなニュアンスでしょうか。ちなみに明治乳業の「おいしい牛乳」はかなり早い段階からパッケージの原乳産地の表記が消えています。
-
- 森永乳業は、独自検査はしていない。福島産の原乳は使用していない(ヨーグルト、デザート等すべてにおいて)
-
- 協同乳業は、独自検査はしていない。福島産の原乳は使用していない。25年前チェルノブイリ事故の際には国内基準が整備されていなかったため、独自検査を行うために社内で決めた基準(30ベクレル)を作った。現在は政府が国内基準を打ち出しているため、それに従っている。現在独自検査をしていないのは、25年前に購入した検査機器が故障したためで、新しい検査機器を発注しているが、品薄でなかなか届かない。届き次第独自検査を再開する予定。その際も、国の基準に則って検査を行う。
- 小岩井乳業は、独自検査はしていない。福島産の牛乳は一部(自販機等で販売されている乳飲料など)で少量使用されている。
-
- 各社独自検査をしていない場合、各県の機関が測定を行っているが、その検査にはストロンチウムの検査は含まれていない。
-
- (牛乳まとめ)やはり牛乳はどの地域のものも危険。
各都道府県の原乳の検査は毎日行われていないし、関西や北海道ではそもそも行われていない。そもそもの検査基準が非常に緩められている。広範囲にわたって飼料が汚染されたことが確認されているし、実際はどこの地域のものでもリスクはあると思われる。外国産の飼料のみで育てられていて、水の汚染が少ない地域産>国内だが牧草からこだわった飼料で育てられていて、水の汚染が少ない地域産の順で安全そう。国産だと各地の原乳を自在にまぜて調整できる大手メーカーよりは、小規模のメーカーで、できるだけ原発から遠い地域の、こだわりの製品がより安心か。
-
- 特に乳清は危険。スキムミルク(脱脂粉乳)も危険
バター、チーズなど水分が減って乳脂肪分の割合が高い加工品の方が汚染の度合いが少ない
-
- 乳清飲料、パン、菓子への添加物として乳清(牛乳を脂肪分と水分に分けた際、もともと含まれていた放射性物質の90%が乳清に移る)が使われていることが多いので、避ける
肉
- 牛は全国へ移動しているので個体識別を参照。
- 国産という表記だけでは安心は担保できないためブランド肉推奨だけど産地ロンダリングあり
- 牛肉は国内の他の農場にも行っているので、注意が必要な範囲広い 。そもそも日本はBSE発生国なので、日本からの牛肉の輸出先は非常に限られているとのこと。外国産は安心できそうです。
- 加工食品になると、産地は完全に不明になる
- 農林水産省が7月14日に稲わらの汚染問題で畜産農家と稲作農家に対し緊急点検をするように指示したのは、福島、岩手、宮城、栃木、茨城、群馬、埼玉、千葉の8県
- 沖縄、熊本、福岡、佐賀、長崎、大分、鹿児島、高知、広島、山口、高知 あくまで県の把握する範囲では、被災地からの家畜の受入はなし。
- 宮崎、島根、北海道は被災地の肉牛の受入あり(2011/07/15沖縄県環境生活部生活衛生課に電話確認沖縄は移動はなしとのことでした)
- 宮崎へは肉牛、鶏、豚も移動したとの情報あり。宮崎に入った汚染牛は佐賀牛・近江牛等と銘柄を変え、全国に流通する可能性あり、 宮崎県農政水産部に電話確認したところ、県で把握している範囲においては、牛、豚、鶏の移動は公的にはなく、牛に関しては一般の農家がセリで購入して宮崎に持ち込んだということは聞いているとのこと)
-
- 北海道に移動した牛は16頭。一時飯舘村にも滞在。いずれも繁殖用で妊娠中。受け入れたのは新ひだか町三石のパシフィック牧場。ここで育った牛は「みついし牛」として出荷される
- 鶏:他県へ移動している(基本的に長距離移動は難しい)(鶏の個体識別検索 ※牛と違って義務ではない)
-
- 豚:宮崎へ524頭、熊本へ15頭移動。緊急時避難準備区域と計画的避難区域から約1万頭が県外(主に長野、群馬、新潟、熊本など)へ移動し、いずれも避難先の県産として出荷されている(豚の個体識別検索 ※牛と違って義務ではない)
-
- (鹿児島県黒豚生産者協議会、福島から豚を受け入れたことはなく、そもそも黒豚証明書つきの「かごしま黒豚」は鹿児島県内で生産・肥育されたもので、他県産のものはない。
-
- (まとめ)農林水産省が5月上旬時点で全国に受入を募った計画的避難区域内の牛は約1万頭。また、計画的避難区域には震災直前に豚約1万頭、鶏約91万羽がいた。家畜の移動を完全に追うのは難しいので、外国産のものをさっと買うほうがストレスと手間が少ない。牛肉は、飼育方法の違いから肉質に差があり、偽装されにくいオーストラリア・ニュージーランド産(牧草で育てられている)がより安心。豚と鶏は肉質で見分けるのは難しい。鶏肉は出来るだけ買わないこと。
農産物(米、小麦、野菜、豆類、大豆、大豆製品、果物)
- 農産物の産地表示は義務。国内産の場合は都道府県名もしくは一般的な地名を示す。輸入品は原産国名を示す
- 野菜の個体識別検索
米、小麦
- 米は汚染の影響が次の収穫期に出る
- 今年の収穫分の米はできるだけ原発から遠い生産地を選ぶ。岩手、秋田、新潟、長野、山梨、愛知より外側は大丈夫。秋田と新潟は大丈夫。
- 麦、ライ麦は汚染されやすさは低いらしいが、米と同じような感覚でいいのでは
- 玄米はミネラル豊富だがぬかに汚染物質を貯めやすいため、今年(2011年秋)の収穫分からは注意
- 日清の薄力粉フラワーは主な原産地アメリカ。ただし群馬、埼玉の小麦粉も調整のため配合。カメリア(強力粉)は100%カナダ、アメリカ産
- 冬まきの麦は6月ごろに収穫される
- 農林水産省が7月14日に稲わらの汚染問題で畜産農家と稲作農家に対し緊急点検をするように指示したのは、福島、岩手、宮城、栃木、茨城、群馬、埼玉、千葉の8県
- セシウムを含む灰30トンが米どころ秋田に入る ← この30トンは流山市に送り返されることが決まったそうです。これまでに搬入された207トンは、すでに埋め立てた分も含め、線量測定がされるとのこと
- 米トレーサビリティ法の施行により、米や米の加工品の取引(外食産業で使われる米や和菓子・酒・みりんなどの加工品なども対象)の記録・保存(2010年10月1日から)と、産地情報の伝達が義務化されている(罰金つき)。ただ、国産は都道府県や一般に知られた地名でも可だが、あくまで「国内産」「国産」という表記でよい。
野菜、豆類
- たけのこ、きのこ は汚染されやすい食物。注意が必要
- 福島、茨城、栃木産は買わない。東京、群馬、千葉、埼玉、宮城も避ける。
- ホウレンソウ、ニラ、ネギ、キャベツ、長い形の豆、丸い形の豆 に、より注意が必要。
- だいこん、にんじん、じゃがいも は注意が必要。
- にんにく、パプリカ、玉ネギ、きゅうり、ズッキーニ、トマト は、より安全。
- 2011/07/03放送のNHKスペシャルにて、大塚厚労副大臣が「野菜の放射能検査は(検査体制が追いつかないので)、規制値を超えた野菜の流通を完全に止められてはいない」と発言
- 出荷制限を受けている時期に福島産の山菜が新潟産、山形産と偽装、出荷自粛の時期に福島産のたけのこが新潟産、山形産、青森産と偽装され出荷されている
大豆、大豆製品
- 大豆はセシウムを吸収しやすいため、注意が必要(一説によるとりんごを1とした場合160倍吸収する)
- 大豆の収穫期は秋
- 大豆の加工食品は豆腐、あげ、おから、醤油、味噌、きなこ、豆乳、納豆など。いずれもこの秋以降は注意(味噌、醤油については下を参照)
- 味噌の熟成期間が夏仕込みで約4ヶ月、冬仕込みで約6ヶ月。商品となって出回るのはそれ以降。
- 醤油の熟成期間は早くて約3ヶ月(白醤油や、速醸醤油と呼ばれる方法で作られた安価な醤油は熟成期間が短い)、本格熟成のものは1年以上。商品となって出回るのはそれ以降。
- 日本の大豆の自給率は低い(およそ5%)。2010年時点での主な輸入先はアメリカ(約71%)ブラジル(約16%)カナダ(約11%)など。国内主要産地は、北海道、九州、東北。
- 国産使用の製品の場合は国産大豆使用と表記してあるので見分けやすい。
- 高野豆腐は豆腐を凍らせたあと乾燥させたもの。カルシウムが豊富。工場生産がほとんどで、生産量の9割が長野県で作られている。外気で凍結乾燥させる天然ものは、長野、福島、宮城などで生産されている
果物
- ブルーベリー、クランベリー、こけももなどベリー類は放射能を取り込みやすいが、栽培環境にも依存
- りんご、なし、あんず、いちご、さくらんぼ、ラズベリー はより安全
加工食品
- 産地表示されていないものは買わない
- 一度でも変な食品を流通させた経歴のある会社のものは買わない(詳細 - 放射能汚染食品情報)
- カレーのルーについて。ハウス食品は原発から約180kmのところに関東工場あり。エスビー食品は原発から約150kmのところに宮城工場あり。
- 比較的安心そうなのは、日本コカ・コーラ、ハインツ、大塚製薬、サントリー、ネスレ、サンガリア、くらこん
- 乳清飲料、パン、菓子への添加物として乳清(牛乳を脂肪分と水分に分けた際、もともと含まれていた放射性物質の90%が乳清に移る)が使われていることが多いので、避ける
- 製造所固有記号は完全にはあてに出来ないが、参考にできるサイト→製造所固有記号Wiki PC モバイル、製造所固有記号リスト
- 加工食品の原料原産地表示は一部(下記)を除いて義務ではない。義務の場合は国内産の場合は国産(あるいは農産物は都道府県名その他一般に知られている地名でも可、畜産物なら主たる飼養地が属する場所の、水産物なら生産水域か水揚港の、都道府県名その他一般に知られている地名でも可)輸入品は原産国を示すのみでよい。主な原材料の原産地が2つ以上ある場合は原材料に占める重量の割合の多いものから順に記載。3つ目以降の原産地はその他と記載してよい。
表示義務の対象品目は20。生鮮食品に近いものを対象としている。きのこの加工品、緑茶、調味した食肉、異種混合したカット野菜、表面をあぶった食肉や魚介類、ゆでたり蒸したりした食肉や卵・魚介類・海藻類、合いびき肉その他異種混合した食肉、衣を漬けた食肉や魚介類、もち、黒糖とその加工品、こんにゃく、干したり塩蔵したりした魚介類や海藻類、豆類など(2011年3月31日改正)
アルコール
- ビールは汚染の影響のピークが1〜2年後
- アサヒビールは原発から約60kmの距離の福島工場が稼働中。高性能の放射性物質検査装置を導入予定(5月時点)。約190kmの茨城県にも工場がある。賞味期限の後ろにある「/アルファベット」のアルファベットが製造工場を表す。福島工場は「H」茨木工場は「B」。その他のアサヒビールの製造所固有番号や代表商品についてはこちらを参照
- 米を原料にした酒(日本酒、焼酎など)は米トレーサビリティ法の施行により産地情報の伝達が義務化されている。ただ、国産は都道府県や一般に知られた地名でも可だが、あくまで「国内産」「国産」という表記でよい
放射性物質の検査を行なっている企業、小売店等
- Oisix(ネットスーパー。全アイテムにつき毎日検査実施。農林水産省の食べて応援しよう!フェアに参加中) - Oisixの放射性物質に関する取り組みについて
- らでぃっしゅぼーや(ネットスーパー。作付け前の土壌分析、出荷前のサンプル分析、納品前のサンプル分析。6月下旬からさらに検査体制を強化予定。農林水産省の食べて応援しよう!フェアに参加中) - 今後の放射性物質の検査体制について
- 大地を守る会(ネットスーパー。1988年から放射能測定を行ってきた。5月までは既存の体制強化と簡易検出器の増量、6月以降は精度の高い測定装置を順次導入して検査体制強化予定) - 食品の放射能汚染につきまして
- 東都生協(個人宅配ありのスーパー。1988年から放射能測定を行ってきた。自主検査は不定期に1日3〜4品目について行っているもよう) - 放射性物質の農畜水産物への影響に関する当面の対応について(2011/6/2)
- グリーンコープ(ネットスーパー。2011/06/23電話確認 現在、外部委託で1日2品目までの食品をサンプリング検査。結果が出るまでに早くて1週間かかる。今後は独自に機材を購入して検査体制を強化する予定) - 残留放射能検査の結果をお知らせします(vol.1)
- ナチュラルハーモニー(ネットスーパー。数日おきに数品目ずつ専門機関による検査を実施) - 福島第一原子力発電所 震災・事故による農産物に関わる情報公開
- 生活クラブ - (ネットスーパー。現在委託による自主検査を行っている。9月から2箇所のデリバリーセンターにて食品放射能測定装置を配備し、ほぼ前品目を対象とする物流品放射能検査を開始する予定) - 第22回総会で決定した「原発対応」について
- パルシステム(ネットスーパー。数日おきに数品目ずつ自主検査を行うと同時に、暫定規制値の見直しを政府に求めている) - 放射性物質の食品汚染への対応について
- コープ自然派(ネットスーパー。ガイガーカウンターによる簡易自主検査と、精密な測定が必要なものは専門測定期間による測定を随時実施) - 福島原発事故による放射能汚染に関する基本見解(その3)
- 成城石井(スーパー)Twitterで肉にガイガーカウンターをあてて検査をしている、関東以外のものを仕入れていく方針があるとの情報があったので2011/07/01にお客様相談室に電話で確認したところ、原発事故以降特に計測を強化しているとか、仕入先を変えているということはしていない。仕入先については法律で禁じられているし、肉の計測については食品の表面にガイガーカウンターをあてても正確に計測することは難しいだろう。とのことでした。ただ、広い地域からまんべんなく食材を仕入れているので、選択肢の幅が広いのは魅力ですね。
- 常総生協(スーパー)Twitterで情報を寄せていただき、2011/07/14 電話で確認。「小さいお子様セット」の野菜は京都を中心に仕入れをしている。普通の野菜商品は、放射性セシウムの検査を行い、ベクレル表記をした近県産のものが届く。農地の測定も始め、今後検査は拡大していく予定とのこと。この生協は4月末に、組合員と職員、地域の産婦人科と協力して母乳検査を行ったところ。HPには情報は少ないが、対応は親切かつしっかりしていて、頼もしい感じだった。生協に加入を希望の場合は、HPに掲載されている電話番号等に連絡をすると、説明に来てもらえるとのこと。