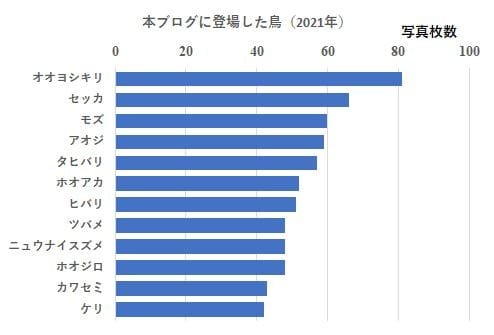奈良散策 第324弾
昨日(12月30日)の午前中に家族と散策に出てみました。日がさして、ちょっと温かそうな気がしたのですが、いざ、外に出てみると、風が強く、しかも途中から曇ってきて、大変寒くなりました。それで、早々と家に戻りました。その途中でちょっとだけ撮った写真です。



途中で見た花です。たぶん、ニンジンではないかと思います。

これはツグミ。寒かったのですが、鳥はツグミを始めとして、ムクドリ、スズメなどが飛び回っていました。




車で走っていると、以前見ていた蓮池が緑色に見えたというので行ってみました。ハスはすっかり枯れてしまい、水の上に水草がいっぱい生えていました。ハスの収穫をした様子も見えないので、放置されているのかもしれません。


そして、蟹川水門に着きました。いつ見ても立派な建物です。これが水門だとは到底思われません。

そして、「蟹す」という文字もありました。以前、なにこれ珍百景に登場した字です。




佐保川にクサシギがいました。ちょっと撮影してから、寒いので引き返しました。



途中、ケリがいました。

そして、アオサギも。


あっ、そういや、このタネツケをまだ調べていなかったなと思い出して採取しました。

根出葉は消えていました。下の方の葉の頂葉は深裂しています。小葉も深く切れ込んでいます。

花は小さく、莢(さや)は細長いです。

花弁は2mm程度の大きさです。

種はまだ熟していませんでした。
というような情報から調べてみました。「帰化&外来植物950種」に載っている検索表では、根出葉なし→茎の毛なし→先端の葉は小葉より大きく深く切れ込む、と進み、種子に翼があればコタネツケバナ、なければニワサキタネツケバナとなります。「図説植物検索ハンドブック」を見ると、コタネツケバナは花弁長2mm、果実に毛なし、果柄短い、種子縁に膜状翼となっています。それで、コタネツケバナの可能性が高いかなと思ったのですが、ネットを見ると、どうもそれほど単純ではないようです。「帰化&外来植物950種」では、コタネツケバナとなっていますが、学名はCardamine kokaiensis、「図説植物検索ハンドブック」では学名が出ていないのですが、コタネツケバナ(コカイタネツケバナ)となっています。ネットを探していると、九州オープンユニバーシティの「日本の野生植物総点検プロジェクト タネツケバナ属 Cardamine」というサイトには、コタネツケバナ C. parvifloraの国内への帰化は確認されていない。さらに、「新種コカイタネツケバナを探そう!」となっています。春になって、種が熟すのを待って翼の有無を調べてみる以外に、もう少しタネツケバナ属自体も調べてみる必要がありそうです。