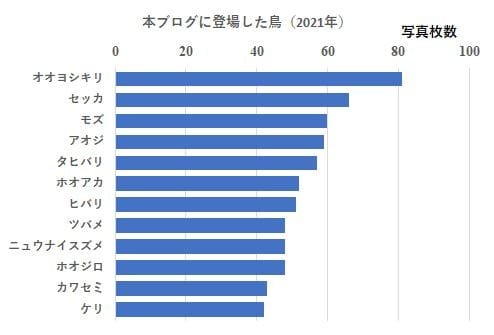今日は寒くて散歩には行きませんでした。それで、昨年撮った写真から目についたものを集めてみました。今日はトンボ編です。

ムスジイトトンボ(5/26撮影)。ここ大和郡山市は金魚の養殖で有名です。それで、町の周囲には広い範囲で養魚池があり、また、ため池も多数あります。池と養魚池や田んぼを結ぶ用水路も縦横無尽に走っていて、また、佐保川、蟹川、地蔵院川、富雄川などの河川もあります。こんなに水が豊かな土地なので、きっとトンボは多いだろうと期待していたのですが、昨年に見たトンボは全部で24種。思ったほどいませんでした。イトトンボではこのムスジイトトンボが珍しいなと思いました。ムスジイトトンボの写真は5月18日から31日まで撮りました。

アオモンイトトンボ(5/26撮影)。一方、このアオモンイトトンボは大量にいました。メスには緑色型(同色型)と赤色型(異色型)があり、同色型はオスとまったく同じ色なので、パッと見ただけではよく分かりません。アオモンイトトンボとムスイイトトンボの見分け方についてはこちらに書きました。撮影できた期間は5月14日から9月25日まで。

ウチワヤンマ(6/20撮影)。ウチワヤンマも養魚池、ため池でよく見かけました。撮影できた期間は5月30日から8月11日。

タイワンウチワヤンマ(7/22撮影)。たくさんいるウチワヤンマの中にタイワンウチワヤンマが混じっていることは、コメントをいただくまでは気が付きませんでした。その後、気をつけて見ていったのですが、見たのは2回だけでした。うちわ状突起の全体が黒いのでウチワヤンマとは見分けられます。それにしても、この2種以外にサナエトンボにはまったく出会えませんでした。

コフキトンボ(5/18撮影)。コフキトンボはこれまでほとんど見たことがなかったのですが、こちらに来たらコフキトンボだらけです。シオカラトンボよりも数がずっと多くて、養魚池ではコフキトンボが優勢で、シオカラトンボは脇の用水路に追いやられていました。見た期間も5月14日から10月15日までと大変長かったです。

マイコアカネ(10/6撮影)。秋になると、アキアカネ、ナツアカネ、リスアカネ、コノシメトンボ、マイコアカネに出会えましたが、この中ではマイコアカネが一番珍しかったです。ほぼ決まったところにしかいなかったのですが、そこに行くと必ず見ることができました。撮影できた期間は10月6日から30日。

チョウトンボ(7/9撮影)。チョウトンボは以前にもよく見ていたので、別に珍しくはなかったのですが、夕方、見に行ったら、群れになって止まっていたのが印象的でした。その時のブログはこちら。
雑談1)コロナに関連してウイルスの基礎的な勉強をしてきたのですが、ほぼ終わりになりました。最後、細胞内でコロナウイルスが再構成され、出芽する部分がどうもはっきりしないのですが、この辺りの研究がかなり少ないようなので仕方がないかもしれません。ウイルスやコロナウイルスの一般的な勉強が終わったので、今後はオミクロン株の基礎的なデータを集めたり、人体の免疫応答の勉強をしてみようかと思っています。
雑談2)先日、換気について調べ、ちょっとしたシミュレーションができるようになったので、自分の家の換気の具合を調べてみようと思って、CO2濃度測定器を購入してみました。これは二酸化炭素O=C=Oの非対称伸縮振動2350cm-1の吸収を4.26μmの赤外線で調べる器械です。絶対値の正確性は分かりませんが、普段は500~900ppmくらいの値を示します。台所でガスを使うと1000ppmを越えることもあります。清浄な空気の基準が1000ppmなので、きわどい所ですね。

ムスジイトトンボ(5/26撮影)。ここ大和郡山市は金魚の養殖で有名です。それで、町の周囲には広い範囲で養魚池があり、また、ため池も多数あります。池と養魚池や田んぼを結ぶ用水路も縦横無尽に走っていて、また、佐保川、蟹川、地蔵院川、富雄川などの河川もあります。こんなに水が豊かな土地なので、きっとトンボは多いだろうと期待していたのですが、昨年に見たトンボは全部で24種。思ったほどいませんでした。イトトンボではこのムスジイトトンボが珍しいなと思いました。ムスジイトトンボの写真は5月18日から31日まで撮りました。

アオモンイトトンボ(5/26撮影)。一方、このアオモンイトトンボは大量にいました。メスには緑色型(同色型)と赤色型(異色型)があり、同色型はオスとまったく同じ色なので、パッと見ただけではよく分かりません。アオモンイトトンボとムスイイトトンボの見分け方についてはこちらに書きました。撮影できた期間は5月14日から9月25日まで。

ウチワヤンマ(6/20撮影)。ウチワヤンマも養魚池、ため池でよく見かけました。撮影できた期間は5月30日から8月11日。

タイワンウチワヤンマ(7/22撮影)。たくさんいるウチワヤンマの中にタイワンウチワヤンマが混じっていることは、コメントをいただくまでは気が付きませんでした。その後、気をつけて見ていったのですが、見たのは2回だけでした。うちわ状突起の全体が黒いのでウチワヤンマとは見分けられます。それにしても、この2種以外にサナエトンボにはまったく出会えませんでした。

コフキトンボ(5/18撮影)。コフキトンボはこれまでほとんど見たことがなかったのですが、こちらに来たらコフキトンボだらけです。シオカラトンボよりも数がずっと多くて、養魚池ではコフキトンボが優勢で、シオカラトンボは脇の用水路に追いやられていました。見た期間も5月14日から10月15日までと大変長かったです。

マイコアカネ(10/6撮影)。秋になると、アキアカネ、ナツアカネ、リスアカネ、コノシメトンボ、マイコアカネに出会えましたが、この中ではマイコアカネが一番珍しかったです。ほぼ決まったところにしかいなかったのですが、そこに行くと必ず見ることができました。撮影できた期間は10月6日から30日。

チョウトンボ(7/9撮影)。チョウトンボは以前にもよく見ていたので、別に珍しくはなかったのですが、夕方、見に行ったら、群れになって止まっていたのが印象的でした。その時のブログはこちら。
雑談1)コロナに関連してウイルスの基礎的な勉強をしてきたのですが、ほぼ終わりになりました。最後、細胞内でコロナウイルスが再構成され、出芽する部分がどうもはっきりしないのですが、この辺りの研究がかなり少ないようなので仕方がないかもしれません。ウイルスやコロナウイルスの一般的な勉強が終わったので、今後はオミクロン株の基礎的なデータを集めたり、人体の免疫応答の勉強をしてみようかと思っています。
雑談2)先日、換気について調べ、ちょっとしたシミュレーションができるようになったので、自分の家の換気の具合を調べてみようと思って、CO2濃度測定器を購入してみました。これは二酸化炭素O=C=Oの非対称伸縮振動2350cm-1の吸収を4.26μmの赤外線で調べる器械です。絶対値の正確性は分かりませんが、普段は500~900ppmくらいの値を示します。台所でガスを使うと1000ppmを越えることもあります。清浄な空気の基準が1000ppmなので、きわどい所ですね。