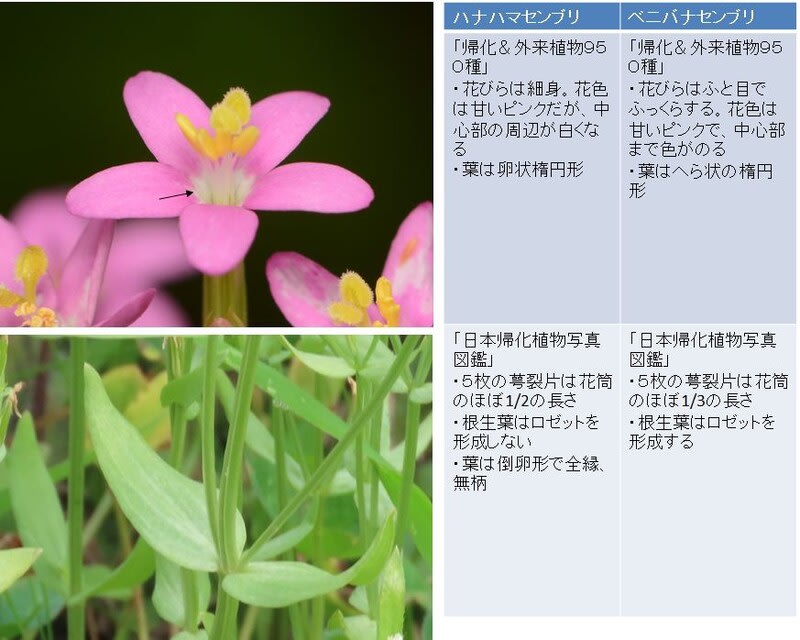奈良散策 第156弾
7月21日朝の散歩のときに撮った写真です。3日ほど前、番条環濠に行ったときに、アマサギの群れを見たので、この日はもう一度確かめに行きました。アマサギの群れは見つからなかったのですが、家を出てすぐのところでアマサギとセッカを写すことができました。

出発前にマンションの廊下で
ウンモンスズメを見つけました。こちらに来てから半年になるのですが、蛾は20種ほどしか見ていません。こんなに少ないものかなと驚いています。

これは
マメコガネ。





佐保川に向かって歩いていたら、近くの草むらに
セッカが降りてきました。ちょうどNIKON P950を持っていたので、一脚を伸ばしてできるだけ固定して撮りました。まあまあでしょうか。

ふと、反対側を見ると、田んぼの中で
アマサギと
ダイサギがいました。この日はそもそもアマサギを見に行くつもりだったので、こんなところで見れるとは思いませんでした。



一応、写したのですが、写真は今一歩。

こちらは
ダイサギ。


佐保川を渡るときに上から撮りました。よく見ると、口ひげが生えているので、
コイでしょうね。


橋を渡ってから見た花です。これはガウラとか、
ハクチョウソウとか呼ばれている栽培種です。もともと、Gaura lindheimeriという名前だったのでガウラと呼ばれていたのですが、現在の学名はOenothera lindheimeriと属名が変わっていました。「日本帰化植物写真図鑑第2巻」には、ヤマモモソウという和名で載っていました。北米原産で、観賞用に栽培されていて、道端や河川敷で見られるのはワイルドフラワーとして播種されたものに由来することが多いとのことです。

これから「下ツ道」を歩きます。この道は平城京から藤原京までを結ぶ古代の幹線道路です。


これは
カボチャ。


大和郡山市では
イチジクの産地でもあるので、あちこちで植えられています。木の茂っているところが番町環濠内の熊野神社です。この間、アマサギの群れを見たのは、ここからちょっと北側の田んぼだったのですが、この日は見つかりませんでした。それで、菩提仙川沿いに佐保川まで歩きました。

セミがうるさく鳴いていたのですが、やっと
アブラゼミの姿を見つけました。

そのすぐ横に
ニイニイゼミが。ニイニイゼミはまだ写真がなかったので、1種ゲット。


佐保川に着くと、
キタテハがいました。

そして、
ツマグロヒョウモン。

最後は、土手で見つけた
ヤノネボンテンカです。「日本帰化植物写真図鑑第2巻」によると、南アメリカ原産で、もともと園芸植物として利用されたものが逸脱しているようです。
雑談1)ブログに出した生き物の写真のデータベースが出来上がったので、これをどのように使おうかと考えていたのですが、大和郡山に来てから半年、その間に撮った写真をまとめた写真集というか手作り図鑑のようなものの暫定版を作ろうと思い立ちました。動物が340種、植物が310種なので、そこそこのものが作れるかなと思って、今日は、以前オンデマンド印刷のときに使ったA5版のテンプレートを使って鳥の写真を入れてみました。ついでに大和郡山の史跡や産物などを紹介した冊子なんかも作るとよいかななんて思ったりして。
雑談2)重いカメラを持って歩き回っていたら、胸の筋肉を傷めてしまいました。たぶん、炎症はもう治まっていると思うのですが、少し動かすとまだ痛みが出てしまいます。少しずつリハビリをしないといけないのでしょう。それ以来、一眼レフか、NIKON P950のどちらかだけを持って出かけているのですが、やはり望遠と接写は両方必要なことが多いので困っています。以前、そのようなことを書いたら、Neotitiさんから、ウェストバッグはどうかと教えていただきました。それ以来、ネットで見たりしているのですが、やはり実物を見ないと何とも言えません。そこで、カメラ屋さんを探しているのですが、奈良県にはカメラ用品を売っている大きな店はないのかなぁ。