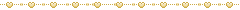お待たせ、しました。
やっと出来ました。
長かったなーーーー。
少々、前書きを。
このお話のもとになってるのは、「cinematic」です。
ご依頼を頂いたから、というのもありますが、
これを歌うすばるの、やわらかな優しい声が、大好きだったから。
それこそ、いろんなシーンを妄想してました。
いろんなシチュエーションで、彼が私を愛してくれたから、
だから、すぐに小説にできる、と思ったんです。
最初は。
なのに、途中で、
彼が、ぱたりと、動かなくなりました。
それこそ、手も足も、身動き一つとれない状況になってしまいました。
ここまで時間が必要だとは、思ってなかった私。
でもどうにか彼が決心してくれて、こういうお話になりました。
読んでいただけたら、嬉しいです。
あ。
ヤプログさんがリニューアルして分かったことのひとつですが。
ここ、携帯からご覧の方が多いみたいなので、注意事項を。
小説、という形態上、ページ数が多くなってますので、申し訳ありません。
出来れば、飽きずに最後までお付き合いください。
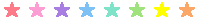
お気に召しましたら、
関ジャニWEBランキング
にほんブログ村ランキング
ぽちんっと押して頂けると、とっても嬉しいです。
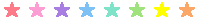
STORY.33 風色の景色
ひとつ、
ふたつ、みっつ。
小さな寝息がかかる。
俺の左の腕の中、安心しきったように眠る彼女の温もりを抱いて、
闇に目をこらす。
ぼんやりと灯るナイトランプの、オレンジ色の光が、
うっすらと、彼女の横顔を浮かびあがらせる。
起こさないように、そっと、俺は彼女の頬を撫でる。
柔らかくて、なめらかな彼女の肌を、俺の指先が滑ってゆく。
髪が揺れて、彼女の香りがたつ。
彼女の体温と交じって、それは、いっそう俺の中に流れ込んでくる。
愛しきもの。
愛すべきもの。
昔やったら、
若いころやったら、
邪魔くさくてしかたなかった、
頼られる、という責任感。
それが、大切なことやって気づいたんは、
気づかせてくれたんは、
この温もりやったんやなと、想う。
無条件に、俺だけを頼ってくる、
無条件に、俺だけを信じてる、
無条件に、俺だけを見つめてる。
ここに辿り着くまでに、
何度もケンカして、
何度も不満を言いあって、
何度も互いの気持ちをすりよせて、
互いの好きなもん、嫌いなもん、
許しあえるもん、
どうやっても許せへんもん、
確かめ合ってきた。
その時間だけは、俺らを裏切らへんから、
ここからも、繋がっていけると信じられる。
それを、どうやって伝えたら、ええ?
こうやって抱き合うだけやなくて、
ここからの時間もずっと、お前だけ信じてると告げるには。
ロマンティックなシチュエーションを演出せな、あかんのかな?
俺は、部屋の片隅に置いた自分のバッグの中身を、思い浮かべた。
前にぶらっと二人で歩いた街角の、
彼女がふと足を止めたショーウィンドウの中で、
それは、ひときわ華やかな輝きを放ってた。
「欲しいんか?」って訊いた俺に、
「いつかは、ね」って返した彼女。
それきり忘れてしまってもいいような、他愛のない会話。
あの時、すんなり買って渡してやったら、
今、こんな風にもどかしいカンジになることもなかったんやろけど。
赤いリボンをかけてもらった、小さな白い小箱。
あれをこいつに渡すタイミング。
自然なカンジで渡したいから。
気負わずに、さらっと受け取って欲しいから。
何気ない時間を、これからも、このまま続けたいから。
俺はぼんやりと天井を見つめる。
次第に俺を覆い尽くす、静寂な闇。
朝が来たら、
日が昇ったら、
そしたら・・・・・・。
枕もとの携帯が、軽やかに鳴り続けてる。
ぼんやりとした意識の奥で、俺は、それを聞いた。
『時間・・・? なんの?』
彼女がかけたアラームの音。
『こいつ、今日、仕事やったっけ?』
隣の彼女が、ゆっくりと手を伸ばして、音を止めた。
「おはよう」
俺の顔を覗き込む彼女の顔。
「んんん・・・なんでぇ?」
「朝、だもん」
待てって、おい。
「もうちっと、寝ようや」
俺の顔の上にある彼女の唇を引き寄せる。
「んん…」
柔らかくて、温かな感触。
指にからみつく細い絹の髪が、俺の頬をくすぐる。
そのままもたれかかってくる香りが、
ひととき俺の肌に馴染んで、ひときわ強い芳香を放つ。
ゆるやかに、互いをいたわり合う時間。
波立つ欲望の淵で、声なき声が求め合う。
俺は彼女の中に、俺を見つける。
彼女は俺の中で、彼女を取り戻す。
この瞬間に、言葉は、いらない。
いらないんだ、言葉は。
ただ、二人、抱きあうだけで、
繋がるだけで、
いいんだ。
カシャン、
カツン、
ガ、ガガ、ガガガッ、
シャー、
キュッ、
ポタン、
カチャッ、
・・・いつのまに、また眠ったんやろう。
小さすぎるほどのカウンターキッチンから聞こえる、さまざまな音が、
俺を眠りから呼び起こした。
窓から差し込んでいる暖かな光と、
彼女が立てる音に混じって、やがて香ってくる、苦い香り。
一人暮らしの、ロクに台所用具すらない、あのキッチンに、
二人で最初に選んだんは、
今、彼女が使ってるコーヒーメーカーやったっけ。
彼女が近づいてくる音がする。
俺は、また、目を閉じる。
「まだ、寝てるの?」
ベッドの端に腰かけた彼女を、すばやく抱きよせる。
「キャッ」
小さな悲鳴を上げた彼女が、俺に倒れこんでくる。
「おはよ」
俺は彼女のおでこに、軽く、口付ける。
彼女が俺を見上げて、
「おはよう。・・・っていっても、もう、お昼に近いけどね」
そう言って、微笑った。
こいつの、こういう表情、
奥に恥ずかしさを隠した、
はにかんだような、テレ隠しの笑顔、
好き、なんだよな。
「起きるでしょ? コーヒー、入ってるよ」
「ん・・・」
身体を起こした俺の目に映り込んだのは・・・。
白いソファに、俺。
低めのテーブルに、二つのマグカップ。
向かい合う形の彼女は、ラグの上に置かれたクッションにもたれる。
大きめの、赤い赤いカバーのかかった、ビーズ入りのクッションは、
シンプルに仕立てた部屋の中で、ひときわ鮮やかに色を添える。
俺はリモコンを手にとって、コンポのスイッチを入れた。
小さな小さな音で、流れだす音楽。
ロックナンバーにしては、少しスローなテンポで、
聞き取れないくらいにかすかな声のボーカルが、響いてる。
楽器としての声、
出しゃばらない、かといって紛れこみもしない、
音の一翼を担ってる声。
自分が、どんなCDを持ってるかさえ、
もうわからんようになるくらいに、雑多なジャンルと数やけど。
そん中でも、これは・・・
「これ、この曲、好きだな」
コーヒーを冷ますように、ふうっとカップを吹きながら、彼女が言った。
「音がどうとか、コードがどうとか、難しいこと、わかんないけど」
「うん・・・」
「好きか嫌いか、って言ったら、好き」
「そんでええよ」
音楽なんて、そんなもんや。
好きか嫌いか。
すんなり耳に馴染むかどうか、だけや。
それは男と女にもいえることやろ。
肌に馴染むかどうか、
心に馴染むかどうか。
必要なんは、そんなシンプルなことだけや。
ごちゃごちゃ飾り立てたって、しゃあない。
俺は、彼女が淹れたコーヒーを口に運ぶ。
ひとくち、また、ひとくち。
ゆっくりと、身体に沁みて広がってくるコーヒーの苦さ。
彼女が淹れてくれるコーヒーは、
いっつもちょっとだけ、アメリカンっぽい。
ミルクも砂糖も入れんと飲む俺には、物足りなくもあって。
だから、つい、
もう一杯、って思ってまうのかな。
湯気の向こう側で、
彼女が、窓の外に視線をそらした。
カーテンを揺らす風が、かすかな音楽になって、部屋を舞う。
俺の目に映るのは、
青い青い空に、掃いたような白い雲が、ひとすじ。
たぶん、彼女の目に映るのも、同じ景色。
こうして、同じ景色の記憶を、
ゆっくりとひとつずつ増やしていきたいと思えるのは、
相手が彼女やから、やんな。
他の誰にも代わりはきかん。
俺と、
彼女と、
ふたりだけの。
筋書きのない、風の通り道。
「ほんなら、これは?」
俺は、赤いリボンの小箱をぽんっとテーブルに置く。
「なに?これ」
「開けてみたらええやん」
彼女は、カップをテーブルに置くと、その小箱を手に取った。
「開けてもいいの?」
「ん」
彼女の手で、スルリ、と、ほどけたリボン。
箱を開けた彼女の手が止まる。
彼女の目が、箱の中の一点を見つめて、
それからゆっくりと、こっちを向いた。
「本気?」
「嘘は、キライやねん。知ってるやろ?」
「うん」
言いながら、彼女はまた、小箱の中身に目を落とした。
俺は、おそるおそる、彼女の横顔に訊いてみる。
「好き?それとも・・・キライ?」
ひととき、風が揺れる。
俺を見上げた彼女の顔が、静かに表情を変えた。
俺の大好きな、あの表情に。
FIN.
やっと出来ました。
長かったなーーーー。
少々、前書きを。
このお話のもとになってるのは、「cinematic」です。
ご依頼を頂いたから、というのもありますが、
これを歌うすばるの、やわらかな優しい声が、大好きだったから。
それこそ、いろんなシーンを妄想してました。
いろんなシチュエーションで、彼が私を愛してくれたから、
だから、すぐに小説にできる、と思ったんです。
最初は。
なのに、途中で、
彼が、ぱたりと、動かなくなりました。
それこそ、手も足も、身動き一つとれない状況になってしまいました。
ここまで時間が必要だとは、思ってなかった私。
でもどうにか彼が決心してくれて、こういうお話になりました。
読んでいただけたら、嬉しいです。
あ。
ヤプログさんがリニューアルして分かったことのひとつですが。
ここ、携帯からご覧の方が多いみたいなので、注意事項を。
小説、という形態上、ページ数が多くなってますので、申し訳ありません。
出来れば、飽きずに最後までお付き合いください。
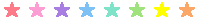
お気に召しましたら、
関ジャニWEBランキング
にほんブログ村ランキング
ぽちんっと押して頂けると、とっても嬉しいです。
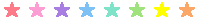
STORY.33 風色の景色
ひとつ、
ふたつ、みっつ。
小さな寝息がかかる。
俺の左の腕の中、安心しきったように眠る彼女の温もりを抱いて、
闇に目をこらす。
ぼんやりと灯るナイトランプの、オレンジ色の光が、
うっすらと、彼女の横顔を浮かびあがらせる。
起こさないように、そっと、俺は彼女の頬を撫でる。
柔らかくて、なめらかな彼女の肌を、俺の指先が滑ってゆく。
髪が揺れて、彼女の香りがたつ。
彼女の体温と交じって、それは、いっそう俺の中に流れ込んでくる。
愛しきもの。
愛すべきもの。
昔やったら、
若いころやったら、
邪魔くさくてしかたなかった、
頼られる、という責任感。
それが、大切なことやって気づいたんは、
気づかせてくれたんは、
この温もりやったんやなと、想う。
無条件に、俺だけを頼ってくる、
無条件に、俺だけを信じてる、
無条件に、俺だけを見つめてる。
ここに辿り着くまでに、
何度もケンカして、
何度も不満を言いあって、
何度も互いの気持ちをすりよせて、
互いの好きなもん、嫌いなもん、
許しあえるもん、
どうやっても許せへんもん、
確かめ合ってきた。
その時間だけは、俺らを裏切らへんから、
ここからも、繋がっていけると信じられる。
それを、どうやって伝えたら、ええ?
こうやって抱き合うだけやなくて、
ここからの時間もずっと、お前だけ信じてると告げるには。
ロマンティックなシチュエーションを演出せな、あかんのかな?
俺は、部屋の片隅に置いた自分のバッグの中身を、思い浮かべた。
前にぶらっと二人で歩いた街角の、
彼女がふと足を止めたショーウィンドウの中で、
それは、ひときわ華やかな輝きを放ってた。
「欲しいんか?」って訊いた俺に、
「いつかは、ね」って返した彼女。
それきり忘れてしまってもいいような、他愛のない会話。
あの時、すんなり買って渡してやったら、
今、こんな風にもどかしいカンジになることもなかったんやろけど。
赤いリボンをかけてもらった、小さな白い小箱。
あれをこいつに渡すタイミング。
自然なカンジで渡したいから。
気負わずに、さらっと受け取って欲しいから。
何気ない時間を、これからも、このまま続けたいから。
俺はぼんやりと天井を見つめる。
次第に俺を覆い尽くす、静寂な闇。
朝が来たら、
日が昇ったら、
そしたら・・・・・・。
枕もとの携帯が、軽やかに鳴り続けてる。
ぼんやりとした意識の奥で、俺は、それを聞いた。
『時間・・・? なんの?』
彼女がかけたアラームの音。
『こいつ、今日、仕事やったっけ?』
隣の彼女が、ゆっくりと手を伸ばして、音を止めた。
「おはよう」
俺の顔を覗き込む彼女の顔。
「んんん・・・なんでぇ?」
「朝、だもん」
待てって、おい。
「もうちっと、寝ようや」
俺の顔の上にある彼女の唇を引き寄せる。
「んん…」
柔らかくて、温かな感触。
指にからみつく細い絹の髪が、俺の頬をくすぐる。
そのままもたれかかってくる香りが、
ひととき俺の肌に馴染んで、ひときわ強い芳香を放つ。
ゆるやかに、互いをいたわり合う時間。
波立つ欲望の淵で、声なき声が求め合う。
俺は彼女の中に、俺を見つける。
彼女は俺の中で、彼女を取り戻す。
この瞬間に、言葉は、いらない。
いらないんだ、言葉は。
ただ、二人、抱きあうだけで、
繋がるだけで、
いいんだ。
カシャン、
カツン、
ガ、ガガ、ガガガッ、
シャー、
キュッ、
ポタン、
カチャッ、
・・・いつのまに、また眠ったんやろう。
小さすぎるほどのカウンターキッチンから聞こえる、さまざまな音が、
俺を眠りから呼び起こした。
窓から差し込んでいる暖かな光と、
彼女が立てる音に混じって、やがて香ってくる、苦い香り。
一人暮らしの、ロクに台所用具すらない、あのキッチンに、
二人で最初に選んだんは、
今、彼女が使ってるコーヒーメーカーやったっけ。
彼女が近づいてくる音がする。
俺は、また、目を閉じる。
「まだ、寝てるの?」
ベッドの端に腰かけた彼女を、すばやく抱きよせる。
「キャッ」
小さな悲鳴を上げた彼女が、俺に倒れこんでくる。
「おはよ」
俺は彼女のおでこに、軽く、口付ける。
彼女が俺を見上げて、
「おはよう。・・・っていっても、もう、お昼に近いけどね」
そう言って、微笑った。
こいつの、こういう表情、
奥に恥ずかしさを隠した、
はにかんだような、テレ隠しの笑顔、
好き、なんだよな。
「起きるでしょ? コーヒー、入ってるよ」
「ん・・・」
身体を起こした俺の目に映り込んだのは・・・。
白いソファに、俺。
低めのテーブルに、二つのマグカップ。
向かい合う形の彼女は、ラグの上に置かれたクッションにもたれる。
大きめの、赤い赤いカバーのかかった、ビーズ入りのクッションは、
シンプルに仕立てた部屋の中で、ひときわ鮮やかに色を添える。
俺はリモコンを手にとって、コンポのスイッチを入れた。
小さな小さな音で、流れだす音楽。
ロックナンバーにしては、少しスローなテンポで、
聞き取れないくらいにかすかな声のボーカルが、響いてる。
楽器としての声、
出しゃばらない、かといって紛れこみもしない、
音の一翼を担ってる声。
自分が、どんなCDを持ってるかさえ、
もうわからんようになるくらいに、雑多なジャンルと数やけど。
そん中でも、これは・・・
「これ、この曲、好きだな」
コーヒーを冷ますように、ふうっとカップを吹きながら、彼女が言った。
「音がどうとか、コードがどうとか、難しいこと、わかんないけど」
「うん・・・」
「好きか嫌いか、って言ったら、好き」
「そんでええよ」
音楽なんて、そんなもんや。
好きか嫌いか。
すんなり耳に馴染むかどうか、だけや。
それは男と女にもいえることやろ。
肌に馴染むかどうか、
心に馴染むかどうか。
必要なんは、そんなシンプルなことだけや。
ごちゃごちゃ飾り立てたって、しゃあない。
俺は、彼女が淹れたコーヒーを口に運ぶ。
ひとくち、また、ひとくち。
ゆっくりと、身体に沁みて広がってくるコーヒーの苦さ。
彼女が淹れてくれるコーヒーは、
いっつもちょっとだけ、アメリカンっぽい。
ミルクも砂糖も入れんと飲む俺には、物足りなくもあって。
だから、つい、
もう一杯、って思ってまうのかな。
湯気の向こう側で、
彼女が、窓の外に視線をそらした。
カーテンを揺らす風が、かすかな音楽になって、部屋を舞う。
俺の目に映るのは、
青い青い空に、掃いたような白い雲が、ひとすじ。
たぶん、彼女の目に映るのも、同じ景色。
こうして、同じ景色の記憶を、
ゆっくりとひとつずつ増やしていきたいと思えるのは、
相手が彼女やから、やんな。
他の誰にも代わりはきかん。
俺と、
彼女と、
ふたりだけの。
筋書きのない、風の通り道。
「ほんなら、これは?」
俺は、赤いリボンの小箱をぽんっとテーブルに置く。
「なに?これ」
「開けてみたらええやん」
彼女は、カップをテーブルに置くと、その小箱を手に取った。
「開けてもいいの?」
「ん」
彼女の手で、スルリ、と、ほどけたリボン。
箱を開けた彼女の手が止まる。
彼女の目が、箱の中の一点を見つめて、
それからゆっくりと、こっちを向いた。
「本気?」
「嘘は、キライやねん。知ってるやろ?」
「うん」
言いながら、彼女はまた、小箱の中身に目を落とした。
俺は、おそるおそる、彼女の横顔に訊いてみる。
「好き?それとも・・・キライ?」
ひととき、風が揺れる。
俺を見上げた彼女の顔が、静かに表情を変えた。
俺の大好きな、あの表情に。
FIN.