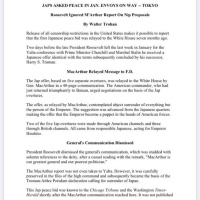世間と個人の折り合いは、キョロキョロして決めるのがほとんどの普通の人の行動基準だろう。なにせミクロな世間は一つとは限らないのだから、自分の所属世間がどこなのかというところから人生が始まる。夏目漱石が描いた正義漢の坊っちゃんにとっては赤シャツや野太鼓は俗物の極み、でもそれは小説の中の世界のこと、現実は自己保身を正当化する俗物だらけの状態(情実と建前、応酬とゴマスリ)を肯定しなければ世間は成り立たない。むしろ赤シャツや野太鼓が多数派なのです。
坊っちゃんも世間を選択して丸くなることを強いられる。この強そうなものに巻かれる原始的な精神があれば日本で十分暮らしてゆける。その長いものを身をもって知らされ、所属階層を人生で初めて強制されるのが学校である。野放しの野生馬が馬銜(はみ)を装着されるときのように教育の中で自然児ではいられない。
『錨を上げよ』を読んで 青年期前半を追記

私も作田又三と同じように資産や権力特権の世間後ろだてのない、親の期待もなければ卒業後のレールもない人生であった。中には15の時から職業と人生の終わりまでの居場所を決めている同級生もあれば、大学以降の栄達の街道を士業や官吏として別の土地にまっすぐに進んでゆく同級生もいた。
しかしそういう世間の成り行きを目に入れつつも自分は何か夢を見るように社会の階層や世間という重苦しい空気空間から自由であると思っていた。実力さえあれば生きて行ける、自分の人生の舵取りは自分だけと考えた。両親や大人の不可解な行動を見て作田同様に、たやすく人を信じて正義にたやすく命をかけられない。わたしを掠る世間はいつも敵の前ぶれだった。
人間の本質は性悪、故に性悪を前提に理想に燃えて又三の近所の兄ちゃんみたいに左翼に出家することなど性悪出家という自己矛盾だと思っていた。又三も出会っている懐かしの『おおかみヘアー』の下級生には自分はなぜかモテたが、自分にはある理想の人がいたので見向きもしなかった。
とにかくどうでもいい世間の産地、故郷釧路には帰るつもりはなく、理想の人も含め中学同級生とは極力会わないようにしていた。
この生意気な中学生は作田のように腕力で暴れてはいなかったが、むしろこの教師に説得され生徒会長などよゐこしていたのだが、反抗はせず原則と筋を通す、教師から見れば不気味で扱いにくい生徒会長だっただろう。このときミクロ世間は口汚くなんで貧乏人の息子が生徒会長などやると親に聞こえるように声をあげていた。
進路を決める時に担任の渋谷薫教諭が俺ん家の貧乏を逆手にとって特待生の待遇でスポーツだけの高校、希望学園系第一高校を受験する話をいい話だと持ってきたが、即時その場で拒否した。私にとって教師とは野生人間の敵・世間の尖兵だった。
万博も札幌オリンピックもあさま山荘事件(この時は大雪で休校になった)もリアルに同じ時代の空気を吸って作田又三とともにTV📺の前に座っていた。

そしてそれから10年後📺ではなく本当に友人が@@れる。小説の中の作田のように善悪に素直な人ほど傷ついていた。真実の行為は変形し、誠意はクズ紙がケチなトイレ紙に換えられるように、やるせない暴力だけが理想社会実現運動と利用交換されていた。華やかに万博といっしょにあけたが、若者から先に腐って行ったそんな70年代だった。