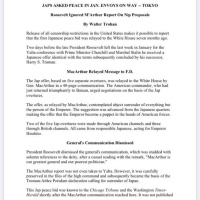私の手元にあるのはもっと古い本だが83歳の柳田國男の後書きが残る朝日新聞社版である。思い出話として神戸新聞に取材されたのが昭和32年頃だからそれから16年してまとめ直したものである。記憶力の鮮明さに驚かされるし、たまたま近所で少年時代を過ごしたということもあり、一度ここにも投稿したが
布川にいた二カ年間の話は、馬鹿馬鹿しいということさえかまわなければいくらでもある。何かにちょっと書いたが、こんな出来事もあった。小川家のいちばん奥の方に少し綺麗な土蔵が建てられており、その前に二十坪ばかりの平地があって、二、三本の木があり、その下に小さな石の祠の新しいのがあった。聞いてみると、小川という家はそのころ三代目で、初代のお爺さんは茨城の水戸の方から移住して来た偉いお医者さんであった。その人のお母さんになる老媼を祀ったのがこの石の祠だという話で、つまりお祖母さんを屋敷の神様として祀ってあった。
この祠の中がどうなっているのか、いたずらだった十四歳の私は、一度石の扉をあけてみたいと思っていた。たしか春の日だったと思う。人に見つかれば叱られるので、誰もいない時、恐る恐るそれをあけてみた。そしたら一握りくらいの大きさの、じつに綺麗な蝋石の珠が一つおさまっていた。その珠をことんとはめ込むように石が彫ってあった。後で聞いて判ったのだが、そのおばあさんが、どういうわけか、中風で寝てからその珠をしょっちゅう撫でまわしておったそうだ。それで後に、このおばあさんを記念するのには、この珠がいちばんいいといって、孫に当る人がその祠の中に収めたのだとか。そのころとしてはずいぶん新しい考え方であった。
その美しい珠をそうっと覗いたとき、フーッと興奮してしまって、何ともいえない妙な気持になって、どうしてそうしたのか今でもわからないが、私はしゃがんだまま、よく晴れた青い空を見上げたのだった。するとお星様が見えるのだ。今も鮮やかに覚えているが、じつに澄み切った青い空で、そこにたしかに数十の星を見たのである。昼間見えないはずだがと思って、子供心にいろいろ考えてみた。そのころ少しばかり天文のことを知っていたので、今ごろ見えるとしたら自分らの知っている星じゃないんだから、別にさがしまわる必要はないという心持を取り戻した。
今考えてみても、あれはたしかに、異常心理だったと思う。だれもいない所で、御幣か鏡が入っているんだろうと思ってあけたところ、そんなきれいな珠があったので、非常に強く感動したものらしい。そんなぼんやりした気分になっているその時に、突然高い空で鵯がピーッと鳴いて通った。そうしたらその拍子に身がギュッと引きしまって、初めて人心地がついたのだった。あの時に鵯が鳴かなかったら、私はあのまま気が変になっていたんじゃないかと思うのである。
両親が郷里から布川へ来るまでは、子供の癖に一際違った境遇におかれていたが、あんな風で長くいてはいけなかったかも知れない。幸いにして私はその後実際生活の苦労をしたので救われた。
それから両親、長兄夫婦と、家が複雑になったので面倒になり、私だけ先に東京に出た。明治二十四年かと思うが、二番目の兄が大学の助手兼開業医になっていたので、それを頼って上京した。そしてまた違った境遇を経たので、布川で経験した異常心理を忘れることができた。
年をとってから振り返ってみると、郷里の親に手紙を書いていなければならなかったような二カ年間が危かったような気がする。
それ以来手元に置いている。学術書ではないから堅苦しくはないが、話が飛び飛びであるから順番に読んでいて何か得るものがあるかというとそうでもないので、パラパラと開いては読み返しているのだ。
色々と今は失われた日本人の気持ちというものが記録されていてハッとすることがある。たとえば水田に下肥を入れるということは禁忌であったということ。今農業といえばなんらかの肥料を施すのは常識だが、江戸時代や明治にあってもそれは常識である。しかし下肥は別物だったということだ。下肥は二次肥料化するなど工夫はあったのであろうが、いかに米作りというものが神聖なものであったかという今は全く失われた感覚が明治の初めには残っていた。基本的に緑肥であり、田を休ませるというのが常識だったという背景には、水耕における神聖性が隠れている。
青年になる十五の儀式というものも、明治期の近代的な教育政策でできなくなってしまったことに柳田國男は無血革命だったと言っている。伝統文化と風習が文部省に壊されてしまったと考えるべき。それがちょうど國男の15歳年上の長兄(1860年生まれ?)、師範学校に行った鼎の時代(1875年:明治8年)頃に医系のエリート家族の周辺から起こってしまう。
柳田 國男(やなぎた くにお、1875年(明治8年)7月31日 - 1962年(昭和37年)8月8日)は、日本の民俗学者・官僚。