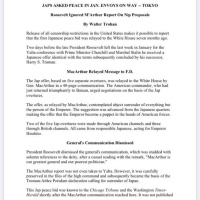『本書を執筆しながら 、私はサイエンスを知る際のワクワク感と 、高揚感 、それに加え 、なつかしさを覚えていた 。かつて私は本書に登場する数人の科学者と研究生活で深くかかわり 、ほとんど全員と学会やパ ーティなどで会い 、サイエンスを中心にさまざまな話をしたことを思い出したからだ 。現在 、私は日本に住み 、物書きとして生計を営んでいるが 、アメリカにいたころは分子生物学者であった 。本書のテ ーマである 、バイオテクノロジ ー誕生で主要な役割をはたす 、板倉啓壱は私の恩師である 。かつて私は 、 C O Hの板倉研で修行し 、博士の学位論文を 2年間で作成することができた 。板倉が指導者としても卓越していることがわかる 。私は 、東京薬科大学の 「薬化学 」講座で彼の後輩にあたり 、彼の上司は 、やがて私の上司にもなった 。また 、彼がコラボレ ーションしたディッカ ーソンは 、後に私が U C L A (カリフォルニア大学ロサンゼルス校 )でポスドクとして働いたときのボスである 。なお 、本文中では人名への敬称は省略させてもらった 。科学の研究は十中八九うまくいかないのが常である 。真の科学者はヘコたれないし 、アセることもない 。読者は 、人間が真剣に努力を続けることで大きな成果が得られることを知ってほしい 。最後に多くの有益なアドバイスをくれた P H P研究所の西村健氏に深く感謝いたします 。 生田哲 2 0 1 3年 4月 』

『ジェネンテック社の目標は 、まず 、ヒトタンパク質のバクテリアによる生産のテストとしてソマトスタチンというタンパク質の生産を行い 、つぎにインスリンに進むという二段構えであった 。』ここでリグスと日本人化学者、板倉啓壱が功績を挙げた。合成DNAが生物の中で機能することを実証したという意味で月に人類が立ったくらいソマトスタチンの大腸菌生産は時代を変える革命の瞬間である(1977年8月15日)。
アーサー・リグス(Art Riggs)が語った創業物語
『ソマトスタチンが生産されたことを確認する 。そして迎えた 8月 1 5日 。今回は見物人はいない 。アーサー・リグス(Art Riggs)と板倉のふたりだけだ 。分析が終わった 。デ ータは予測した通りだった 。こうして彼らは 、ヒトタンパク質を大腸菌につくらせた世界最初の科学者となった 。このデ ータをリグスは実験ノ ートに書いた 。騒ぐことも祝うこともなかった 。この歴史的な日の夕方 、リグスは息子を連れてかねてから約束していたドジャ ースの試合を観にいった 。』
インスリンcDNAのクローニングは1977年1~4月の間のことである。EcoRI、ライゲース、コラージェネース、X-Galここに出てくる遺伝子工学の道具立てがその後も使われ続ける。
1977年大学に入学した自分自身が将来遺伝子治療ベクター開発でこれらの道具と関わりを持つとは思ってもいないことだった。ある日同僚であり部下の鈴木要介が読んでいた科学雑誌の記事の人物に会ってみようかという腰の軽さと全くのめぐり合わせであり、難しいことはその後の飛び込み交渉の連続だった。
時代はめぐりゲノム編集の世代に入ることで、これらの道具は時代物になったが、ゲノムを直接に変更する技術はより慎重に微生物の遺伝子を管理しなければ細胞内感染細菌が容易に細胞のゲノム変異を自然界で起こすようになるというのは、種の絶滅に至るパンドラの箱を開けるようなものだ。


『ジェネンテック社の目標は 、まず 、ヒトタンパク質のバクテリアによる生産のテストとしてソマトスタチンというタンパク質の生産を行い 、つぎにインスリンに進むという二段構えであった 。』ここでリグスと日本人化学者、板倉啓壱が功績を挙げた。合成DNAが生物の中で機能することを実証したという意味で月に人類が立ったくらいソマトスタチンの大腸菌生産は時代を変える革命の瞬間である(1977年8月15日)。
アーサー・リグス(Art Riggs)が語った創業物語
『ソマトスタチンが生産されたことを確認する 。そして迎えた 8月 1 5日 。今回は見物人はいない 。アーサー・リグス(Art Riggs)と板倉のふたりだけだ 。分析が終わった 。デ ータは予測した通りだった 。こうして彼らは 、ヒトタンパク質を大腸菌につくらせた世界最初の科学者となった 。このデ ータをリグスは実験ノ ートに書いた 。騒ぐことも祝うこともなかった 。この歴史的な日の夕方 、リグスは息子を連れてかねてから約束していたドジャ ースの試合を観にいった 。』
インスリンcDNAのクローニングは1977年1~4月の間のことである。EcoRI、ライゲース、コラージェネース、X-Galここに出てくる遺伝子工学の道具立てがその後も使われ続ける。
1977年大学に入学した自分自身が将来遺伝子治療ベクター開発でこれらの道具と関わりを持つとは思ってもいないことだった。ある日同僚であり部下の鈴木要介が読んでいた科学雑誌の記事の人物に会ってみようかという腰の軽さと全くのめぐり合わせであり、難しいことはその後の飛び込み交渉の連続だった。
時代はめぐりゲノム編集の世代に入ることで、これらの道具は時代物になったが、ゲノムを直接に変更する技術はより慎重に微生物の遺伝子を管理しなければ細胞内感染細菌が容易に細胞のゲノム変異を自然界で起こすようになるというのは、種の絶滅に至るパンドラの箱を開けるようなものだ。