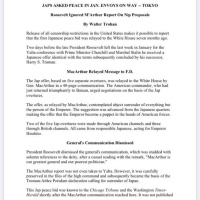以下のように90年代のイスラム政治の研究者の考えたイスラム主義の制御は全く成功しなかった。むしろ恐れていたようにハマスやヒズボラのような他のイスラム右派テロ集団のひとつが、ほとんど地元中心のグループから、より大規模で国際的な野心を持つグループへと転化した。
それが国連のカネによって運営され、イスラエルとハマスの間のガザ人質戦争に発展して今がある。むしろ資金源は国連を超えて大きくソロス オープンソサエティ財団などにまで拡大している。アメリカ合衆国を弱体に導くグレートリセットの一つの駒としてパレスチナとアフガン撤退がある。
『アメリカがイスラム教を作ったわけでも、その原理主義的な変種を作ったわけでもないと主張する人がいるかもしれない。しかしここでは、アメリカのキリスト教右派との類似を考える必要がある。
アメリカには植民地時代から、保守的で福音主義的なキリスト教徒が多数存在していた。ティモシー・ラヘイ牧師のカリフォルニア教会同盟の結成、ラヘイとジェリー・ファルウェルによるモラル・マジョリティの創設、国家政策評議会、キリスト教連合、パット・ロバートソンの放送帝国やジェームス・ドブソン博士のフォーカス・オン・ザ・ファミリーのような組織の台頭におけるこの二人と他の人々の役割などである。それまでは、保守派キリスト教徒は政治的に無機質な勢力であった。過去30年間、執拗に組織化された結果、彼らは自覚的で政治的に強力な運動となった。
同じことがイスラム右派にも当てはまる。イスラム内の反動的傾向は13世紀までさかのぼる。イスラムの初期から、蒙昧主義者、反合理主義者、コーラン直訳主義者が、より啓蒙的、進歩的、穏健な傾向と競い合っていた。最近では、イスラム反動主義者が近代化の足を引っ張り、進歩的な教育、自由化、人権に反対している。しかし、1800年代後半にジャマール・エッディーヌ・アル・アフガーニーが汎イスラム運動を創設し、1928年にハッサン・アル・バンナがエジプトでムスリム同胞団を創設し、1940年にパキスタンでアブル・アラ・マウドゥディのイスラムグループが創設されるまでは、イスラム右派はラヘイズ、ファルウェル、ロバートソンを擁していなかった。初期のイスラム主義者たちは、アメリカにおけるキリスト教右派と同じように、同じ理由で中東における文化戦争を激化させた。
キリスト教右派が裕福な右翼の献金者、特にテキサスや中西部の石油王たちから支持を得たように、イスラム右派も裕福な石油王たち、すなわちサウジアラビアや湾岸諸国の王族たちから資金援助を得た。キリスト教右派が共和党右派と政治的に都合の良い同盟を結んだように、イスラム右派もアメリカの右派外交戦略家と同様の関係を築いた。実際、キリスト教右派とイスラム右派の支持は、レーガン政権時代に見事に一致した。冷戦に目がくらんだ一部のアメリカ人は、過激なキリスト教右派の活動家や熱烈なシオニスト・イスラエル党派が、アフガニスタンでイスラム狂信者を陽気に支援していた。』p21−22
『 両者とも宗教と政治の一体化を信じており、前者はアメリカを「キリスト教国家」だと主張し、後者はイスラム教徒は全権を掌握する宗教政治的なカリフ制か、超正統的なイスラム法(シャリーア)の下での「イスラム共和国」制度によって支配される必要があると主張している。そしてどちらも、信者の盲目的な狂信を奨励している。キリスト教原理主義とイスラム原理主義の信者の間で、世界が文明の衝突に巻き込まれているように見えるのは偶然ではない。』p23
『テロとの戦争は、政治的イスラムがもたらす挑戦に対処するための、まさに間違った方法である。
この挑戦には2つの形がある。
第一に、アル・カイダによるアメリカ人の安全と安心に対する具体的な脅威であり、
第二に、中東と南アジアにおけるイスラム右派の成長によって引き起こされる、はるかに広範な政治的問題である。
アルカイダに関しては、ブッシュ政権はその脅威の大きさを故意に誇張している。アルカイダは万能の組織ではない。アメリカを破壊することも征服することもできないし、アメリカにとって存立の脅威でもない。アメリカ人を殺すことはできても、大量破壊兵器を手に入れたことはないし、今後も手に入れることはないだろう。9.11の後、米司法長官は、アルカイダは米国内に5000人もの工作員を抱えているという根拠のない告発を行ったが、米国内に多数の細胞、資産、工作員を保有しているわけではない。9.11の後に逮捕・拘留された何百人ものイスラム教徒のうち、テロリストとの関係が判明した者は一人もいなかった。9.11後3年半の間、アル・カイダ、あるいは他のイスラム系テロリストグループによる暴力行為は、ハイジャックも爆弾テロも、発砲さえも、アメリカでは一度も起きていない。アル・カイーダとイラク、あるいはイスラム世界のいかなる国家との関係も証明されなかった。
要するに、アル・カイダの脅威は管理可能なものなのだ。
通常の戦争モードで米軍を使うことは、アル・カイダを攻撃する方法ではない。アフガニスタンでの戦争は間違っていた: アルカイダの指導部を壊滅させることに失敗し、タリバンを壊滅させることにも失敗して散り散りになり、戦争で荒廃したアフガニスタンを一時的以上に安定させることにも失敗し、軍閥や元タリバンのギャングに翻弄される弱い中央政府を作り出した。さらに悪いことに、イラク戦争は見当違いで不必要だっただけでなく、ビンラディンの一味とはまったく関係のない国を標的にした。』p24−25
『中東とアジアにおけるイスラム原理主義の勢力の拡大という、より大きな問題は、はるかに複雑である。
当然ながら、第一の問題は第二の問題と関連している。イスラム右派を阻止しない限り、アルカイダが復活する可能性がある。あるいは、米軍侵攻後のイラクのように、反米的な怒りや憤りを利用してアルカイダ型の組織が新たに出現するかもしれない。
あるいは、ハマスやヒズボラのような他のイスラム右派テロ集団のひとつが、ほとんど地元中心のグループから、より大規模で国際的な野心を持つグループへと転化するかもしれない。
中東の暴力を好み、テロリズムに傾倒する集団は、過去30年間に事実上すべてのイスラム諸国で誕生した、より確立されたイスラム原理主義組織から資金援助、神学的正当化、新兵の軍団を引き出している。ストーブの上で沸騰するやかんのように、中東では政治的イスラムに関連する勢力が煮えたぎったままになっている。中東では、政治的イスラムに関連する勢力が煮えたぎったままになっており、そこから過激派が絶え間なく生まれている。
では、米国はこの熱を下げるために何ができるだろうか?イスラム主義運動の政治的温度を下げるためには?
第一にまず米国は、怒れるイスラム教徒がムスリム同胞団のような組織に慰めを求める原因となる不満を取り除くためにできることをしなければならない。もちろん、こうした不満のすべてが米国に起因するわけではないし、米国の行動によってそのすべてが和らげられたり、改善されたりするわけでもない。しかし少なくとも、米国はイスラム右派の新兵獲得能力を弱める重要な措置を取ることができる。国連、ヨーロッパ諸国、ロシアと協力することで、米国はパレスチナ人にとっての正義を保証する形でパレスチナ・イスラエル紛争を解決する手助けができる。それは他のどんな行動よりも、イスラム右派の世界的な詭弁を取り除くことになる。
第二に、米国は中東における帝国的な威信を捨てなければならない。そのためには、アフガニスタンとイラクから米軍を撤退させ、ペルシャ湾の米軍基地とサウジアラビアの施設を解体し、米海軍、軍事訓練任務、武器売却の知名度を大幅に下げる必要がある。この地域で働いたことのある米国の外交官の多くは、中東における米国の挑発的な存在が怒りと憤りを煽ることを知っている。米国はペルシャ湾にも中東にも何の主張も持っていない。将来の経済的結びつきや政治的関係は、たとえそれが米国の利益を損なうものであったとしても、この地域の国々の指導者たちによってのみ決定されうるものであり、また決定されなければならないものである。
第三に、米国は自国の嗜好をこの地域に押し付けようとすることを控えなければならない。2001年以来、米国は「より大きな中東」を米国の民主主義ビジョンに合わせるよう要求することで、計り知れない損害を与えてきた。確かに、ブッシュ政権内の急進的な理想主義者たちにとって、アラブ世界とイランの民主化を求めるブッシュの呼びかけは、主にこの地域への米国の介入を強めるための口実とみなされている。しかし、額面通りに受け取っても、この構想は、中東諸国がそれぞれのペースで、それぞれの時期に民主主義を見つけなければならないという事実を無視している。この地域の民主改革を執拗に推進することは、自滅的であり、中東の国家と国民を侮辱するものである。中東には、改革の準備が整っている国もあれば、そうでない国もある。イスラム右派に力を与え、カイロ、ダマスカス、リヤド、アルジェでムスリム同胞団が権力を握るような民主的改革は、本来の目的を果たさないだろう。新たな国家をイスラム主義者の手に渡すだけだ。米国はイスラム世界の民主化に関して、手を引かない政策を採用すべきである。
そして第4に、米国は、イランやスーダンなど、まだイスラム主義者の支配下にある中東諸国を含め、好戦的な脅しをかける傾向を捨てなければならない。イスラム主義の波はまだ頂点に達していないかもしれない。イスラム主義は数十年にわたって勢いを増してきた勢力だからだ。しかし米国は、武力による威嚇や帝国的な響きを持つ命令がイスラム主義を強化するという事実に慣れなければならない。しかし、武力による威嚇や帝国的な命令によって、イスラム主義が強化されることはあっても、弱体化することはない。
中東の真の解放には、イスラム主義に取り込まれた人々の意識を高め、教育し、近代化するために、この地域の世俗的勢力が行動を起こす必要がある。それには何十年もかかるだろうが、今始めなければならない。
イスラム教には、コーランが政治、教育、科学、文化の世界を支配しなければならないという7世紀の信念にとらわれたままでいなければならないようなものは何もない。それは、何百万人もの欺かれたイスラム教徒が、基本に忠実な原理主義が21世紀の問題や懸念に対する適切な答えであると考えるような文化を変えることを意味する。原理主義は、それがイスラム主義の形をとっていようと、アメリカのキリスト教右派やイスラエルの超正統派入植者運動の形をとっていようと、常に反動的な力である。イスラム世界では、世俗的なものと神的なものの合理的な区分は前代未聞とは言い難い。何千万人ものイスラム教徒が、アメリカで何百万人ものイスラム教徒、キリスト教徒、ユダヤ教徒がそうであるように、個人的に抱いている宗教的信条を政治から切り離すことができる。真のサイレント・マジョリティである彼らこそが、原理主義者から主導権を握らなければならない。彼らは、NGOや大学、研究センターやシンクタンクなど、西側の市民社会からの支援を求めることができるし、また受けるべきである。
中東の人々は、国家建設だけでなく、「宗教建設」にも取り組まなければならない。中東の政治的言説の温室が低くなるにつれて、イスラムの宗教学者、哲学者、社会科学者たちは、寛容で近代的なイスラムの21世紀のビジョンを打ち出すために、大きな討論の場に集うことができる。そしてそのコンセンサスは、主要都市(イスタンブール、カイロ、バグダッド、カラチ、ジャカルタ)から始まり、すべての村やモスクへと広がっていく。それはイスラム世界の教育カリキュラムを改革し、宗教大学やいわゆるマドラサを軽視し、近代的な教育を優先させることを意味する。マスメディアが盛んな場所では新しいマスメディアが必要であり、そうでない場所ではラジオ、衛星テレビ、インターネットを利用する必要がある。これには長い年月がかかるだろう。この地域を混乱に陥れている武力紛争が終結し、経済状況が着実に上向かない限り、宗教建設は実現しない。国家建設と同様、宗教建設にも長い長い時間がかかる。』p25−27
『1885年、レーガン政権の高官がホメイニ師率いるイランに対して極秘のイニシアチブ*をとるちょうど100年前、米国がイスラム原理主義者のムジャヒディンが率いるアフガニスタンでの反ソ聖戦を支援するために何十億ドルもの資金を費やす100年前、あるペルシャ系アフガン人の活動家がロンドンで英国の諜報機関や外交政策の高官と会談し、物議を醸すアイデアを提案した。イギリスは、エジプト、トルコ、ペルシャ、アフガニスタンの間で汎イスラム同盟を組織し、ロシア皇帝に対抗することに興味を示すだろうか、と。*(レーガンの意を汲んだ NSC スタッフが、イランへの武器供与の見返りに人質の解放を求め、その武器供与の利益をニカラグアの反政府勢力コントラの支援に流用したこと)
当時はグレートゲームの時代で、中央アジアの支配権をめぐってロシアとイギリスが長期にわたって帝国闘争を繰り広げていた。インドの所有者であるイギリスは、1881年にエジプトを掌握した。トルコのオスマン帝国は、現在のイラク、シリア、レバノン、ヨルダン、イスラエル、サウジアラビア、湾岸諸国などを含んでいたが、この帝国もぐらつきがあり、重要な領土を手中に収めようとしていた。部族、民族、宗教を巧みに操り、女王陛下の領域のために少数民族を互いの喉元に追いやる名人であるイギリスは、イスラム復興主義の精神を育むというアイデアに興味をそそられた。ロシアもフランスも同じ考えを持っていたが、より広い中東と南アジアに何千万人ものイスラム教徒の臣民を持つイギリスが優位に立っていた。
1885年、イギリス主導の汎イスラム同盟のアイデアを提案したのは、ジャマール・エディン・アル・アフガーニーだった。1870年代から1890年代にかけて、アフガニはイギリスの支援を受けており、インド政府の諜報機関の秘密ファイルによれば、少なくとも一度、1882年にインドで、アフガニがイギリス諜報機関の諜報員としてエジプトに行くことを公式に申し出たことが記録に残っている2。
汎イスラム教の創始者であるアフガニは、生物学的にではなく、イデオロギー的にオサマ・ビンラディンの曾祖父にあたる。右翼イスラム主義の聖書的系図を作るとすれば、次のようになるだろう: アフガーニ(1838-1897)は、アフガーニの一番弟子であり、アフガーニのメッセージを広めるのに貢献したエジプトの汎イスラム活動家、モハメッド・アブドゥ(1849-1905)を生んだ。』p28−29
『1875年から1925年までの半世紀の間に、イスラム右派の基礎は大英帝国によって固められた。アフガーニは、イギリスの庇護とイギリスを代表する東洋学者E・G・ブラウンの支援を受けて、汎イスラム運動の知的基盤を築いた。アフガーニの一番弟子であるアブドゥーは、ロンドンのエジプト総領事であったエヴリン・ベーリング・クロマー卿の助けを借りて、今日でも存在する急進右派、基本に忠実な原理主義者の潮流であるサラフィーヤ運動を創設した。アフガーニとアブドゥの役割を正しく理解するためには、親英的な汎イスラム運動を組織しようとする100年にわたるイギリスの努力の実験として見ることが重要である。アフガーニは、紆余曲折を経て、他の帝国勢力に自分のサービスを売り渡したが、結局、彼の神秘主義的で半近代的なイスラム原理主義バージョンは、大衆運動のレベルに達することはできなかった。彼の一番弟子であるアブドゥーは、エジプトのイギリス支配者とより強固に結びつき、20世紀を通じてイスラム右派を支配したムスリム同胞団の礎石を築いた。イギリスは、第一次世界大戦前にイスラムの熱狂を動員するために2つの計画を立ち上げながらも、アブドゥーを支援した。アラビア半島でイギリスは、イブン・サウード一族に率いられた超原理主義アラブ人の砂漠の一団が、サウジアラビアに世界初のイスラム原理主義国家を創設するのを援助した。同時にイギリスは、メッカのハシェミット家を奨励した。ハシェミット家は、イスラム教の元祖預言者の子孫であるという偽りの主張を持つアラブ第二の一族で、ロンドンはその息子たちをイラクとヨルダンの王として擁立した。』p30
『1979年以前のアフガニスタンにおけるCIA
1979年、イスラムがアジアでソ連を弱体化させるかもしれないという仮説が現実のものとなった。アメリカ、パキスタン、サウジアラビアは、カブール政府を脅かし、ソ連をアフガニスタン侵攻へと駆り立て、10年にわたる内戦を生み出したイスラム聖戦を公式に開始した。ブレジンスキーにとってアフガン戦争は、2つの概念を結びつけるものだった。ひとつは、ソ連に対する防壁として南西アジアに「イスラムの弧」を描くという構想である。アメリカと政治的イスラム』の著者、ファワズ・ゲルゲスはこう書いている:
ソビエト共産主義を封じ込めるためには、ソビエトに対するイスラムの反発を分裂させるようなこと、特にアメリカとイランの軍事的対立を避けることが必要だった: 「今となっては、反ソ連のイスラム連合を形成することの方が重要だと思った」。1950年代、1960年代と同様、アメリカはイスラムを、急進的な世俗勢力とその無神論的同盟国であるソ連に対抗するために利用することを望んでいた。カーター政権の高官たちは今、イスラムの復活と協力する新たな可能性を認識し、共産主義の拡張主義に対してイスラムのイデオロギー的、物質的資源を利用することを望んでいた。米国政府高官の頭の中で最も重要だったのは、世俗的な汎アラブ・ナショナリズムとの戦いでイスラムがイデオロギー的な武器として用いられた1950年代と1960年代の教訓であった20。
ベニグセン・ブレジンスキーは、モスクワのアジアの「下層部」に対抗する武器としてイスラム教を動員するという考え方を、この戦略計画の第二の特徴として挙げていた。
しかし、アフガニスタンのイスラム主義者たちは、CIAの公式支援を受け始めたときに、どこからともなく完全な形で出現したわけではない。1979年よりずっと以前から、アフガニスタン国内ではイスラム右派が強力な勢力として台頭しており、1950年代以降、カブールでは進歩的、左派的、世俗的勢力と戦いを繰り広げていた。アフガニスタンにおけるムスリム同胞団に連なるイスラム原理主義者とアメリカのつながりは、少なくとも1950年代には始まっており、同国におけるイスラム右派の政治運動に対するアメリカの支援は、1973年までさかのぼる。』
『
ルイスとハンティントン
その日まで、文明の衝突という考え方を世に広めた最大の功労者であるバーナード・ルイスとサミュエル・ハンティントンの2人は、主流の国家安全保障や外交政策の専門家からは珍奇な存在とみなされていた。アイビーリーグに所属し、『フォーリン・アフェアーズ』誌などの権威ある出版社に出入りしていたこと、そして彼らの理論が先鋭的であったことから、論争を巻き起こすことは確実であったし、実際に巻き起こした。しかし、彼らの考えを真剣に受け止める者は、1990年代にはフリンジにいたネオコン(新保守主義者)たちを除けば、ほとんどいなかった。ルイス=ハンティントン論文は、多くのジャーナリスト、学者、外交政策の第一人者たちから痛烈な反撃を受けた。
サミュエル・ハンティントンは、新保守主義者の宣戦布告ともいえる『文明の衝突』で物議を醸したが、敵はイスラム右派ではなく、コーランの宗教そのものであると書いた:
西洋にとって根本的な問題はイスラム原理主義ではない。西洋にとっての根本的な問題は、イスラム原理主義ではない。イスラムとは異なる文明であり、その人々は自分たちの文化の優越性を確信し、自分たちの力の劣等性にとらわれている。イスラムにとっての問題は、CIAでも米国防総省でもない。西洋である。西洋とは異なる文明であり、その人々は自分たちの文化の普遍性を確信しており、自分たちの優れた、たとえ衰退しつつあるとしても、その文化を世界中に広める義務が自分たちに課せられていると信じている42。
もちろん、ハンチントンのマニフェストから導かれたのは、ユダヤ教とキリスト教の世界とイスラム教の世界が、恒常的な文化戦争状態にあるということだった。アルカイダのようなテロリストは、ハンチントンの著書が出版された当時はまだ形を成していたが、単なる政治的意図を持った狂信者の集団ではなく、文明的対立の現れであった。現代のデルフィの神託のように、ハンチントンは、神々が衝突を予言したのであり、単なる人間にはそれを止めることはできないと示唆した。』p340
NOTES
I: Imperial Pan-Islam
1. The proposal to London from Jamal Eddine al-Afghani was reported by a British Orientalist and author of the time, W. S. Blunt, a friend of Afghani’s. It is cited in C. C. Adams, Islam and Modernism in Egypt (New York: Russell and Russell, 1933), p. 10, n. 1.
2. Elie Kedourie, Afghani and Abduh: An Essay on Religious Unbelief and Political Activism in Modern Islam (New York: The Humanities Press, 1966), p. 30.
3. Kedourie, p. 6.
4. Ibid., p. 13.
5. Cited in Kedourie, p. 45.
6. Ibid.
7. Afghani’s views on religion are quoted at length in Kedourie, p. 44.
8. Cited in Kedourie, p. 4. Kedourie commented wryly on Gibb’s view, saying: “Afghani would no doubt have been much gratified to see that half a century after his death, his pretentions to ‘sound Koranic orthodoxy’ were still being unquestioningly accepted.”
9. Wilfred Cantwell Smith, Islam in Modern History (New York: New American Library, 1957), p. 54.
10. Smith, pp. 56–57.
11. Ibid., p. 55.
12. Richard P. Mitchell, The Society of the Muslim Brothers (London: Oxford University Press, 1969), p. 321.
13. Nikki Keddie, “Afghani in Afghanistan,” Middle Eastern Studies (1) 4.
14. Kedourie, pp. 20–21.
15. Ibid., p. 8.
16. Adams, p. 54.
17. Ibid., pp. 30–31.
18. Adams, p. 18.
19. Ibid., p. 39. Wrote Kedourie: “It is, at any rate, reasonable to presume that having offered his services to the British, Afghani would offer them again to the French.” In any case, France tolerated The Indissoluble Bond, while Great Britain, Egypt, and India banned it.
20. Adams, p. 9, n. 5.
21. Kedourie, p. 54.
22. Ibid., p. 58.
23. Quoted in Adams, pp. 59–60.
24. Kedourie, p. 14.
25. Adams, p. 83.
26. Ibid., p. 79.
27. Kedourie, p. 56.
28. Cited in Kedourie, p. 57.
29. E. G. Browne, A Year amongst the Persians (London: Adam and Charles Black, 1950), pp. 13–14.
30. For an account of the relationship between Khan and Afghani, see Kedourie, pp. 22–23.
31. Adams, p. 11.
32. Kedourie, p. 4.
33. Ibid., p. 5.
34. David Long, The Kingdom of Saudi Arabia (Gainesville: University Press of Florida, 1997), p. 22.
35. In Arabic, muwahhidin. See Long, p. 23.
36. Hamid Algar, Wahhabism: A Critical Essay (Oneonta, N.Y.: Islamic Publications International, 2002), p. 5.
37. Algar, pp. 14–16.
38. William Gifford Palgrave, Personal Narrative of a Year’s Journey through Central and Eastern Arabia (1862–1863) (London: Macmillan and Co., 1993), p. 184.
39. Algar, pp. 20–22.
40. Ibid., pp. 23–25.
41. Ibid.