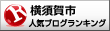「全山の紅葉は神の贈りもの」(乾風孝子)という川柳があります。私たちは毎年秋になると、紅葉の美しさに心を奪われます。
なぜ葉っぱが黄色くなったり赤くなったりするのでしょうか。黄色くなるのは、緑色のもとになっていた葉緑素がだめになるせいです。葉にはもともとニンジンやカボチャのような黄色い色素があって、葉緑素が壊れると浮き出て目立ってくるのだそうです。
一方、カエデ類やナナカマドが赤くなるのは、葉緑素がなくなると同時に、光合成で蓄えた葉の糖分が変化してアントシアンという赤い色素ができるからです。5~10度ぐらいに冷え込むと、葉っぱが赤い色素の合成を始めます。シソやサツマイモの皮の色も同じ色素。条件によっては紫や青にも見えます。
山や渓流の紅葉の美しさは、街路樹と比べると格別です。植物は、昼蓄えた糖分を夜使って生きています。夜の気温が高いと色素の原料になる糖分が余計に使われてしまいます。だから、昼は日光が強く、夜は冷え込むという、寒暖差が大きい所のほうが、発色がいいのだそうです。山や渓流はこうした条件にあっています。
花、新緑、紅葉、氷結・・・。敏感に季節を感じられるのが、日本の山や渓谷の変わらない魅力です。紅葉が終われば、冬の足音が聞こえてきます。