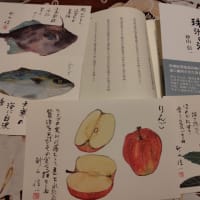先日、中央大学の中澤秀雄さんの新刊『環境の社会学』
(関礼子・丸山康司・田中求との共著・有斐閣)が届いた。

有斐閣アルマシリーズの1冊である本書が想定する読者は、
完全な白紙の学生だとか。環境や社会に興味をもったら
まずは手にしてもらいたい一冊だ。あとがきには、
…漠然と出回っている「常識らしきもの」…を
壊してゆくことは、社会学が伝統的に得意としてきたところであり、
そのスリルを味わってもらえたらうれしい。もっとも、単に破壊することが
私たちの本意ではなく、…技術主義的な知のあり方を変えていきつつ、
柔軟に、コンヴィヴィアリティを大事にしながら持続的な社会を
編み上げていきましょう、というのが私たちの立場…
とある。ちなみに「コンヴィヴィアリティ」とは「convivialな=共生的な」
というところか。さらに、
…「事例から学ぶ、歴史を現在としてとらえる」を合い言葉に、
個々人の生活の身体感覚から出発して、代表的な事例を通じて考え、
その結果読者がより遠くを見通せるようにしようと考えた。定義や
理論は最後に、結果として出てくることになる…
とあとがきは続く。なるほど、スリルを味わえそうな期待がたかまる。
以下に目次をご紹介。
序章 『環境の社会学』への招待
1章 生業の近代化とグローバル化
2章 環境という風景とアイデンテイテイ
3章 環境リスクと環境メデイア
4章 自然を基盤とする暮らしの「当たり前」
5章 自然保護をめぐる葛藤
6章 開発と廃棄
7章 環境問題をめぐるローカルとグローバル
8章 自然と社会をデザインする
9章 持続可能なエネルギーを生かす
10章 市民参加の意味を考える
11章 環境問題の原点はいま
終章 環境と社会を読み解く視点
実際に読みやすくて、あっという間によめる。しかも、
その後も身近において羅針盤のように使いたい書だと思う。
わたしが今後とくに考えたいと思っていることのひとつ:リスク
についても3章でふれられていて、興味ぶかく読んだ。
その関連でわたしが注目する論文が、
最新の『ソシオロゴス』2009年33号に掲載されている。
タイトルは
「自由と統制の個人化論―Ulrich Beck個人化論をめぐる論争と展開―」
(川端健嗣 2009)。

要約の一部を以下にご紹介しよう。
「選択の自由」といわれるように、個人に決定の可能性が
与えられることは自由の増大と同義であると捉えられる傾向が
ある。しかし本稿は個人化研究の再構成を通じて、個人に決定
の可能性が与えられることがむしろ社会統制の一形式として機
能していることを明らかにする。…
ゼミの先輩でもある、この論文の執筆者の川端さんの
個人化論の研究については、この5年で4回ほど口頭発表を拝聴した。
1回目は、難しすぎて、何をいっているのか全然わからなかった。
2回目も、やっぱりわからなかった。
3回目にはじめて、少しわかった気がしたし、「おもしろい」と思えた。
4回目にあたるこの春には、「おもしろい」だけでなく
「この理論研究は原発問題にも使えそう」と思ってワクワクもした。
ただ、ひとさまの研究を「使えそう」っていうのも失礼かも?
と思って、川端さんには「使えそう」と言わずにきた。
でも考えてみれば
「理論はツールです。人の役にたたない理論には意味がない」
と、先生の語録にもある。いまは、
「川端さんの理論研究は使えると思う」というのは褒め言葉と思っている。
そのうえ私の知る限り、ほかの掲載論文も優秀な研究者によるものが多い。
「使える」理論を求めている方をはじめ、ご興味のある方は
どうぞソシオロゴスをご覧ください。
ところで話は戻るが、
中澤秀雄さんが博士論文を全面的に書きあらためて出版した
『住民投票運動とローカルレジーム:新潟県巻町と根源的民主主義の細道、
1994-2004』(2005年、ハーベスト社)をわたしが手にとったのは、
2006年の秋だった。

地域における原発問題をとらえていく際に、中世から
歴史をふりかえっていた点に、ひときわ強く共感した。
そうしなければならない必然をわたしも痛感し、
ちょうどその2ヶ月ほど前に『ためされた地方自治』の
歴史観を書きなおしたところだったから。
原発問題をめぐる現在の主な議論が拠ってたつ歴史観が
(仮に意図せざる効果としてであれ)もたらしている限界や閉塞感
のようなものに、この人も気づいたのだろうと(僭越ながら)思った。
なにより、原発計画の予定地だった石川県珠洲市にわたしが
かよっていたころ、やはり原発の予定地だった新潟県巻町に
かよっていた(ほぼ同世代の)人がいることを知り、
自分が思っているよりも世の中はずっとひろくて
いろんな人がいるんだなぁ、ということを思い知らされた。
腑に落ちないことをそのまま流してやり過ごすことができないまま
みずからの問題関心をおっていると、
世界中の誰からも理解されないような気持ちになる時がないわけではなかった
けれど、実際には各地にさまざまな人が存在していて、
問題関心をおいつづければ、まだ出会えないでいるその人たちに
いつか出会える(可能性がある)ことを知った。
そのことは、少なくない勇気と気力をわたしにもたらしたと思う。
(関礼子・丸山康司・田中求との共著・有斐閣)が届いた。

有斐閣アルマシリーズの1冊である本書が想定する読者は、
完全な白紙の学生だとか。環境や社会に興味をもったら
まずは手にしてもらいたい一冊だ。あとがきには、
…漠然と出回っている「常識らしきもの」…を
壊してゆくことは、社会学が伝統的に得意としてきたところであり、
そのスリルを味わってもらえたらうれしい。もっとも、単に破壊することが
私たちの本意ではなく、…技術主義的な知のあり方を変えていきつつ、
柔軟に、コンヴィヴィアリティを大事にしながら持続的な社会を
編み上げていきましょう、というのが私たちの立場…
とある。ちなみに「コンヴィヴィアリティ」とは「convivialな=共生的な」
というところか。さらに、
…「事例から学ぶ、歴史を現在としてとらえる」を合い言葉に、
個々人の生活の身体感覚から出発して、代表的な事例を通じて考え、
その結果読者がより遠くを見通せるようにしようと考えた。定義や
理論は最後に、結果として出てくることになる…
とあとがきは続く。なるほど、スリルを味わえそうな期待がたかまる。
以下に目次をご紹介。
序章 『環境の社会学』への招待
1章 生業の近代化とグローバル化
2章 環境という風景とアイデンテイテイ
3章 環境リスクと環境メデイア
4章 自然を基盤とする暮らしの「当たり前」
5章 自然保護をめぐる葛藤
6章 開発と廃棄
7章 環境問題をめぐるローカルとグローバル
8章 自然と社会をデザインする
9章 持続可能なエネルギーを生かす
10章 市民参加の意味を考える
11章 環境問題の原点はいま
終章 環境と社会を読み解く視点
実際に読みやすくて、あっという間によめる。しかも、
その後も身近において羅針盤のように使いたい書だと思う。
わたしが今後とくに考えたいと思っていることのひとつ:リスク
についても3章でふれられていて、興味ぶかく読んだ。
その関連でわたしが注目する論文が、
最新の『ソシオロゴス』2009年33号に掲載されている。
タイトルは
「自由と統制の個人化論―Ulrich Beck個人化論をめぐる論争と展開―」
(川端健嗣 2009)。

要約の一部を以下にご紹介しよう。
「選択の自由」といわれるように、個人に決定の可能性が
与えられることは自由の増大と同義であると捉えられる傾向が
ある。しかし本稿は個人化研究の再構成を通じて、個人に決定
の可能性が与えられることがむしろ社会統制の一形式として機
能していることを明らかにする。…
ゼミの先輩でもある、この論文の執筆者の川端さんの
個人化論の研究については、この5年で4回ほど口頭発表を拝聴した。
1回目は、難しすぎて、何をいっているのか全然わからなかった。
2回目も、やっぱりわからなかった。
3回目にはじめて、少しわかった気がしたし、「おもしろい」と思えた。
4回目にあたるこの春には、「おもしろい」だけでなく
「この理論研究は原発問題にも使えそう」と思ってワクワクもした。
ただ、ひとさまの研究を「使えそう」っていうのも失礼かも?
と思って、川端さんには「使えそう」と言わずにきた。
でも考えてみれば
「理論はツールです。人の役にたたない理論には意味がない」
と、先生の語録にもある。いまは、
「川端さんの理論研究は使えると思う」というのは褒め言葉と思っている。
そのうえ私の知る限り、ほかの掲載論文も優秀な研究者によるものが多い。
「使える」理論を求めている方をはじめ、ご興味のある方は
どうぞソシオロゴスをご覧ください。
ところで話は戻るが、
中澤秀雄さんが博士論文を全面的に書きあらためて出版した
『住民投票運動とローカルレジーム:新潟県巻町と根源的民主主義の細道、
1994-2004』(2005年、ハーベスト社)をわたしが手にとったのは、
2006年の秋だった。

地域における原発問題をとらえていく際に、中世から
歴史をふりかえっていた点に、ひときわ強く共感した。
そうしなければならない必然をわたしも痛感し、
ちょうどその2ヶ月ほど前に『ためされた地方自治』の
歴史観を書きなおしたところだったから。
原発問題をめぐる現在の主な議論が拠ってたつ歴史観が
(仮に意図せざる効果としてであれ)もたらしている限界や閉塞感
のようなものに、この人も気づいたのだろうと(僭越ながら)思った。
なにより、原発計画の予定地だった石川県珠洲市にわたしが
かよっていたころ、やはり原発の予定地だった新潟県巻町に
かよっていた(ほぼ同世代の)人がいることを知り、
自分が思っているよりも世の中はずっとひろくて
いろんな人がいるんだなぁ、ということを思い知らされた。
腑に落ちないことをそのまま流してやり過ごすことができないまま
みずからの問題関心をおっていると、
世界中の誰からも理解されないような気持ちになる時がないわけではなかった
けれど、実際には各地にさまざまな人が存在していて、
問題関心をおいつづければ、まだ出会えないでいるその人たちに
いつか出会える(可能性がある)ことを知った。
そのことは、少なくない勇気と気力をわたしにもたらしたと思う。