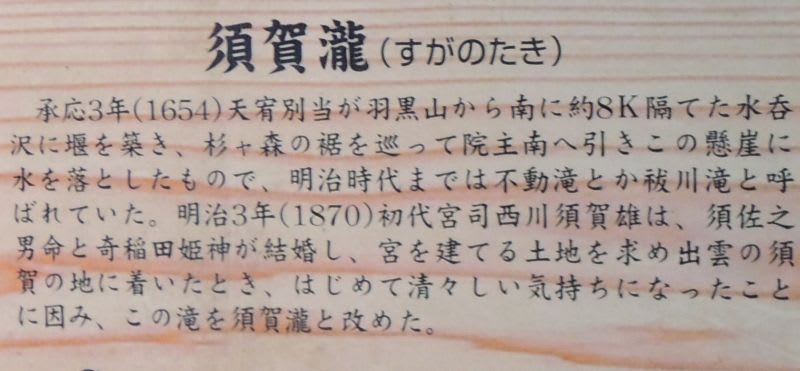今回はウチの近く(歩いて数分)にある西野吉備神社のケヤキを紹介したいと思います
西野吉備神社は旧羽州浜街道 (旧国道7号線)沿いにあり、子供のころから慣れ親しんでいることもあって
特に気に留めることもない場所ではありました。
とは言え、よく見ると幹線道路沿いにあるケヤキは結構な大きさなので、今回取り上げることにしました。
大ケヤキは交通量の多い幹線道路沿いに立っています

近くで見ると幹回りはかなりあることが判ります

反対側からの画像ですが、神社の隣にはレトロなポストがあります

境内の中から見ると、上に遮るものがないので、大きく枝を広げているのが判ります

境内には注連縄の巻かれたこんな木もあります

この神社の境内は昭和40年代頃までは子供の恰好の遊び場で、三角ベースの野球などをして遊びましたし
夏休みの朝のラジオ体操の会場もこの神社の境内でした。
この神社の例大祭は4月13日(ちなみにワタシの住んでいる地域は4月12日)で
夜には地域の住民たちによって「西野神代神楽」が演じられます。
(ワタシの同級生の親父さんが笛と太鼓の名手でした)
ちなみにこの神社の入口は旧羽州浜街道側ではなく、村中の細い通りで、鳥居の横には老木が立っています。

老木の反対側には色づいた木がありましたが、何なのかは知りません

普段は気にも留めない地元にもそれなりに見所があることを再認識した次第です。