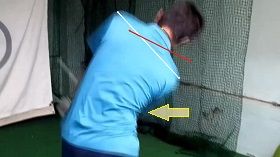ゴルフ! という特別な視点ではなく、
モノ・物質として ゴルフクラブを考えた場合、
1mの長さの棒の先端に
全体重量の 6割(以上)に相当する鉄の塊が付いています。
先端の部分も勿論そうですが、
ゴルフクラブ本体が動く、移動する源・原動力は
この場合は打ち手・人間ですが、
根元(グリップ)の部分を動かしたから、
移動させたから 『その分』
先端部の鉄の塊もゴルフクラブそのものも移動するのです。
ここまでは 小学校の理科…位でしょうか(^^♪
ここで間違ってはいけないのは、
ゴルフクラブは根元が固定され
その先端の重さによって「振り子」のように動く
と考えることです。
このイメージはゴルフスイング・ゴルフスイングを
元からダメにしてしまう危ない考えです。

①先端の重さで「振り子」のように動かすのには
根元の部分を『とめて』おかなくてはなりません。
ゴルフスイング…と言うコトになると
根元の部分はグリップですから
グリップの動き・移動がないのに
クラブ~ヘッドが動くことになります。
ゴルフクラブにには、ヘッドには
距離や方向を司る角度…というモノが存在し、
それによって 距離や弾道が決まってきます。
グリップを固定し、扇~振り子のようにクラブを動かすと
かなり自由に その角度は変わってしまいます。
👉ここの部分で 非常に問題なのは
打ち手・人間を接している
グリップの部分は止まっているのに
ヘッドが動いていると言うコトです。
これで どのようにして同じ(似た)球を打つ
というのでしょうか?
言葉のニュアンスはあまり良くありませんが、
クラブが全く管理されてなく、固定しただけで
ブランブランと勝手に動くヘッドの
そのインパクト時の姿勢をどのように管理する
というのでしょうか?
これでは ボールに向かって ヘッド単体を
投げつけたのと同じような状態になってしまいます。
②そもそもこれも面白い考え・・・だと思うのですが、
ヘッド・シャフト・クラブで振り子に振るためには
常時 グリップの位置を固定しておく必要がありますが、
知っての通り、スイングは機械でやる訳ではなく
かなり柔軟に動く人間が行うのです。
グリップの位置がいつもと同じ場所、同じ時に
固定できるはずもありません。
👉クラブ自身が上下左右どの方向であっても
スライドして移動するよりも
グリップが半固定され、振り子のようにクラブが動く方が
無用な遠心力を生んでしまいます。
中学生の科学レベルに上がりましたが、
遠心力は ソノモノの 軸点から外へ外へ膨らむ
外へはらむようにかかる不可抗力です。
よく考えてみましょう。
市販のドライバーやアイアンの超軽量ヘッドであっても
長さもありますし、運動も加わりますから
その重さは 数キロ~十数キロにもなります。
数キロ・十数キロの鉄の塊を
ほそーい裁縫用の糸でつないでおいたら
糸はどうなります? ある運動を超えると切れますよね
切れた鉄の塊は ボールにぶつかると思います?
どのタイミングで切れた にしても
ボールと鉄の塊はぶつかることはありません。空振りです。
速い速度で振れば振るほど、糸は頑丈なモノが必要になります。
この場合、糸の頑丈さは クラブを遠心力と反対方向に
『ひきつけるチカラ』と言うコトになりますが、
飛ばそうとすればするほど ボールへの方向、
ボールを飛ばそうとする方向と 全く違う
似た方向にならない 90度違う斜め上下に
引っ張られたり 引っ張ったりする力が必要になります。
この力が「飛ばしにつながる」と信じていますか?
③ちょっと高等学校レベルの科学になってきます。
打つ物体は「球体」~ボールです。
✋ゴルフクラブが グリップが1m・ヘッドも1m
スイングに似たような軌跡で スライドして入ってくる
✋グリップは固定・ヘッドだけが
そのクラブの長さの半径で 入ってくる
この二つで 球体に加わる作用 が同じになると思いますか?
ボールの回転が多くなるのはどちらだと思いますか?

言葉は悪いですが、
振り子でクラブを扱うスイングは
ちゃんと打ち手がクラブを動かさない
手抜き というか、ものぐさ なだけです。
『クラブがボールを打ってくれる』
その言葉は半分正しく、半分間違っています。
『クラブは打ち手の作用を増幅してくれるだけ』であって
ゴルフクラブが勝手にボールを打つ訳ではありません。
そうだとしたら、良いショットを繰り返す手段も
悪いショットを修正する手段もなくなってしまいます。
ゴルフスイングは 結果として
体を回す・回転させるので
傍から見ると円弧を描いている『ように』見えますが、
基本、横(前傾姿勢があるので斜めにはなりますが)に
平行に動かしているに過ぎません。
向きを変えるから「結果」円になるだけで、
横にスライドさせて使っているだけなのです。
そう使わないと 角度の意味が発揮されません。