コミュニケーションは言語1割、非言語9割と言われている。
情報の伝達は言葉が全てと思いがちだけど、
言葉なんてたったの1割らしい。
とは言え 言葉がなければ会話のテーマを共有することは出来ないし
言葉はそれがなければ始まらないコミュニケーションの大事な手段です。
考えてみれば朝「おはよう」の挨拶をかわす時、
この活字でいうところの「おはよう」だけでは互いの様子までは伝わらない。
元気なのか眠そうなのか不機嫌なのか慌ててるのか、、、そういった情報を
人は言葉以外の非言語の部分、声のトーンや返事の仕方や表情や視線や仕草などから
感じ取りながら接し合っている。
このように私たちは自分が思う以上に言葉以外の部分に頼って生活している訳だけれど
それにもかかわらずその非言語をどう解釈するかもまた人それぞれ違うのです。
考え方感じ方のクセのようなものが人によって違うからでしょう。
相手の伝えたいことと自分の受け取ったものは違うかもしれないのです。
でも私たちはあまりそのことに気づかない。
日頃 非言語に頼っている私たちは言葉で伝えあうということを
実はすごく疎かにしている、ということがこの作品を読むとわかります。
耳の聞こえない少女に対してだけじゃなくて、
友人同士でも、親子でも。先生も。
聞こえる聞こえないに関係なく、どこの関係を切り取ってもです。
ほとんど伝えていないし聴こうとしていないし分かろうとしていないのです。
自分の言いたいことがその言い方では相手に届いていないかもしれないことや
相手の言いたいことに自分が気づけていないかもしれないということに
気づいていません。
「どういう風に言ったら相手に気持ちが伝わるか」に努力しなさすぎだし
相手の言いたいことは何なのかを「知ろうとする気持ち」が足りなすぎだし
というかそもそも登場人物全員がほぼ大事な場面で
「言葉で自分の気持ちを伝えあう」ことをしていない。
思っているだけで伝えない。
見ているだけで教えない。
自分の中では色々考えているのにそこを伝え合わないから
関係に自信が持てず
読んでいてもどかしくなるのです。
言葉で伝えず、頼りの非言語を自己流に解釈して読み違えていたら
わかりあえないよなあ、と思うのです。

















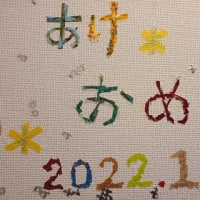


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます