
先哲に学ぶ行動哲学―知行合一を実践した日本人第十二回(『祖国と青年』22年4月号掲載)
至誠を貫いた三十年の生涯 吉田松陰1
祖国の将来を憂え「已むに已まれぬ大和魂」の行動
幕末の尊王攘夷運動を推進し、維新を成し遂げる大きな役割を担ったのは長州藩である。その長州藩の青年達を導き、国家を変革する人材を数多生み出した指導者が松下村塾の吉田松陰である。祖国の将来を憂えて燃え続ける魂の炎は、志を抱かんとする回りの青年達の魂に次々と火を点じて行った。
私が、吉田松陰の存在を知ったのは、陽明学と出会い、日本陽明学派の人物研究を志した二十歳の冬であった。祖国を憂え、道を求め、至誠に生きるその姿に、時代を超えて、青年のあるべき姿を教えられた。翌春、萩を訪れ松陰先生の墓前に額ずいて以来、私は、人生の大きな決断を下す時には、松陰先生の墓前を必ず訪れる。
吉田松陰は天保元年(1830年)8月4日に、長門国萩の郊外松本村に、杉百合之助の二男として生まれた。5歳で、山鹿流兵学師範の叔父吉田大助の仮養子になり、翌天保六年4月に吉田大助が病で亡くなり、吉田家を継ぎ大次郎と改名した。天保九年には、教授見習として、藩校明倫館に出仕し、十一年には藩主毛利敬親の前で山鹿素行の『武教全書』を講じている。松陰十歳の時である。
松陰は暖かで思いやりと信仰深い家庭の中で、学問好きの父と叔父・玉木文之進に導かれて学問に励んで行った。弘化二年(1845年)十六歳の時に長沼流兵学を学び、世界の大勢に眼を開き始め、嘉永元年(1848年)には、山鹿流兵学師範になった。志を立てる事の重要さを次の様に記している。十七・八歳の頃の文章である。
●道の精なると精ならざると、業の成ると成らざるとは、志の立つと立たざるとに在るのみ。故に士たる者は其の志を立てざるべからず。夫れ志の在る所、気も亦従ふ。(生き方が確固たるものになれるか、物事を為し遂げる事が出来るか否かは、全て志が立つか否かにかかっている。志さえ立ったならば気力は自ずと従って来るものである。)
●自ら以て俗輩と同じからずと為すは非なり、当に俗輩と同じかるべからずと為すは是なり。(自分は俗人で無いと思うのは間違いだが、俗人であってはならないと自戒する事は重要な事である。)
行動家松陰を生み出した若き日の遊学
二十一歳から二十四歳の間、松陰は九州・江戸・東北・江戸と様々な人物を訪ね、学問と時代認識とを深めて行く。嘉永三年(1850年)の九州遊学時の「西遊日記」の序にはこう記されている。
●心はもと活きたり、活きたるものには必ず機あり、機なるものは触に従ひて発し、感に遇ひて動く。発動の機は周遊の益なり。(人の心は元来活き活きしており、機会さえあれば大きな弾みがつく。機会は何物かに触れたり感じる事で生まれる。発動の機会を与える点で諸国遊学は大きな益をもたらす。)
松陰が陽明学と出会ったのも、この九州遊学の平戸での事である。佐藤一斎に学んだ葉山左内に王陽明『伝習録』を借りている。九月二十一日の日記には「伝習録の示弟立志説・訓蒙大意・教約を読みて、後巻を釋つること能はず。」と、王陽明の言葉に強く魅かれた事を記しており、数日で完読している。更に、松陰は平戸や長崎で支那のアヘン戦争の詳しい記録や国防に関する様々な書物を読破した。
嘉永四年(1851年)三月、松陰は兵学研究の為江戸へ向かう。江戸で様々な学者の門を叩き学問に精進するが、松陰を惹き付ける様な高い志を持つ師には遂に出合わなかった。焦る松陰は兄杉梅太郎宛の書簡で、到底三年位の修業ではものにならない事を嘆き、次の様に述べている。
●愚鈍ものは人の十歩百歩の間に漸く一歩を移し候位の事にては、三年五年には間に合ひ申す間敷く候。夫れ故死して後已むを以て自ら戒め候事に御座候。(愚かな私は、人が十歩百歩歩む間に一歩を進むのが漸くです。三・五年の修業では物になりません。それ故、死ぬまで学びを止めない覚悟で張り詰めて学んでおります。)
その様な中で松陰が得たのは、全国各地から向学心に燃えて江戸に集まる志ある青年達との熱気溢れる交流であった。松陰は肥後藩の宮部鼎蔵と東北地方視察を計画する。そこに、兄の敵討ちを志す江幡五郎が同行を求めてきたので、出発を赤穂浪士討ち入りの日である十二月十四日とする事を約束する。だが、その日まで藩の許可が下りなかった。松陰は同志との「丈夫の一諾」を重んじて脱藩を決行する。東北行は故郷を思う苦悩の旅路となってしまった。
●三千里外漂泊の身、国を懐ひ家を思ふて感荐りに臻る。を身に纏ひ君恩辱うす。定省幾年か慈親に負く。閑を慰めて時に史乗を取りて読めば、涙は落つ古今忠孝の人。何れの日か応に駑純の力を竭し、報效古今と倫ぶを得べけんや。(今、自分は故郷から三千里も離れた地に流れ漂っている。藩や家の事を思うと感慨がしきりに湧いて来る。私がこの様に何不自由なく暮らせるのは殿様のお陰であり、何の孝養も果たせず両親の慈愛にも背いている。閑を慰める為に歴史書を紐解き、忠義や孝養に尽した人物と出会う度に、自らが省みられて涙が落ちてくる。愚かな自分だが、力の限り尽して、何時の日か、先人に恥じない、恩に報いる立派な人物に、必ずや成って行く事を決意する。)
だが、この東北行で、水戸や会津の士風に触れ、佐渡島の順徳天皇御陵を訪ね、竜飛崎から津軽海峡を通るロシアの船を見た事は松陰の「信念」形成に於て大きな意味を与えた。翌年四月、江戸に戻った松陰は亡命の罪により、萩に帰国を命ぜられ、家禄を没収され浪人の身となる。帰国後松陰は水戸で実感した日本史への探究を深めて行く。
●身皇国に生れて、皇国の皇国たるを知らずんば、何を以て天地に立たん。故に先づ日本書記三十巻を読み、之れに継ぐに続日本紀四十巻を以てす。(日本に生まれて天皇国日本の日本たる所以を知らなければ何を以てこの天地に立つ事が出来ようぞ。そこで、先ず日本書記三十巻を読み、次に続日本紀四十巻に取り組んだ。)
松陰を待ち受けていた黒船来寇
翌年、松陰の才能を惜しむ藩主の仁愛により、松陰は十年間の諸国遊学を許され江戸に向かった。その松陰を待っていたのは、ペリーの黒船来寇だった。浦賀に駆けつけた松陰は佐久間象山から西洋文明の強大さについて詳しく教示を受ける。目の前に現出した日本の危機に対して何を為すべきか、二十四歳の青年の「行動」が模索されて行く。
●日本武士一へこしめる機会来り申し候。賀すべきも亦大なり。(太平に酔いしれている日本の武士達のふんどしを締め直す絶好の機会であり、喜ぶべき事態である。)
●穏便穏便の声天下に満ち、人心土崩瓦解、皆々太平を楽しみ居る中にも、有志の輩は相対して悲泣するのみに御座候。(穏便に穏便にという事勿れの声ばかり天下に満ち、人々の心は土の様に崩れ瓦の様に砕けている。人々が太平を謳歌する中にあって志を抱く我々は悲しみの涙を流すばかりであります。)
●備えとは艦と砲との謂ならず吾が敷島の大和魂(国の備えとは軍艦や大砲を意味するのでは無い。外圧に揺るがない毅然たる日本人の大和魂をいうのである。)
山鹿流軍学師範である松陰は、西洋列強という敵を知り対処法を確立すべく、黒船に乗り込み西洋に渡らんと志した。九月、ロシア軍艦に乗り込む目的で長崎へ行くが、果たせず江戸に戻る。安政元年(1854年)三月、金子重輔と密航の為アメリカ軍艦に乗り込もうとするが、ペリーは松陰の志を評価しつつも、幕府との条約交渉中の為拒絶する。岸に戻された松陰らは自ら縛について江戸伝馬町の獄に送られた。公明正大を信條とする松陰は獄吏に全てを語った。
●一事隠す所なし、願はくは筆を提げて是れを記せよ(一事も隠し立てはしない。筆を持って私の言う事を記せ。)
●世の人はよしあしこともいはばいへ賎が誠は神ぞ知るらん(世の人は何とでも批評すれば良い。私の志と純一な思いは神様だけはご存じである。)
江戸の獄に送られる途中、高輪の泉岳寺前で赤穂義士に思いを馳せつつ詠んだ松陰の絶唱。
●かくすればかくなるものと知りながら已むに已まれぬ大和魂(この様な事を行えばこの様になるとは解ってはいたが、私のこの行動は已むに已まれぬ大和魂の発露なのだ。)
鎖国の禁を破った松陰と金子重輔は、ペリーの口添えも有って死罪を免れて萩に送り戻され、野山獄・岩倉獄に繋がれた。野山獄から兄杉梅太郎に宛てた書簡には松陰の強い志が記されている。鎖国に対して次の様に言う。
●禁は是れ徳川一世の事、今時の事は将に三千年の皇國に関係せんとす。何ぞ之れを顧みるに暇あらんや。(鎖国の禁制はたかだか徳川治世下の事に過ぎない。今日の問題は三千年来続いてきた日本国の自主独立・存亡に関する問題である。その様な時に、一時の禁制などに拘束されようか。)
松陰は三千年の我が国の有り方を考え、徳川二百五十年の限界を突破している(私は、現在の憲法論議の際にこの松陰の言葉を常に思い出す。「平和ぼけ憲法」などという戦後六十五年の特殊な体制に捉われていては、日本国の真姿は顕す事が出来ないのである。)。
今後は大人しくして、文筆活動で国家に尽したら良いではないかという兄に、松陰は次の言葉を投げかける。
●紙上の空言、書生の誇る所、烈士の恥づる所なり。(紙の上だけの空理空論は書生は好むかも知れないが、烈士を自認する私には恥とする所である。)
●扠も扠も思ふまいと思ふても又思ひ、云ふまいと云ふても又云ふものは國家天下の事なり。(それにしても、もう思うまいと思っても又思い、言うまいとしても又言ってしまうのが国家の事と天下の事である。)
日本の危機に際し、その救済の為全身を賭して行動した吉田松陰は、事破れて後、萩の地に幽閉され行動の自由を奪われる。その已むに已まれぬ思いが、自らに代って行動する青年を生み出す強力な感化力となって行くのである。
至誠を貫いた三十年の生涯 吉田松陰1
祖国の将来を憂え「已むに已まれぬ大和魂」の行動
幕末の尊王攘夷運動を推進し、維新を成し遂げる大きな役割を担ったのは長州藩である。その長州藩の青年達を導き、国家を変革する人材を数多生み出した指導者が松下村塾の吉田松陰である。祖国の将来を憂えて燃え続ける魂の炎は、志を抱かんとする回りの青年達の魂に次々と火を点じて行った。
私が、吉田松陰の存在を知ったのは、陽明学と出会い、日本陽明学派の人物研究を志した二十歳の冬であった。祖国を憂え、道を求め、至誠に生きるその姿に、時代を超えて、青年のあるべき姿を教えられた。翌春、萩を訪れ松陰先生の墓前に額ずいて以来、私は、人生の大きな決断を下す時には、松陰先生の墓前を必ず訪れる。
吉田松陰は天保元年(1830年)8月4日に、長門国萩の郊外松本村に、杉百合之助の二男として生まれた。5歳で、山鹿流兵学師範の叔父吉田大助の仮養子になり、翌天保六年4月に吉田大助が病で亡くなり、吉田家を継ぎ大次郎と改名した。天保九年には、教授見習として、藩校明倫館に出仕し、十一年には藩主毛利敬親の前で山鹿素行の『武教全書』を講じている。松陰十歳の時である。
松陰は暖かで思いやりと信仰深い家庭の中で、学問好きの父と叔父・玉木文之進に導かれて学問に励んで行った。弘化二年(1845年)十六歳の時に長沼流兵学を学び、世界の大勢に眼を開き始め、嘉永元年(1848年)には、山鹿流兵学師範になった。志を立てる事の重要さを次の様に記している。十七・八歳の頃の文章である。
●道の精なると精ならざると、業の成ると成らざるとは、志の立つと立たざるとに在るのみ。故に士たる者は其の志を立てざるべからず。夫れ志の在る所、気も亦従ふ。(生き方が確固たるものになれるか、物事を為し遂げる事が出来るか否かは、全て志が立つか否かにかかっている。志さえ立ったならば気力は自ずと従って来るものである。)
●自ら以て俗輩と同じからずと為すは非なり、当に俗輩と同じかるべからずと為すは是なり。(自分は俗人で無いと思うのは間違いだが、俗人であってはならないと自戒する事は重要な事である。)
行動家松陰を生み出した若き日の遊学
二十一歳から二十四歳の間、松陰は九州・江戸・東北・江戸と様々な人物を訪ね、学問と時代認識とを深めて行く。嘉永三年(1850年)の九州遊学時の「西遊日記」の序にはこう記されている。
●心はもと活きたり、活きたるものには必ず機あり、機なるものは触に従ひて発し、感に遇ひて動く。発動の機は周遊の益なり。(人の心は元来活き活きしており、機会さえあれば大きな弾みがつく。機会は何物かに触れたり感じる事で生まれる。発動の機会を与える点で諸国遊学は大きな益をもたらす。)
松陰が陽明学と出会ったのも、この九州遊学の平戸での事である。佐藤一斎に学んだ葉山左内に王陽明『伝習録』を借りている。九月二十一日の日記には「伝習録の示弟立志説・訓蒙大意・教約を読みて、後巻を釋つること能はず。」と、王陽明の言葉に強く魅かれた事を記しており、数日で完読している。更に、松陰は平戸や長崎で支那のアヘン戦争の詳しい記録や国防に関する様々な書物を読破した。
嘉永四年(1851年)三月、松陰は兵学研究の為江戸へ向かう。江戸で様々な学者の門を叩き学問に精進するが、松陰を惹き付ける様な高い志を持つ師には遂に出合わなかった。焦る松陰は兄杉梅太郎宛の書簡で、到底三年位の修業ではものにならない事を嘆き、次の様に述べている。
●愚鈍ものは人の十歩百歩の間に漸く一歩を移し候位の事にては、三年五年には間に合ひ申す間敷く候。夫れ故死して後已むを以て自ら戒め候事に御座候。(愚かな私は、人が十歩百歩歩む間に一歩を進むのが漸くです。三・五年の修業では物になりません。それ故、死ぬまで学びを止めない覚悟で張り詰めて学んでおります。)
その様な中で松陰が得たのは、全国各地から向学心に燃えて江戸に集まる志ある青年達との熱気溢れる交流であった。松陰は肥後藩の宮部鼎蔵と東北地方視察を計画する。そこに、兄の敵討ちを志す江幡五郎が同行を求めてきたので、出発を赤穂浪士討ち入りの日である十二月十四日とする事を約束する。だが、その日まで藩の許可が下りなかった。松陰は同志との「丈夫の一諾」を重んじて脱藩を決行する。東北行は故郷を思う苦悩の旅路となってしまった。
●三千里外漂泊の身、国を懐ひ家を思ふて感荐りに臻る。を身に纏ひ君恩辱うす。定省幾年か慈親に負く。閑を慰めて時に史乗を取りて読めば、涙は落つ古今忠孝の人。何れの日か応に駑純の力を竭し、報效古今と倫ぶを得べけんや。(今、自分は故郷から三千里も離れた地に流れ漂っている。藩や家の事を思うと感慨がしきりに湧いて来る。私がこの様に何不自由なく暮らせるのは殿様のお陰であり、何の孝養も果たせず両親の慈愛にも背いている。閑を慰める為に歴史書を紐解き、忠義や孝養に尽した人物と出会う度に、自らが省みられて涙が落ちてくる。愚かな自分だが、力の限り尽して、何時の日か、先人に恥じない、恩に報いる立派な人物に、必ずや成って行く事を決意する。)
だが、この東北行で、水戸や会津の士風に触れ、佐渡島の順徳天皇御陵を訪ね、竜飛崎から津軽海峡を通るロシアの船を見た事は松陰の「信念」形成に於て大きな意味を与えた。翌年四月、江戸に戻った松陰は亡命の罪により、萩に帰国を命ぜられ、家禄を没収され浪人の身となる。帰国後松陰は水戸で実感した日本史への探究を深めて行く。
●身皇国に生れて、皇国の皇国たるを知らずんば、何を以て天地に立たん。故に先づ日本書記三十巻を読み、之れに継ぐに続日本紀四十巻を以てす。(日本に生まれて天皇国日本の日本たる所以を知らなければ何を以てこの天地に立つ事が出来ようぞ。そこで、先ず日本書記三十巻を読み、次に続日本紀四十巻に取り組んだ。)
松陰を待ち受けていた黒船来寇
翌年、松陰の才能を惜しむ藩主の仁愛により、松陰は十年間の諸国遊学を許され江戸に向かった。その松陰を待っていたのは、ペリーの黒船来寇だった。浦賀に駆けつけた松陰は佐久間象山から西洋文明の強大さについて詳しく教示を受ける。目の前に現出した日本の危機に対して何を為すべきか、二十四歳の青年の「行動」が模索されて行く。
●日本武士一へこしめる機会来り申し候。賀すべきも亦大なり。(太平に酔いしれている日本の武士達のふんどしを締め直す絶好の機会であり、喜ぶべき事態である。)
●穏便穏便の声天下に満ち、人心土崩瓦解、皆々太平を楽しみ居る中にも、有志の輩は相対して悲泣するのみに御座候。(穏便に穏便にという事勿れの声ばかり天下に満ち、人々の心は土の様に崩れ瓦の様に砕けている。人々が太平を謳歌する中にあって志を抱く我々は悲しみの涙を流すばかりであります。)
●備えとは艦と砲との謂ならず吾が敷島の大和魂(国の備えとは軍艦や大砲を意味するのでは無い。外圧に揺るがない毅然たる日本人の大和魂をいうのである。)
山鹿流軍学師範である松陰は、西洋列強という敵を知り対処法を確立すべく、黒船に乗り込み西洋に渡らんと志した。九月、ロシア軍艦に乗り込む目的で長崎へ行くが、果たせず江戸に戻る。安政元年(1854年)三月、金子重輔と密航の為アメリカ軍艦に乗り込もうとするが、ペリーは松陰の志を評価しつつも、幕府との条約交渉中の為拒絶する。岸に戻された松陰らは自ら縛について江戸伝馬町の獄に送られた。公明正大を信條とする松陰は獄吏に全てを語った。
●一事隠す所なし、願はくは筆を提げて是れを記せよ(一事も隠し立てはしない。筆を持って私の言う事を記せ。)
●世の人はよしあしこともいはばいへ賎が誠は神ぞ知るらん(世の人は何とでも批評すれば良い。私の志と純一な思いは神様だけはご存じである。)
江戸の獄に送られる途中、高輪の泉岳寺前で赤穂義士に思いを馳せつつ詠んだ松陰の絶唱。
●かくすればかくなるものと知りながら已むに已まれぬ大和魂(この様な事を行えばこの様になるとは解ってはいたが、私のこの行動は已むに已まれぬ大和魂の発露なのだ。)
鎖国の禁を破った松陰と金子重輔は、ペリーの口添えも有って死罪を免れて萩に送り戻され、野山獄・岩倉獄に繋がれた。野山獄から兄杉梅太郎に宛てた書簡には松陰の強い志が記されている。鎖国に対して次の様に言う。
●禁は是れ徳川一世の事、今時の事は将に三千年の皇國に関係せんとす。何ぞ之れを顧みるに暇あらんや。(鎖国の禁制はたかだか徳川治世下の事に過ぎない。今日の問題は三千年来続いてきた日本国の自主独立・存亡に関する問題である。その様な時に、一時の禁制などに拘束されようか。)
松陰は三千年の我が国の有り方を考え、徳川二百五十年の限界を突破している(私は、現在の憲法論議の際にこの松陰の言葉を常に思い出す。「平和ぼけ憲法」などという戦後六十五年の特殊な体制に捉われていては、日本国の真姿は顕す事が出来ないのである。)。
今後は大人しくして、文筆活動で国家に尽したら良いではないかという兄に、松陰は次の言葉を投げかける。
●紙上の空言、書生の誇る所、烈士の恥づる所なり。(紙の上だけの空理空論は書生は好むかも知れないが、烈士を自認する私には恥とする所である。)
●扠も扠も思ふまいと思ふても又思ひ、云ふまいと云ふても又云ふものは國家天下の事なり。(それにしても、もう思うまいと思っても又思い、言うまいとしても又言ってしまうのが国家の事と天下の事である。)
日本の危機に際し、その救済の為全身を賭して行動した吉田松陰は、事破れて後、萩の地に幽閉され行動の自由を奪われる。その已むに已まれぬ思いが、自らに代って行動する青年を生み出す強力な感化力となって行くのである。
















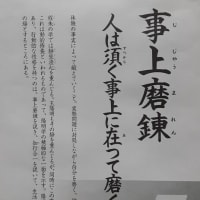



松陰先生の歌「備えとは艦と砲との謂ならず吾が敷島の大和魂」は本当に今の日本人にとって重要なメッセージと思います。どうかこの歌の出典をご教示いただければ幸いです。宜しくお願い致します。
この歌の出典は、嘉永6年12月3日の「兄杉梅太郎宛」書簡です。
尚、明成社から私が編集して『維新のこころ 孝明天皇と志士たちの歌』を出していますので、維新の志士達の和歌に関心ある方にはお薦めです。吉田松陰の和歌も全て掲載しています。