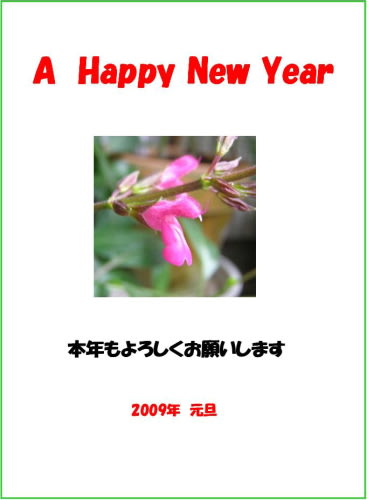古代ギリシャ人にとってスイート・バイオレットは特別の花のようだった。
カーネーションと並び好まれた花だが、結婚式などでの髪飾りとして使われるだけでなく
薬草としての位置をしっかりと占めていた。
また、芳香のある美しさはもちろんのこと、ひっそり隠れたようなキャラクターに魅了され
詩人の心をくすぐった花でもあったようだ。
ヨーロッパの中世時代は、この美しさと香りを楽しむという気質・文化がなく、
修道院で“邪悪な精神”に効く薬草としてひっそりと育てられていた。
これを日向に出したのがナポレオンとジョゼフィーヌだが、その前に16世紀に一度脚光を浴びておりパルマバイオレットの神話として残されている。
ナポレオンが愛したバイオレット
ナポレオン、ジョゼフィーヌともスイート・バイオレットを愛でていて、
二人の結婚式ではジョゼフィーヌがバイオレットを身につけたという。
また、結婚記念日にはバイオレットの花束をナポレオンが贈ったそうだ。
(実際は花束にするにはちょっと厳しいので鉢のようにして贈ったのかもしれない。)
このうわさがパリに広まりバイオレットを栽培する人が増えたという。
ジョゼフィーヌは、マルメゾン庭園にバラだけでなくスイート・バイオレットも集めたようで、
起源・由来がミステリアスで香り豊かな「スイート・バイオレット・オブ・パルマ(Sweet Violet of Parma)」を集めるためにイタリアの都市パルマまで人を派遣させたという。
(写真)スイートバイオレット・オブ・パルマ

このパルマバイオレットは、古代スペインのムーア人の庭に起源があるとか、イタリア経由でトルコから入ってきたという伝説がある。
いづれにしても気候温暖なイスラム圏が育てた花で、16世紀にスペインかポルトガルからブルボン王家によってイタリアのナポリに持ってこられたという。
それにしても素晴らしい逸品だ。
ナポレオン失脚後はバイオレットも忘れられたが、彼が復活するとまたブームになったというので、勝ち組にしっぽを振るという行為はかなりいい加減なものだ。
ワーテルローの戦いに敗れたナポレオンは、ジョゼフィーヌの墓に行きそこに咲いていたバイオレットを2-3本摘みとったという。
そして、彼が死んだ時に胸のロケットには枯れたバイオレットが残っていた。
コルシカ島の寒冷な林の下地に咲く香り豊かなバイオレットは多感な少年の情感を刺激し、その香りの中でナポレオンは一生を終えたのであろう。
それにしてもこれはよく出来た話だが、フランスにバイオレットを定着させたのはナポレオンとジョゼフィーヌであることは間違いない。
そして、マルメゾン庭園のバイオレットは、イギリスに渡りパンジーの作出に関わった。
スイート・バイオレットにも様々な品種が作られているが、その品種名はまるでバラのようだ。
大輪切花用には「ラ・フランス(La Flance)」 、
美しい濃紫色の「プリンセス・オブ・ウエールズ(Princess of Wales)」 、
紅紫色の「マリー・ルイーズ(Marie Louise)」
などイメージと香りが浮かびやすいおしゃれな名前が多い。
英国育ちのパンジーとは名前からして一味違う。
(写真)ラ・フランス La Flance

(写真)マリー・ルイーズ Marie Louise

(写真)プリンセス・オブ・ウエールズ Princess of Wales

日本のスミレもこのスイート・バイオレットに相通じるものがあり素朴な味わいがある。
華麗・豪華な花もいいが、飽きたときに戻るところは原種に近い花になる。
(写真)我が庭のスイートバイオレットの花

スイートバイオレット(Sweet Violet)
・学名は、Viola odorata L.、英名がSweet Violet、和名がニオイスミレ。
・種小名の‘odorata’は芳香のあるという意味。
・原産地はヨーロッパの南部
・匍匐状の茎から根を下ろして広がる。
・葉の形状はハート型で長柄がある。
・開花期は10-4月で紫・桃・白などがある。
・肥沃な土壌で少し湿り気がよい。
・日陰、半日陰でもそだつ。
・栽培温度は、2-3℃で成育し、10-15℃が適温。
・耐寒性は強いが、夏の高温と強い光には弱いので、風通しのよい日陰で育てる。
・ヨーロッパでは、花よりも香りを楽しむ植物として利用されている。