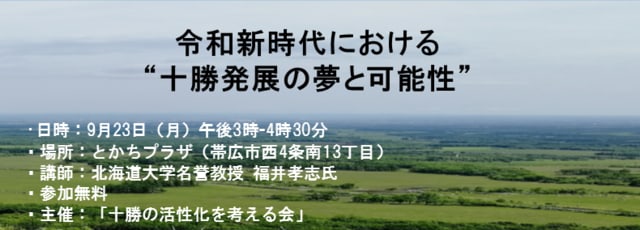令和元年8月18日、北海道税務局による「消費税」の講演を聞いてきた。意見は様々であるが、消費税率アップ(8→10%)は今年10月から実施されるが、私は消費税を以下のように考えている。
① 消費の一時的冷えこみにより、過渡的に不況が到来
② 二桁の消費税率は、消費者心理に大きく影響
③ 景気悪化に伴い、税収入にはマイナス効果
④ 消費税は全ての国民が払う税であり、公平感がある
⑤ 軽減税率もあること
⑥ 他国に類を見ない国の財政状況であり、財政健全化策のひとつ
消費税の税率アップに関しては様々な意見あるが、将来的には更にアップされる可能性がある。なぜなら、国の財政状況がそのぐらい悪化しているからだ。違った方策も考えられるが、そのためには国民の合意(選挙)を得る必要がある。増税は有効かつ将来を見据えた活用を考えてほしい。
いずれにせよ、1,100兆円をこえる国の借金(国債)を、どのようにしていけば良いかをみんなで考えよう。1,100兆円は、1人当たりにすると約900万円の額になる。
「十勝の活性化を考える会」会員
注) 消費税
消費税は、消費に対して課される租税。1953年にフランス大蔵省の官僚モーリス・ローレが考案した間接税の一種であり、財貨・サービスの取引により生じる付加価値に着目して課税する仕組みである。
消費した本人へ直接的に課税する直接消費税と、消費行為を行った者が担税者であるものの納税義務者ではない間接消費税に分類できる。前者の「直接消費税」にはゴルフ場利用税などが該当し、納税義務者が消費行為を行った者であって、物品またはサービスの提供者が徴収納付義務者(地方税の場合は特別徴収義務者)として課税主体に代わって徴収を行い、課税主体に納付することとなる。後者の「間接消費税」には酒税などが該当し、納税義務者は、物品の製造者、引取者または販売者、あるいはサービスの提供者であり、税目によって異なる。間接消費税はさらに課税対象とする物品・サービスの消費を特定のものに限定するかどうかに応じ、個別消費税と一般消費税に分類できる。
- 消費税
- 直接消費税
- 間接消費税
現在では160カ国ほどで導入され、OECD諸国の平均では税収のおおよそ31%を占めており、これはGDPの6.6%に相当する(2012年)。
日本においては、「消費税法に規定する消費税」と「地方税法に規定する地方消費税」の総称であり、付加価値税のひとつに分類される。
消費は所得の存在を前提として発生することから、消費に課税することによって所得税などで十分に把握できない所得に対して間接的に課税することになる。ただし、所得の中には貯蓄に回される部分があるために、所得の大小と消費の大小は必ずしも一致せず、消費者の消費性向が実際の消費税の負担に対して影響を与える。
(出典: 『ウィキペディア(Wikipedia)』より抜粋)