先日、地元作家 鳴海章の本「輓馬(ばんば)」を読んだ。本には、馬の血統のことが書かれていた。この血統であるが、競走馬にはダートに強い馬、芝生に強い馬など様々であるが、勝負の世界は結果が全てであり、レースに勝たなければ馬肉用として売られる馬もいる。
重賞レースを勝ったシンザンやディープインパクトなど引退を惜しまれて最期を迎える馬は、ほんの一部にすぎない。本「輓馬」は、2006年に“雪に願うこと”で映画化もされている。
ばんえい競走は距離200メートル、途中に二つの山がある。一気に山を登る馬もいれば、山の前で立ち止まりエネルギーを蓄える馬もいる。輓馬レースは人生と同じで、あまり無理をすると先行バテバテになるので注意しよう。ただ、先行逃げ切りの競走馬もいるが、あまり多くない。
本には、人間の見栄っ張りのことも書かれていた。都会人は見栄っ張りの人が多く、田舎から都会にでた人も見栄っ張りで頑張るようである。なお、作家鳴海章は、『ナイトダンサー』で第37回江戸川乱歩賞を受賞している。
「十勝の活性化を考える会」会員
注) ばんえい競走

帯広記念・第2障害を越えるカネサブラック(2013年)

ばんえい記念・ゴール前での競り合い(2010年)
ばんえい競走とは、競走馬がそりをひきながら力や速さなどを争う競馬の競走である。 現在、日本国内の公営競技(地方競馬)としては北海道帯広市が主催する「ばんえい競馬(ばんえい十勝)」のみが行われており、世界的にみても唯一となる形態の競馬である。本項目では、主に地方競馬としての「ばんえい競馬」について記述する。
「ばんえい」の漢字表記は「輓曳」となるが、公式表記は平仮名である為、当記事も公式表記に従う。
ばんえい競走では一般的な平地競走で使用されているサラブレッド系種などの「軽種馬」や北海道和種の「どさんこ」は使われず、古くから主に農耕馬などとして利用されてきた体重約800-1200kg前後の「ばんえい馬(重種馬。「ばん馬」ともいう)」が、騎手と重量物を積載した鉄製のそりを曳き、2箇所の障害(台形状の小さな山)が設置された直線200メートルのセパレートコースで力と速さ、および持久力や騎手のテクニックを競う。
帯広市が主催する地方競馬としての「ばんえい競馬」のほか、一部地域では「草ばんば」(後述)も行われるなど北海道が生み出した独自の馬文化として定着しており、それらを含めた「北海道の馬文化」が北海道遺産に選定されたほか、映画「雪に願うこと」やテレビドラマ「大地のファンファーレ」など、映画やドラマの題材にも幾度か取り上げられている。2006年までばんえい競馬を開催していた岩見沢市では、岩見沢駅(3・4番ホーム)にそりを曳く「ばんばの像」が設置されている。
(出典: 『ウィキペディア(Wikipedia)』より抜粋)

















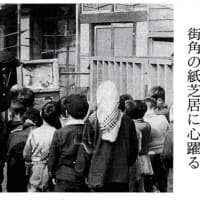


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます