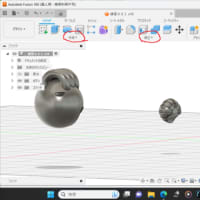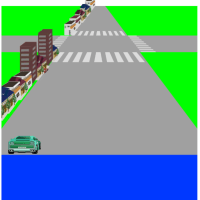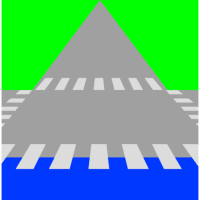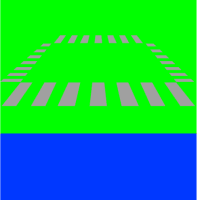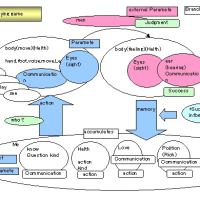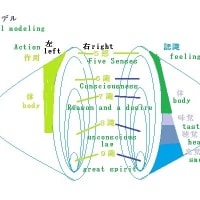0310_悪魔の祈り(002)裕也の冒険-南国の老女①-
-南国の老女①-
少女デルアドは、翌朝早くから苔(こけ)を集めた。
手さげの籠(かご)に山盛りに摘(つ)んだ。
そして、小高い丘の領主の古城へ向かう。
今日は、お婆(おばば)のところには寄(よ)らない。
町を突っ切り、はじめて少女は城を訪(たず)ねた。
石積みの老壁。堀(ほり)に木の橋が架(か)かっている。
壁や橋は、ところどころ欠けている。
少女は、周りを良く見渡した。
城に入るにはこの橋を渡るしかない。
衛兵(えいへい)らしき者は誰もいない。
(この国は、朽(く)ち果てようとしている)
自分の意思か?誰かが囁(ささや)く。
そう人々に思わせるような城の姿である。
もともと、城を訪(おとず)れるものはいない。
領主の持つ意義(いぎ)はエネルギーの流れにある。
土地のエネルギーは、自(おの)ずと領主に流れ支配される。そして、民へ。
歴史の上で、長い間この国を攻めてくる者もいない。
民を守るための兵士が居るわけではないのである。
少女デルアドは、橋を恐る恐るわたる。
「ギィイ。ギィイ」
足の下の木の板が軋(きし)む。
門の前までたどり着いた。
木で出来ている大きな両開きの門が聳(そび)えている。
声を出して呼んでみようかと思ったが、押しとどめた。
「お邪魔します」と聞こえないような小声で言うと扉を押してみた。
「ギィィィィ」(おぉぉ開く!)
少し中に動いた。
(もう少し押してみよう)
少女デルアドは、自分の体が城に入れるくらい扉を押し開けた。
「ギィィィィィ」
ズズゥーーーン。
中には、目の前に塔が三つ聳(そび)え立っている。
くるっと頭が回った気がした。
その手前には、土台の石創りの屋敷。
中央うにぽっかり空いた入口がある。
その前に老婆が一人、背中を丸めてたたずんでいる。
古びたボロボロの布(ぬの)を纏(まと)った衣服。
少し疲れて黒い影に沈んでいるように見えた。
少女デルアドは、恐る恐る喉(のど)の奥から声を絞り出した。
「す。す。すみません。お婆(ばあ)さんは、ここの領主ですか?」
「えへへへ。へ。
ごほぉん。
そんな大層な者に見えるかい。
単なるこの城に使える召使だよ」
老婆は、心の底から力を振り絞り堂々と言い放つ。
「領主様にお取次ぎ願います。
命の苔を献上(けんじょう)しに参りました」
少女デルアドは、恭(うやうや)しく言った。
本当は、祈りのエネルギーを宿(やど)した苔である。
少女は、適度に献上するのに見合う呼び名をつけた。
「その贈り物には、何か目的があるのかのう?」
老婆は、人が訪ねてきたのが嬉しいのか、何か嬉しそうである。
「私を書庫に入てください。
どうしても読まないといけない本があります」
そう聞くと老婆は、さっと少女の手から籠を取り上げた。
じっと見て、匂いを嗅(か)いだ。
(毒ではなさそうだ)
「その苔は、私がもらっとこかの。
ほら、書庫の鍵じゃ。
ほれほれ」
老婆は、何をしに来たのか見透かしていたのか、平然としている。
そして、苔を摘まみ口に運んだ。
少し老婆の顔に光が差した。
(これは、良い)
そして、老婆は石創りの屋敷の奥にある下へ降りる階段を指さした。
「お婆様(おばあさま)。ありがとう」
そう言うと、辺りを見渡してから、下へ降りる階段に向かった。
少女デルアドは、書庫にさえ入れれば満足なのである。
(なにかと文句(もんく)を言われない)
領主に知られない方が得策かもしれないと思った。
「最下位の部屋だよ」
老婆は、言い捨てる。
少女は、歩き出した。
暫くして、老婆もそっと少女の後ろについて行く。
少女は、気付く様子もなく、ゆっくり用心して階段を降りていく。
階段は、下に行くほど暗くなる。
だが、不思議と壁の蝋燭(ろうそく)の灯(あか)りが順に燃え周(まわ)りを照らす。
最後まで降り切った。
そこには、鬼の扉があった。
(書庫の扉!)
それは、鉄で出来ている扉である。
頂点に角のある黒い鬼の頭があしらわれている。
そこから黒い吐息が左右に二つずつ吐き出ている。
枠の下側に燃える太陽と金環の太陽。
華の弦が伸びている。
二つに分かれた扉は、右左の脳を表している。
(神経の模倣(もほう)?)
(知識?)
左の扉には、数字と言葉の塔が描かれている。論理の塔。
右の扉には、音楽と図形が街を形どっている。創造の都市。
扉は繋がって、宇宙を構築する。
それが、脳の中にある。
右の扉には鍵穴があった。
少女デルアドは、恐る恐る老婆からもらった鍵を刺す。
「ギュギュギュギュ」
回してみる。
「ゴォォォン。ガシャン」
扉が動く。
つづく。次回(悪魔の祈り(003)-南国の老女②-)
#裕也の冒険 #自作小説 #悪魔の祈り #裕也 #デルアド #南国の老女
※旧話は、随時、アルファポリスに掲載しています。
イラストは、少しか修正できませんでした。機会があれば色を塗ります。