
(写真は奈良県の田原本考古学ミュージアムにある、盾持人埴輪です。)
2010年度 147冊目 『漆の文化史』
記録のみ
四柳 嘉章 著
著者紹介
四柳 嘉章 (ヨツヤナギ カショウ)
1946年石川県生まれ。國學院大學史学科卒業。歴史学博士。現在、石川県輪島漆芸美術館長、漆器文化財科学研究所長、美麻奈比古神社宮司。専攻、漆器考古学、文化財科学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
岩波書店
岩波新書 新赤版 1223
2009年12月18日
224ページ 本体 798円
久しぶりに図書館に行く。
残念なことに『木々高太郎探偵小説選』(ミステリ叢書)が貸し出し中。
だが、先月から求めていた『漆の文化史』が書棚に。
これはラッキーとばかり、手にとる。
『漆の文化史』は思った通り、興味深い。
特に前半は漆や赤の持つ意味合いが丹念に記され、わたしにとってはおもしろい。
読書中に貼った付箋は前半に集中した。
奈良県某町展示室には赤く(実際には茶色)染まった木棺(あと)が置かれている。
残った赤は、水銀朱。
あれれと読みすすめると、水銀朱が産出する地方は限られており、全国的には漆が主に使用されていたらしい。
水銀朱は伊勢地方でとれたそうなので、伊勢との関係が深いの某町ならば、納得がいく賭場借り、一人妙に納得して遊んでいた。
漆は9000千年も前に使用されていたとのこと。
ホンマかいな?とばかり、読み進め、うなずく。
奈良時代は黒漆、平安時代には赤漆。
あとに著者の考えも付け加えられ、楽しい思い。
黒炭や柿渋を下塗りする方法には感心。
特に柿渋。
京都に生まれ育ったわたしには、友人宅などでごわごわとした柿渋紙を目にする機会は多かった。
柿渋紙は強く厚く、友禅の輪郭を描くゴムにも耐える。
おそらく、烏帽子や紙衣にも使われていたのだろう。
ここで話題が歌舞伎にずれてはなるまい!と、歯をくいしばる。
ベンガラが漆の一種だとは、この本を読むまで知らなかったわたし。
(注意:ベンガラは顔料です)
京都祇園の壁など多くの地方で美しく彩っている。
そうだったんだとわかりもせずに、妙に納得。
古くは 壁に漆や赤を塗り、外からのケガレの侵入を防具といった意味合いもあるのだろうか。
妄想はつきない。
後半、わたしの関心ごとの一つである「文様」にも触れられている。
「蝶文様」について多くを語られていたが、これは中国の吉祥文様に通じる。(これは本文でも書かれていた)
不思議なことに、イランでも「蝶文様」は古くから多く描かれる。
イランも中国や日本と同様、吉祥や祈願を込めた模様、絵柄が多い。
「百足文様」も書かれていた。
百足は毘沙門に関係が深いので、奈良県の信貴山 朝護孫寺にも金色の百足が描かれているよと嬉しい思い。
全体を通して、おもしろい^^
この本は、お勧め致します。
岩波書店より ▼
[要旨]
日本を代表する工芸品として誰もが認める漆器.しかし,その文化の成り立ちや,技法,社会的な広がりについては,意外にも未知のままであった.著者は,縄文から近代まで,土中より発見された漆製品に科学分析の光をあて,その謎に迫る.民俗学の手法や絵巻物・文献資料も活用し,名品鑑賞からだけでは到達できなかった,初めての文化史を描き出す.(カラー口絵一丁)
[目次]
第1章 漆をさかのぼる―縄文漆器の世界(縄文ウルシの発見;九〇〇〇年前の赤色漆塗りの衣服 ほか)
第2章 漆器が語る古代国家(古墳時代の漆の祭;捧げ、祭られる漆 ほか)
第3章 暮らしの中に広がる漆器(食品で作る「時間の物指し」;各地で働く工人たち ほか)
第4章 日本の各地で生まれる漆器―食文化の変遷の中で(広がる近世の漆器産地;合鹿椀―木地屋が塗った漆器 ほか)
コメント一覧

乱鳥より pinky様

pinky
最新の画像もっと見る

『俵藤太物語絵巻』二度目を読む 21 三軸 北山の陣での対戦。影武者六人と並ぶ将門 秀郷たちの軍は将門の陣を攻めた。将門の体は金属で、同じ姿のものが六人いた。官軍は破れて退いた。

『俵藤太物語絵巻』二度目を読む 21 三軸 北山の陣での対戦。影武者六人と並ぶ将門 秀郷たちの軍は将門の陣を攻めた。将門の体は金属で、同じ姿のものが六人いた。官軍は破れて退いた。

『俵藤太物語絵巻』二度目を読む 21 三軸 北山の陣での対戦。影武者六人と並ぶ将門 秀郷たちの軍は将門の陣を攻めた。将門の体は金属で、同じ姿のものが六人いた。官軍は破れて退いた。

『俵藤太物語絵巻』二度目を読む 21 三軸 北山の陣での対戦。影武者六人と並ぶ将門 秀郷たちの軍は将門の陣を攻めた。将門の体は金属で、同じ姿のものが六人いた。官軍は破れて退いた。
最近の「民俗学、柳田國男、赤松啓介、宮田登、折口信夫」カテゴリーもっと見る

『狐猿随筆』 柳田國男 岩波書店(2011/03発売) /バッハ Bach: 無伴奏チェロ組曲 第1番 ト長/

『身毒丸 』 折口信夫 23 彼の聨想が、ふと一つの考へに行き当つた時に、跳ね起された石の下から、水が涌き出したやうに、懐しいが、しかし、せつない心地が漲つて出た。

『身毒丸 』 折口信夫 22 彼は花の上にくづれ伏して、大きい声をあげて泣いた。すると、物音がしたので、ふつと仰むくと、窓は頭の上にあつた。

『身毒丸 』 折口信夫 21 彼は耳もと迄来てゐる凄い沈黙から脱け出ようと唯むやみに音立てゝ笹の中をあるく。

『身毒丸 』 折口信夫 20 あけの日は、東が白みかけると、あちらでもこちらでも蝉が鳴き立てた。昨日の暑さで、一晩のうちに生れたのだらう、と話しあうた。
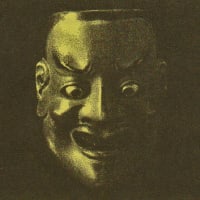
『身毒丸 』 折口信夫 19 分別男や身毒の予期した語は、その脣からは洩れないで、劬る様な語が、身毒のさゝくれ立つた心持ちを和げた。
最近の記事

『俵藤太物語絵巻』二度目を読む 21 三軸 北山の陣での対戦。影武者六人と並ぶ将門 秀郷たちの軍は将門の陣を攻めた。将門の体は金属で、同じ姿のものが六人いた。官軍は破れて退いた。

『俵藤太物語絵巻』二度目を読む 20 中巻読了(次回から下巻) 東海道を行く官軍 朝廷からはさらに軍勢を下総に向かわせた。

『俵藤太物語絵巻』二度目を読む 19 中巻 秀郷は、三井寺斗その守護神である新羅大明神に参拝して加護を祈り、下総に向かった。

『俵藤太物語絵巻』二度目を読む 18 中巻 将門に対面する秀郷 将門の服装や食事の態度が不作法なのを見て、秀郷は軽蔑し、考えを変えた。

『サルヴァドール・ダリ&アルフォンス・ミュシャ(ムハ)展』内『ダリ展』のみ 全26景
カテゴリー
- 繰り返し記号 memo(5)
- 読書全般(古典など以外の一般書)(1057)
- 哲学(129)
- ギリシア神話(53)
- 古典全般(奈良〜江戸時代)(44)
- 漢文(7)
- 文学入門(17)
- 民俗考・伝承・講演(194)
- 民俗学、柳田國男、赤松啓介、宮田登、折口信夫(176)
- 絵巻物、縁起絵巻、巻物、絵解き掛け軸、屏風(223)
- 変体仮名見むとするハいとをかし(43)
- 草双紙:洒落本、仮名草子、黄表紙、黒本、赤本、合巻 等(109)
- 絵本百物語 桃山人著(11)
- 疫病:疱瘡心得草 他(24)
- 俳諧、連句(『役者手鑑』などを含む)、狂歌(18)
- 在原業平、そして、伊勢物語 と、仮名草子 仁勢物語(125)
- 紀貫之(20)
- 菅原道眞(37)
- 説経節、幸若舞、舞の本等(31)
- 浄瑠璃、文楽について(2)
- 近松門左衛門(87)
- 滝沢馬琴(43)
- 井原西鶴(140)
- 山東京傳(140)
- 十返舎一九(44)
- 式亭三馬(3)
- 古事記、日本書紀(5)
- 梁塵秘抄(今様)(5)
- 鴨長明(6)
- 竹取物語(3)
- 源氏物語(35)
- 枕草子(137)
- つれ/″\種→徒然草 詳密色彩大和絵本(八十六段より)(40)
- 和歌、短歌(43)
- 本居宣長 『古今集遠鏡』『玉あられ』(37)
- 藤原定家『明月記』(5)
- 名作歌舞伎全集/古典文学全集(浄瑠璃含)、歌舞伎関係本(39)
- 観世流(続)百番集、日本古典文学大系(謡曲)、能楽関係本(68)
- ことのは(276)
- 書道(2)
- お出かけ(1090)
- 110㏄でお出かけ(5)
- 神社仏閣・祭り(190)
- 美術・文様・展示物(348)
- 歌舞伎(135)
- 能楽・狂言(98)
- 舞台・芝居(100)
- TVで 歌舞伎・能楽(376)
- TVで舞台(74)
- 音楽Live(45)
- クラッシック音楽(43)
- 映画(1026)
- ドラマ(208)
- 舞台・音楽 雑感メモ(470)
- イラン2007~2010(6回)(120)
- 中国 2006~2019(7回)・台湾・ベトナム(122)
- オーストリア・チェコ(22)
- トルコ・エジプト(51)
- 資料での旅(11)
- ヨーキなモモちゃん(26)
- 乱鳥徒然 Rancho's room.(1630)
- Ranking(順番考え1,2,3!)(6)
- 落書き Rancho's picture. 2022年月から(8)
- 外メシ、うまし。家メシ、うまし。昼弁当は、尚も良し。(32)
- ブックマーク(2013年時点)追加予定(1)
バックナンバー
人気記事



