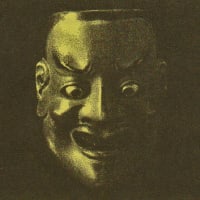2012年 本
1: 『演者と観客 生活の中の遊び』(日本民俗文化大系7)から「田楽」(95-126)

昭和五十九年 初版
小学館
日本民俗学会
494ページ 4500円
著者代表 大林太良
網野善彦
大林太良
高取正男
谷川健一
坪井洋文
宮田 登
森 浩一




昨年の暮れに春日大社のおん祭に行ったので、以前読んだ『演者と観客 生活の中の遊び』(日本民俗文化大系7)から序文、第一章、第二章の中からさらに短い「田楽」部分だけを読む。
但し おん祭「田楽」は「細男」の前で見ることができなかった。今後見る機会もあるだろう…。


わたしが見たのは「細男」~最終まで
とりあえず、本を読む前に freshペディアをみる。次のように書かれていた。
田楽(でんがく)とは、平安時代中期に成立した日本の伝統芸能。楽と躍りなどから成る。
「田植えの前に豊作を祈る田遊びから発達した」「渡来のものである」などの説があり、その由来には未解明の部分が多い。




memo 1 (ほんの一部分)
類感呪術 96
『栄花物語』 98
大田植(花田植) 広島
早処女(本書では、「早処女」そうとめ)
相聞の形 99
田をたらしめる神 薩摩 99
翁姿
能『翁』や『三番叟』
太鼓中心 楽打ち 九州 101
『田楽者』 105
交わり
1/14 祝言、呪言、呪礼 長野 109
赤い着物に嫗面をかぶったものが翁面とぴょんぴょん跳ねるというくだり
「神婆 かんば」
翁と女 109-
五穀豊穣と子育て祈願 新潟(奈良や全国でも見られる)




memo 2 (ほんの一部分)
風流田楽 114-
散楽・猿楽と結びついていた田楽
↓
平安時代中期 風流田楽
熱狂を誇った田楽 118
田植 野性味とエロチシズム + 舶来のギラギラしたエキゾチシズム
(ニューミュージックのような感じ)
田楽芸能の魔力 118-
 125
125注意
資料引用は 『演者と観客 生活の中の遊び』(日本民俗文化大系7)と、一部freshペディア