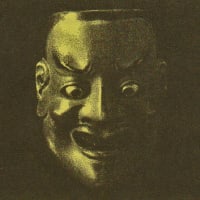(写真は京都の東福寺にある雪舟寺。私の好きな寺の一つ。)
記録だけ
2008年度 99冊目
『宮田登 日本を語る 11 女の民俗学』
宮田登 著
発行所 吉川弘文館
2006年12月10日
217ページ 2730円
『宮田登 日本を語る 11 女の民俗学』を読む。
こちらも、面白い。
歌舞伎に『女殺油地獄』は民族学的にも非常に重き意味合いがあるんだな。
去年の七月に、大阪の松竹座で仁左衛門丈の『女殺油地獄』を三度ばかり観ていたので、宮田氏の書いてあることが手に取るように分かったよ。
芝居も見ておくものだな^^
女の霊力関係の本は、以前に同作者で読んでいたので、わかりやすかった。
他にも早乙女祭や繭、女の家、持ち場ナ、おしら様、喜界島やいろんな話がいっぱいで・・・興味は尽きなかった。
先日読んだ宮田登 日本を語る 7 も、良かったが今回も印象深い。
ただ、宮田登 日本を語るは近くの図書館には無かったので、他の図書館に借りていただいたんだ。
ちょうど手に届くまでに一ヶ月半もかかっちゃったので、次に頼むとすれば十一月だな。
それまで宮田登氏のホントもお別れかと思うと、少し寂しいな。
|
下は宣伝のようになっています。 ・・・が、お金儲けはしておりません(笑み) 自分の記録のためにアドレスを貼っています。 | |
|
http://www.yoshikawa-k.co.jp/miyata1.htm 宮田登シリーズ 全16巻 案内HPより |