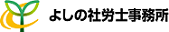こんにちは!社労士の吉野千賀です!
今日は全国的に冷え込んでいますね。東京も8度と一ケタ台の寒さ、そして小雨。ブルブルッ。
寒いと身体も気持ちも縮こまってしまいますね。今夜は温かいお鍋でも食べましょうか。
さて、先日、厚生労働省が平成23年の「障害者雇用状況」を公表しました。
<民間企業>(法定雇用率1.8%)
・雇用障害者数は 36万6,199人 と過去最高を更新 ← 昨年度より4.8%の増加
・実雇用率は 1.65%
・法定雇用率達成企業の割合は 45.3%
1 障害者雇用の法定雇用人数
障害者雇用促進法では、社会連帯の理念に基づき、事業主に対し、常時雇用する従業員の一定割合(法定雇用率、民間企業の場合は1.8%)以上の障害者を雇うことを義務付けています。1.8%というと、従業員56人に1名雇用という割合です。
2 実態は二極化
実雇用率1.65%となっていますが、60%の企業はゼロ採用です。
その反面、2%以上を雇用している優良企業(大企業、特例子会社など)もあり、障害者雇用の実態は二極化となっています。
2%以上雇用の企業は、ユニクロ・スターバックス・シマムラ・資生堂・NTTなどが有名です。
3 未達の場合は納付金の支払い義務
平成27年4月から100人~200人規模の企業に障害者雇用納付金制度の対象が拡大されることになっています。
ゼロ採用を続けていると、満たない障害者数1人当たり月額5万円の納付金が徴収されます。
例えば、168人の会社では3名の障害者雇用が義務化されていますが、ゼロ採用の場合、年間180万円の納付金が徴収されることになります。
中小企業もそろそろ障害者雇用を現実的に考える時期にきていますね。
明日も障害者雇用について書いてみます。
【関連記事】障害年金請求サポート専門社労士吉野千賀ブログの「障害者」記事一覧
See you tomorrow!
Chika Yoshino
障害年金請求サポートの「よしの社労士事務所」 吉野千賀
今日は全国的に冷え込んでいますね。東京も8度と一ケタ台の寒さ、そして小雨。ブルブルッ。
寒いと身体も気持ちも縮こまってしまいますね。今夜は温かいお鍋でも食べましょうか。
さて、先日、厚生労働省が平成23年の「障害者雇用状況」を公表しました。
<民間企業>(法定雇用率1.8%)
・雇用障害者数は 36万6,199人 と過去最高を更新 ← 昨年度より4.8%の増加
・実雇用率は 1.65%
・法定雇用率達成企業の割合は 45.3%
1 障害者雇用の法定雇用人数
障害者雇用促進法では、社会連帯の理念に基づき、事業主に対し、常時雇用する従業員の一定割合(法定雇用率、民間企業の場合は1.8%)以上の障害者を雇うことを義務付けています。1.8%というと、従業員56人に1名雇用という割合です。
2 実態は二極化
実雇用率1.65%となっていますが、60%の企業はゼロ採用です。
その反面、2%以上を雇用している優良企業(大企業、特例子会社など)もあり、障害者雇用の実態は二極化となっています。
2%以上雇用の企業は、ユニクロ・スターバックス・シマムラ・資生堂・NTTなどが有名です。
3 未達の場合は納付金の支払い義務
平成27年4月から100人~200人規模の企業に障害者雇用納付金制度の対象が拡大されることになっています。
ゼロ採用を続けていると、満たない障害者数1人当たり月額5万円の納付金が徴収されます。
例えば、168人の会社では3名の障害者雇用が義務化されていますが、ゼロ採用の場合、年間180万円の納付金が徴収されることになります。
中小企業もそろそろ障害者雇用を現実的に考える時期にきていますね。
明日も障害者雇用について書いてみます。
【関連記事】障害年金請求サポート専門社労士吉野千賀ブログの「障害者」記事一覧
See you tomorrow!
Chika Yoshino
障害年金請求サポートの「よしの社労士事務所」 吉野千賀