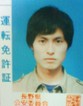2019年、12/23(月)~29(日)、ちひろBLUES作品展「ちひろdeアート 2019」を開催しました。
「【お知らせ】ちひろBLUES作品展「ちひろdeアート 2019」開催します!(12/23~29、ちず屋の2階)」
12/24(火)~27(金)の4日間はトークイベントを開催し、12/24(火)のゲストはぺがさす荘の店主のぺがはるかさんでした。
「12/24(火)、「ちひろdeアート」2日目も無事終了!ぺがはるかさんと朗読的×チェロのセッション、トークイベントも行いました!」
(トークの前に、僕の朗読とぺがさんのチェロのセッションを行ったのですが、そこで朗読したものはこちらです)
「朗読劇用書き下ろし小説『君と演劇』」
というわけで、トークの書き起こしを公開します。
ちひろBLUES作品展「ちひろdeアート 2019」トーク1日目
(2019.12.24 ゲスト:ぺがはるかさん)
ちひろ じゃあ、トークイベント、始めていきたいと思います。一応最初に説明しておくと、今日から4日間、毎晩20時から1時間くらい、トークイベントをやっていこうと思っています。今回の「ちひろdeアート」の最初のゲストが、ぺがはるかさんです。
ぺが よろしくお願いします。
(拍手)
ちひろ よろしくお願いします。ぺがはるかさんは、ぺがさす荘というお店を。
ぺが そうですね。
ちひろ Art Cafe&BAR。
ぺが はい。自分でもよく分からないけど。
ちひろ そういう場所が新潟市内にあって。僕は、毎月トークイベントをやっているんですけど、それの会場にいつも使わせていただいますね。
ぺが そうですね。夏くらいから。
ちひろ もともと、ここ、ちず屋の2階で、去年の年末に初めてトークイベントをやって、それが面白かったから1月から続けようって、最初はちず屋の2階で毎月やってたんですけど、7月にやった時にめちゃくちゃ暑かったんですよ、ここが。
ぺが エアコンないんですか?
ちひろ エアコンあるんですけど、あんまり効かないんですよ、古いエアコンで。
ぺが 木製ですもんね。
ちひろ 木製じゃないですけど。それで、あまりにここが暑いから、どこかエアコンが効いていて使える会場ないかと探した時に、一緒にやってたよしこさんがぺがさす荘をちょうど知ってて。
ぺが ちょうどその前くらいに来てくれて。
ちひろ それで、ちょっと遊びに行って、それから毎月やってます。
ぺが はい。ありがとうございます。
ちひろ ありがとうございます。それで、チェロを弾くってことで…(このトークの前に、ちひろの朗読とぺがさんのチェロでコラボをした)
ぺが ちょうど先月、中央ヤマモダンさんっていう新潟でコントをやっている集団がいるんですけど、ヤマモダンさんと、森田花壇さんっていうすごく大好きなフォークシンガーの方がいるんですけど、その方達がイベントをぺがさす荘でやりたいということで。大体2~3ヶ月くらいに1回やって、今、第3回までいってるのかな、そのくらいのペースなんですけど。先月の、その第3回の時に、ヤマモダンさんの読むコントという、朗読系の面白い話の時に、ちょっとチェロを合わせてみようって話になって。もともとクラシックやってたんですけど、大学からバンドをやり始めて、チェロとバンドってあんまり融合って形があんまりなくて。バンドをやるって言っても、後ろにシンフォニーを迎えて、その前で4人のロックバンドが演奏するとかはあるんですけど、アルバムとかも。もうちょっと、クラッシックってイメージしかない楽器を色んなことに使っていきたいって、結構前から思ってて。それで、一緒やりましょうってことで。今回、第二弾です、こういう形でやるのは。
ちひろ なるほど。中央ヤマモダンに続き、「ちひろdeアート」。ありがとうございます。
ぺが 朗読と、本当にやりたかったんですよ。
ちひろ あ、そうなんですか。
ぺが そう。もともと、宮沢賢治とかの朗読に合わせてとかイメージしてたんですけど。
ちひろ まさに「セロ弾きのゴーシュ」
ぺが フフフ…それをオリジナルの短編と一緒っていうのは、なかなか面白いことだなと思って。ありがとうございました。
ちひろ 僕もよく分からずやってるんですよ。
ぺが いや、いいと思いますよ。僕も分かんないですから。聞いた方がどう思ったのかが一番大事なのかなと思うんですけど。
ちひろ 帰りにすごいTwitterに、「クソ朗読が!死ねちひろ!」とか書かれるかも知れないですけど。
ぺが ハハハ!「何だあれは!時間を無駄にした!」みたいに言われてるかも知れないですね。
ちひろ 朝起きたら炎上してるかも知れないですね。
ぺが ハハハ!
ちひろ そんなことはないことを願って。
ぺが 面白かったですね。汗かきましたけど。
ちひろ なんか、緊張しますね。
ぺが 緊張します。
ちひろ しかも、1回合わせたくらいでしたもんね、ぺがさす荘で。
ぺが うん。多分、あんまり練らない方がいい気がするんですよ。ストーリーとかをリハーサルみたいにやるのはいいと思うんですけど。あんまりガチガチにやっても、面白くないというか。そういうスタンスでいきたいなと思って。わりと即興みたいな方が。
ちひろ そうですね。そっちが向いてるかも知れないですね。それは僕も感じています。何かありますか?朗読について、せっかくなので。
ぺが 俺も、ちひろさんが朗読を毎年このイベントでしてるって聞いて。
ちひろ 毎年って言っても、まだ2年目ですけど。しかも去年と同じ話ですからね。
ぺが なるほど。それを、朗読やってるって聞いて、提案ちょっとしたじゃないですか。チェロとやってみませんか、みたいな。面白そうなんで。
ちひろ はい。
ぺが で、全然乗ってくれて。それで、ブログに載せてるんですよね、その話。
ちひろ そうですね。
ぺが それで、読み始めたんですけど、何とも言えない話だと正直思ったんですよ。
ちひろ ハハハ!面白くもなく、つまらなくもなくみたいな。
ぺが でも俺、結構淡々としてる話好きで。
ちひろ あ、そうなんですか。
ぺが うん。メッセージがあるとか、ありすぎても俺、ちょっと嫌なんですよ。でも、あった中で、多分何かを感じたから作品にしたわけだと思うんですけど。それを、説明とかをあえて省いてたりとかするのかなと思って。
ちひろ ああ。そう…かも知れないです…
ぺが ハハハ!
ちひろ ハハハ!いや、淡々とした話、僕も好きで。ただ話が進んでるだけの話って、結構嫌いじゃないんですよ。
ぺが 俺も好きですね。
ちひろ 何でか分からないですけど、作品にすると、作品になるんですよね。ただ何かが起きてるだけの話でも。
ぺが 普通の話でもね。
ちひろ ただの日常とかでも、文字に起こすとか、言葉にするとか、作品にすると、意外となんてことない話が、ちゃんと作品になると思ってて。
ぺが そうですよね。俺、全然劇団とか、所属したこともなければ、正直まだ観たこともないんですよ、ちゃんとした演劇を。これから観たいなとは思ってるんですけど。
ちひろ 唯一観たのがヤマモダンみたいな。
ぺが あれは劇団なんですか?
ちひろ あれはコントですね。劇団ではないですけど、ちょっと劇団に近いところにはいる。
ぺが そうそう。それが初めてくらい。それも、観たの今年ですから。
ちひろ じゃあ、すごい最近なんですね。
ぺが 5月くらいに初めてヤマモダンさん観て。なので、そういう全然知らないところの話を、淡々と見せられるっていうのは、結構好きなんですよ、面白くて。
ちひろ なるほど。
ぺが 劇団も、そういうサークルとかも。そういう話ですよね、大学のサークルの。部活ですか?
ちひろ そうですね。ノンフィクションでは全然ないんですけど。
ぺが ある程度、実体験に基づいてるのかなと思って。
ちひろ 昔、お芝居を松本でやってて、そのあと新潟でちょこっとやって、今は全然やってなくて、トークイベントとかやってるんですけど。辞めたんですけど、やっぱり昔やってたから、ちょっと気になるんですよね、お芝居のこととかが。自分の中でお芝居に対して、思うところと言うとちょっと大袈裟ですけど、ちょっと考えちゃったりする部分があって。色々な作品とか見て。
ぺが うん。
ちひろ やっぱりあります?バンドとかをやってたじゃないですか。
ぺが はい。
ちひろ そうすると例えば、世の中の音楽に対してちょっと敏感になるとか、やっぱりバンドの人とかもあるんですか?
ぺが うーん、でも、そこまで有名な曲とか、流行りの曲とか、昔から全然分からないんで、それはそんなに。
ちひろ あ、そうなんですか。
ぺが あ、このアーティストさん、すごいんだとか。例えば米津玄師さんとかは、よく聞くんで、調べたりしましたけどね。Wikipedia見たりとか、すごい人なんだなとか思ったりとか、そういうのはありますけど。なんだろう、そんなに敏感じゃないかも知れない。ハハハ…
ちひろ 僕は結構、調べてたんですよね、新潟のお芝居とかを。そういう体験があったからだと思うんですけど。
ぺが 結構、学者みたいなスタイルですよね。
ちひろ 学者ですか。
ぺが トークイベント「おはなし図鑑」、お店やりながら見たんですけど、結構入念に調査して、メモを作ってくるっていうか。
ちひろ あれはですね、去年初めてトークイベントやって、朗読劇もトークイベントも、去年の「ちひろdeアート」の初日が人生ほぼ初めてみたいな状態で、しかも一人で、誰かに習ったとかじゃなくて、全部自分でやったから、ものすごい緊張して、ものすごいテンパったんですよ。で、どうしたらいいんだって思ったら、父が「『徹子の部屋』を見て勉強しなさい」って言って。
ぺが ハハハ!なるほど。
ちひろ 何で「徹子の部屋」なんだって思って。目指すには大御所すぎるじゃないですか、徹子さんって。
ぺが もう、すごい番組ですからね。
ちひろ ただ、徹子さんは、毎回入念に調べるらしいんですよ。トークの内容とか、ゲストのこととかを。で、そこでメモをいっぱい見ながら、色んな質問をしていくってスタイルでやってて。あ、やっぱり予習ってした方がいいんだなって思って。
ぺが 徹子さんも結構適当にやってるわけじゃないんですね。
ちひろ やってないです。あの人はちゃんとやってる人ですよ。
ぺが 徹子さん、すごい人なんですね、やっぱり。
ちひろ すごい人ですよ、徹子さんは。
ぺが 考えられてるんですね、あの番組は。
ちひろ ちゃんと調べて、ああいう質問をしてるんですよ。
ぺが なるほど。
ちひろ それに多分、芸人さんたちが、やっぱり大御所の人からどんな質問が来るんだって緊張しちゃうから、ネタを振られると緊張しちゃうみたいなことが起きるんですよ。それが無茶振りみたいなね。
ぺが ひどいっすよね。公開処刑みたいな。ハハハ!
ちひろ ハハハ!なんか、話がどんどんそれていったんですけど、さっきの演劇の話まで戻すんですけど。お芝居をやってて、辞めたんですけど、自分でお芝居をやってたこととか考えて、辞めたけど結構面白い体験をしていたと思っていて、ある意味貴重な体験というか、あんまりやらないじゃないですか。だから、それを作品とかにできたらいいなと思って。
ぺが なるほど。
ちひろ お芝居をやってると、お芝居がうまくいかない体験とかの方が多いと思うんですよ。だから、お芝居がうまくいかない話が書きたいなと思って。
ぺが なるほど。結局、公演には至ってないですからね。
ちひろ 至ってないですからね。
ぺが 失敗にもなってない失敗みたいな。
ちひろ でも、そういう話が多分、日本中にいっぱいあると思うし。
ぺが 結構いっぱいあるんですかね。
ちひろ バンドとかでもいっぱいあると思うんですけど。
ぺが ありますね。
ちひろ 結成せずに解散みたいな。
ぺが 結成してライブしないで解散は多分いっぱいあると思いますね。
ちひろ そういうアイドルとかもいっぱいいると思うんですよ。そういう人の話が書きたいと思ったんですよ。
ぺが なるほど。多分、色んなところに当てはまるような話ですね。
ちひろ あと、お芝居やめたんですけど、自分がまたお芝居やるとしたら、何も知らない状態でやりたいと思ってて。例えば、どこかの劇団に入って仲良くなった劇場でとかじゃなくて、お芝居のことを何も知らないでぽんと舞台に上がってみたいみたいな気持ちになって。
ぺが もう知っているにもかかわらずってことですか。
ちひろ でも、よく知らないから、僕も。やってたけどよく分からなかったんで。演劇とかがない世界でいきなり演劇やるみたいな。
ぺが それがBLUESだったわけですか?
ちひろ いや、それが今日の朗読です。BLUESは松本にもともと劇団があったので。
ぺが じゃあ、最初からもともと劇団に興味がちひろさんはあったわけじゃなくて、誘ってくれた人がいるわけですね。そうやって、知らない世界に。
ちひろ すごい、僕の方が質問されてる。
ぺが ハハハハハハ!逆に。でも今日、ちひろさんのことも聞いてみたいなと思って。
ちひろ そうですね、お互いのことを聞いていきましょう。僕は、大学の時に、この話の主人公にちょっと通じる部分かも知れないですけど、あんまり学校とかにだんだん行けなくなっていって、就活もしてなかった時に、ふと演劇に誘われて。演劇をやった友達がいたんですよね。こういうのやってみたら面白くない?みたいなことを言われて。で、やったら楽しくて、就職決まらないで卒業したんですけど、特に目標とかないけど、面白かったから演劇続けることにして。松本でフリーターをやりながら。というのが最初で、そうしたらBLUESって劇団を、僕が大学を卒業するくらいに作った、当時高校生の僕の4つ下の男の子がいて。彼は北海道のTWAM NACSって劇団に憧れていて。大泉洋さんとかがいる、「なつぞら」ってドラマに全員出てたりしたんですけど。ああいうのに憧れてて、松本でやりたいって言ってて。そこで若手で演劇始めた人がいたと知って声かけてくれたんですけど、すごく面白くて。ギャグばかりやる劇団で、それが面白くてやっていたんですけど。でも僕もちょっと障害とかがあったり、仕事に行けなかったりすることが続いて、演劇を続けるのが難しくなったから、新潟に帰って来たみたいな感じです。で、ちょっと新潟でも演劇やったけど、それより今の「ちひろdeアート」とか、トークイベントとかの方がどっちかと言うとやりたいなとなっていったのが、今です。そういう感じです。
ぺが 大学行けなかったとか、俺すごい分かるんですよ。俺も全然大学に行ってない時期とかいっぱいあって。新潟大学の院まで一応行ったんですけど、院生になってから特に学校行かなくなっちゃって。専門学校みたいな学校だったんで、新潟大学の中で。検査技師って職業が医療系であるんですけど。1年生だけ、好きなだけ遊んでいいよみたいな。遊んでるわけにもいかないですけど、結構遊べる時間があって。2年生以降は、座学と実習で一日缶詰みたいな。
ちひろ 医学部、忙しいって言いますもんね。
ぺが 他に比べたら、ウチ、マシな方だったと思うんですけど。先生も優しかったし。1限、8時半からあるんですけど。まあ、起きられないじゃないですか。大体、10時くらいになってるんですよ、早くても。遅いと昼過ぎになってるんですけど。昼過ぎになると、午後の実習が始まってるんですよ。ヤバいなってなって、実習ももう遅れてるぐらいなわけですよ。実習って最初行かないと、結構もう班の中で「この野郎」みたいなことになるわけですよ。そういうので、行きたくないなと思って、行かないと単位が取れないしなみたいな。夕方ぐらいに学校に行って、そうすると学校が全部暗いんですけど、実習室だけ明かりが点いてるわけですよ。それを俺、2階から実習室を覗いて、「あー、みんな実習頑張ってるな…」って思って、帰るっていう。ハハハハハハ!!
ちひろ ハハハハハハ!!
ぺが よくやってました。
ちひろ 気持ち分かりますね、その感じは。
ぺが さすがに今更行けないな…みたいなね。それが結局どんどん続いてくんですよ。まあ、卒業はできましたけど。
ちひろ 良かったですね。
ぺが 先生、優しかったんで。ハハハ…
ちひろ 僕も先生が優しくて何とかなりました。
ぺが いい先生に会うといいですね。
ちひろ 恩師です。
ぺが 本当に恩師。向こうは二度と会いたくないって言ってる。ハハハハハハ!!
ちひろ ハハハハハハ!!
(笑)
ちひろ 僕、就活しなかったんですけど。1回就職したんですよ、松本で。ヘルパーの資格を取ったんですよ。学校に通って、卒業したあとで。
ぺが へえー。真面目な時期があったんですね。
ちひろ 真面目な時期があったんですよ。卒業して、ヘルパーの学校に通って。そこはすごい楽しかったんですよ。大人達の学園生活みたいな感じで。
ぺが 専門学校みたいな感じですか?
ちひろ そうですね。それの短期バージョンみたいな。4か月くらいだけ通うんですけど。でも国から補助もらえるんですよ。
ぺが へえー。
ちひろ で、一応、松本市内の老人ホームに就職したんですけど、すごい忙しくて。朝早いと6時くらいからで、夜勤とかも日によってはあって、遅番もあってみたいな。で、やめちゃったって感じなんですけど。やっぱり躁鬱なので、躁の波があると、よっしゃ!頑張るぞ!ってなって、ものすごいやる気で、「こいつは真面目だ」みたいな感じで言われたりしてたんですよ。その人が、2ヶ月後にもう辞めてるっていう。
ぺが それが、躁が終わった瞬間に、それと一緒に辞表を出すみたいな。
ちひろ そうです。ちょっと前に、よしこさんから「アートって何?」ってコメントが来てて。よく考えたら、今日のテーマ「アート」なんですよ。当初の予定のトークテーマとしては、アートについて考えようという。
ぺが 重い話題だ。
ちひろ 重い話題を軽々しくやろうっていう。
ぺが ハハハ!アートについてはすごい重いですよ、今。
ちひろ でも、僕は「ちひろdeアート」じゃないですか。で、「Art Cafe&BAR」のぺがさす荘じゃないですか。
ぺが 確かに。
ちひろ 我々の共通点はアートです。
ぺが 何もアートを知らない人間がアートを名乗ってるっていう。
ちひろ でも、アウトサイダーアートって言葉もありますから。
ぺが なるほど。そっちにしましょう。あんまり怒られない方向で。
ちひろ 我々もアウトサイダーアーティストですから。
ぺが ハハハ…今年は結構、色々ありましたからね、アートの話題は。
ちひろ ありましたね!それ行きます!?
ぺが それもう行くでしょ!「あいちトリエンナーレ」とか、炎上してましたからね。
ちひろ 中でも、「表現の不自由展」ですよね。今年の夏に。ちょっと見に行ってみたかったですね、僕は。
ぺが 色んな思惑があるんだろうなって思いましたね。でも、トータルすると、やっぱりあれアートなんですよ。全部の流れをまとめると、もうそれ自体がアートになってるなって思って。
ちひろ はいはい。
ぺが もともと、結構、俺、リベラルよりも保守寄りの人間なんですけど。
ちひろ あ、そうなんですか。結構、パンク精神の人だと思ってたから、あんまり保守のイメージがなかったんですよ。
ぺが どうなんだろう。でも、リベラルではないんですよね。
ちひろ へえー。
ぺが でも、あれに関しては、アートだろうと思います。
ちひろ 表現の不自由展に関しては。
ぺが 表立ってるのが税金とかだったら、しょうがないかなとは思うんですけど。でも、あの作品自体を見せた時に、誰かが何か感じた時点でアートなんですよ。
ちひろ そうなんですよね。
ぺが 何か考えさせられたら。怒りでも何でもいいんですけど。
ちひろ しかも、千差万別じゃないですか、人々の考え方が。あれを見て、「あの歴史が…」みたいに感じる方もいれば、「これは侮辱だ」って怒りだす人もいるわけじゃないですか。一人一人が感じるのが自由なんですけど、「あいちトリエンナーレ」の面白かったのが、Twitterにそれが流れていくじゃないですか。で、見てない人が怒ったり、見てない人が擁護したりするじゃないですか。だから、本当にみんな考え方が全然違うんだなというのが、すごい分かっちゃって。それを見た時に、そっか、色んな人の心を動かすけど、その動かし方がそれぞれ違うんだって。それはもうアートなんじゃないかって思ったんですよ。
ぺが 俺は、まだ日本人の「アート」ってものに対する考え方が未熟だと思うんですよ、全体的に。全然広まってないし、浸透してないんですよ、アートの考え自体が。だから怒る人もいれば、それで何か議論になるじゃないですか、中止にしたりとか。中止になんてしなくていいんですよ。嫌だったら、別に怒ってもいいんですけど、見に行かなきゃいいし。まあ、税金がどうこうってのは正直よく分からない。
ちひろ そこは僕の弱いポイントです。経済の話になると何も分からない。
ぺが ハハハ…まあ、主催者が自分の金でやったら誰も文句は言わないのかなとは思いますけど。でも表現はやっぱり、許された方がいいと思いますよ。
ちひろ アートに関して、会田誠さんと、当時の篠田昭市長の講演を見に行ったことがあるんですけど。人間は作品を大昔から作ってるじゃないですか、遺跡みたいな時代から。だけど、アートってものの概念に気付いたのが、どうやらフランス革命の時らしくて。そういう話をしていたんです、会田誠さんが。民主主義ができて、国の財産は国民みんなものだと、それまでは一部のお金持ちのものだったのが全員のものになった時に、当時はヨーロッパが芸術の中心ですけど、絵画とか音楽とかそういうアートというものを、みんなで楽しんでいこうという概念がそこから生まれたらしくて。だから、税金とか使うのは良くないっていうのは、そもそも違うんじゃないかなと思ったんです。
ぺが うん。それに比べたらね。
ちひろ あと、アートって何だ?みたいな話で、これは何かで聞いた話なんですけど、「芸術」とか「美術」って言葉を、アートに使うじゃないですか、日本では和訳する時に。というと、美しいものこそがアート、芸があるものがアート、という考えに日本人は無意識のうちに言葉のイメージでなってるんですけど。でも多分、本来「美しくなければいけない」とかそういうものではなくて。人の心を動かすもの、見た人の世界の見え方をちょっと変えるものが、アートだと思ってるところがあって。それは必ずしも美しくなかったりすると思うんですよ。やっぱり現代アートとか見ると、必ずしも美しくなかったりするわけじゃないですか。何だこれ?みたいな変なものとかもあって。
ぺが いっぱいあります。
ちひろ で、そういうものに対して、「こんなのアートじゃない」「こんな誰もわけの分からないものやったらアートじゃない」みたいな考えが生まれちゃうんだろうなと思うんですよね。「アートとは何か」の考え方が違うから。
ぺが 同列に語っていいのか分からないですけど、俺、音楽、クラシックやってて。クラシックも結局、昔は神のために曲を作ってたんですけど、それで芸術を高め合って、美しい曲を作る、神に捧げる曲を作る。
ちひろ 本当に昔ですよね。教会とかで。
ぺが バッハとか、そういう時代です。その時は、教会が音楽の場所だったんですけど。それが、ずっと経って、途中は超端折りますけど、現代音楽というのができるんですよ。(イーゴリ・)ストラヴィンスキーとか、ロシアとか有名なんですけど。色んな人がやってたんですけど。その時に、ストラヴィンスキーなんてまだポップな方で、聞ける音楽で、もうわけ分からないやつがいっぱいいるわけですよ。前、Twitterで見たけど、ピンポンの台を持ち込んで、ピンポンを打って太鼓に叩きつけながら演奏するとか。あと、超有名なのは、ピアノの椅子の前に座って何も弾かないでずっと待ってる時の、会場の音を音楽にするっていう作品とかがあるわけすよ。(4分33秒)
ちひろ 譜面に何も書いてないやつですよね。
ぺが その時の客の咳とかくしゃみすら、その時の音楽だよっていう作品とかもあったりとかして。何でもアリなわけですよね。
ちひろ 可能性は無限にあるわけですね。
ぺが で、現代音楽は何が違うかと言うと、今までの美術という考え方を、もうぶっ壊しにかかってくるわけですよ。美術って何だろうってところに美術家が立ち返って、その既成の美術をぶち壊すというか。でもそこにあるのは、やっぱり人の心なんですよね。クラシックコンサートに行こうって言って、みんな美しい曲が聞けると思って待ってるところに、何も弾かないでピアノの前で座ってるだけの作品を出された時に、人はどう思うだろうっていうのが、根本だと思うんです。どう感じる?っていう。クラシックのコンサートに行って美しい曲を聞けるっていうのは、思い込みじゃないですか、現代人の。そういうイメージをぶっ壊したよって作品なんですよね。これも曲だよ、っていう。そういう時にどう思う?っていう問いかけみたいなものが。
ちひろ そう、問いかけっていう視点が、多分、アートにすごく大事なポイントだと思ってて。
ぺが でもまだ、日本人だけじゃないと思うんですよ、現代美術に関しては。世界中でも、全然。でも日本は結構遅れてるか。かなり遅れてると思いますけど。
ちひろ 日本は遅れてるって聞きますね。アジアの、例えば中国、韓国とかと比べても、すごく遅れてるって聞きますね。映画とかも。
ぺが そうですね。最近、俺、アンチテーゼって言葉すごくいっぱい使ってるんですけど。何かが栄えると、その下にアンチテーゼがいて、塗り替えて、そしてまたその下のアンチテーゼが出てきてどんどん文化が生まれていくと思ってるんですけど。抽象画とかも、今の日本人とかでも好きな人いっぱいいると思うんですけど、よく分からないけどいいなあって感じるわけじゃないですか。当時は叩かれたわけですよ。抽象画って、もともとは批判された言葉なんですよ。揶揄されて、あいつらが描いたものは何も分からない、抽象的だって言って、抽象画っていうのが最初なんですけど。今ではそれが浸透していて。
ちひろ 当時は、風景にしろ人物にしろ、それをそのまま美しく描くことが、イコール優れている絵だったわけじゃないですか。でも、写真の登場とかで絵画にその役割がなくなった時にっていうのもあるらしいですね。
ぺが どうしようかって、多分画家もすごい考えたと思うんですよね。新しい技術が生まれると、芸術家はすごい考えるわけですよね。今まで写真の代わりだった絵が、肖像画とかも写真でよくなっちゃうわけですよね。パシッと撮ったらそれでもう終わり。でも写真家の方だったら、写真も難しいよって言われると思うんですけど。当時の画家は、きっと多分、ああー!っと思ったと思います。肖像画の仕事がなくなった!と。
ちひろ スマホが流行って、カメラ屋が怒ってるみたいな、そういうことですよね。
ぺが そういうことです。どんどん移り変わっていくんですよね。
ちひろ 配信が始まって、CDが売れないって嘆いてる音楽関係者とか。
ぺが だから、今まさに、YouTuberがもっと盛り上がっていったら、テレビがなくなるかも知れないし。そういう技術の革新によって、変わっていきますよね、文化も。
ちひろ すごく思うのが、写真が生まれても、絵画はなくならないじゃないですか。抽象画だったり、色んな種類の表現の幅が広がって。それを、こういう表現もできる、こういう表現もできるって、広げてきた人達がいると思うんですよ。で、YouTubeとテレビも、YouTubeで何でもできちゃうってなったけど、いや、でもYoutbeができないことをテレビができるよって、また、テレビの表現の可能性を探ってる人達がいると思うんですよ。
ぺが そうですね。面白いですよね、こういう話は。
ちひろ アートの話かどうかは分からないですけどね。
ぺが いや、アートの話だと思いますよ。大事なところなんですよ、多分。何でこんなに発展してきたかっていうことですよね。昔みたいに、上手い絵が1枚描ければOK!最高!って時代はもう終わって、もうみんなすごい文化的になってるわけですよ。
ちひろ 当時だったら、金持ちしか一生目にすることができないような、それこそルーベンスの絵を見ようとしていた、「フランダースの犬」のネロみたいな。そういう、当時はすごい金持ちしか、一生に何回かしか見られないみたいなものが、もう簡単に誰でも見ることができちゃう。
ぺが そうですね。美術館に行けば見ることができちゃう。
ちひろ なんなら、ネットで見ることもできたり。だから、昔の人から見ると、すごい豊になってる。みんなの目が肥えてるというか。
ぺが そうですね。多分、さっきのフランスの話(フランス革命)以降で、美術は浸透してるとは思うんですけど、まだでも全然足りないなっていうのは思って。もっと何でもアリでいいと思うんですよ、本当に。何でも、何かを見て感じたら美だと思って。思ってることがあるんですけど、アーティストって名乗ってる人が、何かを作っても、そのままでもアートにならないと思ってるんですよ。誰かの目を介した時に、その人が認識して、初めてアートだと思っていて。例え話で、村上春樹の「騎士団長殺し」っていう、2017年に書かれた最新作があるんですけど。話の根幹にもかかわらない結構序盤ですけど、主人公が別荘に行くんですよ。で、そこは有名な日本画家の家だった。そこで暮らしてるうちに、屋根裏部屋を発見するんですよ。そうすると、そこに、1枚の未発表の絵があるわけです。超有名な日本画家の家に行ったら、誰も見てない絵が隠されていた。でも、それはそこにあった時点ではアートじゃないんですよ、誰も見てないから。
ちひろ 主人公が見付けた瞬間、アートになったという。
ぺが そうです。
ちひろ 僕も「ちひろdeアート」を始めた時に、ものすごく考えた時期があって。俺がやってることって何なんだ、みたいな。考えてるうちに、例えばお芝居をやってた時とかも、このお芝居やってて意味があるのか?とか。これを頑張ることに俺の人生、何の意味があるんだ?とか。この作品を作って何になるんだ?とか考えちゃうんですけど。で、手応えがあるやつとないやつがあるんですよね。上手く言えないんですけど。お客さんが少なくても、手応えがあったぞというものもあれば、多くても、これ何のためにやったんだろうなとなるやつもあって。「ちひろdeアート」とかも、本当そうなんですけど。これは何なんだろう?と思って。俺がやってることって、意味があるのかないのか、どっちだ?って悩んでたんですよ。で、毎日悩んでると、だんだん悩み方が発展していって、人は何故芸術を作るのだろう?みたいな、芸術の勉強とかしたことないのにそういう難しいことを考えだして。俺がやってることに意味があるのか?とか。芸術と芸術じゃないものに違いはあるのか?とか疑問に思えてきて。それは知名度で違うのか、絵の上手さで違うのか、何で違うのかがもう分からなくなってきて。ある時、障害者アートの展示に行ったんですよ。滋賀県にある「やまなみ工房」という施設で、精神疾患とか知的障害とかがあるような人達に、施設の中で自由に作品を作ってくださいっていう。あくまでそれはアート制作というよりは、セラピー的な感じで。絵を描いてみる人もいれば、粘土細工をする人もいるんですけど。それが気付いたら、本当にすごいアートが大量に生まれてしまって。その人達が全国的に色んなところで展覧会をやっていたりとか。その作品をすごい高額で買いたい人が現れたりとか。あと、絵があまりにカッコいいから、デザイナーの人がそれを服にして販売したりとか。その人がりゅーとぴあに来たんですよ。展示を実際見たんですけど、やっぱり上手い下手とかの世界じゃないんですけど、すごい心が動かされるんですよね。よく分からないけど、これはすごい!ってなる感じの絵ばかりで。でも、その人達は上手く絵を描こうとかは全然考えてなくて、とにかく情熱のままに、欲求のままに描いてるという感じで。何でこんなアートになってしまったのか、すごい不思議に思って。まったく同じ日に、シネ・ウインドで、その施設を描いたドキュメンタリー映画が上映されて。そこに「やまなみ工房」の施設長さんがゲストで来てたんですよ。だから終わったあとに聞いてみようと思って、質問したんですよね。何を聞いたかというと、僕とかも絵とか描くんですけど、アートだなって思わないんですよ、自分の絵を見て。だけど、あの人達の絵はアートだなってなっちゃう。そこに何か違いがあるのかなみたいな。あの人たちの絵にはアートを生み出す力があって、自分にはないんじゃないかみたいに思って。聞いてみたら、「アートとアートじゃないものの境目はありません」って言うんですよ、施設長の人が。「じゃあ、何がアートなんですか?」って聞いたら、「それは、何がアートみたいな定義はなくて、見た人の心が決めることです」と。
ぺが おおー。同じことですね。
ちひろ そう、同じこと話してるなと思って。見た人の心が動いたらそれはアートという言い方をその人はしていて。で、その施設の人達は、「アートを作ってくれ」みたいなことは一切言わなくて、「あなたの望むままに、あなたの作りたいものを作ってください」とだけ言ってて、それが結果、アートになってしまったという。結構すごい話なんですよね。アートに関しては今年色々あったんですけど、僕の中でそれがその一つでした。
ぺが 結構、アートと、商業が結びついてしまうわけですよ。絵画とか音楽もそうなんですけど。それで、ちょっと曇る部分もあるんですよね、本当にいいものかどうかっていうのは。例えば、絵画で、ゴッホ、いるじゃないですか。あの人は、生前は1枚しか絵が売れてなかったんですけど。すごい安い値段でしか買われてなくて、酒代にしかならないくらいだったらしいんですけど。それを死んだあとで画商とかが売りだして、それで認められて。今、ゴッホって言ったら誰でも知ってる画家じゃないですか。世界一有名くらいの。でも、当時は、発表の仕方が悪かったりとか、例えば。でも、ゴッホは画家として30歳とかで決意してやり始めて、頑張ってたはずなんですけど、当時はまったく認められなかった。それが、見る人が値段をつけて出されたら、めっちゃいいじゃん!ってなって、すごい高額で買ったりとか。本当に、億単位っていう価格で。そういうのが結構あって。逆に今の芸術だって、ものすごい額がついてるけど、人によっては、こんなの全然価値ないよってことが、山ほどあるじゃないですか。だから、なかなか難しいところがあって。お金と結びついちゃうと、ちょっと変わってくるんですよね。甲本ヒロトが言ってるみたいに、世界一売れてるラーメンが美味いラーメンかって言ったら、カップラーメンになってしまうみたいな。そういう発言が昔ありましたけど。
ちひろ さっき、商品の話、出ましたけど。アートって、ものすごい可能性が広がっていってるわけですよ。こんなこともできる、いや、これがアリなんだったらこれもアリだ、みたいな。そうやって色んなことやってるわけじゃないですか。芸術家は表現の可能性をどんどん広げていこう、広げていこうってやってるんですけど。結構難しい問題として、芸術家でも何でもない僕らみたいな一般の人が、それを見て、本当に良さが分かるのか問題というのがあって。こういうアートの歴史があってこれが生まれたからすごいんだよとか、あの作品に対してこれを作ったからすごいんだよとか、ある程度の知識が求められたりすることがあると思うんですけど、そこまで辿り着けないという話があるらしくて。「アートのお値段」っていう映画を観たんですけど、現代アートってものすごい高額で、億単位で取引されてるらしいんですね。世界の富裕層、資産家たちがものすごい高額で売買してる世界らしくて。そうなってくると、もう現代アートの最先端の作品とかを、我々は目にすることができないわけですよ。もう金持ちたちにみんな買われちゃうから。
ぺが 美術館にも出ないくらいになっちゃう。
ちひろ まあ、美術館に出るものもありますけど。そういうことがあるから、結構難しいらしいですね、現代アートの最先端は。
ぺが なるほど。
ちひろ だから、さっきちょっと話したんですけど、昔は金持ちだけのものだった芸術が、民衆に開かれて。
ぺが また金持ちのものに戻っていく。
ちひろ そういうことが起きてるらしいですね。あと、民主主義と一緒にアートの歴史が始まったとしたら、逆にその民主主義がなくなっちゃうと、例えばさっきの資本主義がいきすぎるとか、そういうことが起きると、アートの時代も進みが遅くなっちゃうみたいなことがあるらしいですね。それこそ、ファシズムみたいな時代がきてしまうと、アートの可能性がどんどん狭まっていくみたいなことも。これは会田誠さんの時に聞いたんですけど。
ぺが そういう歴史は過去にはありましたね。日本もあったのかな。海外でも、ソビエトとかドイツのあたりはかなりそういうのがあって、芸術家が亡命したりとか。ショスタコーヴィチとかは、かなりスターリンの時代のソビエトとバトってて。すごい複雑なんですよ。「こういう音楽はダメだ、もっとソビエトを称える曲を作れ」とスターリン側が言うと、ショスタコーヴィチは、ちょっと迎合するわけですよ。ちょっと国家を奨励する曲を作りながらも、その中にアンチテーゼの意味を込めて、交響曲にしたりとか。「バカどもこれを流しとけ」って言って、そこには、自分の思想的には、弾圧する国家をパンクの精神で。クラシックは結構、パンク入ってますよ。時代によりますけど。最初はやっぱり神々に対しての曲だったんですけど、そこにだんだん政治的な部分が出てくるわけですよ、時代によって。そうすると、パンクの精神は出てきますね。面白いですよ。
ちひろ 日本とかでも、例えば、本とか映画とかお芝居とかの脚本が検閲される時代とかもあったわけじゃないですか。でも、大衆とか、権力に迎合しつつ、パンクの精神をぶちこむみたいな。俺、これ言っても炎上しないと思うので話すんですけど、来年オリンピックあるじゃないですか。オリンピックとかパラリンピックの開会式、閉会式にかかわってるアーティストで、そういうこと誰かやるんじゃないかって、ちょっと思ってるんですよね。
ぺが ああ、そうなったら面白いですけどね。分からないようにはするってことですか、炎上しないように。
ちひろ 炎上しないように、巧みに思想を織り込んでいく、みたいな。
ぺが ああ、なるほどね。やってほしいですけどね。俺、それ日本で上手くやってるのは、ジブリだと思ってます。
ちひろ ジブリは上手いですね。
ぺが ジブリはものすごく上手くやってるので。でも、それをジブリマニアみたいな人に言うと、すごい怒られるんですけど。トトロが死の国の話だったりとか。
ちひろ あれは都市伝説って話ですけど、どうなんですかね。
ぺが 俺は信じてますね。
ちひろ わりとぺがさん、何でも信じますよね。スピッツのこれは殺人の歌だとか。
ぺが あれはガチです。マサムネさんの言葉もあるので。性と死という初期のテーマは載ってるし、読めば分かります。
ちひろ なるほど。
ぺが ジブリも俺は100%あると思ってるので。だから面白いんですよ。
ちひろ 「火垂るの墓」とかは分かりやすいですけど。
ぺが あんなの別に普通のただの話ですよ。トトロの方がやばいです。まあ、都市伝説のまんまなんですけど、七国山病院っていうのは、八国山っていう、結核病患者の病院が埼玉にあるんですよ。あと、あれは狭間山事件というのを元にしてるって話で。
ちひろ 女の子たちが亡くなったみたいな。
ぺが そうです。誘拐されて、妹は殺されて、姉は発狂してしまったっていう。それが5月に行われていて、だから名前がサツキとメイ。色々繋がるわけですよ。
ちひろ 本当かなあ…
ぺが でも、辻褄合わせだと思うんだったら、だって、何でも名前なんていいわけですよ。それを敢えて、場所を選んで、映画作るって大変な作業ですよ。そして、結構、水のカットが多いんですよ、よく見ると。あと、地蔵のカットとか。
ちひろ 池で誰かのサンダルが見つかるとか。
ぺが めちゃくちゃ水に関するカットが多くて。
ちひろ それは暗喩なのではなかろうかと。
ぺが 映画見てたら分かると思うんですけど、監督は1カットたりとも無駄にしないわけですよ。何か自分の思想を入れたカットしか使わないわけですよ。無駄なカットなんてないんですよ、映画って。だから、それを普通に見たら、トトロは、「ああ、良かったね」って話ですよ。ハハハ!
ちひろ いい話ですよ。まあ、そういう見方もできますよっていう。
ぺが そうそう。それが面白いっていう。
ちひろ その多面性こそがアートですからね。
ぺが だから、大人も子供も好きなんだと、俺は思うんですよね。
ちひろ 強引にまとめた。
ぺが ハハハ!
ちひろ と、言ってるうちに時間が来てしまったので、アートの話は尽きないですけど。ありがとうございました。
ぺが ありがとうございました。