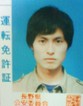10/27(日)、映画「ところ(常呂)でどしたいっ! 『阿賀に生きる』その後のその後」の上映会に行ってきました。
新潟水俣病の裁判を戦いながら、阿賀野川流域で伝統を守りながら暮らす人達を追った1992年の「阿賀に生きる」は、2022年に続編「それからどしたいっ!『阿賀に生きる』その後」が作られているのですが、今作はそのさらに続編です。

会場は、北区、福島潟の近くにある、県立環境と人間のふれあい館。
この施設には新潟水俣病資料館もあり、その繋がりで「阿賀に生きる」発起人で今回の上映会の中心人物でもある旗野秀人さんは館長と交流があるとのこと。
上映前に、旗野さんが「館長から自由にやってもらっていいと言われたので、ぱーっと賑やかにやりましょう!」と楽しそうに登場。
一緒にトークをするのは、今回の映画の佐藤睦監督と、映画にも登場する川崎那恵さん、侑季さん母娘。
まず今回の映画が作られた経緯として、「阿賀に生きる」の完成後、映画に登場した人達で「冥土のみやげツアー」として全国各地で映画の上映会を行い、その様子をプライベートフィルムとして撮影していたそうです。
しかし、その中心人物であった渡辺参治さんが2020年に亡くなり、その追悼のためにそれまで撮影してきた記録映像を映画化することになり、それが2022年の佐藤睦監督による「それからどしたいっ!『阿賀に生きる』その後」。
その「冥土のみやげツアー」の行き先の一つが北海道の常呂町で、もともと札幌での「阿賀の生きる」上映会がきっかけで交流が生まれたそうです。
その常呂町を渡辺参治さんの追悼のために2023年に再び訪れ上映会を行った際、その様子を記録した映像を映画化したのが、今回の「ところ(常呂)でどしたいっ! 『阿賀に生きる』その後のその後」ということ。
説明が長くなってちょっとややこしいですが、要は「阿賀に生きる」の上映会のドキュメンタリーが続編として2作品作られ、その最新作ということ。
「阿賀に生きる」公開後にも映画に携わる人達のその後がずっとドキュメンタリーとして作られ続けるという凄い映画だ…
その映画に登場し、常呂町にも同行した川崎那恵さん、侑季さん母娘もトークに登場。
川崎那恵さんは京都の方ですが、20年前に学生時代に京都で「阿賀に生きる」に出会い、そこから交流が生まれて今では毎年新潟を訪れているとのこと。
その娘、10歳の侑季さんがクレヨンで書いた「ところでどしたいっ!」はなんと映画の題字にもなっていて、その動画も紹介されました。
そんな侑季さん、今では新潟の小学校での上映会がきっかけで新潟にも友達ができたそうで、その親子も上映会に来ていました。
そんな上映会について、旗野さんの「新潟水俣病を知らない子供達も交流を楽しんでくれる、それが一番大切」という温かい言葉が印象的でした。
かと思えば、旗野さんは上映会を訪れた伊藤環境大臣とのツーショット写真を紹介しながら、「でもこの人は石破総理になってやめさせられた」とまさかの政治風刺をする。
そんな和やかな雰囲気で始まった映画の上映は、かつて旗野秀人さんら「阿賀に生きる」の一行で訪れた常呂町で、渡辺参治さんが楽しそうに歌う場面から始まる。
そして現在、渡辺参治さんの墓参りの場面では、アーティストの古田木綿子さんが渡辺参治さんの好きだった歌を歌い、「阿賀に生きる」発起人の旗野秀人さんも感激。
その後、一行は渡辺参治さん追悼のため再び常呂町へ。
旅の中心にいる旗野さんは旅先でもお酒を飲んだりみんなと交流したりして、とても楽しそう。
特に、旗野さんと10歳の侑季さんがお祖父さんと孫みたいに仲良く遊ぶ場面には、本当に温かい気持ちになりました。
個人的に最近は選挙を前に、高齢者と若者を分断するような高齢者差別的な発言をよく見ていたので、高齢の旗野さんと子供達の交流を見て、そうだよね、これが正しい人間の姿だよね!と嬉しい気持ちに。
常呂の旅では、先程登場した古田木綿子さんの娘、シンガーソングライターの古田春花さんも同行するのですが、なんと旅先で段ボールを太鼓に、渡辺参治さんの歌を歌って盛り上げる。
お金がなくても楽器がなくても人は音楽を楽しめるという、人間の土着的な感動が現代にも響いてくるような感動がありました。
そして上映後には、古田木綿子さんが会場で同じ歌を披露。
渡辺参治さんが大好きだった阿賀に昔から伝わる歌は、古田母娘へと歌い継がれていくのだなと、世代を超えて伝わるものを確かに感動しました。
ちなみに古田木綿子さんは、この前日にシネ・ウインド前で行ったパレスチナ連帯スタンディングで、ガザで亡くなった詩人リフアト・アライールさんの詩「If I must die」を歌ってくれた方。
だから僕は2日連続で会ったわけですが、歌を届けることを大切にした本物のミュージシャンだなと思います。
そして、そんなスタンディング発起人でこの日も来ていた小森はるかさんの監督作、「二重のまち/交代地のうたを編む」に、古田春花さんは出ているのです。
だからうまくまとまらないけれど、新潟水俣病も、東日本大震災も、ガザも、全部繋がっている、そんなことを思う上映会でした。
しかもそれが、地域を越えた人々の交流という温かさで繋がっている。
理不尽な現実の中でも、日常の大切さ、前を向く勇気を教えてもらえたし、その一端に自分もいられることに感謝です。