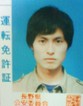1/28(月)、シネ・ウインドで『家へ帰ろう』を観て来ました。
シネ・ウインドでは1/19(土)~2/1(金)に上映していました。
予告編はこんな感じです。
『恐怖の報酬』は、もともと1953年にアンリ=ジョルジュ・クルーゾ監督によって撮られ、それがさらに1977年にウィリアム・フリードキン監督によってリメイクされたということです。
今回、1977年のフリードキン監督版の『恐怖の報酬』が「オリジナル完全版」として復活し全国公開、シネ・ウインドでも上映されたということです。
実は僕は昨年12月に「まつもと爆音映画祭」で初めて観たんですが、新潟でも上映されるということでもう一度観て来ました。
正直、初めて松本で観た時は爆音上映ということもあり凄まじい衝撃を受けていたのですが、2回目の今回はあらためてよりじっくりと楽しめました。
物語は、異なる国でそれぞれ事件を起こし逃亡し、同じ南米の村に流れ着いた4人が、巨額の報酬を得るために、油田で発生した大火災を止めるためにニトログリセリンを巨大トラックで運ぶ命懸けの旅に出る、というものです。
ストーリーは単純なものなのですが、銃撃、爆発、豪雨、エンジンの轟音、極限状態のスリルなどなど、何もかも迫力が規格外に凄まじい映画だなと思いました。
冒頭で登場人物の一人(一応主人公に当たるのかな)が引き起こす車のクラッシュ、それぞれの人物が流れ着いた南米の国で発生した油田の大爆発、ニトログリセリンを運ぶ途中のトラックが巻き込まれる豪雨、他にも次々訪れるアクシデント、その一つ一つが本当に衝撃的でした。
ポスターにもなっている、巨大なトラックが豪雨の中を今にも千切れそうな吊り橋を渡るというシーンを始め、手に汗握るという言葉では足りないくらい、絶対に体験したくないような地獄の連続なのですが、あまりに力強い映像から目が離せなくなってしまう映画でした。
昨年『戦争のはらわた』を観た時も思ったのですが、やっぱりCGもなかった時代に、直に撮影している爆発などの過激なシーンって、本当に目の前でそういう事件に巻き込まれてしまったかのような心にグサグサ刺さってくる衝撃があって、時代は変わっても色褪せないよなって思います。
そういう映像から伝わってくる熱量があるからこそ、映画の中の本当に生きるか死ぬかの危機一髪なシーンにも、映画を観ているその時間だけは実際に自分の身に起こっているかのように映画に没入してしまうという、まさに映画という「体験」ができる映画だと思いました。
それにしても、先程「地獄」という言葉を使いましたが、この映画は「地獄」以外のシーンがまったくないんじゃないかってくらい、本当に容赦ないんですよね。
事故や事件、爆発や災害などの暴力的の表現はもちろんのこと、登場人物たち一人一人が本当に人生のどん底なんだなっていう「逃げ場のなさ」をあらゆる手段でじわじわと表現もしてくるんですよね。
例えば、4人が2人ずつ2台のトラックに分かれてニトログリセリンを運ぶというのも、「どちらかが死んだ時のための保険」という、このシビアな設定が本当にぞっとします。
衝撃映像による動的な地獄から、精神的にじわじわ追い詰めてくる静的な地獄まで、本当にあらゆる地獄を見せてくるんですよね。
でも、そんな地獄の極みみたいな状況だからこそ、時にはその中でもがいて生き残ろうとする人間たちの執念深さが、思いがけず感動的だったりもしました。
例えば、常にいがみ合っている4人が、巨大な倒木を乗り越えるためにその瞬間だけは一致団結して知恵を絞って解決するシーンなど、友情などという言葉では表現できないくらい、切迫するものがありました。
そこまでして危機を乗り越えた彼らがそれぞれ辿る結末の一つ一つが、また容赦なかったりするわけですが、それでもちゃんとカタルシスを感じられるエンディングにもなっているんですよね。
と思いきやまさかのエンディング…という、本当に最後の最後まで徹底的に残酷で暴力的で容赦ない、しかし人間というものの本質をある意味描いているとも言えるような、非常に見応えのある映画でした…にしても、観終わるとどっと疲れる映画でした!