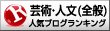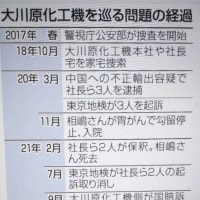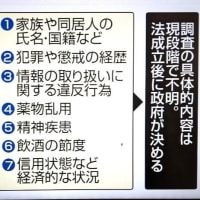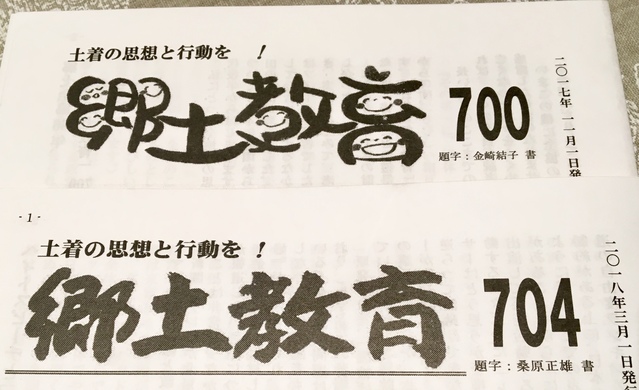小中学校の頃、私の住む町では未だ完全給食が実施されていなかった。
半ドンの土曜日を除いて5日間は毎日弁当持参で通学した。
弁当箱は上級学年になるにつれ大きくはなったが、アルマイト製であることに変わりはなかった。
小学校へ入学したての頃、私は楕円形の薄く小さな弁当箱で蓋には野球少年の絵が描いてあったのを覚えている。
作ってくれたのは母親である。
今では「愛妻弁当」等という微笑ましいものもあるが、当時も親の愛情あふれる弁当だったに違いない。
敗戦後数年経っていたとはいえ、まだまだ物は不足していた時代に毎日弁当を作る母親の苦労は想像に難くない。
四角い弁当箱の真ん中に梅干し一つという「日の丸弁当」も、話の上の世界ではない時代であった。
家庭内での食事もメニューがおおよそ決まっていた。
農家だった我が家では畑で採れる季節の野菜の他、米と味噌と醤油(次第に作らなくなったが)は事足りていたが、店で購入する食品は極々限られていた。
動物性たんぱく質は大部分が魚であった。
銚子から定期的にやって来る自転車の魚屋さん(ハチマキという愛称のおじさん)から購入するのである。
このおじさんの話し言葉はこの地域独特の濁ったものではなく、とても洗練れたきれいな発音をしていたので印象深い。
おじさんが運んでくるものは全てが旬の魚ばっかりで、カツオのシーズンなら毎回カツオばっかり…。
いくら栄養があるといっても、連日のカツオ料理には飽きてくる。
時々は面白い魚がやって来た。
それは、アカエイ!
何だかグロテクスに見えて気持ち悪かった。
そんなわけで、カツオの角煮が弁当のオカズになることも多かったが、これはご馳走の部類で、最も多かったのは卵焼きと海苔や昆布であった。
卵焼きといえば、我が家ではニワトリを母屋の庇の下で飼っていた。
毎日いくつかの卵を産んだが、老鶏となり産卵もしなくなると、裏の竹山でされ鶏肉となる。
この役は常に祖父であったが、私は何度かその場面に居合わせたことがある。
苦しまないようにと一気にナタで斬首するのだが、血が滴り落ちる光景は見るのが辛かった。
それでも、釜の熱湯で茹で羽毛をむしり取ると肉屋さんの鶏肉らしくなる。
私は、さすがにはできなかったが、羽毛のむしり取りは手伝った。
今でもあの温かい胴体の触感が忘れられない。
肉といえばこの鶏肉がほとんどで、豚肉は年に数回程度口にするだけ、牛肉なんて見たこともなかった。
-S.S-