
2泊2日のプチ旅から戻った翌日は茶道の稽古。
疲労はあまりなかったと思いきや、朝寝坊
そして、起きたら足 が痛かった~
が痛かった~
(奈良でけっこー歩いたからなぁ。時間経ってから痛くなるって、歳をとった証拠 )
)
で、ちょっと朝はダラダラしちゃった
おまけに家を出てから忘れ物に気がついて、引き返し~
ちょっと出遅れたかなぁ と思ったけど、なんとか揃っての挨拶には間に合った
と思ったけど、なんとか揃っての挨拶には間に合った
今回は開炉。
“茶道の正月”だから、やはり新鮮な気持ちになる
(根来塗の炉縁が美しい )
)
まず、当番のお弟子さんの初炭手前を見学。
年末で入門から丸4年になる若手さん。
半年ぶりの炉だというのに、炭手前をちゃんと覚えてる
えらいっ
しかも、棚ありなのに、手順に危なげがなく、流れもスムーズ
安心して見ていられた
その後、みんなで先生手作りの栗&白玉善哉を食べて開炉を祝った。
ワタシは3番目の到着だったので、点前は午後かなぁって思っていたら、次だって
後輩がいい手前をして、善哉直後の点前って プレッシャーだわぁ
プレッシャーだわぁ
10月後半の稽古は薄茶点前で逃げちゃったしなぁ
でも、ここは先輩らしくビシッと決めたいっ
ということで、濃茶平点前をさせていただいた。
淡々斎好の秋泉棚もすごく久しぶりで緊張したけれど、
旅のいい気持ちをそのまま出すように、点前できた
釜の煮え もよくて、4人前の濃茶もいい感じに練れたし
もよくて、4人前の濃茶もいい感じに練れたし
(中棚に荘られた鵬雲斎好の寿輪棚が堂々としていたよいな と思った)
と思った)
午後は男子クンから。
「20分後には出たいんですけど 」
」
そーゆーことは先に言ってよぉ
出来るところまでいいから~と薄茶平点前を始めてもらう。
(先生が奥入っちゃって、戻ってこないけど )
)
と、平棗の扱い 正客の位置から手をレクチャーする。
正客の位置から手をレクチャーする。
この先、急に点前をふられた時でも正しい道具の扱いが出来るようにしないとねー
ホントはね、男子は素手で釜の蓋を開けるんだよ
(稽古の時は火傷しないように帛紗で開けてるけど)
結局、途中で他のお弟子さんが仕舞いを引き取った
その後、濃茶平点前を見学して、ワタシも早めに上がった。
先生が炉開きの茶事をしないことを少し事を気にしていらっしゃるようで
「お茶の稽古って、ただ茶筅を振ってるだけだと思ってほしくないの」
とは云うものの、米寿を迎える先生に茶事稽古をリクエストするのは気が引ける
「若い方々には、検定の勉強を通じてとか、茶会に参加してもらうなど、
まずは知識から入って、理解した上で茶事を体験してもらうやり方もアリだと思います~」
と、自分なりの考えも申し上げた。
そりゃ、希望を言えばキリがない。
カリキュラム上、カンペキな環境ではないけれど、
炭手前に花月に奥秘の稽古を別稽古をせずに月3回の中で組み込んでいただける。
現代の住宅事情を考えれば、とても恵まれている稽古環境だと思う。
今ある環境の中で、利点を最大限に生かした稽古を十二分にすればいい。
少なくとも、ワタシ自身は恵まれた環境を生かしきった稽古はできていない
他のお弟子さんたちも同じだ。
だから今は先生を大事に守りながら一日でも長く稽古を続けることがワタシたちがすべきことかな。
で、稽古が終わった後は日本橋三越本店へ。

開炉という時期ということもあり、今週は盛りだくさん。→こちら
まずは三浦竹泉さんの個展。
今回は招待券もらってないので、自腹で茶券を購入して呈茶席に入った。
御園棚でスーツ姿の若い男性による点前。
ちゃんと素手で釜の蓋開けてるし、大ぶりの平棗の扱いも正しく出来てた
(お菓子は鶴屋吉信の亥の子餅 )
)
竹泉さんといえば、カッチリした無難な京焼~という印象があったけど、
パッと見た限りでは今回は磁器が多いという印象。
呈茶の道具組も赤絵部分が引き立つ金襴手の水指だったし、主茶碗も俵形の呉須赤絵。
(あいさつ文には「テーマは祥瑞写しの茶わん」と書いてあったっけ)
ワタシが薄茶いただいた茶碗も外側は白瓷金襴手、内側は染付。
初めて接した茶碗で珍しいなぁと思った。
他の展示も赤絵に金襴手と華やか。
ただ、磁器はお茶を点てる時に点てづらくないかなぁとか、手が滑りそう
って、ワタシはニガテ。
磁器ということもあって、煎茶道具も出ていた。
(他は省略)
ついでだからと、三越の隣の三井記念美術館にも寄った。
でも、円山応挙展は鑑賞しない。
他美術館のチラシが置いてあるコーナーで出光美術館の割引券をGetし
ちょっと気が引けたので、受付で次の展覧会の前売券を購入した。
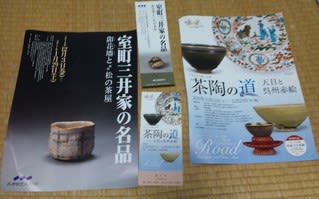
さらに帰り道に図書館にも寄って、名物裂の本を4冊借りた。
前日に鑑賞した京博の袈裟の展覧会がよかったから
★来週は旅の話や、フリーク中に鑑賞した展覧会のレビューが中心になります。
乞うご期待
ランキング投票もよろしく 致しマス
致しマス

にほんブログ村

疲労はあまりなかったと思いきや、朝寝坊

そして、起きたら足
 が痛かった~
が痛かった~
(奈良でけっこー歩いたからなぁ。時間経ってから痛くなるって、歳をとった証拠
 )
)で、ちょっと朝はダラダラしちゃった

おまけに家を出てから忘れ物に気がついて、引き返し~

ちょっと出遅れたかなぁ
 と思ったけど、なんとか揃っての挨拶には間に合った
と思ったけど、なんとか揃っての挨拶には間に合った
今回は開炉。
“茶道の正月”だから、やはり新鮮な気持ちになる

(根来塗の炉縁が美しい
 )
)まず、当番のお弟子さんの初炭手前を見学。
年末で入門から丸4年になる若手さん。
半年ぶりの炉だというのに、炭手前をちゃんと覚えてる

えらいっ

しかも、棚ありなのに、手順に危なげがなく、流れもスムーズ

安心して見ていられた

その後、みんなで先生手作りの栗&白玉善哉を食べて開炉を祝った。
ワタシは3番目の到着だったので、点前は午後かなぁって思っていたら、次だって

後輩がいい手前をして、善哉直後の点前って
 プレッシャーだわぁ
プレッシャーだわぁ
10月後半の稽古は薄茶点前で逃げちゃったしなぁ

でも、ここは先輩らしくビシッと決めたいっ

ということで、濃茶平点前をさせていただいた。
淡々斎好の秋泉棚もすごく久しぶりで緊張したけれど、
旅のいい気持ちをそのまま出すように、点前できた

釜の煮え
 もよくて、4人前の濃茶もいい感じに練れたし
もよくて、4人前の濃茶もいい感じに練れたし
(中棚に荘られた鵬雲斎好の寿輪棚が堂々としていたよいな
 と思った)
と思った)午後は男子クンから。
「20分後には出たいんですけど
 」
」そーゆーことは先に言ってよぉ

出来るところまでいいから~と薄茶平点前を始めてもらう。
(先生が奥入っちゃって、戻ってこないけど
 )
)と、平棗の扱い
 正客の位置から手をレクチャーする。
正客の位置から手をレクチャーする。この先、急に点前をふられた時でも正しい道具の扱いが出来るようにしないとねー

ホントはね、男子は素手で釜の蓋を開けるんだよ

(稽古の時は火傷しないように帛紗で開けてるけど)
結局、途中で他のお弟子さんが仕舞いを引き取った

その後、濃茶平点前を見学して、ワタシも早めに上がった。
先生が炉開きの茶事をしないことを少し事を気にしていらっしゃるようで

「お茶の稽古って、ただ茶筅を振ってるだけだと思ってほしくないの」
とは云うものの、米寿を迎える先生に茶事稽古をリクエストするのは気が引ける

「若い方々には、検定の勉強を通じてとか、茶会に参加してもらうなど、
まずは知識から入って、理解した上で茶事を体験してもらうやり方もアリだと思います~」
と、自分なりの考えも申し上げた。
そりゃ、希望を言えばキリがない。
カリキュラム上、カンペキな環境ではないけれど、
炭手前に花月に奥秘の稽古を別稽古をせずに月3回の中で組み込んでいただける。
現代の住宅事情を考えれば、とても恵まれている稽古環境だと思う。
今ある環境の中で、利点を最大限に生かした稽古を十二分にすればいい。
少なくとも、ワタシ自身は恵まれた環境を生かしきった稽古はできていない

他のお弟子さんたちも同じだ。
だから今は先生を大事に守りながら一日でも長く稽古を続けることがワタシたちがすべきことかな。
で、稽古が終わった後は日本橋三越本店へ。

開炉という時期ということもあり、今週は盛りだくさん。→こちら
まずは三浦竹泉さんの個展。
今回は招待券もらってないので、自腹で茶券を購入して呈茶席に入った。
御園棚でスーツ姿の若い男性による点前。
ちゃんと素手で釜の蓋開けてるし、大ぶりの平棗の扱いも正しく出来てた

(お菓子は鶴屋吉信の亥の子餅
 )
)竹泉さんといえば、カッチリした無難な京焼~という印象があったけど、
パッと見た限りでは今回は磁器が多いという印象。
呈茶の道具組も赤絵部分が引き立つ金襴手の水指だったし、主茶碗も俵形の呉須赤絵。
(あいさつ文には「テーマは祥瑞写しの茶わん」と書いてあったっけ)
ワタシが薄茶いただいた茶碗も外側は白瓷金襴手、内側は染付。
初めて接した茶碗で珍しいなぁと思った。
他の展示も赤絵に金襴手と華やか。
ただ、磁器はお茶を点てる時に点てづらくないかなぁとか、手が滑りそう

って、ワタシはニガテ。
磁器ということもあって、煎茶道具も出ていた。
(他は省略)
ついでだからと、三越の隣の三井記念美術館にも寄った。
でも、円山応挙展は鑑賞しない。
他美術館のチラシが置いてあるコーナーで出光美術館の割引券をGetし

ちょっと気が引けたので、受付で次の展覧会の前売券を購入した。
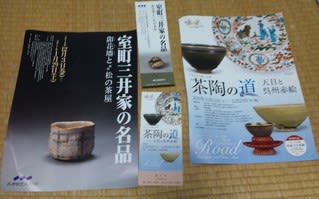
さらに帰り道に図書館にも寄って、名物裂の本を4冊借りた。
前日に鑑賞した京博の袈裟の展覧会がよかったから

★来週は旅の話や、フリーク中に鑑賞した展覧会のレビューが中心になります。
乞うご期待

ランキング投票もよろしく
 致しマス
致しマス
にほんブログ村


























