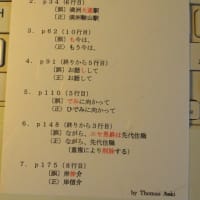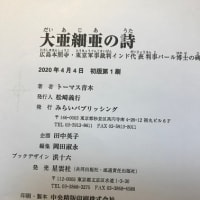<添付画像>:河出書房新社・日本文学全集(14)志賀直哉集
このところエセ男爵的「ブログ更新不振症候群」の真っ只中にて、なかなか治癒しないから困っている。(困っているのは「トーマス青木」君であって我輩のことではない……)
たぶん、この症候群に冒された最一回目は2006年夏場から秋口まで、さらに第二回目が昨年2007年8月上旬から晩秋までか? 第二回目の症状は未だ完治せず、現在も尚継続している。と云っても過言ではなかろう……
彼の症候群の原因解明するに及ばず、既に十分な自覚症状を心得ているのだ。 言い換えれば「文章書けない症候群」であり、書こうと思えば思うほどますます書けなくなる「精神的障害」のことである。 書かなければますます書けなくなるという事だから、始末が悪い。
てなことで、この厄介な精神的障害を乗り越えるには「良書の読書」しか解決方法がなく、このところむさぼるように明治大正昭和初期の巨匠たちの小説を再度紐解き始めたのである。いわゆる日本文学の古典の再読を始めたのだ。ここはしかし、やたら濫読ではなく、やはり好みの作家あり。好みでない作家の小説を読んだら最後、ますます日本語がいやになってくるから決して読まないよう心がけ、まずは夏目漱石に森鴎外あたりから始めて行き着く所、やはり我輩の場合は志賀直哉先生に到達する。 本音は「司馬遼太郎」先生から「開高健」さんなのだが、このあたりの再読となるともう一年掛かる。
「ま、今回、これはやめておこう……」
さて、志賀直哉の場合、猫でも杓子でも知っているのは「暗夜航路」。
コレを読むのはヤバイ。暗夜航路は志賀作品の中でも駄作!?否、百歩譲って未だ当方の解明理解不行き届き?さらに譲って難解な交響曲的クラシック音楽か?と我輩は思う。
やはり短編がよい。
志賀直哉短編は、今から先の人生に於いても時にふれ折にふれて繰り返し読みたいものだ。
さて本日、禁じて中の禁じてをやってみたい。つまり、偉大なる日本文学の巨匠の作品を丸ごと写してブログ掲載するというものだ。
モノカキを志す人間、美しい文章を書きたいと願う人間は、だれでもやって通らなくてはならない手法がある。それは唯一、好きな作家の文章を「手書きで書き写す」こと。つまり「写経」と同じ、、、。
エセ男爵は、否、不肖トーマス青木は、尊敬してやまない志賀直哉先生作品の中、「清兵衛と瓢箪」を模写してブログ掲載する。トーマス青木作品として発表掲載すればコレは歴然として盗作になるけれど、出処をはっきりさせて「トーマス青木的駄文」でも付け加えれば、コレは立派な文学論評になるからして怖くない。
何故に志賀作品をよしとするか?
志賀直哉先生の文章から、無駄な修飾語は一切見当たらず、物事を裏から眺めるような捻くれた感性も無く、あくまでも貴族趣味風の「自己主張」と「我が儘の一途」なのであり、そこには志賀流「男の粋」と「ダンディズム」に満ち溢れつつ「無粋」の腐臭は一切無く、漂ってくるのは香り高い白樺派の貴族的エスプリである。
これを夏目漱石的に喩えれば、ひとえに「坊ちゃん」的な勢いであり、コレが夏目漱石的で良いのであって、「それから」的人生観に見受けられるデカダン風な逃避は全く無い。(志賀作品の中「暗夜航路」にこの逃避を感ずる…)
「瓢箪と清兵衛」の文章表現から志賀直哉的嗜好が漂ってくる。発表された時期はなんと大正2年。今からかれこれ90年も以前に書かれた作品であるが、現代に通ずる美文である。(志賀作品の中、美文と称される作品はもっと外にあるようだが)我輩は小説の主人公「清兵衛」に、志賀直哉的美しさと力強さを感じる。(夏目漱石「坊ちゃん」に通ずる強引さを感じつつ)イチズに美形の瓢箪を好む清兵衛の素直な美的感覚に、志賀直哉好みの「理想の少年像」を観るのである。たぶん、当時の志賀先生は主人公清兵衛の持つ感性を「良し!」とされたに違いない。学校の教師にも両親にも理解されない「美的センス」や「卓越した能力」を持ち合わせた少年の可能性の芽を次々と摘み取りつぶしてしまう大人の閉鎖的常識は、今の時代にも通じる事象であるか。
父親との間の不理解に悩む若き志賀直哉の例(たとえ)を挙げてみれば、
「その夏、おおよそつまらぬことから、私は父と衝突した。一週間ほどして、父は宮城県の方に新しく買った小さな銅山を一緒に見に行かぬかと誘った。私は不思議な気がした。……」から始まる作品「山形」に、その確執が伺える。
『清兵衛と瓢箪』の清兵衛は志賀直哉自身への置き換え可能にて、清兵衛の父(職業は大工)は志賀直哉の父(職業は鉱山経営の実業家)と同列であるか。
この志賀直哉的切り口の小説は、過去のほとんどの論評において「私小説」的とも「微視的感覚」の小説とか称されながら、文学評論家的な枠組みで一括りにされているのが気に入らない。志賀直哉の感性は、そんなに狭小なものではなく、私的でもなく、もっと広大なところにあったと思うけれど、我国評論家感覚の視野狭く度量少なき証拠こそ、過去の「文学論評」の中で暴露されているようだ。だから評論家の屁理屈は不様でおもしろい。(ま、付け焼刃的論評論は急遽中止、こちらの勉強不足が丸出しになってますます恥をかく…)
清兵衛の感性を通して、志賀直哉的深遠な人生哲学と美意識や美観が観えて来るのだ。日本的美観を通り越して西洋的美感を包括して止まず、この頃(明治末期から大正初期頃)すでに地球規模的なずうずうしさを持っていた日本人志賀直哉の世界観が伺える。つまり「清兵衛の凝り性」は志賀直哉の非日本人的な頑固一徹であり、「清兵衛の美的感覚」は(ここは瓢箪に置き換えられているけれど)志賀直哉の求める美の世界の象徴であったはず、、、。
この志賀直哉的心意気を、こよなく尊敬してやまない、、、。
まぁ~ いろいろ考えると面白い。
前置きが長くなりすぎた。
〆て、
一時期の志賀直哉先生が遊んだ「広島県の尾道市」を舞台に展開する小説「清兵衛と瓢箪」!初めての方はこれを機会に是非ご通読いただきたい。既に読まれた方は再読されたし。。。
そして「反省」!
アァ~、こんなこと書いてるからますます書けなくなるのだ……
------------------------------
[日本文学全集(14)志賀直哉集]より抜粋記載 P304~P307(約3,400文字)
― 清兵衛と瓢箪 ―
これは清兵衛という子供と瓢箪との話である。この出来事以来清兵衛と瓢箪とは縁が断(ki)れてしまったが、間もなく清兵衛には瓢箪に代わる物が出来た。それは絵を描くことで、彼は嘗(katu)て瓢箪に熱中したように今はそれに熱中している……
清兵衛が時々瓢箪を買って来ることは両親も知っていた。三四銭から十五銭位までの皮つきの瓢箪を十ほども持っていたろう。彼はその口を切ることも種を出すこともひとりで上手にやった。栓も自分で作った。最初茶渋(chya-shibu)で臭味をぬくと、それから父の飲みあました酒を貯えて置いて、それで頻り(shikiri)に磨いていた。
全く清兵衛の凝りようは烈しかった。ある日彼はやはり瓢箪のことを考え考え浜通りを歩いていると、ふと、目に入った物がある。彼ははッとした。それは路端に浜を背にしてズラリと並んだ屋台店の一つから飛び出して来た爺さんの禿頭であった。清兵衛はそれを瓢箪だと思ったのである。「立派な瓢じゃ」こう思いながら彼はしばらく気がつかずにいた。 ――気がついて、流石(sasuga)に自分で驚いた。その爺さんはいい色をした禿頭を振り立てて彼方(mukou)の横丁へ入っていった。清兵衛は急に可笑しくなって一人大きな声を出して笑った。堪らなくなって笑いながら彼は半町ほど馳けた。それでもまだ笑いは止まらなかった。
これほど残りようだったから、彼は町を歩いていれば骨董屋でも八百屋でも荒物屋でも駄菓子屋でもまた専門にそれを売る家でも、凡そ瓢箪を下げた店といえば必ずその前に立って凝(ji)っと見た。
清兵衛は十二歳でまだ小学校に通っている。彼は学校から帰ってくると他の子供とも遊ばずに、一人よく町へ瓢箪を見に出かけた。そして、夜は茶の間の隅に胡坐をかいて瓢箪の手入れをしていた。手入れが済むと酒を入れて、手拭で巻いて、鑵にしまって、それごと炬燵へ入れて、そして寝た。翌朝は起きるとすぐ彼は鑵を開けてみる。瓢箪の肌はすっかり汗をかいている。彼は厭かずにそれを眺めた。それから丁寧に糸をかけて陽のあたる軒へ下げ、そして学校へ出かけて行った。
清兵衛のいる町は商業地で船つき場で、市にはなっていたが、割に小さな土地で二十分歩けば細長い市のその長い方が通りぬけられるくらいであった。だから仮令(tatoe)瓢箪を売る家はかなり多くあったにしろ、ほとんど毎日それを見歩いている清兵衛には、おそらくすべての瓢箪は眼を通されていたろう。
彼は古瓢にはあまり興味を持たなかった。まだ口も切ってないような皮つきに興味を持っていた。しかも彼の持っているのは大方所謂瓢箪形の、割に平凡な格好をした物ばかりであった。
「子供じゃけえ、瓢いうたら、こういうんでなかにゃあ気に入らんもんと見るけえのう」大工をしている彼の父を訪ねて来た客が、傍で清兵衛が熱心にそれを磨いているのを見ながら、こう言った。彼の父は、
「子供の癖に瓢いじりなぞをしおって……」とにがにがしそうに、その方を顧みた。
「清公、そんな面白うないのばかり、えっと持っとってもあかんぜ、もちっと奇抜なんを買わんかいな」と客が言った。
清兵衛は、
「こういうがええんじゃ」と答えて済ましていた。
清兵衛の父と客との話は瓢箪のことになって行った。
「この春の品評会に参考品で出ちょった馬琴の瓢箪という奴は素晴しいもんじゃったのう」と清兵衛の父が言った。
「えらい大けえ瓢じゃったけのう」
「大けえし、大分長かった」
こんな話を聞きながら清兵衛は心で笑っていた。馬琴の瓢というのはその時の評判な物ではあったが、彼はちょっと見ると、 ――馬琴という人間も何者だか知らなかったし―― すぐ下らない物だと思ってその場を去ってしまった。
「あの瓢はわしには面白うなかった。かさ張っとるだけじゃ」彼はこう口を入れた。
それを聴くと彼の父は目を丸くして怒った。
「何じゃ、わかりもせん癖して、黙っとれ!」
清兵衛は黙ってしまった。
ある日清兵衛が裏通りを歩いていて、いつも見なれない場所に、仕舞屋(shimotaya)の格子先に婆さんが干柿や蜜柑の店を出して、その背後の格子に二十ばかりの瓢箪を下げて置くのを発見した。彼はすぐ、
「ちょっと、見せてつかあせえな」と寄って一つ一つ見た。中に一つ五寸ばかりで一見ごく普通な形をしたので、彼には奮いつきたいほどにいいのがあった。
彼は胸をどきどきさせて、
「これ何ぼかいな」と訊いてみた。婆さんは、
「ぼうさんじゃけえ、十銭にまけときやんしょう」と答えた。彼は息をはずませながら、
「そしたら、きっと誰にも売らんといて、つかあせえのう。すぐ銭持って来やんすけえ」くどく、これを言って走って帰って行った。
間もなく、紅い顔をしてハアハアいいながら還って来ると、それを受け取ってまた走って帰って行った。
彼はそれから、その瓢が離せなくなった。学校へも持って行くようになった。しまいには時間中でも机の下でそれを磨いていることがあった。それを受持ちの教員が見つけた。修身の時間だっただけに教員は一層怒った。
他所から来ている教員にはこの土地の人間が瓢箪などに興味を持つことが全体気に食わなかったのである。この教員は武士道を言うことの好きな男で、雲右衛門が来れば、いつもは通りぬけるさえ恐れている新地の芝居小屋に四日の興行を三日聴きに行くくらいだから、生徒が運動場でそれを唄うことにはそれほど怒らなかったが、清兵衛の瓢箪では声を震わして怒ったのである。「とうてい将来見込のある人間ではない」こんなことまで言った。そしてそのたんせいを凝らした瓢箪はその場で取り上げられてしまった。清兵衛は泣けもしなかった。
彼は青い顔をして家に帰ると炬燵に入ってただぼんやりとしていた。
そこに本包みを抱えた教員が彼の父を訪ねてやって来た。清兵衛の父は仕事へ出て留守だった。
「こういうことは全体家庭で取り締まって頂くべきで……」教員はこんなことをいって清兵衛の母に食ってかかった。母は、ただただ恐縮していた。
清兵衛はその教員の執念深さが急に恐ろしくなって、唇を震わしながら部屋の隅で小さくなっていた。教員のすぐ後ろの柱には手入れの出来た瓢箪がたくさん下げてあった。今気がつくか今気がつくかと清兵衛はヒヤヒヤしていた。
散々叱言を並べた後、教員はとうとうその瓢箪には気が付かずに帰って行った。清兵衛はほッと息をついた。清兵衛の母は泣き出した。そしてダラダラと愚痴っぽい叱語を言いだした。
間もなく清兵衛の父は仕事場から帰ってきた。で、その話を聞くと、急に側にいた清兵衛を捕らえて散々に撲りつけた。清兵衛はここでも「将来とても見込みのない奴だ」と言われた。「もう貴様のような奴は出て行け」と言われた。清兵衛の父はふと柱の瓢箪に気がつくと、玄能(gen-nou)を持って来て、一つ一つ割ってしまった。清兵衛はただ青くなって黙っていた。
さて、教員は清兵衛から取り上げた瓢箪を穢れた物ででもあるかのように、捨てるように、年寄った学校の小使にやってしまった。小使はそれを持って帰って、くすぶった小さな自分の部屋の柱へ下げて置いた。
二ヶ月ほどして小使はわずかの金に困った時にふとその瓢箪をいくらでもいいから売ってやろうと思い立って、近所の骨董屋へ持って行って見せた。
骨董屋はためつ、すがめつ、それを見ていたが、急に冷淡な顔をして小使の前へ押しやると、
「五円やったらもろうとこう」と言った。
小使は驚いた。が、賢い男だった。何食わぬ顔をして、
「五円じゃとても離し得やしえんのう」と答えた。骨董屋は急に十円に上げた。小使はそれでも承知しなかった。
結局五十円でようやく骨董屋はそれを手に入れた。 ――小使は教員からその人の四カ月分の給料をただもらったような幸福を心ひそかに喜んだ。が、彼はそのことは教員には勿論、清兵衛にもしまいまで全く知らん顔をしていた。だからその瓢箪の行方については誰も知る者がなかったのである。
しかしその賢い小使も骨董屋がその瓢箪を地方の豪家に六百円で売りつけたことまでは想像も出来なかった。
……清兵衛は今、絵を描くことに熱中している。これが出来た時に彼にはもう教員を恨む心も、十あまりの愛瓢を玄能で破ってしまった父を恨む心もなくなっていた。
しかし彼の父はもうそろそろ彼の絵を描くことにも叱言を言い出して来た。
(大正2年1月 読売新聞にて)
出処:『日本文学全集(14)』志賀直哉集 抜粋記載
P304~P307(約3,400文字)
日本文学全集(14)志賀直哉集
昭和41年6月2日 初版発行
昭和44年9月1日 五版発行
定価:580円
著者:志賀直哉
発行者:中島隆之 / 印刷者:多田基 / 装幀者:亀倉雄策
発行所:株式会社河出書房新社
------------------------------
〔参考資料〕以下紹介の「ちくま日本文学全集」の中に『清兵衛と瓢箪』の集録があるようだ。 志賀先生ご自身の論評もあるとの事、興味深い日本文学全集の現代版か、、、。
このところエセ男爵的「ブログ更新不振症候群」の真っ只中にて、なかなか治癒しないから困っている。(困っているのは「トーマス青木」君であって我輩のことではない……)
たぶん、この症候群に冒された最一回目は2006年夏場から秋口まで、さらに第二回目が昨年2007年8月上旬から晩秋までか? 第二回目の症状は未だ完治せず、現在も尚継続している。と云っても過言ではなかろう……
彼の症候群の原因解明するに及ばず、既に十分な自覚症状を心得ているのだ。 言い換えれば「文章書けない症候群」であり、書こうと思えば思うほどますます書けなくなる「精神的障害」のことである。 書かなければますます書けなくなるという事だから、始末が悪い。
てなことで、この厄介な精神的障害を乗り越えるには「良書の読書」しか解決方法がなく、このところむさぼるように明治大正昭和初期の巨匠たちの小説を再度紐解き始めたのである。いわゆる日本文学の古典の再読を始めたのだ。ここはしかし、やたら濫読ではなく、やはり好みの作家あり。好みでない作家の小説を読んだら最後、ますます日本語がいやになってくるから決して読まないよう心がけ、まずは夏目漱石に森鴎外あたりから始めて行き着く所、やはり我輩の場合は志賀直哉先生に到達する。 本音は「司馬遼太郎」先生から「開高健」さんなのだが、このあたりの再読となるともう一年掛かる。
「ま、今回、これはやめておこう……」
さて、志賀直哉の場合、猫でも杓子でも知っているのは「暗夜航路」。
コレを読むのはヤバイ。暗夜航路は志賀作品の中でも駄作!?否、百歩譲って未だ当方の解明理解不行き届き?さらに譲って難解な交響曲的クラシック音楽か?と我輩は思う。
やはり短編がよい。
志賀直哉短編は、今から先の人生に於いても時にふれ折にふれて繰り返し読みたいものだ。
さて本日、禁じて中の禁じてをやってみたい。つまり、偉大なる日本文学の巨匠の作品を丸ごと写してブログ掲載するというものだ。
モノカキを志す人間、美しい文章を書きたいと願う人間は、だれでもやって通らなくてはならない手法がある。それは唯一、好きな作家の文章を「手書きで書き写す」こと。つまり「写経」と同じ、、、。
エセ男爵は、否、不肖トーマス青木は、尊敬してやまない志賀直哉先生作品の中、「清兵衛と瓢箪」を模写してブログ掲載する。トーマス青木作品として発表掲載すればコレは歴然として盗作になるけれど、出処をはっきりさせて「トーマス青木的駄文」でも付け加えれば、コレは立派な文学論評になるからして怖くない。
何故に志賀作品をよしとするか?
志賀直哉先生の文章から、無駄な修飾語は一切見当たらず、物事を裏から眺めるような捻くれた感性も無く、あくまでも貴族趣味風の「自己主張」と「我が儘の一途」なのであり、そこには志賀流「男の粋」と「ダンディズム」に満ち溢れつつ「無粋」の腐臭は一切無く、漂ってくるのは香り高い白樺派の貴族的エスプリである。
これを夏目漱石的に喩えれば、ひとえに「坊ちゃん」的な勢いであり、コレが夏目漱石的で良いのであって、「それから」的人生観に見受けられるデカダン風な逃避は全く無い。(志賀作品の中「暗夜航路」にこの逃避を感ずる…)
「瓢箪と清兵衛」の文章表現から志賀直哉的嗜好が漂ってくる。発表された時期はなんと大正2年。今からかれこれ90年も以前に書かれた作品であるが、現代に通ずる美文である。(志賀作品の中、美文と称される作品はもっと外にあるようだが)我輩は小説の主人公「清兵衛」に、志賀直哉的美しさと力強さを感じる。(夏目漱石「坊ちゃん」に通ずる強引さを感じつつ)イチズに美形の瓢箪を好む清兵衛の素直な美的感覚に、志賀直哉好みの「理想の少年像」を観るのである。たぶん、当時の志賀先生は主人公清兵衛の持つ感性を「良し!」とされたに違いない。学校の教師にも両親にも理解されない「美的センス」や「卓越した能力」を持ち合わせた少年の可能性の芽を次々と摘み取りつぶしてしまう大人の閉鎖的常識は、今の時代にも通じる事象であるか。
父親との間の不理解に悩む若き志賀直哉の例(たとえ)を挙げてみれば、
「その夏、おおよそつまらぬことから、私は父と衝突した。一週間ほどして、父は宮城県の方に新しく買った小さな銅山を一緒に見に行かぬかと誘った。私は不思議な気がした。……」から始まる作品「山形」に、その確執が伺える。
『清兵衛と瓢箪』の清兵衛は志賀直哉自身への置き換え可能にて、清兵衛の父(職業は大工)は志賀直哉の父(職業は鉱山経営の実業家)と同列であるか。
この志賀直哉的切り口の小説は、過去のほとんどの論評において「私小説」的とも「微視的感覚」の小説とか称されながら、文学評論家的な枠組みで一括りにされているのが気に入らない。志賀直哉の感性は、そんなに狭小なものではなく、私的でもなく、もっと広大なところにあったと思うけれど、我国評論家感覚の視野狭く度量少なき証拠こそ、過去の「文学論評」の中で暴露されているようだ。だから評論家の屁理屈は不様でおもしろい。(ま、付け焼刃的論評論は急遽中止、こちらの勉強不足が丸出しになってますます恥をかく…)
清兵衛の感性を通して、志賀直哉的深遠な人生哲学と美意識や美観が観えて来るのだ。日本的美観を通り越して西洋的美感を包括して止まず、この頃(明治末期から大正初期頃)すでに地球規模的なずうずうしさを持っていた日本人志賀直哉の世界観が伺える。つまり「清兵衛の凝り性」は志賀直哉の非日本人的な頑固一徹であり、「清兵衛の美的感覚」は(ここは瓢箪に置き換えられているけれど)志賀直哉の求める美の世界の象徴であったはず、、、。
この志賀直哉的心意気を、こよなく尊敬してやまない、、、。
まぁ~ いろいろ考えると面白い。
前置きが長くなりすぎた。
〆て、
一時期の志賀直哉先生が遊んだ「広島県の尾道市」を舞台に展開する小説「清兵衛と瓢箪」!初めての方はこれを機会に是非ご通読いただきたい。既に読まれた方は再読されたし。。。
そして「反省」!
アァ~、こんなこと書いてるからますます書けなくなるのだ……
------------------------------
[日本文学全集(14)志賀直哉集]より抜粋記載 P304~P307(約3,400文字)
― 清兵衛と瓢箪 ―
これは清兵衛という子供と瓢箪との話である。この出来事以来清兵衛と瓢箪とは縁が断(ki)れてしまったが、間もなく清兵衛には瓢箪に代わる物が出来た。それは絵を描くことで、彼は嘗(katu)て瓢箪に熱中したように今はそれに熱中している……
清兵衛が時々瓢箪を買って来ることは両親も知っていた。三四銭から十五銭位までの皮つきの瓢箪を十ほども持っていたろう。彼はその口を切ることも種を出すこともひとりで上手にやった。栓も自分で作った。最初茶渋(chya-shibu)で臭味をぬくと、それから父の飲みあました酒を貯えて置いて、それで頻り(shikiri)に磨いていた。
全く清兵衛の凝りようは烈しかった。ある日彼はやはり瓢箪のことを考え考え浜通りを歩いていると、ふと、目に入った物がある。彼ははッとした。それは路端に浜を背にしてズラリと並んだ屋台店の一つから飛び出して来た爺さんの禿頭であった。清兵衛はそれを瓢箪だと思ったのである。「立派な瓢じゃ」こう思いながら彼はしばらく気がつかずにいた。 ――気がついて、流石(sasuga)に自分で驚いた。その爺さんはいい色をした禿頭を振り立てて彼方(mukou)の横丁へ入っていった。清兵衛は急に可笑しくなって一人大きな声を出して笑った。堪らなくなって笑いながら彼は半町ほど馳けた。それでもまだ笑いは止まらなかった。
これほど残りようだったから、彼は町を歩いていれば骨董屋でも八百屋でも荒物屋でも駄菓子屋でもまた専門にそれを売る家でも、凡そ瓢箪を下げた店といえば必ずその前に立って凝(ji)っと見た。
清兵衛は十二歳でまだ小学校に通っている。彼は学校から帰ってくると他の子供とも遊ばずに、一人よく町へ瓢箪を見に出かけた。そして、夜は茶の間の隅に胡坐をかいて瓢箪の手入れをしていた。手入れが済むと酒を入れて、手拭で巻いて、鑵にしまって、それごと炬燵へ入れて、そして寝た。翌朝は起きるとすぐ彼は鑵を開けてみる。瓢箪の肌はすっかり汗をかいている。彼は厭かずにそれを眺めた。それから丁寧に糸をかけて陽のあたる軒へ下げ、そして学校へ出かけて行った。
清兵衛のいる町は商業地で船つき場で、市にはなっていたが、割に小さな土地で二十分歩けば細長い市のその長い方が通りぬけられるくらいであった。だから仮令(tatoe)瓢箪を売る家はかなり多くあったにしろ、ほとんど毎日それを見歩いている清兵衛には、おそらくすべての瓢箪は眼を通されていたろう。
彼は古瓢にはあまり興味を持たなかった。まだ口も切ってないような皮つきに興味を持っていた。しかも彼の持っているのは大方所謂瓢箪形の、割に平凡な格好をした物ばかりであった。
「子供じゃけえ、瓢いうたら、こういうんでなかにゃあ気に入らんもんと見るけえのう」大工をしている彼の父を訪ねて来た客が、傍で清兵衛が熱心にそれを磨いているのを見ながら、こう言った。彼の父は、
「子供の癖に瓢いじりなぞをしおって……」とにがにがしそうに、その方を顧みた。
「清公、そんな面白うないのばかり、えっと持っとってもあかんぜ、もちっと奇抜なんを買わんかいな」と客が言った。
清兵衛は、
「こういうがええんじゃ」と答えて済ましていた。
清兵衛の父と客との話は瓢箪のことになって行った。
「この春の品評会に参考品で出ちょった馬琴の瓢箪という奴は素晴しいもんじゃったのう」と清兵衛の父が言った。
「えらい大けえ瓢じゃったけのう」
「大けえし、大分長かった」
こんな話を聞きながら清兵衛は心で笑っていた。馬琴の瓢というのはその時の評判な物ではあったが、彼はちょっと見ると、 ――馬琴という人間も何者だか知らなかったし―― すぐ下らない物だと思ってその場を去ってしまった。
「あの瓢はわしには面白うなかった。かさ張っとるだけじゃ」彼はこう口を入れた。
それを聴くと彼の父は目を丸くして怒った。
「何じゃ、わかりもせん癖して、黙っとれ!」
清兵衛は黙ってしまった。
ある日清兵衛が裏通りを歩いていて、いつも見なれない場所に、仕舞屋(shimotaya)の格子先に婆さんが干柿や蜜柑の店を出して、その背後の格子に二十ばかりの瓢箪を下げて置くのを発見した。彼はすぐ、
「ちょっと、見せてつかあせえな」と寄って一つ一つ見た。中に一つ五寸ばかりで一見ごく普通な形をしたので、彼には奮いつきたいほどにいいのがあった。
彼は胸をどきどきさせて、
「これ何ぼかいな」と訊いてみた。婆さんは、
「ぼうさんじゃけえ、十銭にまけときやんしょう」と答えた。彼は息をはずませながら、
「そしたら、きっと誰にも売らんといて、つかあせえのう。すぐ銭持って来やんすけえ」くどく、これを言って走って帰って行った。
間もなく、紅い顔をしてハアハアいいながら還って来ると、それを受け取ってまた走って帰って行った。
彼はそれから、その瓢が離せなくなった。学校へも持って行くようになった。しまいには時間中でも机の下でそれを磨いていることがあった。それを受持ちの教員が見つけた。修身の時間だっただけに教員は一層怒った。
他所から来ている教員にはこの土地の人間が瓢箪などに興味を持つことが全体気に食わなかったのである。この教員は武士道を言うことの好きな男で、雲右衛門が来れば、いつもは通りぬけるさえ恐れている新地の芝居小屋に四日の興行を三日聴きに行くくらいだから、生徒が運動場でそれを唄うことにはそれほど怒らなかったが、清兵衛の瓢箪では声を震わして怒ったのである。「とうてい将来見込のある人間ではない」こんなことまで言った。そしてそのたんせいを凝らした瓢箪はその場で取り上げられてしまった。清兵衛は泣けもしなかった。
彼は青い顔をして家に帰ると炬燵に入ってただぼんやりとしていた。
そこに本包みを抱えた教員が彼の父を訪ねてやって来た。清兵衛の父は仕事へ出て留守だった。
「こういうことは全体家庭で取り締まって頂くべきで……」教員はこんなことをいって清兵衛の母に食ってかかった。母は、ただただ恐縮していた。
清兵衛はその教員の執念深さが急に恐ろしくなって、唇を震わしながら部屋の隅で小さくなっていた。教員のすぐ後ろの柱には手入れの出来た瓢箪がたくさん下げてあった。今気がつくか今気がつくかと清兵衛はヒヤヒヤしていた。
散々叱言を並べた後、教員はとうとうその瓢箪には気が付かずに帰って行った。清兵衛はほッと息をついた。清兵衛の母は泣き出した。そしてダラダラと愚痴っぽい叱語を言いだした。
間もなく清兵衛の父は仕事場から帰ってきた。で、その話を聞くと、急に側にいた清兵衛を捕らえて散々に撲りつけた。清兵衛はここでも「将来とても見込みのない奴だ」と言われた。「もう貴様のような奴は出て行け」と言われた。清兵衛の父はふと柱の瓢箪に気がつくと、玄能(gen-nou)を持って来て、一つ一つ割ってしまった。清兵衛はただ青くなって黙っていた。
さて、教員は清兵衛から取り上げた瓢箪を穢れた物ででもあるかのように、捨てるように、年寄った学校の小使にやってしまった。小使はそれを持って帰って、くすぶった小さな自分の部屋の柱へ下げて置いた。
二ヶ月ほどして小使はわずかの金に困った時にふとその瓢箪をいくらでもいいから売ってやろうと思い立って、近所の骨董屋へ持って行って見せた。
骨董屋はためつ、すがめつ、それを見ていたが、急に冷淡な顔をして小使の前へ押しやると、
「五円やったらもろうとこう」と言った。
小使は驚いた。が、賢い男だった。何食わぬ顔をして、
「五円じゃとても離し得やしえんのう」と答えた。骨董屋は急に十円に上げた。小使はそれでも承知しなかった。
結局五十円でようやく骨董屋はそれを手に入れた。 ――小使は教員からその人の四カ月分の給料をただもらったような幸福を心ひそかに喜んだ。が、彼はそのことは教員には勿論、清兵衛にもしまいまで全く知らん顔をしていた。だからその瓢箪の行方については誰も知る者がなかったのである。
しかしその賢い小使も骨董屋がその瓢箪を地方の豪家に六百円で売りつけたことまでは想像も出来なかった。
……清兵衛は今、絵を描くことに熱中している。これが出来た時に彼にはもう教員を恨む心も、十あまりの愛瓢を玄能で破ってしまった父を恨む心もなくなっていた。
しかし彼の父はもうそろそろ彼の絵を描くことにも叱言を言い出して来た。
(大正2年1月 読売新聞にて)
出処:『日本文学全集(14)』志賀直哉集 抜粋記載
P304~P307(約3,400文字)
日本文学全集(14)志賀直哉集
昭和41年6月2日 初版発行
昭和44年9月1日 五版発行
定価:580円
著者:志賀直哉
発行者:中島隆之 / 印刷者:多田基 / 装幀者:亀倉雄策
発行所:株式会社河出書房新社
------------------------------
〔参考資料〕以下紹介の「ちくま日本文学全集」の中に『清兵衛と瓢箪』の集録があるようだ。 志賀先生ご自身の論評もあるとの事、興味深い日本文学全集の現代版か、、、。
 | 志賀直哉 (ちくま日本文学全集)志賀 直哉筑摩書房このアイテムの詳細を見る |