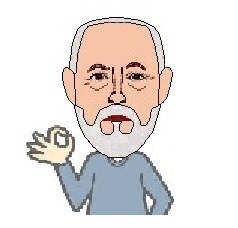年配のIさんが真山一郎の“瞼の母”を唄った。バックの映像は時代劇の設定で縞の合羽を着た渡世人が出てきた。
私 「縞の合羽か。こういう曲にぴったりやね」
客T「何で糸偏に高いで、シマて言うんやろなア?」
私 「それはやなあ、高島屋があるからや」
客T「なんで?」
私 「高シマ…高シマや!」
客T「ちょっと苦しいなあ。シマりないなあ」
私 「シマったシマった島倉千代子…」
客T「それは古いギャグや!」
私 「足を洗って出直シマす」
客T「もうエエって」
私 「はい、これでシマいにシマす」
客T「くどい!因みに縞の方向によって縦縞、横縞、斜め縞があるね」
私 「そうそう、北の方向が北島、西の方向が 私 「西島…」
客T「それは柄の縞と違(チゴ)て名字や」
※「縞」=日本に南蛮貿易で南方諸島産の縦縞の木綿がもたされると、それらは「島」の字を用いて島物と呼ばれた。
それまでの日本には縦線はほとんどみられず、横縞が「筋(スジ)」と呼ばれて使われているくらいであった。
江戸時代の文化・文政の頃に、単純で明快な縦縞の柄が「粋」な渋みをもつとして大流行し「縞」の字が当てられた。
一句:シマのネタ尽きることなくシマい無し
謎かけ:縞とかけて、正しくないこと解く。どちらも(横縞・横しま)もあります
私 「縞の合羽か。こういう曲にぴったりやね」
客T「何で糸偏に高いで、シマて言うんやろなア?」
私 「それはやなあ、高島屋があるからや」
客T「なんで?」
私 「高シマ…高シマや!」
客T「ちょっと苦しいなあ。シマりないなあ」
私 「シマったシマった島倉千代子…」
客T「それは古いギャグや!」
私 「足を洗って出直シマす」
客T「もうエエって」
私 「はい、これでシマいにシマす」
客T「くどい!因みに縞の方向によって縦縞、横縞、斜め縞があるね」
私 「そうそう、北の方向が北島、西の方向が 私 「西島…」
客T「それは柄の縞と違(チゴ)て名字や」
※「縞」=日本に南蛮貿易で南方諸島産の縦縞の木綿がもたされると、それらは「島」の字を用いて島物と呼ばれた。
それまでの日本には縦線はほとんどみられず、横縞が「筋(スジ)」と呼ばれて使われているくらいであった。
江戸時代の文化・文政の頃に、単純で明快な縦縞の柄が「粋」な渋みをもつとして大流行し「縞」の字が当てられた。
一句:シマのネタ尽きることなくシマい無し
謎かけ:縞とかけて、正しくないこと解く。どちらも(横縞・横しま)もあります