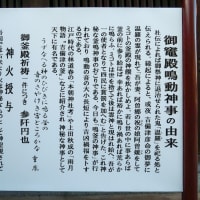「ゆとり―とライン」の愛称で知られる名古屋ガイドウェイバスは、案内軌条に沿って進む日本初の交通機関です。
案内軌条方式をとるのは大曽根から小幡緑地までの区間で、専用高架線を走ります。
この区間を特に「ガイドウェイバス志段味線」と呼ぶそうです。
専用高架線を走るガイドウェイバスは輸送力は鉄道に劣るものの、路線バスに多くある交通事情による遅延の恐れもなく定時運行が可能。
車社会の名古屋都市圏では輸送力はあまり期待されていないのかも。
それでも日中は10分おきに運行していることからも利用しやすいです。
また、ガイドウェイバスのメリットは専用軌道から一般道路へ乗り入れも可能なことです。
郊外は住宅地が分散するため、一般道に直通した後は路線バスと同じくいくつかの系統に分かれ運行されます。
都市部では他の影響を受けない高架区間、郊外では枝分かれが可能な地上区間を使い分けたガイドウェイバスは鉄道とバスの中間のような存在になっています。

起点となる大曽根はJR中央線・地下鉄名城線・名鉄瀬戸線が停車するターミナル駅。
瀬戸線・中央線・ゆとり―とラインの順に高架駅が平行に並んでいます。
ゆとり―とラインの乗降場は地上3階に位置しておりバス停とは思えないほど立派な造り。

大階段を登って、2階部分には改札のようなものがありますが、実際には使われていないようです。
起点のため右手が乗り場、左手は出口専用になっています。
大曽根はゆとりーとラインで唯一、有人の停留所。

乗り場はバス2両分くらい停まることができそうなプラットホーム。
行き先によって停車位置が異なるそうでだが、現在は高蔵寺行と中志段味行(2系統あり)の3系統しか運行していないよう。
小幡緑地までの高架区間はすべての系統が通ることになります。
見た目は路線バスと変わりない車両ですが、高架区間では前後輪に付いた案内装置を使ってハンドルなしの走行が可能。
案内装置を格納することによって一般道では路線バスになります。

道路の両側にあるレールに従って進むので、出発しても運転手はハンドルを握らずに安全確認をするだけ。
大曽根を出発するとすぐに右に90度曲がって環状線の上空を進みます。
地上の環状線の地下には地下鉄名城線が走っており、三層構造になっています。

「ナゴヤドーム矢田」を過ぎて「砂田橋」までの区間を名城線と並走。
架線も無く、視界は良好。
停留所はすべて相対式のかまぼこドーム型になっているようです。
休日の日中とはいえ、短距離区間で利用するお客さんも多いようで、砂田橋で何人か降りていきました。

砂田橋を出て、次は左に90度曲がると矢田川を渡り、守山付近で名鉄瀬戸線と交差。
いよいよ都市部に背を向けて郊外を目指します。
遠くの山脈と煙を吐くのは製紙工場の煙突。
普段地上からでは見ることのできない景色を車窓から楽しむ事ができます。
信号も道路工事もなく、愁い知らず。
バスなのでスピードは出ませんが快適です。

「川村」を過ぎると小幡緑地まで急坂を上ります。
名古屋郊外には丘陵地帯が多くあり、急傾斜が苦手な鉄道より新交通が選ばれるのでしょう。
坂を上りきると「白沢渓谷」、その次が「小幡緑地」です。

小幡緑地の先で高架線は終わり、一般道に乗り入れます。
一般道に出る前に案内装置を格納するためのモードインターチェンジが設けられています。
軌道と道路を使い分けるデュアルモードの開発は昔からなされていますが、なかなか実用に辿り着きません。
そんな中、西洋で実用化しているガイドウェイバスを改めて取り入れたわけですが、都市部(専用道)・郊外(一般道)という切り替えは便利かと思います。
しかし一般道に降りた先の系統が少なくてはあまり効果を発揮できていないような気も。
安産装置付きの特殊車両への統一も予算などの関係で難しいのかもしれません。
一般道路上に専用レーンを設ける基幹バスも名古屋では実例がありますが、浮き彫りになった課題からよりよい交通手段を整備してほしいものです。
実用化するためのスペースもない東京では不可能でしょうし、そういう意味でも名古屋は交通手段の発展を最も望める都市ではないでしょうか。