元々節分は年4回あり2月だけ行事(仕来り)が残ったのは「旧正月」だったから

■平安時代、「鬼」とは“目に見えない”邪気を指し江戸時代にツノと寅のパンツ絵が創作された
 池上彰氏のTV情報番組を参考にしました/2月の『節分』行事は、鬼に豆をぶつけて「鬼は外」「福は内」と家内安全・健康を願う。しかし、元々の「節分」は年に4回あった。「節分」の字の通り、季「節」を「分」けることで季節の分かれ目に因む行事だった。二十四節気の立春(2~4月)・立夏(5~7月)・立秋(8~10月)・立冬(11~1月)と、4つの季節の始まりの前日が節分と言う訳である。2025年の立春は2月3日で節分はその前日の2月2日、太陽の動き・位置関係によってその年によって日にちが変わる。さて4つの節分があるうち、なぜ2月の節分だけ行事(仕来り)が残ったのか?元々が旧正月だったからで、立春は春の始まり・1年の始まり、旧暦の<正月>とされ立春の前日(節分)は大晦日。昔の年寄りは、“年またぎ”とも言った。一連の正月行事だったため、他の節分より重きが置かれ盛大に行われた。現在の新暦(太陽暦)に変わっても、脈々と受け継がれている。2月の節分は中国や神道・仏教の影響はなく、日本独自の風習である。
池上彰氏のTV情報番組を参考にしました/2月の『節分』行事は、鬼に豆をぶつけて「鬼は外」「福は内」と家内安全・健康を願う。しかし、元々の「節分」は年に4回あった。「節分」の字の通り、季「節」を「分」けることで季節の分かれ目に因む行事だった。二十四節気の立春(2~4月)・立夏(5~7月)・立秋(8~10月)・立冬(11~1月)と、4つの季節の始まりの前日が節分と言う訳である。2025年の立春は2月3日で節分はその前日の2月2日、太陽の動き・位置関係によってその年によって日にちが変わる。さて4つの節分があるうち、なぜ2月の節分だけ行事(仕来り)が残ったのか?元々が旧正月だったからで、立春は春の始まり・1年の始まり、旧暦の<正月>とされ立春の前日(節分)は大晦日。昔の年寄りは、“年またぎ”とも言った。一連の正月行事だったため、他の節分より重きが置かれ盛大に行われた。現在の新暦(太陽暦)に変わっても、脈々と受け継がれている。2月の節分は中国や神道・仏教の影響はなく、日本独自の風習である。 節分になるとなぜか鬼が出てきて人間様が豆を投げつけるのは?鬼は悪さをするものと思われ、穏やかな正月を迎える前に「邪気」(鬼)を祓おうとした。その鬼に「豆」をぶつけるのは、豆=穀物には生命力と魔除けの呪力が備わっている」という信仰の影響とされる。それが今日、節分に豆をまく習慣ができた。豆をまいて「福は内」、災いを招く「鬼は外」と叫んで邪気や悪いものを追い払う。しかし地域よって、必ずしも掛け声は「福は内・鬼は外」ではないそうだ。一例では青森県・弘前市の一部では「福は内・鬼も内」~村人が角(つの)がない優しい鬼に助けられた言い伝えが残るため。京都府福知山市の一部では、「鬼は内・福は外」と正反対だ。神社に来た悪い鬼が神様に諭され改心、良い鬼になって人々に福をもたらした。神社の本殿に鬼が“鎮座”しているから「鬼は内」、外にいる村人に福を授けることから「福は外」。投稿者は、子供が小さい頃、窓を開けて近所に響くほどわざと大きな声で「福は内」とやった。だから、子供達から鬼以上に嫌われた(苦)。
節分になるとなぜか鬼が出てきて人間様が豆を投げつけるのは?鬼は悪さをするものと思われ、穏やかな正月を迎える前に「邪気」(鬼)を祓おうとした。その鬼に「豆」をぶつけるのは、豆=穀物には生命力と魔除けの呪力が備わっている」という信仰の影響とされる。それが今日、節分に豆をまく習慣ができた。豆をまいて「福は内」、災いを招く「鬼は外」と叫んで邪気や悪いものを追い払う。しかし地域よって、必ずしも掛け声は「福は内・鬼は外」ではないそうだ。一例では青森県・弘前市の一部では「福は内・鬼も内」~村人が角(つの)がない優しい鬼に助けられた言い伝えが残るため。京都府福知山市の一部では、「鬼は内・福は外」と正反対だ。神社に来た悪い鬼が神様に諭され改心、良い鬼になって人々に福をもたらした。神社の本殿に鬼が“鎮座”しているから「鬼は内」、外にいる村人に福を授けることから「福は外」。投稿者は、子供が小さい頃、窓を開けて近所に響くほどわざと大きな声で「福は内」とやった。だから、子供達から鬼以上に嫌われた(苦)。 鬼と言えば赤い身体に角が2本、金棒と虎のパンツを連想する。ここから、現在の鬼のイメージが定着するまでの過程を説明する。元々の「鬼」とは、“目に見えない存在”を指していた。鬼の語源は平安時代に遡り、『隠』(おぬ)と言われ、“目に見えない”邪気やなんとなく悪いもの、災害や疫病なども含まれ「鬼(隠)の仕業」とされた。鬼がやや形づけられる発端となったのが、飛鳥時代に中国から伝わった宮中行事「追儺(ついな)」。邪気を祓い無病息災を祈る役目の者がいて、大声を発し盾や矛・弓などで見えない鬼を撃退する儀式だった。その容姿が、「4つ目の赤い面(めん)」を着けていたことによる。平安時代に鬼が出入りするのは北東の方角とされ、今でも「鬼門」(きもん)と呼ぶ。そして江戸時代になると、浮世絵師が“見える鬼”を創作し現在の鬼のイメージが定着した。鬼門の北東は干支で言う丑(うし)と寅(とら)の間に当たり、鬼に牛(丑)の角を着け+虎(寅)のパンツをはかせた絵を描いたと言われる。それが今日まで続いている。<諸説あり>
鬼と言えば赤い身体に角が2本、金棒と虎のパンツを連想する。ここから、現在の鬼のイメージが定着するまでの過程を説明する。元々の「鬼」とは、“目に見えない存在”を指していた。鬼の語源は平安時代に遡り、『隠』(おぬ)と言われ、“目に見えない”邪気やなんとなく悪いもの、災害や疫病なども含まれ「鬼(隠)の仕業」とされた。鬼がやや形づけられる発端となったのが、飛鳥時代に中国から伝わった宮中行事「追儺(ついな)」。邪気を祓い無病息災を祈る役目の者がいて、大声を発し盾や矛・弓などで見えない鬼を撃退する儀式だった。その容姿が、「4つ目の赤い面(めん)」を着けていたことによる。平安時代に鬼が出入りするのは北東の方角とされ、今でも「鬼門」(きもん)と呼ぶ。そして江戸時代になると、浮世絵師が“見える鬼”を創作し現在の鬼のイメージが定着した。鬼門の北東は干支で言う丑(うし)と寅(とら)の間に当たり、鬼に牛(丑)の角を着け+虎(寅)のパンツをはかせた絵を描いたと言われる。それが今日まで続いている。<諸説あり>余談/投稿者は2月・4月を迎えると鬱陶しさを感じる。花粉症ではなく、2月・4月のアクセント。NHK放送文化センターのHP(最近気になる放送用語)を見ると、『「~月」のアクセントには、「尾高型<おだかがた>」と「頭高型<あたまだかがた>」がある。尾高型は、「~月」の終わりまでを高く発音するもので、1、2、4、6、7、8、10、11、12月。頭高型は、最初の1拍だけを高く発音するもので、3、5、9月。ところが本来・尾高型の2月と4月を、頭高型で[ニ\ガツ][シ\ガツ]と発音する人が増えています。間違えないように、「頭高はゴー(5)、サンキュー(3・9)」と覚えておきましょう』。
恵方巻きが大量に売れ残り食料廃棄の深刻化と店員へノルマ・買い取り強要











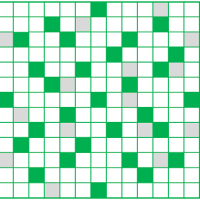











 1月 ベスト10
1月 ベスト10 










 2月のピックアップ!
2月のピックアップ!














