中学受験で疲弊しないために、親子で楽しむ受験になるヒントを綴っていきたいと思います。
中学受験で子どもと普通に幸せになる方法
親の心構えの作り方
いよいよ、入試が近づいてきました。
母親講座等でこの時期、
「親はどーんとかまえましょう」
というお話をします。
お母さんが心配すると、子どもに伝染します。
「そうか、僕は危ないかもしれない」
と思うようになってしまうと、これはまずい。子どもに妙なプレッシャーがかかります。子どもはもう「合格するだけ」という気持ちになるのがいいのです。ですから、お母さんは「どーん」とかまえた方が良い。
しかし、まだ何か方法があるのではないか、何か手は打てないのか、そんな気持ちが強いと思います。
それはそれで考えた方がよいでしょう。ただ、すでに子どもたちのスケジュールはいっぱいになっているはずだし、勉強もある程度やることが決まっています。ここまでくれば、決めたことを黙々とこなしていく方が良いのです。
特にこれから始める勉強はなるべく短期で終わるものが良いです。「やりきった」という気持ちになれるようにしてあげてください。
さて、親の心構えの作り方。
心配はなくなりません。結果が出るまでは。そして、結果が出てはじめて次の手になるのです。
ですからこう考えてください。
「どこに行こうと、それをベストにすればいい」
お子さんは小学生ですから、次は中学生。義務教育です。浪人はありません。
だから、来年の4月には中学生としてスタートする。
それが子どもの成長にとってベストにしよう、とそう決めればいいのです。
私はこれまでたくさんの子どもたちを見てきましたが、要は入学後が大事なのです。合格してもそれで「ほっ」として遊びぐせがついてしまうと、第一志望に入っても落ちこぼれてしまいます。一方、残念でもそこからがんばれば、新たな可能性が開くのです。
ですから、親としては「通う学校が子どもにとってベストになればいいんだ」と考えることです。
そうすると、自然、ふっと心が落ち着いてきます。
そしてお母さんがそうなると、子どもにも自然、自信がわいてくるものなのです。
==============================================================
田中貴.com通信を発刊しています。登録は以下のページからお願いします。無料です。
田中貴.com通信ページ
==============================================================

「中学受験、成功する親、失敗する親」
母親講座等でこの時期、
「親はどーんとかまえましょう」
というお話をします。
お母さんが心配すると、子どもに伝染します。
「そうか、僕は危ないかもしれない」
と思うようになってしまうと、これはまずい。子どもに妙なプレッシャーがかかります。子どもはもう「合格するだけ」という気持ちになるのがいいのです。ですから、お母さんは「どーん」とかまえた方が良い。
しかし、まだ何か方法があるのではないか、何か手は打てないのか、そんな気持ちが強いと思います。
それはそれで考えた方がよいでしょう。ただ、すでに子どもたちのスケジュールはいっぱいになっているはずだし、勉強もある程度やることが決まっています。ここまでくれば、決めたことを黙々とこなしていく方が良いのです。
特にこれから始める勉強はなるべく短期で終わるものが良いです。「やりきった」という気持ちになれるようにしてあげてください。
さて、親の心構えの作り方。
心配はなくなりません。結果が出るまでは。そして、結果が出てはじめて次の手になるのです。
ですからこう考えてください。
「どこに行こうと、それをベストにすればいい」
お子さんは小学生ですから、次は中学生。義務教育です。浪人はありません。
だから、来年の4月には中学生としてスタートする。
それが子どもの成長にとってベストにしよう、とそう決めればいいのです。
私はこれまでたくさんの子どもたちを見てきましたが、要は入学後が大事なのです。合格してもそれで「ほっ」として遊びぐせがついてしまうと、第一志望に入っても落ちこぼれてしまいます。一方、残念でもそこからがんばれば、新たな可能性が開くのです。
ですから、親としては「通う学校が子どもにとってベストになればいいんだ」と考えることです。
そうすると、自然、ふっと心が落ち着いてきます。
そしてお母さんがそうなると、子どもにも自然、自信がわいてくるものなのです。
==============================================================
田中貴.com通信を発刊しています。登録は以下のページからお願いします。無料です。
田中貴.com通信ページ
==============================================================

「中学受験、成功する親、失敗する親」
コメント ( 0 )
PISA型入試の影響(田中貴.com)
PISA型入試の影響(田中貴.com)
==============================================================
田中貴.com通信を発刊しています。登録は以下のページからお願いします。
無料です。
田中貴.com通信登録ページ
==============================================================

「中学受験、合格して失敗する子、不合格でも成功する子」
==============================================================
田中貴.com通信を発刊しています。登録は以下のページからお願いします。
無料です。
田中貴.com通信登録ページ
==============================================================

「中学受験、合格して失敗する子、不合格でも成功する子」
コメント ( 0 )
PISA型入試
今朝のNHKの番組で、PISA型入試が話題になっていましたね。
近年、公立の中高一貫校がたくさんできて、また最初の入学者が大学受験の結果を出しているので、注目が集まっているからでしょう。
私立でも募集が大変なところは、むしろ入試形式をこれまでの中学入試の傾向からPISA型入試に切り替えていくのではないかと思います。
公立中高一貫校は、平均倍率が5倍。私立中学は平均倍率が3倍。つまり公立の方が集まっているので、その層に対して枠を作っていく私立学校は増えていくでしょう。
ではPISA型入試というのは何でしょうか。私立中学入試と何が違うのでしょうか?
基本的にOECDの学力調査の方式とほぼ同じ型のものです。
PISA型学力とは何か
で、今の私立問題と何が違うか。
算数は、かなりやさしいと思っていいでしょう。これは私立入試の方がやはりかなり高度といえます。
ただ、それ以外は、むしろ問われている能力が違うと思います。
まず、資料やグラフ、を読み解く力。さらに自分で問題点を洗い出し、その解決方法を自分の言葉で記述する力。
練習しなければならないでしょう。
公立一貫校の入試は検査という言い方をします。つまり、試験ではない。
だから、ある程度、公立一貫の対策をすれば、私立を受ける子どもたちには難しことではない、ということなのです。
逆は難しいかもしれない。公立一貫の対策をしたからといって、私立は難しい。つまり、理科、社会の出題がまったく違うからですね。
また公立は東京の場合2月3日しかない。
だから、公立一貫だけを受けるのか、それとも私立を合わせるのか、という選択がやはり必要なわけで、私立を受けるとなるとまた別の入試形態の練習をしないといけないわけでしょう。
ただ実は、私立受験生の中で2月3日を公立一貫に向けている子どもたちは増加しています。例えばサピックスでも小石川中等教育で27名の合格者がいます。
確かに求められている中身が違うので、いわゆる4教科型の偏差値では高くなくとも、PISA型では結構良い点がでる、という子はいるかもしれません。
公立一貫だけ受けるのであれば、対策はシンプルで、それだけやればいい。専門の塾もたくさんあります。こちらの方が確かに私立型に比べれば学習する内容の負担は大きくないでしょう。
ただ、それ以外の選択肢をどう考えるか、でまたやり方が変わってきます。
私立でもPISA型が増えれば、また対策の方法は変わってくるかもしれませんね。
==============================================================
田中貴.com通信を発刊しています。登録は以下のページからお願いします。無料です。
田中貴.com通信ページ
==============================================================
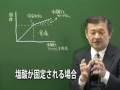 「映像教材、これでわかる水溶液」(田中貴)
「映像教材、これでわかる水溶液」(田中貴)
近年、公立の中高一貫校がたくさんできて、また最初の入学者が大学受験の結果を出しているので、注目が集まっているからでしょう。
私立でも募集が大変なところは、むしろ入試形式をこれまでの中学入試の傾向からPISA型入試に切り替えていくのではないかと思います。
公立中高一貫校は、平均倍率が5倍。私立中学は平均倍率が3倍。つまり公立の方が集まっているので、その層に対して枠を作っていく私立学校は増えていくでしょう。
ではPISA型入試というのは何でしょうか。私立中学入試と何が違うのでしょうか?
基本的にOECDの学力調査の方式とほぼ同じ型のものです。
PISA型学力とは何か
で、今の私立問題と何が違うか。
算数は、かなりやさしいと思っていいでしょう。これは私立入試の方がやはりかなり高度といえます。
ただ、それ以外は、むしろ問われている能力が違うと思います。
まず、資料やグラフ、を読み解く力。さらに自分で問題点を洗い出し、その解決方法を自分の言葉で記述する力。
練習しなければならないでしょう。
公立一貫校の入試は検査という言い方をします。つまり、試験ではない。
だから、ある程度、公立一貫の対策をすれば、私立を受ける子どもたちには難しことではない、ということなのです。
逆は難しいかもしれない。公立一貫の対策をしたからといって、私立は難しい。つまり、理科、社会の出題がまったく違うからですね。
また公立は東京の場合2月3日しかない。
だから、公立一貫だけを受けるのか、それとも私立を合わせるのか、という選択がやはり必要なわけで、私立を受けるとなるとまた別の入試形態の練習をしないといけないわけでしょう。
ただ実は、私立受験生の中で2月3日を公立一貫に向けている子どもたちは増加しています。例えばサピックスでも小石川中等教育で27名の合格者がいます。
確かに求められている中身が違うので、いわゆる4教科型の偏差値では高くなくとも、PISA型では結構良い点がでる、という子はいるかもしれません。
公立一貫だけ受けるのであれば、対策はシンプルで、それだけやればいい。専門の塾もたくさんあります。こちらの方が確かに私立型に比べれば学習する内容の負担は大きくないでしょう。
ただ、それ以外の選択肢をどう考えるか、でまたやり方が変わってきます。
私立でもPISA型が増えれば、また対策の方法は変わってくるかもしれませんね。
==============================================================
田中貴.com通信を発刊しています。登録は以下のページからお願いします。無料です。
田中貴.com通信ページ
==============================================================
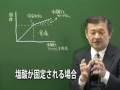 「映像教材、これでわかる水溶液」(田中貴)
「映像教材、これでわかる水溶液」(田中貴)コメント ( 0 )
「中学受験、成功する親、失敗する親」リリースのお知らせ(田中貴.com)
「中学受験、成功する親、失敗する親」リリースのお知らせ(田中貴.com)
==============================================================
田中貴.com通信を発刊しています。登録は以下のページからお願いします。
無料です。
田中貴.com通信登録ページ
==============================================================
==============================================================
田中貴.com通信を発刊しています。登録は以下のページからお願いします。
無料です。
田中貴.com通信登録ページ
==============================================================
コメント ( 0 )
5年2学期が合否の分かれ目?
5年生の1学期と2学期では結構ボリュームも難しさも違いがあります。
以前は、小数、分数がこの5年2学期で出てきたので、それもあって5年2学期が受験準備のひとつの分かれ目になっていました。ところが、今はもっと早い。そろそろ入試範囲を勉強する最終段階に入ってきているのです。
以前のカリキュラムで言えば、飛び級的な感覚があります。
かつ、最近の塾は全部やります。取捨選択があまりない。
出そうなところは片っ端からやる。そして覚えさせる。
でも5年2学期って、まだ1年以上入試は先なんです。覚えてられますか?そこまで。
その結果として、それをこなせた子どもたちとそうでない子どもたちに分かれます。結局、頭のいい子、というのはすぐに覚えたり、わかったりするので、そこまで負荷をかけてもできてしまう。
そういう子どもたちは何の問題もないです。
が、しかし、そうでない子も少なくありませんね。
ところが、親は、「いつかはやってくれるだろう」と思いがちです。でも、なかなかそうはならない、だってできる子どもたちが上にいるんですから。だから席は空きません。クラスの順位もここからめきめきと上がる子はそう多くはない。
ひとつ勝負がついているんです。
ただし、このやり方で。
全部の範囲を片っ端から、優先順位もなく全部やる、というと学校のカリキュラムでいうと小学校5年生から中学2年ぐらいまでの範囲になります。それを1年かそこらでやりきる、ということを考えれば、なかなかできる話ではない。
お子さんが開成を受けるなら、そのくらいできないとだめでしょう。(そういう子たちが競う場ですから。)
でも、もし開成を受けないのなら、その子たちと競争する意味はないのでは?
例えば1番がいて300番がいると300人の子どもたちが並びますね。模擬試験とか、組み分けテストというのはそういう全体の勝負ですが、入学試験は本当は、ある学校へ行きたい子たちの勝負なので、ことの本質が違うのです。別に開成を受ける子と争う必要はない。
では、どうしたらいいのか。第一志望校を考えればいいのです。
第一志望はどこか、決めれば次のステップが出てきます。開成を受けるなら開成を受ける勝負をしないといけないから、それは今の勝負を続けないといけないかもしれない。しかし、他の学校を第一志望とするならば、それはまた違う考え方をしないといけないのではないでしょうか。
これは子どもが考えられることではありません。
親が考えないといけない。
私は
「5年のうちは基礎を固めて、6年で応用の枝葉を学校別傾向で伸ばす」
という勉強法を提唱しています。
東京、神奈川の試験は2月1日から2月3日までです。
勝負をする学校は2~3校でしょう。(1校は滑り止めを考えるでしょうから。)
そのどこを受けるかは、どういう学校に行きたいかで、本来決めるべきなのではないでしょうか?
そこをまず決める必要はあります。で、それが決まれば、方法はおのずと見えてくる。
5年2学期でひとつの勝負はつきました。
でも、本当の勝負はこれからです。そのために、親は考えないといけません。
ただ、「がんばって」では、努力の甲斐がない勝負になってしまいます。5年の2学期でまず第一志望を決めましょう。
==============================================================
田中貴.com通信を発刊しています。登録は以下のページからお願いします。
無料です。
田中貴.com通信登録ページ
==============================================================
以前は、小数、分数がこの5年2学期で出てきたので、それもあって5年2学期が受験準備のひとつの分かれ目になっていました。ところが、今はもっと早い。そろそろ入試範囲を勉強する最終段階に入ってきているのです。
以前のカリキュラムで言えば、飛び級的な感覚があります。
かつ、最近の塾は全部やります。取捨選択があまりない。
出そうなところは片っ端からやる。そして覚えさせる。
でも5年2学期って、まだ1年以上入試は先なんです。覚えてられますか?そこまで。
その結果として、それをこなせた子どもたちとそうでない子どもたちに分かれます。結局、頭のいい子、というのはすぐに覚えたり、わかったりするので、そこまで負荷をかけてもできてしまう。
そういう子どもたちは何の問題もないです。
が、しかし、そうでない子も少なくありませんね。
ところが、親は、「いつかはやってくれるだろう」と思いがちです。でも、なかなかそうはならない、だってできる子どもたちが上にいるんですから。だから席は空きません。クラスの順位もここからめきめきと上がる子はそう多くはない。
ひとつ勝負がついているんです。
ただし、このやり方で。
全部の範囲を片っ端から、優先順位もなく全部やる、というと学校のカリキュラムでいうと小学校5年生から中学2年ぐらいまでの範囲になります。それを1年かそこらでやりきる、ということを考えれば、なかなかできる話ではない。
お子さんが開成を受けるなら、そのくらいできないとだめでしょう。(そういう子たちが競う場ですから。)
でも、もし開成を受けないのなら、その子たちと競争する意味はないのでは?
例えば1番がいて300番がいると300人の子どもたちが並びますね。模擬試験とか、組み分けテストというのはそういう全体の勝負ですが、入学試験は本当は、ある学校へ行きたい子たちの勝負なので、ことの本質が違うのです。別に開成を受ける子と争う必要はない。
では、どうしたらいいのか。第一志望校を考えればいいのです。
第一志望はどこか、決めれば次のステップが出てきます。開成を受けるなら開成を受ける勝負をしないといけないから、それは今の勝負を続けないといけないかもしれない。しかし、他の学校を第一志望とするならば、それはまた違う考え方をしないといけないのではないでしょうか。
これは子どもが考えられることではありません。
親が考えないといけない。
私は
「5年のうちは基礎を固めて、6年で応用の枝葉を学校別傾向で伸ばす」
という勉強法を提唱しています。
東京、神奈川の試験は2月1日から2月3日までです。
勝負をする学校は2~3校でしょう。(1校は滑り止めを考えるでしょうから。)
そのどこを受けるかは、どういう学校に行きたいかで、本来決めるべきなのではないでしょうか?
そこをまず決める必要はあります。で、それが決まれば、方法はおのずと見えてくる。
5年2学期でひとつの勝負はつきました。
でも、本当の勝負はこれからです。そのために、親は考えないといけません。
ただ、「がんばって」では、努力の甲斐がない勝負になってしまいます。5年の2学期でまず第一志望を決めましょう。
==============================================================
田中貴.com通信を発刊しています。登録は以下のページからお願いします。
無料です。
田中貴.com通信登録ページ
==============================================================
コメント ( 0 )
地震の入試問題のポイント
震度は、揺れの大きさを表し、マグニチュードはエネルギーを表します。
震源は地震の起きた場所。震央は震源の真上の地表の位置。したがって、地震の速報で震源地という言い方は実は震央を表し、震源の深さで震源がわかるという仕組みになっています。
地震波は2つあり、第1波をP波、第二波をS波といいます。
P波が初期微動を起こし、主要動(大きな揺れ)を起こします。
P波は秒速5~7km S波は秒速3~4km。
問題ではP波を秒速8km、S波を秒速4kmとすることが多いようです。
P波が到着してからS波が到着するまでの間をP-S時と呼び、この時間によって観測地からの距離を測定します。
例えばP-S時が4秒であれば、上のP波、S波の秒速を使えばかかる時間の比は1:2になりますから差が4秒。したがってP波が到達するまでにかかった時間は4秒ですから、8×4=32kmが観測地から震源までの距離ということになります。
(例題)
以下の観測データから、次の時刻を求めなさい。
(ア)震源からの距離が45kmの地点における、ゆれはじめの時刻。
(イ)この地震が発生した時刻
観測点A 震源からの距離 30km ゆれはじめの時刻 午後6時10分20秒
観測点B 震源からの距離 90km ゆれはじめの時刻 午後6時10分32秒
観測点C 震源からの距離 150km ゆれはじめの時刻 午後6時10分44秒
ゆれはじめの時刻とは、P波が到着した時刻です。したがって90-30=60kmの距離を12秒で動いていますから、この問題ではP波の秒速は5km。
(ア)は45km地点ですから、45-30=15
15÷5=3秒ですから、ゆれはじめの時刻は午後6時10分23秒になります。
(イ)したがって30km÷5=6秒なので午後6時10分20秒から6秒ひけばいいので、発生時刻は午後6時10分14秒と計算すればいいのです。

理科重要問題ノート
理科重要問題ノートサンプル
震源は地震の起きた場所。震央は震源の真上の地表の位置。したがって、地震の速報で震源地という言い方は実は震央を表し、震源の深さで震源がわかるという仕組みになっています。
地震波は2つあり、第1波をP波、第二波をS波といいます。
P波が初期微動を起こし、主要動(大きな揺れ)を起こします。
P波は秒速5~7km S波は秒速3~4km。
問題ではP波を秒速8km、S波を秒速4kmとすることが多いようです。
P波が到着してからS波が到着するまでの間をP-S時と呼び、この時間によって観測地からの距離を測定します。
例えばP-S時が4秒であれば、上のP波、S波の秒速を使えばかかる時間の比は1:2になりますから差が4秒。したがってP波が到達するまでにかかった時間は4秒ですから、8×4=32kmが観測地から震源までの距離ということになります。
(例題)
以下の観測データから、次の時刻を求めなさい。
(ア)震源からの距離が45kmの地点における、ゆれはじめの時刻。
(イ)この地震が発生した時刻
観測点A 震源からの距離 30km ゆれはじめの時刻 午後6時10分20秒
観測点B 震源からの距離 90km ゆれはじめの時刻 午後6時10分32秒
観測点C 震源からの距離 150km ゆれはじめの時刻 午後6時10分44秒
ゆれはじめの時刻とは、P波が到着した時刻です。したがって90-30=60kmの距離を12秒で動いていますから、この問題ではP波の秒速は5km。
(ア)は45km地点ですから、45-30=15
15÷5=3秒ですから、ゆれはじめの時刻は午後6時10分23秒になります。
(イ)したがって30km÷5=6秒なので午後6時10分20秒から6秒ひけばいいので、発生時刻は午後6時10分14秒と計算すればいいのです。

理科重要問題ノート
理科重要問題ノートサンプル
コメント ( 0 )
試験度胸って必要(田中貴.com)
試験度胸って必要(田中貴.com)
========
お知らせ
========

邦学館出版でiPhone,iPadのユニバーサルアプリ「HougakkanBooks」がリリースされ、「中学受験、合格して失敗する子、不合格でも成功する子」が買い求めいただけるようになっています。
iPhone、iPadをお持ちの方はAPP Storeにて「HougakkanBooks」で検索してください。
アンドロイド版もリリースされました。
amazonでの本書のお買い求めはこちらから
========
お知らせ
========

邦学館出版でiPhone,iPadのユニバーサルアプリ「HougakkanBooks」がリリースされ、「中学受験、合格して失敗する子、不合格でも成功する子」が買い求めいただけるようになっています。
iPhone、iPadをお持ちの方はAPP Storeにて「HougakkanBooks」で検索してください。
アンドロイド版もリリースされました。
amazonでの本書のお買い求めはこちらから
コメント ( 0 )
田中貴.com通信(田中貴.com)
田中貴.com通信
========
お知らせ
========

邦学館出版でiPhone,iPadのユニバーサルアプリ「HougakkanBooks」がリリースされ、「中学受験、合格して失敗する子、不合格でも成功する子」が買い求めいただけるようになっています。
iPhone、iPadをお持ちの方はAPP Storeにて「HougakkanBooks」で検索してください。
アンドロイド版もリリースされました。
amazonでの本書のお買い求めはこちらから
========
お知らせ
========

邦学館出版でiPhone,iPadのユニバーサルアプリ「HougakkanBooks」がリリースされ、「中学受験、合格して失敗する子、不合格でも成功する子」が買い求めいただけるようになっています。
iPhone、iPadをお持ちの方はAPP Storeにて「HougakkanBooks」で検索してください。
アンドロイド版もリリースされました。
amazonでの本書のお買い求めはこちらから
コメント ( 0 )
溶解度のポイント
溶解度はポイントがあります。
というのは、実は最初濃度を習っているときは、食塩水の重さを考える。
食塩水の濃度というのは食塩水の中に含まれる食塩の重さの割合をいいます。
したがって 食塩水の濃度=食塩の重さ/(水の重さ+食塩の重さ)×100(%)
という計算で習うのです。ところが溶解度はこう考えない。
100gの水に何g溶ける、という表示をします。
例えば100gの水に25gのホウ酸が溶ける。ということは濃度は?
25%ではありません。
そう、25/(100+25)×100=20%になっていないといけない。濃度と溶解度はここが違うのです。これがごちゃごちゃになる。濃度と一緒にしてしまう。
だから間違うわけで、そこがしっかり理解できていれば、溶解度はそれほど難しくはないはずです。
温度による溶解度の違いも、水の重さと溶質の重さを温度ごとに理解できていればいいことになります。
例題をひとつ。
ホウ酸は20℃、100gの水に4.9g、80℃、100gの水に23.5g 溶けることがわかっています。これについて次の問いに答えなさい。
(1)300gの水を80℃にしてホウ酸を溶けるだけ溶かした後、これを20℃にすると何gのホウ酸が溶け残りますか。
(2)80℃の飽和ホウ酸水溶液247gから水を50g蒸発させた後、20℃にすると何gのホウ酸が溶け残りますか。
(1)100g、80℃の水に23.5g溶けるのであれば、水が300gになればその3倍溶けることになります。したがって23.5×3=70.5g溶けたことになります。さて、これを20℃にしても水が300gあることには変わりがないので、20℃の場合は100gで4.9gですから300gであれば4.9×3=14.7g溶けることになります。したがってその差が溶け残ることになりますから、70.5-14.7=55.8gが答えです。
(答え)55.8g
(2)80℃の場合、飽和水溶液は100gの水に対して23.5g溶けますから全体は100+23.5=123.5gになります。247÷123.5=2よりちょうど2倍ですから、水は100×2=200gあり、ホウ酸は247-200=47gということになります。水を50g蒸発させたのだから、残りは200-50=150gになります。20℃では100gにつき、4.9g溶けるのだから、4.9×1.5=7.35g溶けます。したがってその差が溶け残るので、47-7.35=39.65gが答えです。 (答え)39.65g
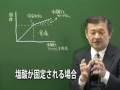 「映像教材、これでわかる水溶液」(田中貴)
「映像教材、これでわかる水溶液」(田中貴)
というのは、実は最初濃度を習っているときは、食塩水の重さを考える。
食塩水の濃度というのは食塩水の中に含まれる食塩の重さの割合をいいます。
したがって 食塩水の濃度=食塩の重さ/(水の重さ+食塩の重さ)×100(%)
という計算で習うのです。ところが溶解度はこう考えない。
100gの水に何g溶ける、という表示をします。
例えば100gの水に25gのホウ酸が溶ける。ということは濃度は?
25%ではありません。
そう、25/(100+25)×100=20%になっていないといけない。濃度と溶解度はここが違うのです。これがごちゃごちゃになる。濃度と一緒にしてしまう。
だから間違うわけで、そこがしっかり理解できていれば、溶解度はそれほど難しくはないはずです。
温度による溶解度の違いも、水の重さと溶質の重さを温度ごとに理解できていればいいことになります。
例題をひとつ。
ホウ酸は20℃、100gの水に4.9g、80℃、100gの水に23.5g 溶けることがわかっています。これについて次の問いに答えなさい。
(1)300gの水を80℃にしてホウ酸を溶けるだけ溶かした後、これを20℃にすると何gのホウ酸が溶け残りますか。
(2)80℃の飽和ホウ酸水溶液247gから水を50g蒸発させた後、20℃にすると何gのホウ酸が溶け残りますか。
(1)100g、80℃の水に23.5g溶けるのであれば、水が300gになればその3倍溶けることになります。したがって23.5×3=70.5g溶けたことになります。さて、これを20℃にしても水が300gあることには変わりがないので、20℃の場合は100gで4.9gですから300gであれば4.9×3=14.7g溶けることになります。したがってその差が溶け残ることになりますから、70.5-14.7=55.8gが答えです。
(答え)55.8g
(2)80℃の場合、飽和水溶液は100gの水に対して23.5g溶けますから全体は100+23.5=123.5gになります。247÷123.5=2よりちょうど2倍ですから、水は100×2=200gあり、ホウ酸は247-200=47gということになります。水を50g蒸発させたのだから、残りは200-50=150gになります。20℃では100gにつき、4.9g溶けるのだから、4.9×1.5=7.35g溶けます。したがってその差が溶け残るので、47-7.35=39.65gが答えです。 (答え)39.65g
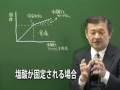 「映像教材、これでわかる水溶液」(田中貴)
「映像教材、これでわかる水溶液」(田中貴)コメント ( 0 )
正月特訓
いろいろな塾のパンフレットを見ると、正月特訓というのがありますね。
だいたい3日間ぐらい。さすがに元旦は授業をしない、というところが多いようですが、元旦からやるという強者もありますね。
正月特訓で3日間ぐらい勉強したって、そう効果はない?と思われるかもしれませんが、正月だからいいんです。
日本人は正月に勉強したり、仕事したりしていると、憐れむ習性があるみたいで。
「あら、かわいそうね。」とか「あら、大変ね。」とか。
私もよく元旦から仕事、と言ってそういわれました。でもね。ほんとは通勤もガラガラだし。
で、子どもたちもそういう扱いを受ける。ので、その分、気合が入るというか、やっぱり、今年は特別だと。
12歳の子どもたちですが、まだ入試というものを特別体験しているわけではないので、それがどういうものか、よくわからない。だいたい模擬試験の延長戦ぐらいにしかとらえられていないでしょう。
しかし、正月まで塾に行く?ということになると、これはいよいよだなあ、という感じになっていいのです。
私は正月は本番に似せた試験をよくやってました。
12月31日に受験票を渡し、1月1日に試験、1月2日に合格発表。俗に元旦模試。
まったく入試と同じシミュレーションをここでやります。だから手を抜かない。受験票を作り、合格発表も受験番号でやる。(ついでに補欠まで発表して。)
「落ちること」を恐れないようにしたかったのです。これは子どもによりますが、もう落ちるのが怖くて、今から自分で理由を作っている子までいるのです。(勉強しないのがその理由ですが。)
入試は落ちる方が多いのです。それを怖がっていても仕方がない。だからシミュレーションする。「落ちたって、君たちは変わらないよ。」ということを経験させるのですね。
やる方は元旦から採点でしたが、まあ、子どもたちが少しずつでも気持ちを太くできれば効果はあるというもの。
だから正月特訓は決して意味がないわけではないのです。(もちろん、各塾の工夫にもよりますが。)
中身を聞いて、出るか、出ないか、決められたら良いのではないでしょうか。3日間ですが、他の講習よりも案外効果があったりするのです。
やはり日本人に正月は特別なのでしょうね。
========
お知らせ
========

邦学館出版でiPhone,iPadのユニバーサルアプリ「HougakkanBooks」がリリースされ、「中学受験、合格して失敗する子、不合格でも成功する子」が買い求めいただけるようになっています。
iPhone、iPadをお持ちの方はAPP Storeにて「HougakkanBooks」で検索してください。
アンドロイド版もリリースされました。
amazonでの本書のお買い求めはこちらから
だいたい3日間ぐらい。さすがに元旦は授業をしない、というところが多いようですが、元旦からやるという強者もありますね。
正月特訓で3日間ぐらい勉強したって、そう効果はない?と思われるかもしれませんが、正月だからいいんです。
日本人は正月に勉強したり、仕事したりしていると、憐れむ習性があるみたいで。
「あら、かわいそうね。」とか「あら、大変ね。」とか。
私もよく元旦から仕事、と言ってそういわれました。でもね。ほんとは通勤もガラガラだし。
で、子どもたちもそういう扱いを受ける。ので、その分、気合が入るというか、やっぱり、今年は特別だと。
12歳の子どもたちですが、まだ入試というものを特別体験しているわけではないので、それがどういうものか、よくわからない。だいたい模擬試験の延長戦ぐらいにしかとらえられていないでしょう。
しかし、正月まで塾に行く?ということになると、これはいよいよだなあ、という感じになっていいのです。
私は正月は本番に似せた試験をよくやってました。
12月31日に受験票を渡し、1月1日に試験、1月2日に合格発表。俗に元旦模試。
まったく入試と同じシミュレーションをここでやります。だから手を抜かない。受験票を作り、合格発表も受験番号でやる。(ついでに補欠まで発表して。)
「落ちること」を恐れないようにしたかったのです。これは子どもによりますが、もう落ちるのが怖くて、今から自分で理由を作っている子までいるのです。(勉強しないのがその理由ですが。)
入試は落ちる方が多いのです。それを怖がっていても仕方がない。だからシミュレーションする。「落ちたって、君たちは変わらないよ。」ということを経験させるのですね。
やる方は元旦から採点でしたが、まあ、子どもたちが少しずつでも気持ちを太くできれば効果はあるというもの。
だから正月特訓は決して意味がないわけではないのです。(もちろん、各塾の工夫にもよりますが。)
中身を聞いて、出るか、出ないか、決められたら良いのではないでしょうか。3日間ですが、他の講習よりも案外効果があったりするのです。
やはり日本人に正月は特別なのでしょうね。
========
お知らせ
========

邦学館出版でiPhone,iPadのユニバーサルアプリ「HougakkanBooks」がリリースされ、「中学受験、合格して失敗する子、不合格でも成功する子」が買い求めいただけるようになっています。
iPhone、iPadをお持ちの方はAPP Storeにて「HougakkanBooks」で検索してください。
アンドロイド版もリリースされました。
amazonでの本書のお買い求めはこちらから
コメント ( 0 )
| « 前ページ | 次ページ » |





