公開中の日本映画「のぼうの城」はいわば以下の有名な格言であらわせるでしょう。
「人間には、負けるとわかっていても戦わなければならない時がある」
この格言は仏の詩人ボードレールの言葉だとか、米作家W・サローヤンのだとか言われていますが定かではありません。
まぁ、我々の世代ではあれですよね松本零士先生の「キャプテン・ハーロック」のセリフとして有名です。
曰く
「男には負けるとわかっていても戦わなければならないときがある。
死ぬとわかっていても、行かなければならないことがある…」
戦後、いわゆる進歩的文化人と称する知識人どもは訳知り顔で「日本は到底勝ち目のない愚かな戦争をした」と散々「大東亜戦争」で散って行った帝国軍人を批判、攻撃してきました。
人間の誇りや尊厳以上に自分の命だけが大切な彼らには、おそらく「チンプンカンプン」な格言でしょう。
そしておそらく、こういう知識人ぶった御仁方が観てもさっぱり意味がわからない映画がこの「のぼうの城」だと思うワケ。

攻めよせる秀吉の軍勢は2万人。一方それに立ち向かう味方の兵はたった500人。到底勝てるはずのない戦を決意し、知略を尽くして、さわやかな和睦までに持ち込んだ、戦国のあっぱれな殿様を描いたのが本映画。

戦国末期。天下統一を目前に控えた豊臣秀吉(市村正親)は、最後の敵、北条家に大群を投じていた。
周囲を湖で囲まれ“浮き城”の異名を持ち、人々が平穏に暮らす“忍城”に対し、秀吉は2万の軍勢で落とすよう、寵愛の家臣・石田三成(上地雄輔)に命じる。

忍城の侍たちに緊張が走る中、農民や子供たちと楽しそうに戯れる侍、成田長親(野村萬斎)がいた。城主・成田氏長(西村雅彦)の従弟で、智も仁も勇もないが人気だけはある不思議な男。
領民からは“でくのぼう”を意味する“のぼう様”の愛称で呼ばれ、皆に慕われていた。
 野村萬斎
野村萬斎
そんな長親に密かに想いを寄せる城主の娘、甲斐姫(榮倉奈々)。長親の幼馴染で歴戦の強者、丹波(佐藤浩市)。その丹波をライバル視する豪傑・豪腕の和泉(山口智充)。戦の経験は無いが“軍略の天才”を自称する靭負(成宮寛貴)。
 佐藤浩市
佐藤浩市
緊迫する仲間たちを前に、長親は呑気なことを言って皆を唖然とさせるが、ある日、天下軍が遂に忍城を包囲する。成田氏長は「秀吉軍とは一戦も交えずに速やかに開城せよ」との言葉を残し、長親に城を任せ、既に小田原に向かっていた。忍城の500人の軍勢では2万の大軍相手に戦っても勝ち目はない。
やむなく開城することを決意する長親たちだったが、天下軍の威を借り、なめきった態度を取る長束正家(平岳大)と対面した長親は、一転戦うことを決意。
 戦を決意
戦を決意
長親のその強い決意に導かれるように、丹波をはじめとする武将たちや普段から長親を慕う百姓たちも立ち上がる。
それは、戦によって名を挙げることに闘志を燃やす三成の思う壺であったが、秀吉に三成を支えるよう命を受けた盟友・大谷吉継(山田孝之)だけは、忍城軍のあり得ない士気の高さに警戒心を抱く。忍城軍は襲いくる大軍を前に、農民や老兵までが侍に劣らぬ活躍を見せ、地の利を生かし、騎馬鉄砲や火攻めなど多彩な戦術で天下軍を退けていく。

想像を超える忍城軍の奮闘ぶりに三成は、城の周辺に巨大な人工の堤を築き、それを決壊させる“水攻め”を決断。濁流が流れ出し、領民たちは高台にある忍城本丸に必死に逃げ込む。このままでは本丸が沈むのも時間の問題。だが、忍城軍が絶望に包まれる中、長親はただ一人で武器も持たずに小舟で三成が築いた堤へと向かっていくのだった……。
 まさに野村萬斎の独壇場。というより彼でなければできない。
まさに野村萬斎の独壇場。というより彼でなければできない。
さて、映画は2時間半の大作ですが、テンポの良い語り口で、もう見る者を釘づけにしてしまい、あっという間に時間が経ちます。
もう一言で「面白い」っ!!
まぁ、中にはこの城周辺のみだけ描かれていて、世界観が狭すぎるという批評や、時代考証がおかしいとかいった意見もあります。
なるほど、室町時代の甲冑をつけた若武者や、逆に西洋の南蛮甲冑の侍もいてなんだか突っ込みどころも満載なのですが、いいじゃないですか。本がよく書けているのでともかく楽しい。
小生的には、あれだけCG見事に使っているんだから、馬がなんとかならなかったのかなぁという気はしました。よく見ると馬が10頭以上出てないんですね。やっぱ戦国の合戦は馬でしょう馬。まぁ、予算の関係もあるでしょうからないものねだりなんでしょうけど。

あんまり書くとネタバレになっちゃうのでアレなんですが、このラストの両陣営の幕引きの仕方といい、実にさわやかで、なんだか激闘のサッカー試合後のジェントルマンたちを見ているようでした。
んでね、例によって、エンドロールが始まるとお客さんたちがゾロゾロ帰りだすんですが、このエンドロール中盤、この合戦があった埼玉県行田市の城跡周辺の現在の様子が紹介されるんですが、ここのシーンが実にいい。ぶっちゃけ、ここ見逃したらもったいないです。
だから、せっかくお金払って観に来てんだからなんで途中で席立つんだか意味解りません。
 今も埼玉県に残る光成が水攻めに建設した「石田塚」
今も埼玉県に残る光成が水攻めに建設した「石田塚」
「人間には、負けるとわかっていても戦わなければならない時がある」
この格言は仏の詩人ボードレールの言葉だとか、米作家W・サローヤンのだとか言われていますが定かではありません。
まぁ、我々の世代ではあれですよね松本零士先生の「キャプテン・ハーロック」のセリフとして有名です。
曰く
「男には負けるとわかっていても戦わなければならないときがある。
死ぬとわかっていても、行かなければならないことがある…」
戦後、いわゆる進歩的文化人と称する知識人どもは訳知り顔で「日本は到底勝ち目のない愚かな戦争をした」と散々「大東亜戦争」で散って行った帝国軍人を批判、攻撃してきました。
人間の誇りや尊厳以上に自分の命だけが大切な彼らには、おそらく「チンプンカンプン」な格言でしょう。
そしておそらく、こういう知識人ぶった御仁方が観てもさっぱり意味がわからない映画がこの「のぼうの城」だと思うワケ。

攻めよせる秀吉の軍勢は2万人。一方それに立ち向かう味方の兵はたった500人。到底勝てるはずのない戦を決意し、知略を尽くして、さわやかな和睦までに持ち込んだ、戦国のあっぱれな殿様を描いたのが本映画。

戦国末期。天下統一を目前に控えた豊臣秀吉(市村正親)は、最後の敵、北条家に大群を投じていた。
周囲を湖で囲まれ“浮き城”の異名を持ち、人々が平穏に暮らす“忍城”に対し、秀吉は2万の軍勢で落とすよう、寵愛の家臣・石田三成(上地雄輔)に命じる。

忍城の侍たちに緊張が走る中、農民や子供たちと楽しそうに戯れる侍、成田長親(野村萬斎)がいた。城主・成田氏長(西村雅彦)の従弟で、智も仁も勇もないが人気だけはある不思議な男。
領民からは“でくのぼう”を意味する“のぼう様”の愛称で呼ばれ、皆に慕われていた。
 野村萬斎
野村萬斎そんな長親に密かに想いを寄せる城主の娘、甲斐姫(榮倉奈々)。長親の幼馴染で歴戦の強者、丹波(佐藤浩市)。その丹波をライバル視する豪傑・豪腕の和泉(山口智充)。戦の経験は無いが“軍略の天才”を自称する靭負(成宮寛貴)。
 佐藤浩市
佐藤浩市緊迫する仲間たちを前に、長親は呑気なことを言って皆を唖然とさせるが、ある日、天下軍が遂に忍城を包囲する。成田氏長は「秀吉軍とは一戦も交えずに速やかに開城せよ」との言葉を残し、長親に城を任せ、既に小田原に向かっていた。忍城の500人の軍勢では2万の大軍相手に戦っても勝ち目はない。
やむなく開城することを決意する長親たちだったが、天下軍の威を借り、なめきった態度を取る長束正家(平岳大)と対面した長親は、一転戦うことを決意。
 戦を決意
戦を決意長親のその強い決意に導かれるように、丹波をはじめとする武将たちや普段から長親を慕う百姓たちも立ち上がる。
それは、戦によって名を挙げることに闘志を燃やす三成の思う壺であったが、秀吉に三成を支えるよう命を受けた盟友・大谷吉継(山田孝之)だけは、忍城軍のあり得ない士気の高さに警戒心を抱く。忍城軍は襲いくる大軍を前に、農民や老兵までが侍に劣らぬ活躍を見せ、地の利を生かし、騎馬鉄砲や火攻めなど多彩な戦術で天下軍を退けていく。

想像を超える忍城軍の奮闘ぶりに三成は、城の周辺に巨大な人工の堤を築き、それを決壊させる“水攻め”を決断。濁流が流れ出し、領民たちは高台にある忍城本丸に必死に逃げ込む。このままでは本丸が沈むのも時間の問題。だが、忍城軍が絶望に包まれる中、長親はただ一人で武器も持たずに小舟で三成が築いた堤へと向かっていくのだった……。
 まさに野村萬斎の独壇場。というより彼でなければできない。
まさに野村萬斎の独壇場。というより彼でなければできない。さて、映画は2時間半の大作ですが、テンポの良い語り口で、もう見る者を釘づけにしてしまい、あっという間に時間が経ちます。
もう一言で「面白い」っ!!
まぁ、中にはこの城周辺のみだけ描かれていて、世界観が狭すぎるという批評や、時代考証がおかしいとかいった意見もあります。
なるほど、室町時代の甲冑をつけた若武者や、逆に西洋の南蛮甲冑の侍もいてなんだか突っ込みどころも満載なのですが、いいじゃないですか。本がよく書けているのでともかく楽しい。
小生的には、あれだけCG見事に使っているんだから、馬がなんとかならなかったのかなぁという気はしました。よく見ると馬が10頭以上出てないんですね。やっぱ戦国の合戦は馬でしょう馬。まぁ、予算の関係もあるでしょうからないものねだりなんでしょうけど。

あんまり書くとネタバレになっちゃうのでアレなんですが、このラストの両陣営の幕引きの仕方といい、実にさわやかで、なんだか激闘のサッカー試合後のジェントルマンたちを見ているようでした。
んでね、例によって、エンドロールが始まるとお客さんたちがゾロゾロ帰りだすんですが、このエンドロール中盤、この合戦があった埼玉県行田市の城跡周辺の現在の様子が紹介されるんですが、ここのシーンが実にいい。ぶっちゃけ、ここ見逃したらもったいないです。
だから、せっかくお金払って観に来てんだからなんで途中で席立つんだか意味解りません。
 今も埼玉県に残る光成が水攻めに建設した「石田塚」
今も埼玉県に残る光成が水攻めに建設した「石田塚」















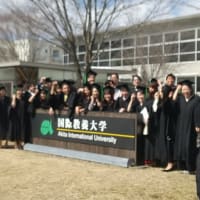



※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます