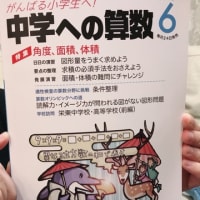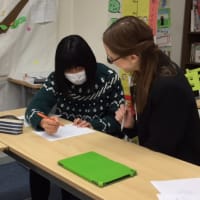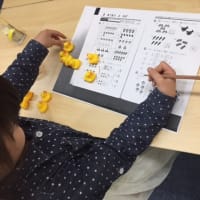小学生、特に低学年の国語についてです(高学年はこれらが終了しているとみなされます)
漢字の「音を表している」「意味を表している」のはどれですか?
糸+会=絵
日+生=星 などがありました。
というプリントを見ていて、昔は低学年でこんな学習をしたかしら?っと考えてしまいました。
これは中学生の「会意文字」や「象形文字」となっていくのですね。
新指導ではスパイラル学習となり、同じ単元を徐々に難易度を上げていく。
まさしくそうですね。
低学年では詩の問題も多く扱われて、背景や心情などを読み取る練習もしています
詩を理解するのは年々難しくなっています。
それはお子さんの問題と言うより、時代の流れの中に忘れ去られがちな部分だからでしょうか・・
事実私は田舎がありませんので、地方の風習をよく知りませんし
昔は「当たり前」だった事が今では「珍しい」に変わってきています。
例えば、昔・・夕方に「お豆腐屋さん」が自転車に乗ってお豆腐を売りに来ていました。
ボールをもってよく買いに行かされた事を思い出しますが
それも、珍しい部類になってしまったのではないでしょうか?
縁側という一つの言葉にしても現代住宅に縁側があるお家は少ないですよね・・・
生徒さん達が国語で苦手としてる詩の問題ですが、詩が苦手なのは
今まで親しんでこなかった事と、生活の中に今はもうない、触れる機会が少ない事が原因のような気がします。
親御さんは大人なので経験上理解は出来てもそれを説明するのは大変かもしれません。
詩は多くの言葉を使わず、明確に表現せず、間接的に情景を“想い描かせる”文がおおい。
今は夏・・・
夕方になって・・・とは書きません。
またその詩全体を通して筆者が何を伝えたいのかを読み取らなくてはいけません。
詩は小学生さんには特にですが、現代っ子の知らない言葉が並びます。
縁側、夕立、朝凪、打ち水、五月晴れ・・・
困った事に、これは中学生になって更に難易度を上げます。
四字熟語や漢詩なども常用では無いものも出ますよ!
中学受験とはまた違う難しさを感じさせます。
低学年の場合、算数を始めとする教科で理解していないように感じる事があったとしても
ほとんどの場合、「問題の意味を理解できていない」のであって、その教科を理解していないのでは
無いと思います。
お子さんと季節の言葉を使ってみてください。発見が沢山あって楽しいですよ♪
漢字の「音を表している」「意味を表している」のはどれですか?
糸+会=絵
日+生=星 などがありました。
というプリントを見ていて、昔は低学年でこんな学習をしたかしら?っと考えてしまいました。
これは中学生の「会意文字」や「象形文字」となっていくのですね。
新指導ではスパイラル学習となり、同じ単元を徐々に難易度を上げていく。
まさしくそうですね。
低学年では詩の問題も多く扱われて、背景や心情などを読み取る練習もしています
詩を理解するのは年々難しくなっています。
それはお子さんの問題と言うより、時代の流れの中に忘れ去られがちな部分だからでしょうか・・
事実私は田舎がありませんので、地方の風習をよく知りませんし
昔は「当たり前」だった事が今では「珍しい」に変わってきています。
例えば、昔・・夕方に「お豆腐屋さん」が自転車に乗ってお豆腐を売りに来ていました。
ボールをもってよく買いに行かされた事を思い出しますが
それも、珍しい部類になってしまったのではないでしょうか?
縁側という一つの言葉にしても現代住宅に縁側があるお家は少ないですよね・・・
生徒さん達が国語で苦手としてる詩の問題ですが、詩が苦手なのは
今まで親しんでこなかった事と、生活の中に今はもうない、触れる機会が少ない事が原因のような気がします。
親御さんは大人なので経験上理解は出来てもそれを説明するのは大変かもしれません。
詩は多くの言葉を使わず、明確に表現せず、間接的に情景を“想い描かせる”文がおおい。
今は夏・・・
夕方になって・・・とは書きません。
またその詩全体を通して筆者が何を伝えたいのかを読み取らなくてはいけません。
詩は小学生さんには特にですが、現代っ子の知らない言葉が並びます。
縁側、夕立、朝凪、打ち水、五月晴れ・・・
困った事に、これは中学生になって更に難易度を上げます。
四字熟語や漢詩なども常用では無いものも出ますよ!
中学受験とはまた違う難しさを感じさせます。
低学年の場合、算数を始めとする教科で理解していないように感じる事があったとしても
ほとんどの場合、「問題の意味を理解できていない」のであって、その教科を理解していないのでは
無いと思います。
お子さんと季節の言葉を使ってみてください。発見が沢山あって楽しいですよ♪