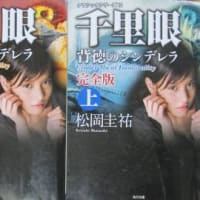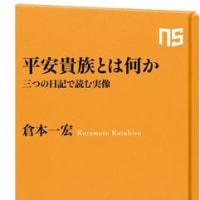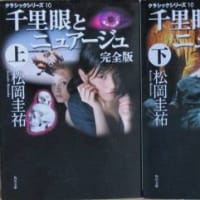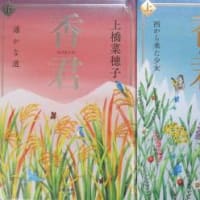坂岡真の鬼役シリーズを読み継いでいる。その中に江戸城本丸の間取り図の一部が掲載されている。江戸城全体の間取り図・縄張り図に関心を持ち始めていた。一方、NHKの大河ドラマ「べらぼう」が蔦重を題材にしているので見始めて、遊郭吉原の間取り図にも関心を持つようになってきた。
タイミングよく、本書のタイトルが目に止まった次第。パラパラと眺めると、「第一章 江戸城の間取り」。「第三章 町人地の間取り」の末尾には、吉原の項もある。ということで、本書を読んでみた。
各章には基本的な最小限度の知識の説明があり、代表例となる間取り図を載せて、その間取りについて説明がなされている。図解を中心に据えた解説本。江戸時代を扱う時代小説を読むのに便利な参照資料となる。
本書は、2024年5月に単行本が刊行されている。
奥書によれば、本書は『百万都市を俯瞰する 江戸の間取り』『図解 江戸の間取り』を元に、作成されたという。故に「新版」を冠している。(先行書については知らない。)
江戸について、本書で最も基本的なことを学んだ。
今、拙文を読んでいただいている方は次の諸点をご存じだっただろうか。
*江戸は武家地が約70%、町人地と寺社地がそれぞれ約15%ずつだった。
*江戸が百万都市に成長する転機は明暦の大火(1657年)。この時から防火対策として都市の拡張事業が始まった。
*1713(正徳3)年に町数が江戸八百八町を超える。
*1745(延享2)年に人口50万人を超えた。
私には、江戸時代について、一歩踏み込む参照本になった。
本書は間取り図を主軸に、背景となる基礎知識は最小限に抑えつつ、解説されているので、まず読みやすい。感想を含めつつ、どのような間取り図が掲載されているか、全体構成とともに、列挙してご紹介しよう。
< 第一章 江戸城の間取り >
江戸城が皇居となった明治の時点では、江戸城内部の面積は堀を含めて、306,760坪。東京ドーム21個分以上にあたるとか。それは、家康が幕府を開いた後、江戸城を「天下普請」と称して、拡張工事を進めて行った結果である。
江戸城内郭図。江戸城天守の間取り図(1607~1609頃)。本丸御殿表【将軍の応接間】の間取り図(1844)。本丸御殿・中奥の間取り図(1844)。江戸城本丸の全体図。本丸御殿大奥の間取り。御年寄の部屋の間取り図(1845)。
面白いと思ったのは、将軍が政務を行うのは本丸中奥の「御座之間」が主体。中奥に入れたのは側用人、御側衆、御小姓衆、御小納戸衆、奥医師位に限定されていた。老中等幕府の政務を執る官僚群は本丸表が仕事場。老中でさえ、中奥には入れない。お側衆をして案件を取り次がせたのだという。側用人が実質的な権力を握れたことにナルホド!である。本丸中奥と大奥の間には、「銅塀(あかがねべい)」という仕切り塀があったとか。
大奥に出入りするのは、原則として将軍だけ。
とは言えど、大奥には、「広敷向」という区域があり、そこは実務上、事務・警護の男性役人が職務時間中に詰める空間だった。そこは逆に女人禁制となっていた。
大奥の三分の二の面積を占める「長局向」が側室も含めた奥女中たちの住居で、多い時は奥女中が1000人近く居住し、住み込み勤務の奥女中たちは部屋ごとに自炊していたという。煮炊き・給仕・水汲みなどの下働きの女性も住み込みで働くことになるので、大奥に居住する女性の数が多くなるのもうなずける。
< 第二章 武家地の間取り >
武家地の過半は「大名屋敷」で、その土地は幕府が大名の在府中の居住場所として下賜した。大名に土地所有権はなく、幕府の命令で予告なく取り上げられることもあったそうである。だから、明治政府は諸大名屋敷の土地の接収がしやすかったのだろうなと思った。
この下賜も当初は大盤振る舞い、後には土地不足で拝領地に一定の基準-「高坪」(石高による基準)、「格坪/並坪」(役職による基準)-を設定するようになったとか。
「幕臣屋敷」には「旗本」と「御家人」の区分があり、その格差はかなり大きい。それと、「幕府の用地」(官有地)がある。
福井藩上屋敷の間取り図。尾張藩麹町中屋敷の間取り図(1716~1736)。尾張藩戸山屋敷の間取り図(1751~1764)。浜御庭【将軍の庭】の間取り図。六義園【大和郡山藩の庭園】の間取り図。後楽園【水戸藩の庭園】の間取り図。吉良上野介(上級旗本)の屋敷の間取り図。武井善八郎(中級旗本)の屋敷の間取り図。山本政恒(御家人)の屋敷の間取り図。与力谷村猪十郎の屋敷の間取り図(1837)。南町奉行所の間取り図(1810)。小伝馬町牢屋敷の間取り図(江戸時代後期)。人足寄場の間取り図(1790)。小石川養生所の間取り図(1835)。医学館の間取り図。
おもしろいと思ったのは、旗本・御家人は、下賜された屋敷内に貸家を設け、町人などに貸すという土地活用が普通の経済活動として公認されていたという点である。
禄高400石の旗本で「鬼平」こと、火付盗賊改の長谷川平蔵の本所の屋敷でも、屋敷内に町人などを住まわせ地代収入を得ていたという。
< 第三章 町人地の間取り >
江戸の町内の俯瞰図。三井越後屋江戸本店の間取り図。裏長屋の間取り図。表店と裏長屋の俯瞰図。割長屋と棟割長屋の違い。木戸番・自身番の間取り図。自身番拡大図。湯屋の間取り図。堺町の芝居町の間取り図。元吉原の間取り図。新吉原の間取り図。
これだけの間取り図と引用されている浮世絵を参考にすると、江戸庶民どのような住まい事情の下で日常生活をしていたがかなりイメージしやすくなる。時代劇映画に登場する裏長屋のシーンがなるほどとなる。かなり時代考証はちゃんとされているのだ。
< 第四章 寺社地の間取り >
増上寺・寛永寺が徳川将軍家の二大霊廟になった背景話がさらりと述べられている箇所もあり興味深い。天台宗と浄土宗にまたがっている。その例外は徳川慶喜。本人の意志で神式葬儀を望んだので、両寺とは無縁。江戸時代に「葬儀のみならず法事の際に香典料や回向料などの名目で莫大な金が落ち続けたから」(p113)という説明が納得でき、かつ面白い。
増上寺の鳥瞰図。増上寺の将軍家霊廟。寛永寺の境内図。浅草寺の間取り図。日枝神社(山王権現)周辺の俯瞰図。成田山新勝寺の開帳小屋の間取り図(1806)。
江戸時代に出開帳ということがかなり行われていたということは知っていたが、開帳小屋が設けられていたことやその間取り図などを初めて知った。江戸の庶民は本格的なイベント会場の出現に、手軽に行ける場所として、信仰がらみもあり詰めかけたのだろうなと感じる。
浅草寺の雷門や仲見世通りは、テレビの報道などで比較的目にしているが、「境内全体で何と169体もの神仏が祀られていた」(p114)という説明を読み、びっくり。これは知らなかった。「境内に祀られている多数の神仏は、浅草寺の図抜けた集客力の源泉となっていた」(p115-116)という説明にうなずける。これなら、毎日が縁日になっても不思議ではなさそう・・・・・。
< 第五章 江戸郊外地の間取り >
江戸郊外地の代表例は、江戸四宿と呼ばれた宿場町。東海道品川宿、甲州道中内藤新宿、中山道板橋宿、日光・欧州道中千住宿である。
品川宿本陣の間取り図。品川宿の街並み。千人同心組頭の屋敷の間取り図。豪農・吉野家の屋敷の間取り図。
歌川広重筆「東海道五十三次 品川宿」の錦絵は幾度も見ているが、その街並みが具体的にどうだったのか、その街並み図が部分図として載っていて興味深い。ある時点で、品川宿には、「品川宿などは飯盛女と呼ばれた女性が働く飯盛旅籠が93軒、飯盛女が置かれていなかった旅籠屋も19軒あった」(p132)、「水茶屋64軒、煮売り屋44軒、餅菓子屋16軒、蕎麦屋9軒」(p133)を含んでいたそうだ。
江戸から約40km離れた甲州道中八王子宿周辺に「八王子千人同心」という江戸の警護役が居たということを本書で初めて知った。普段は上層農民として働く武士が存在したという。北海道の屯田兵を連想した。
江戸時代について、間取りという観点から、人々の生活実態に想像を広げられる一冊である。間取り図を知ることで、江戸時時代小説を読むとき、描写場面に連なる空間環境の奥行きを具体的に広げる一助となるように思う。本書は気軽に楽しめ、江戸を知れる一冊である。
ご一読ありがとうございます。
タイミングよく、本書のタイトルが目に止まった次第。パラパラと眺めると、「第一章 江戸城の間取り」。「第三章 町人地の間取り」の末尾には、吉原の項もある。ということで、本書を読んでみた。
各章には基本的な最小限度の知識の説明があり、代表例となる間取り図を載せて、その間取りについて説明がなされている。図解を中心に据えた解説本。江戸時代を扱う時代小説を読むのに便利な参照資料となる。
本書は、2024年5月に単行本が刊行されている。
奥書によれば、本書は『百万都市を俯瞰する 江戸の間取り』『図解 江戸の間取り』を元に、作成されたという。故に「新版」を冠している。(先行書については知らない。)
江戸について、本書で最も基本的なことを学んだ。
今、拙文を読んでいただいている方は次の諸点をご存じだっただろうか。
*江戸は武家地が約70%、町人地と寺社地がそれぞれ約15%ずつだった。
*江戸が百万都市に成長する転機は明暦の大火(1657年)。この時から防火対策として都市の拡張事業が始まった。
*1713(正徳3)年に町数が江戸八百八町を超える。
*1745(延享2)年に人口50万人を超えた。
私には、江戸時代について、一歩踏み込む参照本になった。
本書は間取り図を主軸に、背景となる基礎知識は最小限に抑えつつ、解説されているので、まず読みやすい。感想を含めつつ、どのような間取り図が掲載されているか、全体構成とともに、列挙してご紹介しよう。
< 第一章 江戸城の間取り >
江戸城が皇居となった明治の時点では、江戸城内部の面積は堀を含めて、306,760坪。東京ドーム21個分以上にあたるとか。それは、家康が幕府を開いた後、江戸城を「天下普請」と称して、拡張工事を進めて行った結果である。
江戸城内郭図。江戸城天守の間取り図(1607~1609頃)。本丸御殿表【将軍の応接間】の間取り図(1844)。本丸御殿・中奥の間取り図(1844)。江戸城本丸の全体図。本丸御殿大奥の間取り。御年寄の部屋の間取り図(1845)。
面白いと思ったのは、将軍が政務を行うのは本丸中奥の「御座之間」が主体。中奥に入れたのは側用人、御側衆、御小姓衆、御小納戸衆、奥医師位に限定されていた。老中等幕府の政務を執る官僚群は本丸表が仕事場。老中でさえ、中奥には入れない。お側衆をして案件を取り次がせたのだという。側用人が実質的な権力を握れたことにナルホド!である。本丸中奥と大奥の間には、「銅塀(あかがねべい)」という仕切り塀があったとか。
大奥に出入りするのは、原則として将軍だけ。
とは言えど、大奥には、「広敷向」という区域があり、そこは実務上、事務・警護の男性役人が職務時間中に詰める空間だった。そこは逆に女人禁制となっていた。
大奥の三分の二の面積を占める「長局向」が側室も含めた奥女中たちの住居で、多い時は奥女中が1000人近く居住し、住み込み勤務の奥女中たちは部屋ごとに自炊していたという。煮炊き・給仕・水汲みなどの下働きの女性も住み込みで働くことになるので、大奥に居住する女性の数が多くなるのもうなずける。
< 第二章 武家地の間取り >
武家地の過半は「大名屋敷」で、その土地は幕府が大名の在府中の居住場所として下賜した。大名に土地所有権はなく、幕府の命令で予告なく取り上げられることもあったそうである。だから、明治政府は諸大名屋敷の土地の接収がしやすかったのだろうなと思った。
この下賜も当初は大盤振る舞い、後には土地不足で拝領地に一定の基準-「高坪」(石高による基準)、「格坪/並坪」(役職による基準)-を設定するようになったとか。
「幕臣屋敷」には「旗本」と「御家人」の区分があり、その格差はかなり大きい。それと、「幕府の用地」(官有地)がある。
福井藩上屋敷の間取り図。尾張藩麹町中屋敷の間取り図(1716~1736)。尾張藩戸山屋敷の間取り図(1751~1764)。浜御庭【将軍の庭】の間取り図。六義園【大和郡山藩の庭園】の間取り図。後楽園【水戸藩の庭園】の間取り図。吉良上野介(上級旗本)の屋敷の間取り図。武井善八郎(中級旗本)の屋敷の間取り図。山本政恒(御家人)の屋敷の間取り図。与力谷村猪十郎の屋敷の間取り図(1837)。南町奉行所の間取り図(1810)。小伝馬町牢屋敷の間取り図(江戸時代後期)。人足寄場の間取り図(1790)。小石川養生所の間取り図(1835)。医学館の間取り図。
おもしろいと思ったのは、旗本・御家人は、下賜された屋敷内に貸家を設け、町人などに貸すという土地活用が普通の経済活動として公認されていたという点である。
禄高400石の旗本で「鬼平」こと、火付盗賊改の長谷川平蔵の本所の屋敷でも、屋敷内に町人などを住まわせ地代収入を得ていたという。
< 第三章 町人地の間取り >
江戸の町内の俯瞰図。三井越後屋江戸本店の間取り図。裏長屋の間取り図。表店と裏長屋の俯瞰図。割長屋と棟割長屋の違い。木戸番・自身番の間取り図。自身番拡大図。湯屋の間取り図。堺町の芝居町の間取り図。元吉原の間取り図。新吉原の間取り図。
これだけの間取り図と引用されている浮世絵を参考にすると、江戸庶民どのような住まい事情の下で日常生活をしていたがかなりイメージしやすくなる。時代劇映画に登場する裏長屋のシーンがなるほどとなる。かなり時代考証はちゃんとされているのだ。
< 第四章 寺社地の間取り >
増上寺・寛永寺が徳川将軍家の二大霊廟になった背景話がさらりと述べられている箇所もあり興味深い。天台宗と浄土宗にまたがっている。その例外は徳川慶喜。本人の意志で神式葬儀を望んだので、両寺とは無縁。江戸時代に「葬儀のみならず法事の際に香典料や回向料などの名目で莫大な金が落ち続けたから」(p113)という説明が納得でき、かつ面白い。
増上寺の鳥瞰図。増上寺の将軍家霊廟。寛永寺の境内図。浅草寺の間取り図。日枝神社(山王権現)周辺の俯瞰図。成田山新勝寺の開帳小屋の間取り図(1806)。
江戸時代に出開帳ということがかなり行われていたということは知っていたが、開帳小屋が設けられていたことやその間取り図などを初めて知った。江戸の庶民は本格的なイベント会場の出現に、手軽に行ける場所として、信仰がらみもあり詰めかけたのだろうなと感じる。
浅草寺の雷門や仲見世通りは、テレビの報道などで比較的目にしているが、「境内全体で何と169体もの神仏が祀られていた」(p114)という説明を読み、びっくり。これは知らなかった。「境内に祀られている多数の神仏は、浅草寺の図抜けた集客力の源泉となっていた」(p115-116)という説明にうなずける。これなら、毎日が縁日になっても不思議ではなさそう・・・・・。
< 第五章 江戸郊外地の間取り >
江戸郊外地の代表例は、江戸四宿と呼ばれた宿場町。東海道品川宿、甲州道中内藤新宿、中山道板橋宿、日光・欧州道中千住宿である。
品川宿本陣の間取り図。品川宿の街並み。千人同心組頭の屋敷の間取り図。豪農・吉野家の屋敷の間取り図。
歌川広重筆「東海道五十三次 品川宿」の錦絵は幾度も見ているが、その街並みが具体的にどうだったのか、その街並み図が部分図として載っていて興味深い。ある時点で、品川宿には、「品川宿などは飯盛女と呼ばれた女性が働く飯盛旅籠が93軒、飯盛女が置かれていなかった旅籠屋も19軒あった」(p132)、「水茶屋64軒、煮売り屋44軒、餅菓子屋16軒、蕎麦屋9軒」(p133)を含んでいたそうだ。
江戸から約40km離れた甲州道中八王子宿周辺に「八王子千人同心」という江戸の警護役が居たということを本書で初めて知った。普段は上層農民として働く武士が存在したという。北海道の屯田兵を連想した。
江戸時代について、間取りという観点から、人々の生活実態に想像を広げられる一冊である。間取り図を知ることで、江戸時時代小説を読むとき、描写場面に連なる空間環境の奥行きを具体的に広げる一助となるように思う。本書は気軽に楽しめ、江戸を知れる一冊である。
ご一読ありがとうございます。