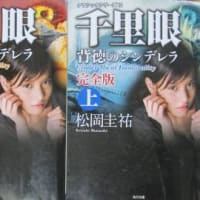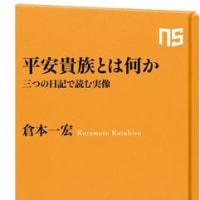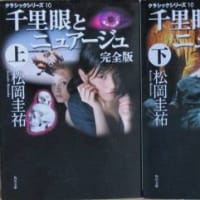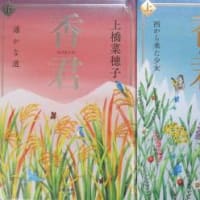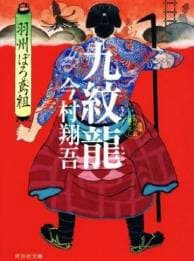
羽州ぼろ鳶組シリーズの書き下ろし第3弾。平成29年(2017)11月に文庫が刊行された。
町火消「に」組の頭・辰一は、火消番付で東の関脇に位置づけられている。町火消最強と評される男。身の丈六尺三寸(189cm)で筋骨隆々の巨体の持ち主であり、背中に九頭の龍の入れ墨を彫っている。そこから九紋龍と通称されている。本書のタイトルは辰一のこの通称に由来する。
序章は上方から始まる。長谷川平蔵が京都西町奉行に着任した当時、千羽一家という押し込み強盗が京を荒していた。平蔵は千羽一家を追う。千羽一家は京から姿を消す。そして、大坂で火事を起こして、火事を囮にして大坂南堀江の両替商「篠長」に押し入り、皆殺しにして金を奪って、消えた。火事は燃え広がった。上方で平蔵は切歯扼腕する。
その千羽一家が、江戸に戻ってきたのだ。再び、大胆な手口で火付け押し込み強盗を開始する。江戸で発生した火事に敏速に対処するため源吾たち羽州ぼろ鳶組は率先して活躍する。一方、松永源吾は起こった火事の不審さに疑問を抱く。同時期に発生した悲惨な強盗事件との関連に気づいていく。不審を感じる源吾の思考と行動がこのストーリーの推進力となっていく。そんな折、長谷川平蔵から伝馬で源吾宛に文が届く。
もう一人、「に」組の頭・九紋龍が千羽一家の動きを察知していた。九紋龍は千羽一家を壊滅することに執念を持っている。それはなぜか。それがこのストーリーの要になっている。
このストーリーの面白さを生み出す背景にある構造的な要素をご紹介しよう。
第1は、幕政を一手に担う田沼意次と将軍を輩出する資格を有する御三卿の一つである一橋家の当主・一橋治済(はるさだ)との間の政治的確執が継続している。前作で、田沼意次が建造を推進した弁財船、鳳丸が大火の消火手段に使われ、一度の航海もしないまま座礁した。この結果が、田村追い落としの材料に利用され、田村意次は守勢に回る状況になっていた。一橋治済は田沼潰しに黒幕として暗躍する。
一橋治済は田沼意次に、新庄藩の方角火消の役割を免じてやればとすら言い始める。
第2は、長谷川平蔵が栄転の形で、京都西町奉行に転出したことに起因する状況。島田弾正政弥(まさひさ)が火付盗賊改方の長官後継者となった。島田には長谷川平蔵のような気概もなければ能力も無い。源吾は頼りにならない人物と判断する。源吾にとり島田は事件解決で連携プレイがとれない負の要素に過ぎなくなる。長谷川平蔵が居てくれたならば・・・・というところ。 平蔵が京に去ってから、府下の火付け事件は増加の一途を辿るという状況にあった。
第3は、新庄藩に状況変化が生まれる。新庄藩の家老、六右衛門は国元に帰ると、その後病の床に就いた。国元から御連枝戸沢正親が江戸に出て来て、家老の代行を始めた。正親は新庄藩の財政が困窮していることと、国元を優先させるという方針で、藩財政の運営を始める。源吾には、鳶の俸給を減じ、その他火消道具などへの費用を五個年差し止めると通告してきた。方角火消の役割も管轄範囲内に留めよという。源吾にとっては承伏できない方針である。正親は何処かから、それなりの情報を入手した上で、己の方針を打ち出してきたのだ。正親の言を受け入れるなら、新庄藩火消は壊滅する。源吾は再び窮地に立たされる。源吾、どうする・・・・。火消の矜持とぼろ鳶組の存続をかけて、源吾は正親に対峙しなければならなくなる。正親と源吾の関係はどのように進展するのか。
第4は、前作で魁の武蔵が登場した。戸沢正親が江戸に出てくる以前の段階で、源吾は武蔵を新庄藩火消一番組頭に迎え入れていた。竜吐水の扱いが滅法上手い武蔵をぼろ鳶組の強力な戦力にしようとしていた。源吾は新庄藩の火消道具の老朽化への対処に迫られていた。
第5は、源吾の妻、深雪が前作の最後の時点で身籠もっている事実がわかった。さらに深雪は己の才覚で近隣諸家の奥方たちと社交を広げ、交流ネットワークを築いていた。その結果が現れてくるという側面が織り込まれて行く。
こういう背景要素が絡まり合って、正親の言を半ば無視する源吾と羽州ぼろ鳶組の火消活動が展開されていくというストーリーが展開する。その源吾の前に町火消「に」組の九紋龍が現れてくる。火事現場に乱入してきて、大混乱を引き起こす因となる。火消同士の喧嘩も始まる。配下の火消に命じるだけで、己の考えを語らない九紋龍のなぞの行動の有り様が、読者の関心を引き付けていく。
火消活動が度重なるにつれ、源吾と九紋龍の関わり方が変化していく。今回のストーリーでは、消火活動と併せて千羽一家の撲滅をめざすという目的に向かった両者の関わり方が読ませどころとなっていく。勿論、火消たちの連携プレーを含めてである。
火事の発生、火消たちの消火活動。それと同時期に事件が発生する。それらの名称だけ時系列でご紹介しておこう。
麻布宮村町 有馬兵庫守下屋敷の火事 :六本木町の商家「朱門屋」で18名斬殺・強盗
日本橋南、元大工町 会所の火事 :日本橋、谷町の材木問屋「菱屋」で皆殺し・強盗
南小田原町、乾物商「小谷屋」の火事
浅草阿部川町、墨屋「染床」の火事 : 一軒の札差宅で11名皆殺し・強盗
神田橋御門近く三河町、そして小伝馬町 :最後の大団円となる。お楽しみに・・・。
最後に火事を喰い止める場所が、小伝馬上町となる。源吾の一言「各火消! 俺の指揮に従ってくれ!」火消の一致協力が力を発揮する。著者はここの躍動的で迫力ある場面描写により読者を引き込んでいく。さすが、エンターテインメント性を存分に発揮する。
九紋龍・辰一は背中に9頭の龍を彫っていた。8頭までは見事な龍の彫りと仕上げなのだが、1頭だけは筋彫りで輪郭を彫るだけに留めていた。この不可思議さが辰一の過去と現在の思いを表象している。この九紋龍を彫り込んだ辰一の思いが、彼の行動の原点になっている。源吾は星十郎、新之助、寅次郎らの協力を得て、その謎解きを試みる。また、「に」組の宗助が、辰一と源吾の間をつなぐ役割として要所要所に登場する。
それがこのストーリーの読ませどころにリンクしていくということに触れておこう。
ここからは読んでのお楽しみである。
この第3作、「第6章 勘定小町参る」で締めくくられる。勘定小町とは源吾の妻、深雪のこと。新庄藩の財政運営の為に、深雪が一働きするというエピソードで締めくくられるところが楽しい。そこに、上方きっての豪商、大文字屋四代の下村彦右衛門素休を登場させるのだから、おもしろい。大文字屋の通称はご存知の大丸である。
実在した新庄藩と大丸の下村彦右衛門は、史実として商取引の関係があったのだろうか。それともこれは時代小説としてのフィクションにすぎないのか。小説を離れてちょっと関心が湧いた。
最後に本書から印象深い箇所を引用、ご紹介する。
*無欠な者などおりません。それを補い合い人は生きているのです。個の力には限界があるかと。 p162
*新庄の民は貧しい。しかし決して明日への希を捨てぬ。人への思いやりを忘れはせぬ。人の真の貧しさとは、それらを忘れることではなかろうか・・・・先代のお言葉よ。 p253
松永源吾率いる羽州ぼろ鳶組がその存亡の窮地を脱する目途が立ったところで終わるのがいい。著者は読者の心をつかむのがうまいと感じる。第4弾への期待を募らせる。
ご一読ありがとうございます。
補遺
消防雑学辞典 江戸時代の消防ポンプ :「東京消防庁」
龍吐水 :「消防防災博物館」
坪内定鑑 :「民俗学の広場」
坪内定鑑 :「用例.jp」
喧嘩両成敗 :「コトバンク」
インターネットに有益な情報を掲載してくださった皆様に感謝します。
(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません。
その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。
その点、ご寛恕ください。)
こちらもお読みいただけるとうれしいです。
『夜哭烏 羽州ぼろ鳶組』 祥伝社文庫
『火喰鳥 羽州ぼろ鳶組』 祥伝社文庫
『塞王の楯』 集英社
町火消「に」組の頭・辰一は、火消番付で東の関脇に位置づけられている。町火消最強と評される男。身の丈六尺三寸(189cm)で筋骨隆々の巨体の持ち主であり、背中に九頭の龍の入れ墨を彫っている。そこから九紋龍と通称されている。本書のタイトルは辰一のこの通称に由来する。
序章は上方から始まる。長谷川平蔵が京都西町奉行に着任した当時、千羽一家という押し込み強盗が京を荒していた。平蔵は千羽一家を追う。千羽一家は京から姿を消す。そして、大坂で火事を起こして、火事を囮にして大坂南堀江の両替商「篠長」に押し入り、皆殺しにして金を奪って、消えた。火事は燃え広がった。上方で平蔵は切歯扼腕する。
その千羽一家が、江戸に戻ってきたのだ。再び、大胆な手口で火付け押し込み強盗を開始する。江戸で発生した火事に敏速に対処するため源吾たち羽州ぼろ鳶組は率先して活躍する。一方、松永源吾は起こった火事の不審さに疑問を抱く。同時期に発生した悲惨な強盗事件との関連に気づいていく。不審を感じる源吾の思考と行動がこのストーリーの推進力となっていく。そんな折、長谷川平蔵から伝馬で源吾宛に文が届く。
もう一人、「に」組の頭・九紋龍が千羽一家の動きを察知していた。九紋龍は千羽一家を壊滅することに執念を持っている。それはなぜか。それがこのストーリーの要になっている。
このストーリーの面白さを生み出す背景にある構造的な要素をご紹介しよう。
第1は、幕政を一手に担う田沼意次と将軍を輩出する資格を有する御三卿の一つである一橋家の当主・一橋治済(はるさだ)との間の政治的確執が継続している。前作で、田沼意次が建造を推進した弁財船、鳳丸が大火の消火手段に使われ、一度の航海もしないまま座礁した。この結果が、田村追い落としの材料に利用され、田村意次は守勢に回る状況になっていた。一橋治済は田沼潰しに黒幕として暗躍する。
一橋治済は田沼意次に、新庄藩の方角火消の役割を免じてやればとすら言い始める。
第2は、長谷川平蔵が栄転の形で、京都西町奉行に転出したことに起因する状況。島田弾正政弥(まさひさ)が火付盗賊改方の長官後継者となった。島田には長谷川平蔵のような気概もなければ能力も無い。源吾は頼りにならない人物と判断する。源吾にとり島田は事件解決で連携プレイがとれない負の要素に過ぎなくなる。長谷川平蔵が居てくれたならば・・・・というところ。 平蔵が京に去ってから、府下の火付け事件は増加の一途を辿るという状況にあった。
第3は、新庄藩に状況変化が生まれる。新庄藩の家老、六右衛門は国元に帰ると、その後病の床に就いた。国元から御連枝戸沢正親が江戸に出て来て、家老の代行を始めた。正親は新庄藩の財政が困窮していることと、国元を優先させるという方針で、藩財政の運営を始める。源吾には、鳶の俸給を減じ、その他火消道具などへの費用を五個年差し止めると通告してきた。方角火消の役割も管轄範囲内に留めよという。源吾にとっては承伏できない方針である。正親は何処かから、それなりの情報を入手した上で、己の方針を打ち出してきたのだ。正親の言を受け入れるなら、新庄藩火消は壊滅する。源吾は再び窮地に立たされる。源吾、どうする・・・・。火消の矜持とぼろ鳶組の存続をかけて、源吾は正親に対峙しなければならなくなる。正親と源吾の関係はどのように進展するのか。
第4は、前作で魁の武蔵が登場した。戸沢正親が江戸に出てくる以前の段階で、源吾は武蔵を新庄藩火消一番組頭に迎え入れていた。竜吐水の扱いが滅法上手い武蔵をぼろ鳶組の強力な戦力にしようとしていた。源吾は新庄藩の火消道具の老朽化への対処に迫られていた。
第5は、源吾の妻、深雪が前作の最後の時点で身籠もっている事実がわかった。さらに深雪は己の才覚で近隣諸家の奥方たちと社交を広げ、交流ネットワークを築いていた。その結果が現れてくるという側面が織り込まれて行く。
こういう背景要素が絡まり合って、正親の言を半ば無視する源吾と羽州ぼろ鳶組の火消活動が展開されていくというストーリーが展開する。その源吾の前に町火消「に」組の九紋龍が現れてくる。火事現場に乱入してきて、大混乱を引き起こす因となる。火消同士の喧嘩も始まる。配下の火消に命じるだけで、己の考えを語らない九紋龍のなぞの行動の有り様が、読者の関心を引き付けていく。
火消活動が度重なるにつれ、源吾と九紋龍の関わり方が変化していく。今回のストーリーでは、消火活動と併せて千羽一家の撲滅をめざすという目的に向かった両者の関わり方が読ませどころとなっていく。勿論、火消たちの連携プレーを含めてである。
火事の発生、火消たちの消火活動。それと同時期に事件が発生する。それらの名称だけ時系列でご紹介しておこう。
麻布宮村町 有馬兵庫守下屋敷の火事 :六本木町の商家「朱門屋」で18名斬殺・強盗
日本橋南、元大工町 会所の火事 :日本橋、谷町の材木問屋「菱屋」で皆殺し・強盗
南小田原町、乾物商「小谷屋」の火事
浅草阿部川町、墨屋「染床」の火事 : 一軒の札差宅で11名皆殺し・強盗
神田橋御門近く三河町、そして小伝馬町 :最後の大団円となる。お楽しみに・・・。
最後に火事を喰い止める場所が、小伝馬上町となる。源吾の一言「各火消! 俺の指揮に従ってくれ!」火消の一致協力が力を発揮する。著者はここの躍動的で迫力ある場面描写により読者を引き込んでいく。さすが、エンターテインメント性を存分に発揮する。
九紋龍・辰一は背中に9頭の龍を彫っていた。8頭までは見事な龍の彫りと仕上げなのだが、1頭だけは筋彫りで輪郭を彫るだけに留めていた。この不可思議さが辰一の過去と現在の思いを表象している。この九紋龍を彫り込んだ辰一の思いが、彼の行動の原点になっている。源吾は星十郎、新之助、寅次郎らの協力を得て、その謎解きを試みる。また、「に」組の宗助が、辰一と源吾の間をつなぐ役割として要所要所に登場する。
それがこのストーリーの読ませどころにリンクしていくということに触れておこう。
ここからは読んでのお楽しみである。
この第3作、「第6章 勘定小町参る」で締めくくられる。勘定小町とは源吾の妻、深雪のこと。新庄藩の財政運営の為に、深雪が一働きするというエピソードで締めくくられるところが楽しい。そこに、上方きっての豪商、大文字屋四代の下村彦右衛門素休を登場させるのだから、おもしろい。大文字屋の通称はご存知の大丸である。
実在した新庄藩と大丸の下村彦右衛門は、史実として商取引の関係があったのだろうか。それともこれは時代小説としてのフィクションにすぎないのか。小説を離れてちょっと関心が湧いた。
最後に本書から印象深い箇所を引用、ご紹介する。
*無欠な者などおりません。それを補い合い人は生きているのです。個の力には限界があるかと。 p162
*新庄の民は貧しい。しかし決して明日への希を捨てぬ。人への思いやりを忘れはせぬ。人の真の貧しさとは、それらを忘れることではなかろうか・・・・先代のお言葉よ。 p253
松永源吾率いる羽州ぼろ鳶組がその存亡の窮地を脱する目途が立ったところで終わるのがいい。著者は読者の心をつかむのがうまいと感じる。第4弾への期待を募らせる。
ご一読ありがとうございます。
補遺
消防雑学辞典 江戸時代の消防ポンプ :「東京消防庁」
龍吐水 :「消防防災博物館」
坪内定鑑 :「民俗学の広場」
坪内定鑑 :「用例.jp」
喧嘩両成敗 :「コトバンク」
インターネットに有益な情報を掲載してくださった皆様に感謝します。
(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません。
その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。
その点、ご寛恕ください。)
こちらもお読みいただけるとうれしいです。
『夜哭烏 羽州ぼろ鳶組』 祥伝社文庫
『火喰鳥 羽州ぼろ鳶組』 祥伝社文庫
『塞王の楯』 集英社