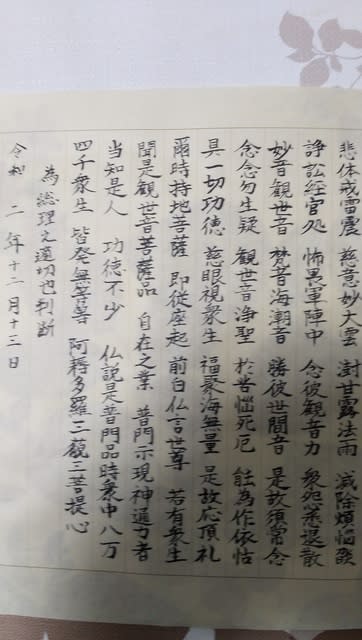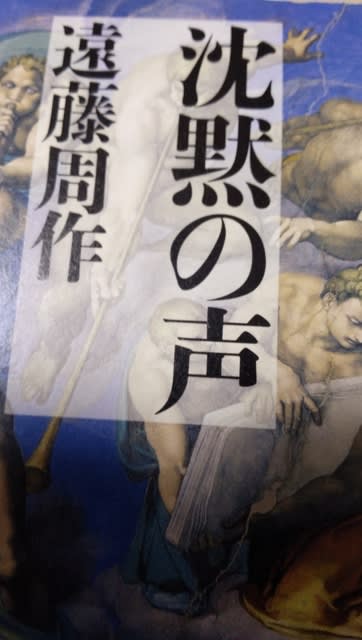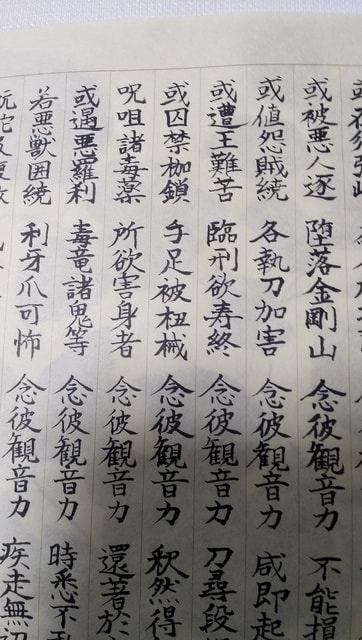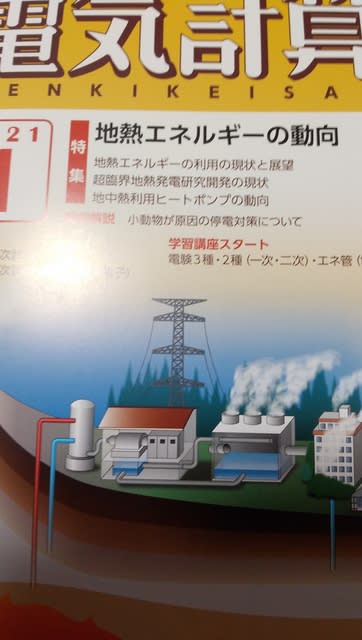ビザンツ帝国についてホント久々にレビューしてみましょう。
前にビザンツ帝国に触れてから年月を経て、自分自身も人生の行き詰まり感にさいなまされたり、一方でそんな中で電験2種の免状取得と色々ありました。
いよいよ日本でいう弥生時代にドミティアヌス暗殺によりフラウィウス朝が終焉したところから思えばビザンツ帝国もいよいよ末期、日本でいえば室町時代になってきます。
コンスタンティノープルを奪還したビザンツ帝国パライオロゴス朝であったが、もはや大国の面影をどこにも見出せない地中海の一小国家に成り下がっていた。
対トルコの従属的な関係、コンスタンティノープルの奪回に協力したジェノバにはもちろん、ラテン帝国の黒幕ベネチアにも通商上の特権を与えている。
そんなパライオロゴス朝の末期に即位したのがマヌエル2世であった。幼少期にトルコの人質であったマヌエル2世はすきを見て帰国後に祖国のために東奔西走する。すきを見て帰国と言えば桶狭間で今川義元が討たれたどさくさに岡崎に帰還した徳川家康を連想させるが、そんなサクセスストーリーとは程遠かった。
トルコへの臣従を取り消したビザンツ帝国に当然トルコは攻撃を加えてくる。
そこで帝国は西欧の援助を求めようと皇帝自らが旅に出てドーバー海峡を渡りイングランドまで行く。
西欧の人々は「ギリシア人のローマ皇帝」を歓迎し、マヌエル2世もローマ帝国皇帝のプライドもなげうった。
が、実際に援軍を出すとなると西欧諸国は二の足を踏んだ。
その間にトルコに包囲されたコンスタンティノープルでは都の明け渡し寸前であったが、東方から思いがけない援軍が来る。
ティムール帝国である。チャガタイ・ハン国が諸侯乱立の状態の中からレースに勝ち出たティムールはオスマン・トルコを壊滅的な状態にする。本来ならばここでオスマン帝国を挟撃して脅威を打ち払うべきところであるがビザンツ帝国はそうしなかった。いや出来なかった。そこまで帝国の力は落ちていた。やがてティムールは攻撃の矛先を明帝国に向かわせる途中で死去する。
西欧の傍観とティムールの死に救われたトルコは再びビザンツ帝国に圧力をかけてきた。滅亡の危機は何度もあったが、マヌエル2世はそのたび巧みな外交をもって帝国の滅亡を免れる。人々はこの皇帝ある限り帝国はつぶれないと信頼していた。そんなマヌエル2世にも死が近づいた。それまで強硬路線でトルコのくびきをほどこうとする息子ヨハネス8世をマヌエル2世は諫めてきたが、死の床にあって「これからはお前の好きなようにしなさい」と言い、帝国の滅亡を予感しながら世を去った。
ある歴史家は「良い時代に生まれていたならばさぞや名君と呼ばれたに違いない」と彼を惜しんだが、私は名君であることと人物の有能・無能とは少し乖離があると思っている。要は時代の制約を踏まえ歴史上の人物評価をすべきものと思っている。
長くなったのでさらに次の機会にこのことをもう少し述べてみたいと思う。
前にビザンツ帝国に触れてから年月を経て、自分自身も人生の行き詰まり感にさいなまされたり、一方でそんな中で電験2種の免状取得と色々ありました。
いよいよ日本でいう弥生時代にドミティアヌス暗殺によりフラウィウス朝が終焉したところから思えばビザンツ帝国もいよいよ末期、日本でいえば室町時代になってきます。
コンスタンティノープルを奪還したビザンツ帝国パライオロゴス朝であったが、もはや大国の面影をどこにも見出せない地中海の一小国家に成り下がっていた。
対トルコの従属的な関係、コンスタンティノープルの奪回に協力したジェノバにはもちろん、ラテン帝国の黒幕ベネチアにも通商上の特権を与えている。
そんなパライオロゴス朝の末期に即位したのがマヌエル2世であった。幼少期にトルコの人質であったマヌエル2世はすきを見て帰国後に祖国のために東奔西走する。すきを見て帰国と言えば桶狭間で今川義元が討たれたどさくさに岡崎に帰還した徳川家康を連想させるが、そんなサクセスストーリーとは程遠かった。
トルコへの臣従を取り消したビザンツ帝国に当然トルコは攻撃を加えてくる。
そこで帝国は西欧の援助を求めようと皇帝自らが旅に出てドーバー海峡を渡りイングランドまで行く。
西欧の人々は「ギリシア人のローマ皇帝」を歓迎し、マヌエル2世もローマ帝国皇帝のプライドもなげうった。
が、実際に援軍を出すとなると西欧諸国は二の足を踏んだ。
その間にトルコに包囲されたコンスタンティノープルでは都の明け渡し寸前であったが、東方から思いがけない援軍が来る。
ティムール帝国である。チャガタイ・ハン国が諸侯乱立の状態の中からレースに勝ち出たティムールはオスマン・トルコを壊滅的な状態にする。本来ならばここでオスマン帝国を挟撃して脅威を打ち払うべきところであるがビザンツ帝国はそうしなかった。いや出来なかった。そこまで帝国の力は落ちていた。やがてティムールは攻撃の矛先を明帝国に向かわせる途中で死去する。
西欧の傍観とティムールの死に救われたトルコは再びビザンツ帝国に圧力をかけてきた。滅亡の危機は何度もあったが、マヌエル2世はそのたび巧みな外交をもって帝国の滅亡を免れる。人々はこの皇帝ある限り帝国はつぶれないと信頼していた。そんなマヌエル2世にも死が近づいた。それまで強硬路線でトルコのくびきをほどこうとする息子ヨハネス8世をマヌエル2世は諫めてきたが、死の床にあって「これからはお前の好きなようにしなさい」と言い、帝国の滅亡を予感しながら世を去った。
ある歴史家は「良い時代に生まれていたならばさぞや名君と呼ばれたに違いない」と彼を惜しんだが、私は名君であることと人物の有能・無能とは少し乖離があると思っている。要は時代の制約を踏まえ歴史上の人物評価をすべきものと思っている。
長くなったのでさらに次の機会にこのことをもう少し述べてみたいと思う。