醍醐寺を拝観 その2
京都山科から地下鉄で8分。醍醐駅で下車し回廊風の道を歩いて10分。
醍醐寺の境内は200万坪におよぶ広大な敷地です。
盆地の東側、笠取の山頂にかけての広大な地域に位置し、
山頂一帯を「上醍醐」山裾を「下醍醐」と称しています。
醍醐寺には、上醍醐、下醍醐の伽藍に、
国宝6棟、重文10棟を含む92棟の建造物
及び文化財を管理保管しています。

総門から入り、正面にみえる仁王門(西大門)をくぐると、
広大な敷地が広がります。
左手に金堂、右手に五重塔がありますが、
いずれも後回しにして、一気に弁天池へと足を早めます。
(弁天池の脇の寿庵で食事をしたい為 
葉に陽があたると眩しいくらいの鮮やかさ。

2018年9月4日に上陸した台風21号によって甚大な被害を受け、
スギやマツなどおよそ3,000本に及ぶ倒木や、
醍醐寺を取り巻く白壁塀の損壊がでました。

仁王門を入った両脇に、今でもその無惨な様子が目を覆います。
下醍醐の一番奥に弁天堂があります。



観音堂を背景に真っ青に染まった水面。



丁度12時、お目当ての「寿庵」に入店。

席待ちで10分ほど待たされましたが、四人席にご案内。
弁天堂を臨む「寿庵」は、かつて高僧が宿舎としていた
落ち着いた佇まいのお休み処です。

娘はゆば丼をお願いしました。

かつおだしで炊き上げた生ゆばを京風あんかけだしに
たっぷり入れたどんぶりです。
老人夫婦は湯葉うどんをお願いしました。

湯葉巻きが入っていて、出汁が極めて美味しい。
いずれも黒糖わらび餅が付いています。
お値段は場所柄、少々お高めです。。
大変美味しかったです。ご馳走様でした。
寿庵の脇を山手に登ります。
上醍醐から沢を流れて来た水が、弁天池へと注いでいます。

弁天池を後にして参道を降りながらの紅葉狩り。
観音堂脇にある鐘楼。

周りにはイチョウの葉が一際目立ちます。

モミジに☀️が注ぎ見事に紅に染まる。 思わずパチリ。📸

残念ながら時間切れで、金堂と国宝五重塔は拝観出来なかった。
ウォッチの歩数計が12000歩を超えました。

同行者がギブアップ
仁王門に戻って来ました。

紅葉の見頃時期が心配でしたが、何とか満足いく紅葉狩りが叶えました。
何回来ても京都の紅葉は綺麗です。
また来年も新たな見所を探して訪れたいと思います。
(おわり)





























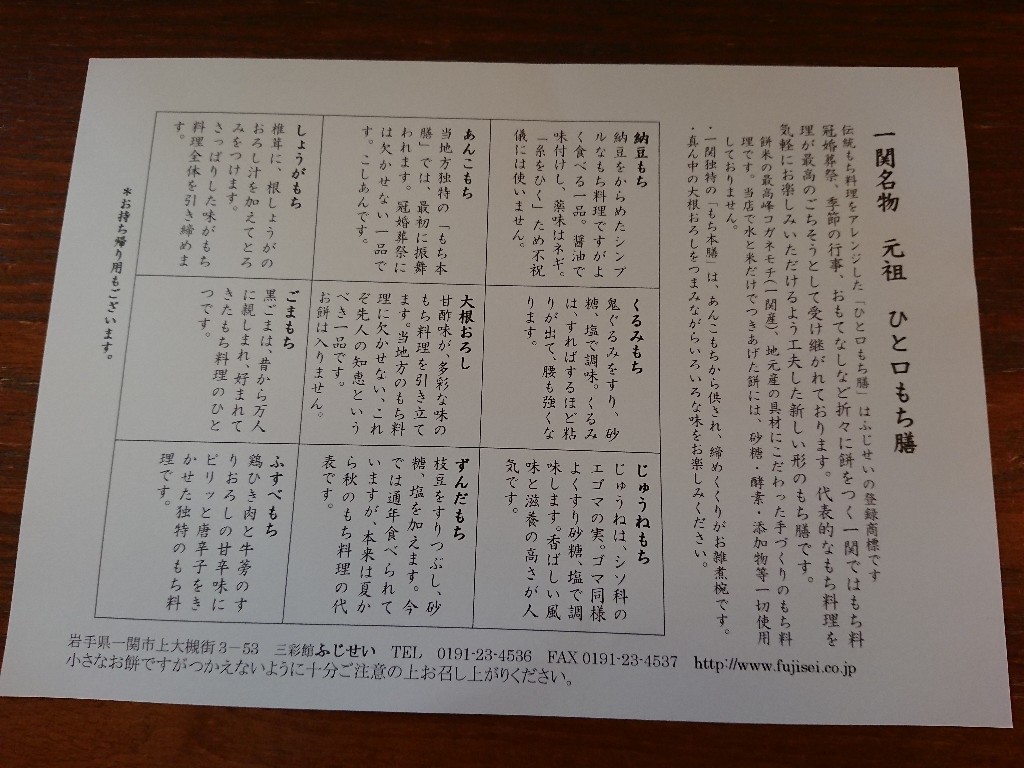


































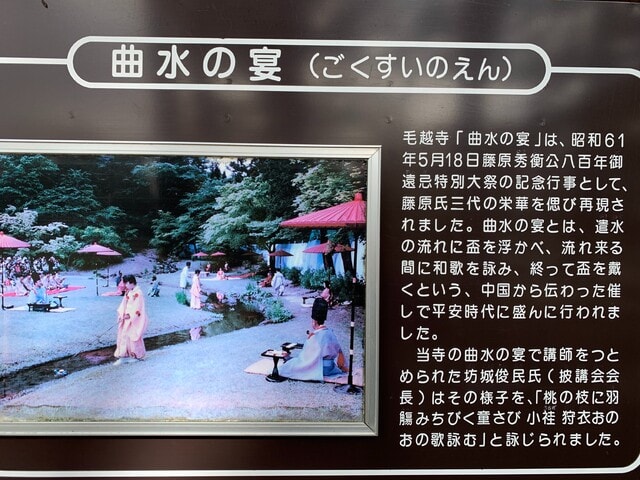
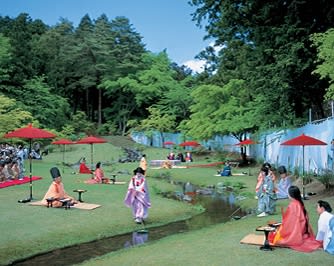








 で平泉駅へ。
で平泉駅へ。

 で境内入り口(
で境内入り口(




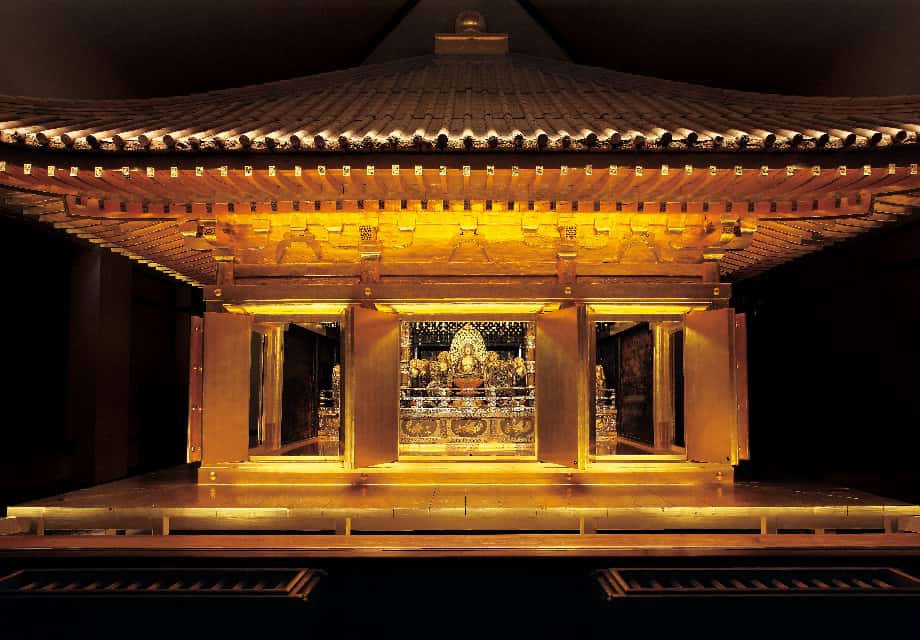
 中国か韓国か?
中国か韓国か?

 )
)




