昨年の人間ドックで再検査と診断され、
半年ほど前から眼科の診察を受けています。
白内障と診断され手術をすることに決め、準備を進めてきました。
昨今は白内障の手術をする人が多く、
日程が取れたのは5ヶ月先のこの一月でした。
そして今日手術に行ってきました。

待合室で瞳孔を開く点眼を2回受け、
待つこと20分後、手術前処置室に案内されました。

低いベッドが四台。今日の白内障の手術する人は3人。
追加の点眼と血圧測定があり、感染予防の点滴が始まりました

ベッドに横たわって20分程が経過。
手術室に案内され、椅子形式の手術台に座ります。
先生と助手のナースが二人。
顔面に手術する目の穴が開いたカバーがかけられ、
機器で目の開きを固定されます。
機器が眼前にあるのか、見えるのは四角な光が二つ⁉️
真っ暗な世界❗️
「始めます」の先生の声。
麻酔をして目の洗浄が行われました。
処置行程を復唱している先生の声が聞こえます。
今回の手術行程は要約すると以下の通りです。

水晶体は周りが『水晶体嚢』という透明な膜に覆われています。
先が少し曲がった針を入れ、水晶体嚢の前面を丸く切ります。
その後、超音波の力で水晶体の濁った中身だけを吸い出します。

金属のチップが電動歯ブラシのように微細に高速で動き、
水晶体を掘りながら砕いて吸い込む装置になっています。
「……を削ります?」と言う声が聞こますが何のことやら?
超音波が作動している時は、ブーンと言う様な音がしています。
そしていよいよレンズの挿入です。
「水晶体にレンズを取り付けます、」と先生。
残った薄い膜(水晶体嚢)の中に
水晶体の屈折力を補正するための眼内レンズが挿入されます。

レンズを折りたたんだ状態で眼の中に挿入し、
眼の中に入った後にレンズが開く仕組みの様です。
「傷口は縫わないの?」と思いますが、
眼の中の圧を高めることで、
縫わなくても傷口がきれいに塞がる『自己閉鎖』と
いう方法で傷口が閉じられるらしい。
最後に眼帯を固定して終了です。
顔面接着テープで丹下左膳の気分⁉️
手術の時間は15分間位だったと思います。
この後の一日間は片目の世界。
遠近感がなく気をつかう時間が待っています。
明日眼帯を外した世界が待ち遠しい😁
この記事は片目で打ち込んでいます。
誤字脱字やおかしな表現があればお許しを





















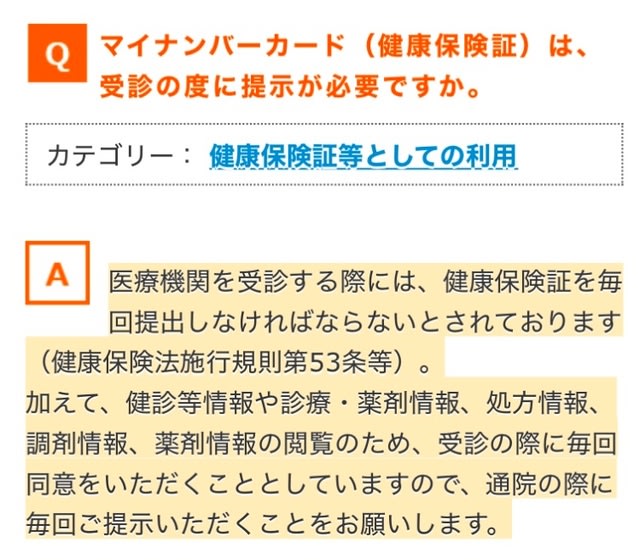


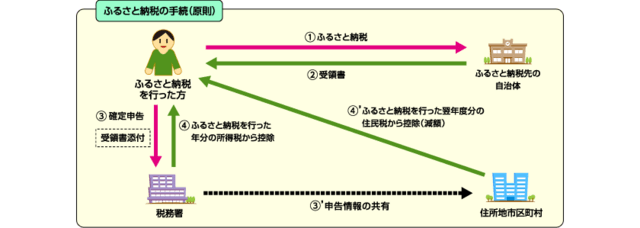

 )
)






