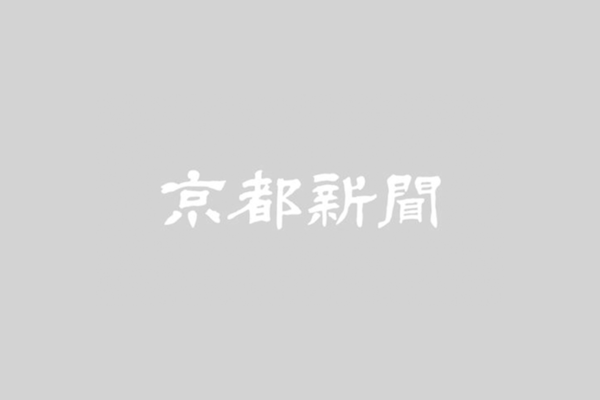今日は、お休みの日で、外に出るのが暑そうだったので、家の中で涼しく過ごしました。
12月の『京都検定』まで、あと3か月ちょっとになったので、そろそろペースを上げて勉強しないといけません。
この間、あちこち「京都歩き」をして、いろいろな場所に足を運んでいるので、知識としては増えています。
けれども、実際に試験問題ができるかどうかは、別問題のような気がします。


京都新聞さんがこれまでの「京都検定」の問題をサイトに載せていただいているので、最近の問題から去年の問題、一昨年の問題とさかのぼってやっています。
今日は2007年に実施された第4回の問題をやりました。。。
何回も同じような問題をやっているので、だんだんと問題を覚えるようになりました。
また、断片的な知識が少しずつリンクしてつながってきたような気がします。

たとえば一口に「平安時代」と言っても、泣くよウグイス(794年)に平安京ができてから、良い箱作ろう鎌倉幕府(1185年)まで400年近くあったわけです。
初期に桓武天皇や嵯峨天皇が苦心して、まちづくりを進めた頃もあれば、藤原氏などの貴族が権力を持って、平等院など寺院をたくさん作った時代もあり、後半になってくると武士が登場し、対立する人物同士が武士を抱えて、内乱が幾度もあった時代もありました。
単に、問題を暗記すればいいのではなくて、そういった、大きな時代の流れをつかむことが大事ではないかという気がしました。
紫式部や清少納言などの文学が発展したのは、ちょうど中間にあたる1000年のあたりですね。

歴史の流れを見ていると、不思議な感じがします。
いつも誰かと誰かが権力争いをしているのです。
それは、戦国時代も幕末も現代でも同じことなのでしょうか。
話がそれてしまいました。。。
今日のテストの結果は100点満点で85点でした。
70点以上が合格なので、まずまずです。
あてずっぽうで、とった点が10点ほどありますので、確実にとれるようにしていきたいものです。

今朝は、高い木の上にダイサギ君がとまっているのを見つけました。

高いところから、川の中が見えるのかと感心します。

ワシやタカも高い空から、小さい鳥などを見つけるのが上手なので、よく見えるのでしょうね。
さて、明日は仕事ですが、まだまだ暑そうです。
気合を入れて、出勤します。