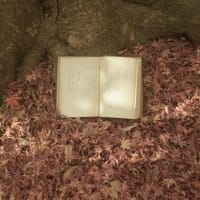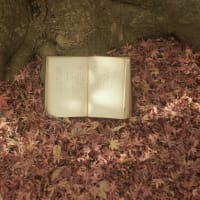肌寒くなってくると、温かいスープが有難い。
西洋の隠者の伝統食と言えば、質素なパンとスープしかないだろう。
ファンタジー映画やゲームでの旅の吟遊詩人や冒険者も、野宿の焚火で作る食事は硬いパンと乾燥野菜のスープと、たまに干し肉でも付けば上等だ。
私も還暦を過ぎてからはそんな食事の良さがわかって来て、血糖の呪いもあり近年は中世修道院並み(蛋白質は多めだが)の食事になっている。
パン皿にはイギリスアンティークのピュータープレートが定番だが、これに日本の陶器(ストーンウェア)を組み合わせると中世ヨーロッパの雰囲気が出る。
下の写真では家人の為に沢山並べたが、私が食べられるのはこの内の半分である。

例によって拙い料理ながら、ハロウィンの余りの赤蕪(ケルトは南瓜ではなく蕪)と挽肉の中世風スープ、ちょっと贅沢なベーカリーの惣菜パン、鶏の骨付肉とハーブソーセージにサラダ。
今週の食器類は荒川真吾氏作の陶器を主に取合わせた。
和食や茶懐石の一汁一菜(三菜)にあたるパンとスープと肉の組合せは、簡素にして無限のバリエーションがあり、使う器を考えるのも楽しい。
禅の修行僧は鉄鉢一つで全ての食事をすますが、禅の懐石から始まった茶懐石では料理も器も文化の粋を極めた工夫がある。
茶懐石を参考に、洋食でも究極の器セットに到達してみたい。

16世紀ヨーロッパ風の豆と鶏肉のスープ、フォカッチャ、チーズメンチとビーフステーキ。
幸いにも今世紀の陶芸家達は、一昔の人間国宝連中が雑器と馬鹿にして作らなかった洋食器も作るようになって、今は手頃な価格で最高峰の技術の器が買える。
簡素な朝食には器も単純な取合わせとなるが、単純なほど対比と調和は難しい。

きのことブロッコリーのスープにカンパーニュ。
陶製の野兎を賑わいに置いて、遍歴の山野を眼裏に思い起こそう。
染付や色絵磁器も手描きの物で色調が部屋や料理に合うなら良いと思う。
ただヨーロッパの色絵磁器制作は近世以後なので、隠者には中世風の武骨な陶器の方が似合うだろう。
こんな感じで我が残生は、洋風一汁一菜の料理と器選びに費やするのも楽しいだろう。
©️甲士三郎