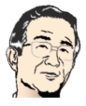10月31日、立命館大阪キャンパスで、立命館プロムナードセミナー「大阪・京都文化講座『大阪・京都の風土と景観』」の3回目を受講しました。「城下町大坂~江戸時代の大阪を考える~」と題して大阪大学大学院文学研究科教授の小林茂さんが講義しました。概要は以下の通りです。
大阪城は大阪のシンボル。現在の大阪の町は大坂城の城下町として発展した。しかし大坂は「天下の台所」、「町人の町」などと呼ばれ、武士の影が薄い。
豊臣時代の大坂城は秀吉入城から大坂夏の陣までのわずか32年。これに対し、徳川時代の大坂城は夏の陣から大坂城明け渡しまでの250年以上。しかし、話題になるのは豊臣時代の大坂城。
江戸時代、大坂城内にいたのは、
大坂城代:譜代大名が交代で就任。任期は特になく、最長21年、延べ70名が就任。
大坂在番
大坂定番:大名(1~2万石)、定まった任期なし、2名。
大番:旗本、任期1年、2組。
加番:大名、任期1年、4名。
大坂城代のもとにいる幕府諸役人
大坂在番
定番(2名)+与力(各30騎)・同心(各100名)(大阪在住)
大番頭(2名)+与力(各10騎)・同心(各20人)
加番
大坂町奉行(2名)+与力(各30騎)・同心(各50名)(大坂在住)
各藩の大坂蔵屋敷
主として米販売、その他専売品の販売、江戸仕送り・借銀、京都・大阪での買い物。約85の蔵屋敷。
大坂は多くの武士にとって一時的勤務。大坂城代・大坂町奉行は譜代大名・旗本の出世の階段。
→「名君」の出る可能性がない。
名城代、名奉行がいても長く記憶されない→秀吉や秀頼、淀君のような話題性に欠ける。
大坂の武士の数は町人に比べて少ない。家族も含めて約1万人。
→武士の影が薄い。
武家屋敷は退去・入居を繰り返す仮住まいとしての性格が強い。
大番・加番の場合は「小屋」と表記。
大阪城は大阪のシンボル。現在の大阪の町は大坂城の城下町として発展した。しかし大坂は「天下の台所」、「町人の町」などと呼ばれ、武士の影が薄い。
豊臣時代の大坂城は秀吉入城から大坂夏の陣までのわずか32年。これに対し、徳川時代の大坂城は夏の陣から大坂城明け渡しまでの250年以上。しかし、話題になるのは豊臣時代の大坂城。
江戸時代、大坂城内にいたのは、
大坂城代:譜代大名が交代で就任。任期は特になく、最長21年、延べ70名が就任。
大坂在番
大坂定番:大名(1~2万石)、定まった任期なし、2名。
大番:旗本、任期1年、2組。
加番:大名、任期1年、4名。
大坂城代のもとにいる幕府諸役人
大坂在番
定番(2名)+与力(各30騎)・同心(各100名)(大阪在住)
大番頭(2名)+与力(各10騎)・同心(各20人)
加番
大坂町奉行(2名)+与力(各30騎)・同心(各50名)(大坂在住)
各藩の大坂蔵屋敷
主として米販売、その他専売品の販売、江戸仕送り・借銀、京都・大阪での買い物。約85の蔵屋敷。
大坂は多くの武士にとって一時的勤務。大坂城代・大坂町奉行は譜代大名・旗本の出世の階段。
→「名君」の出る可能性がない。
名城代、名奉行がいても長く記憶されない→秀吉や秀頼、淀君のような話題性に欠ける。
大坂の武士の数は町人に比べて少ない。家族も含めて約1万人。
→武士の影が薄い。
武家屋敷は退去・入居を繰り返す仮住まいとしての性格が強い。
大番・加番の場合は「小屋」と表記。