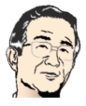16日、立命館大阪キャンパスで、立命館大阪プロムナードセミナー「木津川 計/大阪学講座」5回目の「<戦後文学都市>をなぜ大阪は構築したのか-井上靖に始まり、司馬遼太郎で終焉するまで―」を受講しました。内容は以下の通りです。戦後大阪文学は、織田作之助、小野十三郎、井上靖に始まり司馬遼太郎で終焉した。織田作之助の「可能性の文学」は、大阪が投げつけた東京の権威的既成文壇への挑戦状であった。また、詩人の小野十三郎も「短歌的抒情の否定」を大阪から歌壇に投げつけた。井上靖は大阪毎日新聞社に勤め、阪急西宮球場で行われた「闘牛」に取材した短編を書いた。戦後の文学都市大阪が何故に熱気をたたえたのか。一つは、商工業都市大阪のバイタルで猥雑な地熱は若くて有能な作家たちのエネルギーを爆発さすにふさわしい都市だった。二つ目は、司馬遼太郎が人気作家になっても東大阪に居を構えたまま、東上しなかったことである。有能でありさえすれば大阪にあっても人気作家たり得ることを証した。その上、人は人を呼ぶ。司馬は多くの作家を引き寄せた。戦後大阪の文化と経済が共に元気だった時代である。山崎豊子の「花のれん」、菊田一夫の「がめつい奴」が大阪を”ど根性”と”がめつい”都市とイメージさせた。今東光は河内のイメージをフリーセックス地帯のように描出した。なぜ、文学都市大阪がその面影をなくしたのだろうか。多くの猥雑とど根性が描かれた60年代の高度経済成長後の70年以降、大阪の猥雑とど根性を必要とした文学の時代が過ぎた。96年に終生大阪を離れず、日本文学の灯台的役割を果たした司馬遼太郎が72歳で死去した。大阪から照らした文学の灯が消えたのだった。