
三原乙吉(1864-1946)は今津町471に居住した御仁だ。不動産は昭和32年に山形武に名義変更(相続)されている
三原喜七の息子だったようだ。喜七は屋敷を担保に村上重右衛門に借金したようで、明治33年3月3日に乙吉が村上から買い戻している。炊事場のほかに2間しかない粗末なかやぶき屋根の家だった。むかし後継者の山形武は玄関先で、仕入れたウナギを器用にさばき、店で出すかば焼きの下ごしらえをよくしていた。時には家の前の溝を泳いでいるドジョウを捕まえ、それをいきなりかば焼きにすることもあった。こういうwildなことをする山形武さんのことだからアナゴやウナギのかば焼きに混ぜてドジョウのそれをお客にふるまっていたかもしれぬ。奥さんに関しては私の記憶にはほとんど残っていないのだが、仲居さんだということを子供のころ祖母から一度聞いた覚えがある。昭和32年に国道二号線が建設され、以後山形家の人々の消息は不明だ。今回見かけたお墓に榊が手向けられていたので山形さんを含む三原乙吉さんの親類縁者は健在なのだろ。


「地方文化開拓者」という言い方は聞きなれないやや力んだ表現だ。
念のため、矢野天哉『人生画帳』を調べてみたが、わかったのは文選堂という新聞雑誌販売店を経営した御仁だったってこと。それを捉えて地方文化開拓者と称していたわけだ。なるほど、なるほど定期購読者を増やす業務(市場開拓)は活字に縁のない人々の中に分け入って行くわけだから明治後半期においてはまさしく文明のすそ野を開拓する行為そのものだったろ。三原はそのことに関してなにがしかの矜持を持ち、使命感を抱いていたのだろうか。その後、『松永市本郷町誌』・本郷町誌年表/明治25年の項目に「今津村三原乙吉新聞配達業を始む」(953頁)とあることを確認した。新聞配達店の開業はまさにそのくらい画期的なことだった事が判ろう。なお、三原という苗字はこの地方では駅家(万能倉)・赤坂(長者原)に多い。
大正2年本殿再建費寄付者芳名碑
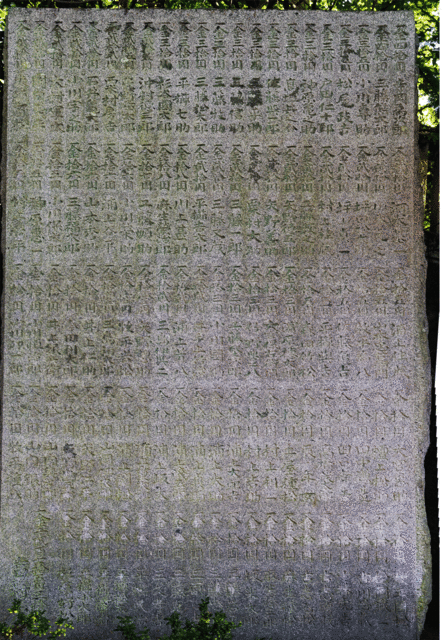
下の方に三原乙吉の名前
大正2年本殿再建費寄付者芳名碑に見る高額寄付者


なんとなくだが西組(剣大明神鳥居前の薬師寺所有地に居住)の「栄虎」とはやはり見栄の張り方からして平櫛民治郎かなぁ。これはわたしの勘だからあまり大きな声では言えない。















