
津市美里町穴倉の
福徳寺の「馬頭観音(ばとうかんのん)」です。
お寺の本堂の脇に観音堂があり、そちらに安置されています。

像は木製の立像で、腕や足の先を除いて、
一本の木より削りだされたものです。
頭部に馬の頭が載っていることから「馬頭観音」と呼ばれています。
「馬頭観音」は、元々は馬のように天地を疾駆し、あらゆる病魔災厄と戦う神であったようですが、
江戸時代以降、輸送手段として馬が一般的に飼育されるようになると、
民間信仰においては馬の守護仏(馬を病気から守る)として、
あるいは、死んだ馬の供養として「馬頭観音」を信仰するようになったようです。

こちら福徳寺の馬頭観音は、
容貌がふくよかで優しいことから、一般的に憤怒相の多い馬頭観音と異なるため、
何かの観音菩薩像に馬の頭を追加して、馬頭観音に作り変えた可能性が高いのです。
江戸時代初期に、津から穴倉村に移って来たということで、
それ以前の経緯は分からないのですが、
江戸時代になって馬頭観音信仰が盛んになり、
必要に迫られて「改造」が行われたということだったのでしょう。

馬頭観音のある、福徳寺観音堂の内部です。
奥が御厨、手前には護摩行を行う炉があります。
護摩行は毎年3月の初午(はつうま)と
観音さんの命日である8月18日に行われています。

堂内に保管されている棟札です。
宝永5年(1708年)観音堂の建立
天保9年(1838年)観音堂の修復
大正2年(1913年)観音堂の修復
らの普請が行われる度に、棟札が遺されており、
当時の様子を知ることができます。
これらの史料から、こちらの馬頭観音は、
津の四天王寺の寺仏であったものを、
津藩士渡邉甲之丞吉隆が、寛永年間に穴倉の自宅に移し、
その後、福徳寺に移したということが伝えられています。

美里町穴倉の穴倉バス停付近の畑地です。
このあたりに津藩士渡邉甲之丞の屋敷があったようです。
屋敷の面影は無く、渡邉家の墓碑だけが残っています。

(渡辺家の墓碑)
さて、元々この馬頭観音があった津の四天王寺は、
千年以上の歴史のある古寺ですが、戦乱大火で荒れ果てていたものを
津に入府した藤堂高虎が再建したものです。
ちょうど渡邉甲之丞が穴倉に馬頭観音を移した時期と、
四天王寺が再建された時期が一致しています。
とすると
焼け残っていた幾つかの小堂のひとつにこの馬頭観音
(当時は普通の観音菩薩だったかもしれない)があり、
「このお堂はいかがいたしましょう?これも修復しますか?」
「いやいやそんな小さなお堂よりも、まずは本堂を立派にしようではないか」
と修復の対象にされなかったために
お堂は取り壊され、渡邉甲之丞が安置されていた観音像を貰い受けた、
ということが想像されます。
誰が何時の頃に馬の頭をくっつけたのかはわかりません。
渡邉甲之丞は、津藩士であり、
江戸時代初期には穴倉村の庄屋も務めていました。
が、
後の時代になると、穴倉村の庄屋は
稲垣家になっています。
けれども、甲之丞の子孫はそのまま穴倉に住んでいたようなので、
渡邉家は無足人の家柄から、正式な津藩士に昇格し、
庄屋の役職を稲垣家に譲り渡した、ということが考えられます。

資料
棟札に書かれたていた内容(抜粋)
宝永五年(1708)建立
津の四天王寺の寺仏であった観音を、津藩士渡邉甲之丞吉隆が寛永年中に穴倉の自宅に移し祭った。
しばらく渡邉家で祭った後、福徳寺に移したが堂守も完全でなかった。
五十余年の後、里民一同が志をたて、観音堂を建立した。
住職 盛覚和尚
願主 渡邉九大夫義豊
天保九年(1838)修復
住職 眞順西堂 第十四世
津藩 渡邉九大夫義富
里保 稲垣市郎兵衛
工師 平尾清兵衛
瓦師 木下新吉
大正二年(1913)修理
住職 藤田堯暹(ぎょうせん)
区長 渡邉良太
副区長 若林民次郎
大工 小野權四郎 川合平蔵 川合久三郎
組頭 (略)

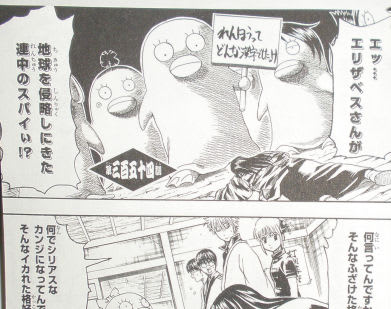


















 資料
資料
